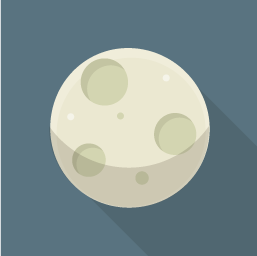式部と敦道親王
みなさん、こんにちは。
元都立高校国語科教師、すい喬です。
今回は女性に人気のある『和泉式部日記』を取り上げます。
学校ではあまりやりません。
授業では、書き出しの部分を扱うことが1番多いでしょうか。
やるせない女性の心が、これでもかと表現されています。
高校生には少し難しいかもしれませんね。
ところで、彼女のつくった和歌の中で最もよく知られているのはどれか、あなたは御存知ですか。
代表作はズバリこの歌です。
あらざらむこの世のほかの思ひ出にいまひとたびの逢ふこともがな
百人一首にとられているので、1度は目にしたことがあるでしょう。
他にもう1作と言われたら、やはりこの歌ですかね。
もの思へば沢の蛍もわが身よりあくがれ出ずる魂かとぞ見る
激しい気性の女性だったと思われます。
京都の奥、鞍馬に至る貴船神社に参詣した時の、心の様子をうたったものと言われています。
「男に忘れられたころ」と詞書にはあります。
魂と蛍との出会いを歌にしたところが新鮮ですね。
想像力の賜物でしょう。

彼女は越前の守、大江雅致の娘で、二十歳前に和泉の守、橘道貞と結婚。
後に小式部の内侍(ないし)を産みました。
夫婦仲がうまくいかずにいたところ、冷泉院の第三皇子為尊(ためたか)親王と出会います。
ほどなく、身のほども知らずに関係は深まっていきました。
しかし数年後、親王は病没してしまいます。
和泉式部が喪に服している頃、皇弟の帥(そち)の宮、敦道(あつみち)親王が彼女に好意をしめしたのです。
さすがに最初は遠ざけていましたが、やがて召人として、宮廷に迎え入れられることとなりました。
この間の様子を綴った恋物語が『和泉式部日記』なのです。
ところが敦道親王も数年後に、あっけなく亡くなってしまいます。
この日記は為尊親王の喪のあける二か月前、弟宮から橘の花と歌が届けられたところから始まります。
敦道親王と式部の人目を忍ぶ恋は、季節の移り変わりとともに深まっていきました。
十月、敦道親王は式部を自邸に迎えようとします。
そのあたりの記述を日記の本文から抜き出してみましょう。
本文
二日ばかりありて、女車のさまにてやをらおはしましぬ。
昼などはまだ、御覧ぜねば、はづかしけれど、あさましうはぢ隠るべきにもあらず。
またのたまふさまにもあらば、はぢきこえさせてやはあらむずるとて、いざり出でぬ、日ごろのおぼつかなさなど語らはせたまひて、しばしうち臥せさせたまひて、
宮「この聞こえさせしさまに、はやおぼし立て、かかる歩のつねにうひうひしうおぼゆるに、さりとて参らぬはおぼつかなければ、はかなき世の中に苦し」とのたまはすれば、

女「ともかくものたまはせむままにと思ひたまふるに、「見ても嘆く」といふことにこそ思ひたまへほづらひぬれ」と聞こゆれば、
宮「よし見たまへ、「塩焼き衣」にてぞあらむ」とのたまはせて、出でさせたまひぬ。
前近き透垣のもとに、をかしげなる檀の紅葉のすこしもみぢたるを、折らせたまひて、高欄におしかがらせたまひて、
宮「言の葉ふかくなりにけるかな」とのたまはすれば、
女「白露のはかなくおくと見しほどに」と聞こえさするさま、なさけなからずをかしとおぼす。
宮の御さまいとめでたし、御直衣に、えならぬ御衣、出たしうちぎにしたまへる、あらまほしう見ゆ。
目さへあだあだしきにやとまでおぼゆ。
現代語訳
二日ほど経って、宮は女車のように見せかけてそっとお越しになりました。
昼などにまだお目にかけたことがないので、恥ずかしいけれど、みっともなく恥じらって隠れているわけにもいきません。
それに宮さまがおっしゃるようにお邸に移ることになったら、いつまでも恥ずかしがってなどいられないのです。
そう思って、にじり出ました。
宮はこの数日ご無沙汰していたことなどをお話しになって、しばらく横になられ、
「わたしが申し上げたとおりに、早く決心なさい。こういう外出はいつも気恥ずかしく、だからといってお伺いしないと気がかりだし、こんな頼りない関係では苦しくてならないのです。」
とおっしゃるので、
とにかくお言葉通りにと思っているのですが、逢えば逢うほど逢いたくなるので 親しくなると人は嫌がるようになるのでしょうという話もありますから、私はいま思い悩んでいるのです
と申し上げると、

「まあ、見ていなさい。伊勢の海人が塩を焼く時に着る衣のように、馴れ親しんでこそ人は恋しくなるものですといいますからね。」
とおっしゃって、部屋を出て行かれた。
庭先の透垣(すいがい・垣根)のところに、美しい檀(まゆみ)が少しだけ紅葉したのを、宮はお折りになって、欄干に寄りかかりながら、
「檀の葉が色づくように、わたしたちの言葉も深くなったね」
とおっしゃるので、
「白露がほんの少し置くのを見ていた間に」と申し上げる女の様子を、宮は情趣があってなんて素晴らしい人だとお思いになられる。
女は、宮のご様子にもとても心ひかれるのでした。
直衣をお召しになり、その下になんとも言えないほど美しい袿(うちき)を、それも出し袿にしていらっしゃるのが、理想的に見えるのです。
女は、わたしの目まで色香に酔っているせいからかしら、とさえ思われたのでした。
第三者の目
未亡人となった式部は、亡夫の弟帥の宮から求愛されます。
手紙のやりとりだけでは満足できず、ある夜帥の宮は式部を訪れるのです。
式部は戸惑うものの、つい熱情にほだされてしまいます。
帥の宮がくれた後朝(きぬぎぬ)の文は思いやりに満ちたやさしいものでした。
しかしお互いに社会的な地位や世間体が気になります。
そのため式部の心は揺れ動くのです。
しかし敦道親王は積極的です。
これがこの場面の味わいをより深いものにしているのです。
和泉式部の心の揺れを知りながら、一途に進んでいく親王の様子が見て取れますね。
敦道親王は大宰帥だったために、帥(そち)の宮と呼ばれました
最初のところに女車のさまにて、という表現があります。
牛車の下簾の下から、女性の衣装の袖口などを出した車のことを言います。
宮は昼間なので、人目を忍んで女車を装ってやってきたのです。
よほど、周囲の目を気にしていたのでしょう。
彼女はわざと「女」と第三者の目で自分を表現しています。

もしかしすると、彼女が書いたものではないのではないかという説もないことはないのです。
普通なら「私」はというところでしょう。
しかしそれが和泉式部の持つ鳥瞰的な視野だったのでしょう。
歌がここにも登場します。
伊勢の海女の塩焼き衣慣れてこそ人の恋しきことも知らるれ
敦道親王の「塩焼き衣」の言葉はどのような気持ちを告げようとしたものなのでしょうか。
彼女を想う心の激しい様子がみてとれます。
いけないと思いながら、奔放な恋に突き進んでしまうところが、和泉式部の魅力です。
敦道親王が亡くなった後の、喪に服している一年の間にこの日記は書かれたといわれています。
その時の彼女の気持ちはどんなものだったのでしょうか。
50歳の頃、最愛の娘だった小式部の内侍にも死なれています。
その後いくつまで生きたのかも、実はわかっていないのです。
この日記を読んでいると、中世の女性の生き方の典型を見る気がしてなりません。
ぜひ、あなたもこの本を手にとってみてください。
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。