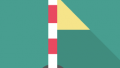神の眼
みなさん、こんにちは。
元都立高校国語科教師、すい喬です。
今回はめったにお目にかかれない小説をやります。
高校で習ったことがありますか。
横光利一の『蠅』という小説です。
名前を聞いたこともないという人が大半かもしれません。
この作品以外に横光利一の小説は教科書に載っていないのです。
今や、この小説も選択科目の「文学国語」の中に入っていればいいというレベルです。
新感覚派の作家といわれてもなんのことかわからないかもしれませんね。
文学史の中では大切な流れを築いた人たちです。

日本文学の一流派なのです。
1924年に創刊された同人誌『文藝時代』を母胎として登場した新進作家のグループを総称してそう呼んでいます。
彼らが登場するまで、日本の小説の大半は私小説と呼ばれるリアリズムが中心でした。
自分の周囲に起こった事件やできごとをそのまま題材にした内容のものが多かったのです。
それを徹底的に彼らは嫌いました。
周囲に取材するとしても、それを全く別の角度から描写する。
そこに新しい言葉の可能性を探るというのが主旨でした。
代表は川端康成です。
日本で最初にノーベル文学賞を獲得した作家です。
『伊豆の踊子』『雪国』などの代表作を読んだことがありますね。
教科書にも『伊豆の踊子』は載っています。
その彼と並び称されたのが横光利一なのです。
横光利一という作家
彼は、1898年生まれ福島県出身の小説家です
文藝春秋社を創設した作家、菊池寛を介して川端康成と出会い、2人は生涯に渡る友人となりました。
新感覚派の作家として活躍したのです。
『日輪』と『蠅』を同時に発表したことで文壇の注目を浴びました。
さらに『機械』が評論家、小林秀雄に絶賛され、次第に志賀直哉と並んで「小説の神様」と称されるようになったのです。
しかし今日、彼の小説を読む人はほとんどいません。
教科書に所収されているこの『蠅』という作品がなかったら、横光の名前はいずれ忘れ去られてしまうかもしれません。
全編は大変に短いものです。
青空文庫で読むことができます。

試みに一読してみてください。
小説の冒頭の部分をここに掲載します。
—————————–
真夏の宿場は空虚であった。
ただ眼の大きな一疋の蠅だけは、薄暗い厩の隅すみの蜘蛛の巣にひっかかると、後肢で網を跳ねつつ暫しばらくぶらぶらと揺れていた。
と、豆のようにぼたりと落ちた。
そうして、馬糞の重みに斜めに突き立っている藁の端から、裸体にされた馬の背中まで這い上あがった。
馬は一条の枯草を奥歯にひっ掛けたまま、猫背の老いた馭者の姿を捜している。
馭者は宿場の横の饅頭屋の店頭で、将棋を三番さして負け通した。
「何なに? 文句をいうな。もう一番じゃ。」
すると、廂を脱れた日の光は、彼の腰から、円い荷物のような猫背の上へ乗りかかって来た。
視線はどこに
いかがでしょうか。
古い内容の文章です。
風景があまりにも現代のそれとはかけ離れています。
しかしじっくりと読んでみると、不思議な味わいに引き込まれます。
視線はどこにあると思いましたか。
ズバリ蠅です。
正確にいえば、その上位にある第三者とでもいえるものです。
ここに新しい感覚の源があるともいえるでしょう。
あらすじは簡単です。
蜘蛛の巣に蝿が引っかかっています。
蝿は落ちて馬の背中までのぼり、そこでかろうじて生き続けています。
馬車を引く馭者は饅頭屋の前でのんびり将棋を指しています。

老婆は息子の危篤の知らせを受け取り、馬車を待っているのです。
しかし馭者はすぐに出発しようとはしません。
親子と若いカップルが順番待ちをしています。
老婆は息子が危篤だから馬車を出してくれと頼むものの、馭者は出そうとしません。
というのも彼は饅頭を食べてからでないと出発しないと決めていたのです。
まだ饅頭は蒸しあがっていませんでした。
やがてお腹が一杯になった馭者は眠くなります。
しかしそれを知っているのは蠅だけです。
それでもやっとのことで馬車は出発しました。
しかし崖に差しかかったところで車輪が道から外れてしまうというアクシデントに見舞われました。
河原に馬車が転落していきます。
人も馬も動きません。
蝿は一匹、その後青空に飛んでいったという話です。
不条理な世界
どんな感想を持ちましたか。
不条理といえば、そう言えないこともありません。
本当のところ語り手は誰なのかという問題も残ります。
確かに蠅の視線で書いてはありますが、もっとアングルをひけば世界をじっとみつめ続けている神の領域まで広げられます。
人間の生きざまは、まさにここに示されたようなものかもしれませんね。
やっと通常の暮らしに戻れると安心した途端に不慮の事故に出会うということはよくあることです。
視点が微妙に変更していくことでユニークな表情をみせる登場人物の横顔がみえます。
馬車の運転手は独身で、あまり清潔感を感じさせません。
農婦の老婆は危篤だという電報を受け取り、街へ行く馬車を夢中で探しています。
若者と娘は駆け落ちの途中なのでしょう。
互いの身を気遣っています。
重い荷物を持っており、追っ手がくるのが気がかりです。

男の子は無邪気に馬を見て喜んでいるだけです。
母親にあれこれと話しかけても母親は無関心なままです。
田舎紳士は大金を得たばかりで気分が高ぶっています。
とにかく懐の大金が心配で仕方がないのです。
お腹がいっぱいの馭者の居眠りが大事故の原因なのでしょうか。
突然、蒸し上がった饅頭にスポットライトがあたります。
それを食べなければ目は冴え冴えとしていたのかもしれません。
しかし饅頭を食べてから出発するのが彼の日課でした。
馬車の脱輪は人々の死に直結します。
誰もがそのわずか前の瞬間には事故も知らず、自分の死までも知らなかったのです。
命の意味をはるか高みで見ている第三者にとって、蠅も人も全く変わりはありません。
登場人物たちのやり取りが実に見事です。
会話が生きています。
5分で読めます。
僅かな時間の間に文学の深みにはまってしまうかもしれません。
最後までお付き合いいただきありがとうございました。