進学の機会
みなさん、こんにちは。
小論文添削歴20年の元都立高校国語科教師、すい喬です。
今回は教育格差の問題を取り上げましょう。
教育学部を受験する人にとっては絶対に避けて通ることのできない問題です。
経済学部でも学費の問題はよく出題されます。
進路選択は重要なテーマです。
将来の生き方に直結するからです。
このテーマは格差社会の問題と極めて密接な関係にあります。

貧困家庭に育った子供は学力や意欲があっても進学の機会に恵まれないと言われています。
その結果、職業選択の幅が狭まり、安定した職業につける可能性が低くなるのです。
フリーターや非正規雇用に甘んじる確率も上がります。
つまり貧困の再生産が起こるのです。
安定した職業につけないと、晩婚化、非婚化も起こり、出産を諦めたり出生数を抑える傾向が
増加します。
その結果、少子化現象が起こります。
国力が弱まっていくのは明らかです。
日本では教育の利益を受けるのは教育を受けた本人であることから、教育費は自己負担が当然であるという考え方が根強くあります。
国全体の方向としては経済成長があくまでも優先課題です。
したがって教育は個人の問題として捉えられがちです。

現在は公立の小中学校に加えて、高校の授業料も公立は無償、私立も公立と同額の補助がなされるようになりました。
その結果、教育の機会はかなり保証されているといえます。
しかし1990年代の半ば頃から1世帯あたりの所得はあまり伸びていません。
むしろ落ちているのです。
学校以外の学習費
学習塾などの補助学習費は高所得の家庭ほど増加傾向にあります。
所得の高い家の子供ほど、学校外で教育を受ける割合が高く、学力が高くなる傾向があると推測されます。
家庭の経済力が子供の学力に影響を与えているのです。
この事実は多くの人が見聞きしている現実と重なります。
有名大学などに進学する生徒の家庭はかなりの高所得層が多いです。
そうでないと受験するための学習費を捻出できません。
これは厳然たる事実です。
大学は依然として自己負担が基本です。
国立大学の学費は近年値上がりを続け、私立との差もそれほどになくなってきました。
かつては国立と私立の学費には6~7倍近い差がありました。
現在ではほぼ倍です。
奨学金に頼るという考え方もあります。
しかし日本の奨学金は返済を前提とする貸与型が中心です。
そのため、利息を含めた返済の負担が重くなる一方なのです。
さらにコロナ禍でアルバイトなども限定的なものになりつつあります。
ネット授業だけで満たされない時間がかさなる中、退学を真剣に考えている学生が多いという報道もありました。
卒業した時点で数百万円の借入金を背負ったまま、人生を生きていくのはあまりにも重すぎるのではないでしょうか。
教育に対する公的支援を推し進めるためには家庭の負担という考え方から、より社会全体で支えていく方向への変換が必要かもしれません。
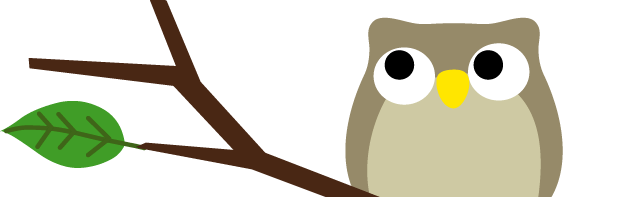
ここまで経済問題を中心とした問題をピックアップしてきました。
教育格差というテーマが出ると必ず親の所得の問題になります。
特に地方から都市の大学へ入学することは容易なことではありません。
親の仕送りも限界に来ています。
それだけに今回のコロナ禍がより深刻なダメージを与えたことは間違いがないのです。
ジェンダー格差
教育における格差の2つ目は性差の問題です。
教育には本来、性別による格差があってはなりません。
しかし現実に大学進学率を見た時、そこにはかなりの開きがあります。
一貫して男性の進学率の方が高いのです。
現在、男性が56%、女性が47%前後です。
高校進学率が男女ともにほぼ100%に近いことを考慮した時、大学進学率の差が気になります。
さらに大学院進学率は男性15%、女性6%。
ここにもジェンダー格差と呼んでいい現象があります。

かつて女性の進学は高校か短大までという時代がありました。
現在は4年制が中心になっています。
それでも世界全体からみると、女性の大学進学率は低いのです。
このことが女性の社会進出を遅らせているという見方もあります。
男性と互角に働く総合職ではなく一般職と呼ばれるアシスタント的な仕事に就く例が多いのです。
男女共同参画社会ということが言われてかなりの年数がたちました。
しかし現実は教育格差があり、それが就職への足枷にもなっています。
特にこの内容は女子大を受験する人はきちんと把握しておいてください。
女性問題との関わりの中で出題されるケースがかなりあります。
被害妄想のような文章ではダメです。
きちんと社会の構造を見抜いた文章を書く練習をしてください。
問題の具体例
ここでは教育格差を扱った課題文がどのように出題されたのかについてみてみましょう。
これが実際の問題です。
教育に関わる格差の問題を踏まえた上で、日本の公的な教育支出の在り方について書きなさい。社会に広く受け入れられるための方策について考えること。
ここではあくまでも経済的な問題としてスポットをあてるというのが主旨です。
逆にいえば、それ以外の論点をメインにしても高い評価は得られません。
何を主題にもってくればいいのか。
キーワードは何でしょうか。

「公的な教育支出のあり方」についてどのように考えればいいのか。
このあたりがメインです。
大学の学費を誰が出すのかという問題です。
教育は個人の問題として捉えていいのかということです。
日本には国民皆保険制度という健康保険システムがあります。
誰もが同じ条件の医療を決まった医療費で受けられます。
アメリカなども同じシステムを導入しようとしていますが、いまだにうまくいっていません。
個人の健康は自分で管理し守るという考え方です。
逆に大学へ入りたいという学生に対しては、高額の奨学金を無償で与えるということが行われています。
そのかわりに厳しい卒業判定が待っているのです。
ある意味、日本と真逆の発想だと言ってもいいかもしれません。
公的な教育費を無償にして教育をというシステムをどこまで実現できるのか。

経済成長がかつてのようではなくなった現在、コンセンサスをとるにはかなりの議論が必要なことはいうまでもありません。
しかし経済の格差が学力の格差を生むという負のスパイラルが許されるものではありません。
どこにそのための分水嶺をひけばいいのか。
難しい問題です。
自分自身の問題として学費と学業の関係をじっくり考えてみてください。
このテーマは特に今年のコロナ禍とからめて出題される可能性があります。
アルバイトに依存してまで都会で暮らし、大学を出ることにどれほどのメリットがあるのか。
企業の人事制度や就職システムなどを含めて考えなくてはならないことが、山ほどあるような気がします。
真剣に取り組んでみてください。
最後までお読みくださりありがとうございました。


