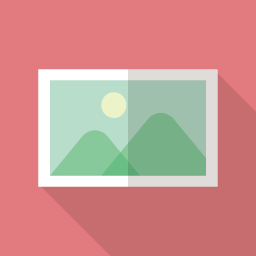何を提示するための小論文なのか
みなさん、こんにちは。
小論文添削歴20年の元都立高校国語科教師、すい喬です。
毎日苦しいですね。
勉強は予定通りになんか、とても進むもんじゃないです。
いくつもの教科をやらなくてはならないし、そのための時間も十分にありません。
学校の勉強と受験と、全くどうしたもんでしょう。
少しは息抜きをしないと、ほんとにくたびれちゃいます。
しかし考えてみれば、全て自分のためです。
将来の夢をかなえるために、今頑張っているのだと思えば、少しは我慢もできるというもの。
だからこその勉強なのです。
それにしても、小論文は難しいです。
文の構成については、あちこちに書きました。

qimono / Pixabay
まだ読んでいない人はこちらのサイトも覗いてみてください。

一番のボイントは文章の順序です。
意見提示
展開
結論
この4段階を正確に進めてください。
そうするだけで、きちんとした小論文になります。
一番最初に書くべきことを忘れてはいけません。
突然、自分の意見なんか書かれたら、採点者は戸惑うだけです。
ちゃんと進むべき方法を守ってください。
最初はなんですか。
そうです。
書き出しです。
別名、問題提起。
ここを正確にまとめないと、なんのためにこの文章があるのかということがわかりません。
いわば顔の輪郭です。
問題の本質は何か
問題提起の役割は全体の文の方向性を示すことです。
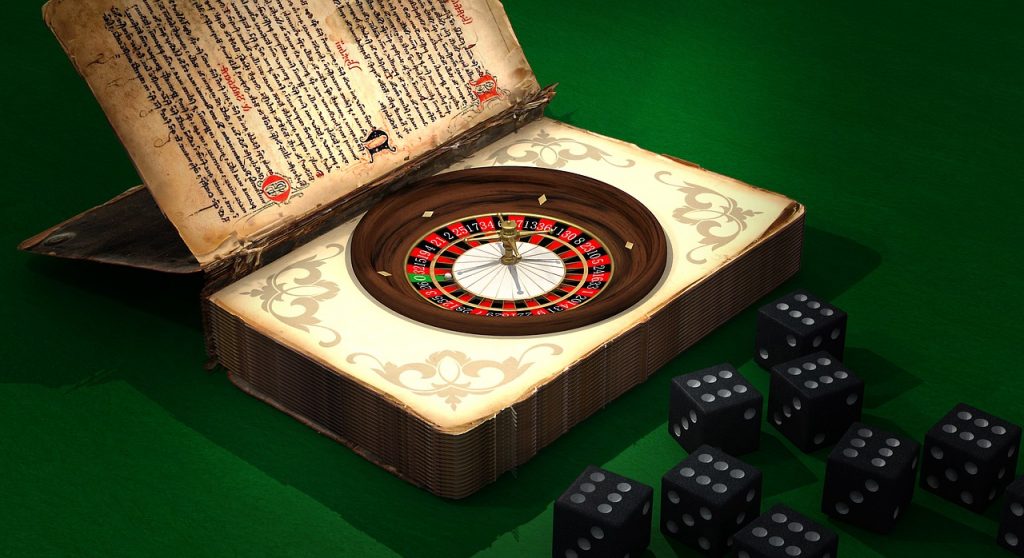
PIRO4D / Pixabay
文章がどちらに向いているのかを正確に提示しなければなりません。
ポイントは次の2つです。
どのよう意図と順序で書くのか
この2つを正確に提示することが大切です。
これがきちんとできると、その次の段階に進めます。
すなわち
その理由はどのようなものか
ということになります。
つまり次の最も大切な意見提示に向かっての水先案内の役割を果たすのです。
もしこの部分がないと、どうしてこの文章を書いたのかという目的がみえなくなります。
採点者はそれを後の文の中から探りながら読むという手間をかけなければなりません。
その分だけ、評価が下がるということになるのです。
例
二酸化炭素の排出量が加速度的に増加し、そのことによって世界の気温が確実に上昇している。
地球の砂漠化が食料の危機を招き、漁業においても潮流の温度変化により、漁獲量が目減りしている。
食生活への影響は誠に深刻である。
世界は手をこまねいてこの現状を憂えていればいいのだろうか。
全地球的に今後考え得る地球温暖化への影響をどう低減させればいいのか。
自分がどの論点からこの問題に切り込むのかということを明確にしながら、文章を構成しなくてはなりません。
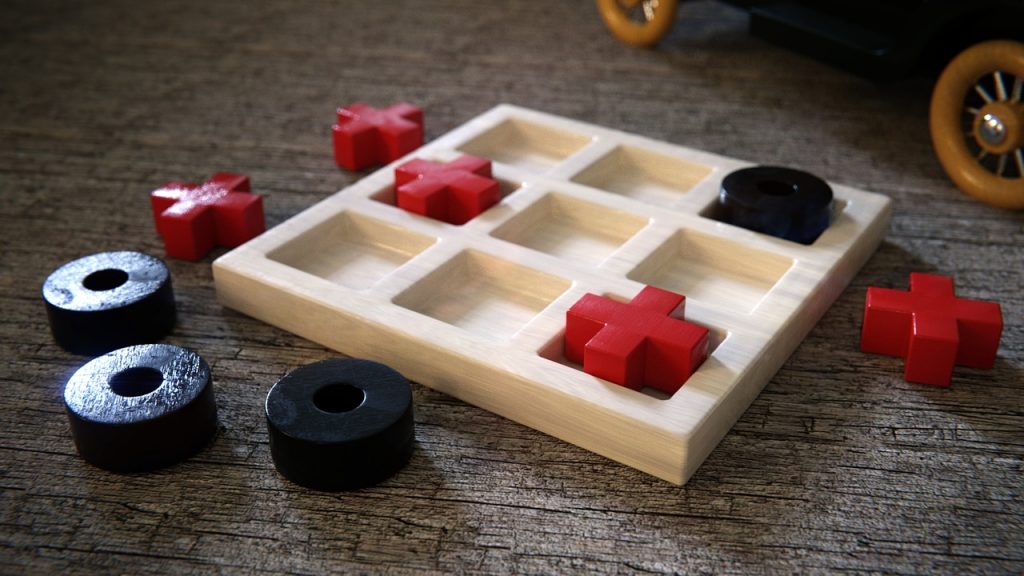
Aenigmatis-3D / Pixabay
ここにあげた例に関していえば、正面から課題文の内容に対して否定するというのは難しいでしょう。
だからこそ、ある程度筆者の立場を了解した上にたって、さらに内容を深めていくという方法をとればいいのではないでしょうか。
もちろん、ただ意見を繰り返すというのではなく、課題文にあった世界の気温上昇と砂漠化、潮流の温度変化といった別の面からのテーマを補いつつ、論じていくという方向が考えられます。
問題意識の説明をていねいに
書き出しでは何が問題なのかということをきちんと認識してから書き出しますよというメッセージを発信することが大切です。
一番ダメなのが次のパターンです。
自分の個人的な興味関心で、文章をなんとかまとめたというもの。
よく理解していないが、とにかく試験の制限字数を埋めたもの。
最後まで読んで、このパターンだと採点者としては悲しくなります。
しかし実は書き出しの部分にもうその予兆は出ているのです。
つまり問題点がなんであるのか不明なものが多いのです。
何を書こうとしているのかが見えてこないので、それほどの評価を与えられないということになります。
着眼点がアイマイなのです。

Wokandapix / Pixabay
着眼点が大切な理由は何でしょうか。
それがきちんと書き出しの中に出てくれば、それだけで文章は前へ進みます。
すなわち、結論まで一本の道が見えているということになるわけです。
ではどのように書けばわかりやすくなるのでしょうか。
あまり難しく考えすぎ、ここで躓いてしまったのであまりにももったいないです。
どうしてもひらめかずに先へ進みたい時は、一定の型に押し込めるしかないでしょう。
最初に課題文の主張を簡単にまとめます。
次に課題文の筆者は「~と主張しているが、それは本当に正しいのであろうか」と文を繋げます。
これだけではあまりにも単純なので、「新聞では~のような報道がよくなされている」と少し具体的な内容を入れ込むというのも1つの方法です。
あるいは「ある本によれば」と言いながら、その本のタイトルを示しつつ、自分なりの理解をしているということを相手にアピールするというやり方もあります。
客観的な事実をあげてから、これらのことは許されるのであろうかとか、こうしたことが認められる素地はどこにあるのかなどという書き出しでの言い回しを使うこともできます。
曖昧な内容の時は、その説明を入れるのも1つの有効な方法です。
いずれにしてもここにあげたような形にまず持っていくことが基本だと考えてください。
もう少し書けるようだったら、ここで課題文への理解を示し、自分の意見の元となる考え方を述べるということもできます。
ただしあまり長くしてはいけません。
全体の字数の10~15%程度で押さえてください。
書き出しの基本パターン
問題提起なしの文は絶対にNGです。
小論文に馴れていない人ほど、ここをカットしてしまいます。
そういうものが必要だということを知らないのです。
絶対に書き込むことです。
どういう視点から取り組むのか。
何を前提の意見とするのか。
そのために何を書こうとしているのか。

qimono / Pixabay
「~であること」が必要であるといったん書きましょう。
それだけで十分ではないとしたら、ではその他に何が必要なのかを示します。
他に何があれば十分なのかということまでは最初に全部語らなくてもいいです。
字数の関係があるので、その前でとめることも可能です。
しかしその後の意見提示や展開のところで十分に論点を整理してください。
採点者は皆さんの伸びしろをみたいのです。
課題文の問題からどの程度の広がりをもたせて論じることができたのか。
知識の量、想像力、論理展開力のそれぞれを計りたいのです。
骨子は決まった、よし書こうと思っても、どこかで腰砕けになりそうなところがあるとすれば、まだ論理の整合性がないということになります。
自分で違和感を感じるような文章の運びは避けなければなりません。
とにかく練習してください。
書き続けてください。
必ずうまくなります。
先生に見てもらいましょう。
最初は恥ずかしいかもしれません。
しかしあなたが真剣であれば、先生は必ず引き受けてくれます。
繰り返して書いてみてください。
過去問を必ず数年分はやること。
合格の日が来るのを夢見て頑張ってくださいね。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。