 ノート
ノート 「高村薫」日本が崩れていく現実を冷徹に見て取った作家の目「反論不能」
作家高村薫の冷徹な目で今の日本をみると、どう見えるのか。あまりにも杜撰なシステム管理と未来を見抜く目を持たない日本人。それでいて妙にぬるま湯のような平和の中で静かに暮らしている。この先、この国はどこへいくのか。
 ノート
ノート  本
本 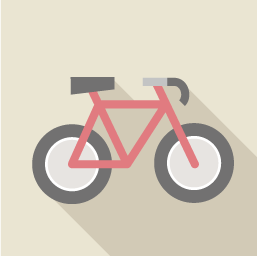 学び
学び 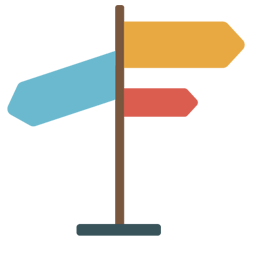 本
本  学び
学び 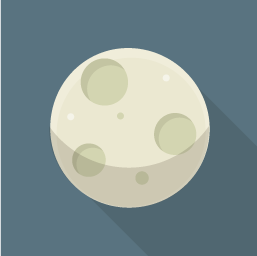 本
本  本
本  本
本 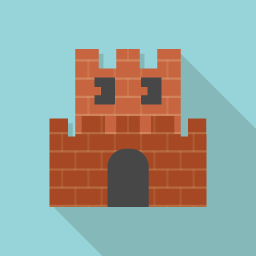 学び
学び 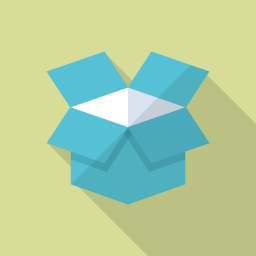 小論文
小論文  学び
学び  学び
学び  ノート
ノート  小論文
小論文  小論文
小論文  ノート
ノート