漫罵
みなさん、こんにちは。
元都立高校国語科教師、すい喬です。
今回は日本の開国にあたって、文化の移入がどのような行われたかについて考えます。
北村透谷(とうこく)という作家の名前をご存知でしょうか。
明治初期に文芸評論や詩作などの活動を行った人です。
近代的な彼の文章は、島崎藤村などに大きな影響を与えました。
その透谷が書いた文章を読んでみることにします。
「論理国語」の教科書に所収されているものです。
難しいタイトルですね。
「漫罵」(まんば)という言葉の意味がわかりますか。
ぼくは授業で扱った記憶がありません。

おそらく他にやらなければならない教材がたくさんあったので、割愛したのでしょう。
明治の擬古文です。
それでなくても生徒は古文に対するアレルギーが強いので、厄介な文章は森鴎外の『舞姫』にとどめたというのが実情でした。
「漫罵」とは、相手をののしること意味します。
なぜこのようなタイトルにしたのか。
この文章は、北村透谷が短い文学的人生の最後に書いた評論の1つです。
明治26年10月30日に、雑誌「文学界」に発表されました。
彼はこの罵倒の言葉を残して、自死をはかりました。
1度は未遂に終ったものの、最後は自宅の庭で縊死したのです。
25歳という若さでした。
「漫罵」には、透谷の焦燥感と悲愴感が強く出ています。
全体に激しい文面で、事実上の遺言といってもいい内容です。
現代との接点
透谷は何を告げようとしたのか。
この文章が教科書に所収されている理由は何であるのか。
現代語訳をまじえながら、現代との接点を探ってみます。
じっくりと深堀りして読んでみると、そこには現代の状況につながる共通点があると考えられます。
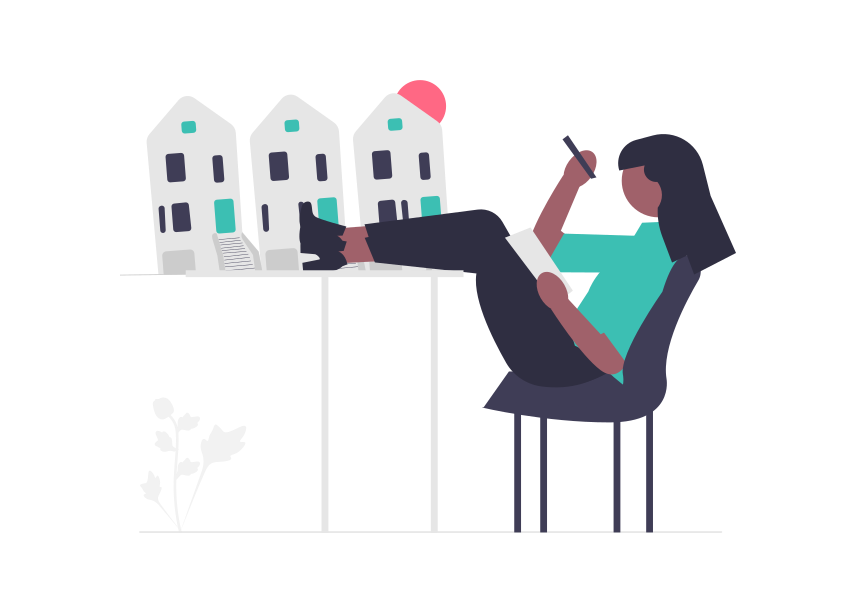
文章は語り手である筆者が、銀座の木挽町にある橋の上から町を眺めるところから始まります。
すると詩ができそうだと思ってはみるものの、すぐに風景の無節操さによって詩興が壊されてしまうのです。
その後、思いを文章にして吐き出そうとします。
憤りを込めて世間を罵倒しようとしたのです。
全文はそれほど長いものではありません。
これを彼の遺書と考えると、そこに1つの考えが浮かんできます。
内容をじっくりと読んてみてください。
本文
一夕友とともに歩して銀街を過ぎ、木挽町に入らんとす、第二橋辺に至れば都城の繁熱やうやく薄らぎ、家々の燭影水に落ちて、はじめて詩興生ず。
われ橋上に立つて友を顧み、同に岸上の建家を品す。
あるは白堊を塗するあり、あるは赤瓦を積むもあり、洋風あり、国風あり、
あるは半洋、あるは局部に於て洋、あるは全く洋風にしてしかして局部のみ国風を存するあり。
さらに路上の人を観るに、あるは和服、あるは洋服、フロックあり、背広あり、紋付あり、前垂あり。
持つものを見るに、ステッキあり、洋傘あり、風呂敷あり、カバンあり。
ここにおいて、われ憮然として嘆ず、今の時代に沈厳高調なる詩歌なきはこれをもつてにあらずや。
今の時代は物質的の革命によりて、その精神を奪はれつつあるなり。
その革命は内部において相容れざる分子の撞突より来たりしにあらず。
外部の刺激に動かされて来たりしものなり。
革命にあらず、移動なり。
人心自ら持重するところあるあたはず、知らず識らずこの移動の激浪に投じて、自から殺さざるものまれなり。
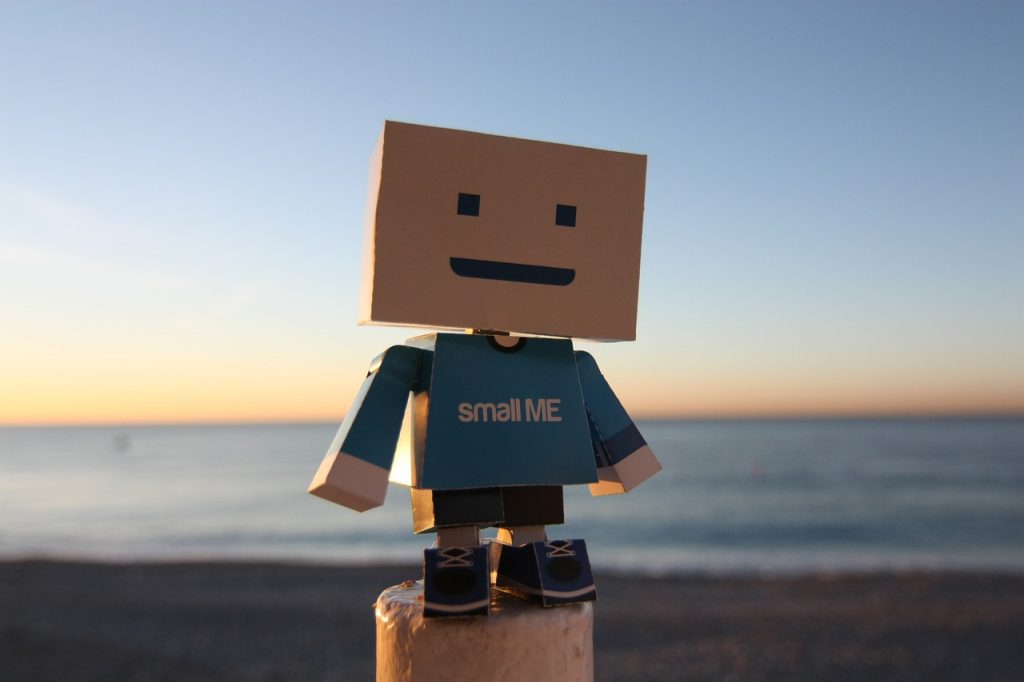
その本来の道義は薄弱にして、もつて彼等を縛するに足らず、その新来の道義は根蔕を生ずるに至らず、以て彼等を制するに堪へず。
その事業その社交、その会話その言語、ことごとく移動の時代を証せざるものなし。
かくのごとくにして国民の精神はよくその発露者なる詩人を通じて、文字の上にあらはれ出でんや。(中略)
今の時代に創造的思想の欠乏せるは、思想家の罪にあらず、時代の罪なり。
物質的革命に急なるの時、いずくんぞ高尚なる思弁に耳を傾くるの暇あらんや。
いずくんぞ幽美なる想像にふけるの暇あらんや。
彼等は哲学をもつて懶眠の具となせり、彼等は詩歌を以て消閑の器となせり。
彼等が眼は舞台の華美にあらざれば奪ふことあたはず。
彼等が耳は卑猥なる音楽にあらざれば娯楽せしむることあたはず。
彼等が脳膸は奇異を旨とする探偵小説にあらざればもつて慰藉を与ふることなし。(中略)
彼等は詩歌なきの民なり。
文字を求むれども、詩歌を求めざるなり。
現代語訳
夕方、友と一緒に銀座を過ぎ、木挽町に向かいました。
第二橋あたりまで来ると、にぎやかな都会の喧噪も静まり、家々の灯りが川の水面に映って、はじめて詩情がわきおこるのを感じたのです。
私は橋の上に立って、友を振り返り、一緒になって川べりの家々を眺めてそれらを見比べました。
白亜の壁、煉瓦の家、洋風、和風、あるいは和洋折衷、和風の中に一部だけ洋風、あるいはその逆もあり、実にさまざまです。
さらに道行く人を見れば、和服、洋装、フロックコート、背広に紋付、前掛け姿もいます。
手にするのはステッキ、洋傘、鞄に風呂敷など。
ここまで眺めて、私は落胆して嘆きました。
今の世に厳めしく高尚な詩歌が見当たらないのはこのためでなのでしょう。
今の世は即物主義の西洋化に心奪われていますが、それは日本の内的精神の葛藤にもたらされたものではありません。
外的作用によるもので、心中に革命があった訳ではないのです。

伝播に過ぎません。
自重した訳でもなく、知らぬうちに流れ込んできた文化の激流にさらわれただけで、自ら封じ込めたものはわずかです。
本来の道義的事由が希薄だから、新しく導入されたものも根付かず、
言葉も会話もすべてが上滑り、このありさまはみな、国民の精神性を顕す詩人を通じて言語化されています。
声を大にして問うても、誰も耳を傾けようとしません。
国としてひとつになり、国民として同じ理想を持ち、人種として同じ意志を持とうともしません。
のんべんだらりと日々を過ごせれば、それでいいのです。
思想を渇望する者などはいません。
今の世に創造的な思想が欠けているのは思想家の責任ではなく、時代の責任です。
即物主義が席捲するときに、高尚な弁舌に耳を傾け、幽美な想像にふける者がいるでしょうか。
哲学も詩歌も無用の長物、舞台も音楽も娯楽性が第一、小説は面白いものでなければ売れません。
詩歌などは無意味です。
文字を必要とするのは詩歌のためではないのです。
根本的な問題
北村透谷は何度も嘆いています。
「漫罵」には、透谷の焦燥感と悲愴感しかないといってもいいでしょう。
彼は何に憤っていたのか。
日本という国の持つ根本的な問題がそこにはあります。
これは夏目漱石の有名な評論「現代日本の開化」とも通じる大きな問題です。
明治維新から近代化を急速に遂げようとした日本は、西洋列強の文化を慌てて取り込もうとしました。
その結果、「洋風」の取り込みのために、己れの精神の根本を見据えることを忘れてしまったというのです。
「今の時代は物質的の革命によりて、その精神を奪はれつゝあるなり。
その革命は内部に於て相容れざる分子の撞突より来りしにあらず。外部の刺激に動かされて来りしものなり」と述べています。
日本の開化は内からの革命ではなく、移動でしかないという認識を持っていました。
新奇なものを西洋から次々と持ってくるだけの、文明開化だと考えたのでしょう。

内側から必要に応じてなされた革命ではありません。
それだけに付け焼刃の持つ危うさを、心の底から感じたものと思われます。
時代の精神に入り込もうとしない文学者の群れに対して、激しい憤りを感じていたのです
内発的な要素などはどこにもありません。
新しい思想だといって飛びつき、すぐに飽きてしまう。
もしかすると、この流れは現代にも繋がっているのかもしれません。
彼は詩人でした。
それだけにこの時代に生まれたことの不運を呪ってもいるのです。
芸術を解する人間も、芸術を論じる人間も、評価できる人間も、もはやこの国のどこにもいないと断じています。
詩論を語るものや詩歌をうたう者は、詩で身を立てることなどをあきらめなさい。
帰って、店先に立って普通に働けばそれでいいのだと最後に呟いています。
読んでいるだけで胸が痛くなりますね。
しかし現代にもこの嘆きは通用するのではないでしょうか。
そんな気がしてならないのです。
あなたはどう考えますか。
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。


