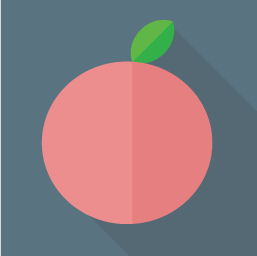信州に上医あり
みなさん、こんにちは。
ブロガーのすい喬です。
南木佳士がかなり前に書いた岩波新書『信州に上医あり』を再読しました。
なんとなく本棚から手にとったのです。
出会いはいつも偶然の重なりから始まります。
ご存知ですか。
地味な作家です。
しかし確実な文体で自分の世界を築き上げていった人ですね。
彼には芥川賞をとった『ダイヤモンドダスト』や『山中静夫氏の尊厳死』といった大変いい作品があります。
『阿弥陀堂だより』も好きです。
けっして浮わついたところがありません。
医者をしながら小説を書くというのは、大変なことだったろうと思います。
その中でこの新書に収められたルポは少し異質のものと言えるかもしれません。
かつて何の気なしに読んで、いい作品だなと思いました。

今度読み返してみて、やはりここに登場する佐久総合病院の院長、若月俊一さんの存在の重みを感じました。
同時に、彼を心の底から敬愛している彼がいたから、上梓できた本だという気もしたのです。
若月院長の横顔についてはこの新書を読んでもらえばわかるはずです。
一言でいえば波乱に満ちた人生といえるでしょう。
裕福な少年時代から一転しての貧窮生活。
東大医学部を卒業した後、共産党運動に身を投じようとする直前に転向しました。
その後アカという烙印をおされたまま、治安維持法で1年間の牢獄生活を余儀なくされます。
大学在学中も1年間停学処分になっています。
卒業後、どこの医局でも拾ってもらえず、偶然分院の助教授の世話になり、それが元で外科を学ぶことになりました。
佐久の診療所
その後戦争が激化。
彼は佐久平にある小さな診療所へ疎開していきます。
そこで若月医師がみたものは、疲弊した貧しい農民でした。
満足に医者にかかれない彼らに、何がしてあげられるのかと悩みました。
それが佐久総合病院への道の入り口です。
南木佳士の筆はけっして踊っていません。
じっと若月という人間の日向と陰を見つめ続けます。
清濁あわせのむロマンチストの横顔と、経営者の側面を捉え続けました。
どうして自分が若月医師のいる病院へきたのか。
これが南木佳士の原点です。
最初のところから自分自身を見つめ直そうとしている点が、とても新鮮です。
医療は現在、予防医学から先端の専門医学へと変化しつつある時代です。
その中で最初に佐久総合病院へ志願してきた医者と現在のように何もかもがそろっている状態で、日々診療にあたっている医者とは意識がまるで異なっています。

ある意味当然のことでしょうね。
200人近い医師相互の関係も現在は希薄になりつつあるといいます。
その中で日々仕事をしている自己の内面を凝視する目は確かです。
若月という人間の大きさを素直に描いている点にも共感できます。
若月俊一医師は赤ひげ先生などではありません。
いつも最後には腰を低くして、若い医者に酒をついでまわった、ただの人間なのです。
この新書は若月という希有な信州の上医を描きながら、実は南木佳士という人間の内面を描いたという側面も持ち合わせているのです。
そこがまたこのルポの斬新な所以でしょう。
もしよかったら1度読んでみてください。
今は全てをお金に換算する世の中です。
成績がよければ安定収入のある医者になれという時代です。
一生生活に苦労することはないからといったような風潮もあります。
そういう外野の声を聞きながら、日々診療にあたり、小説を書く作家の内面は複雑です。
定年後
彼は数年前、信州の佐久総合病院を定年退職しました。
非常勤医になったのです。
元々、精神を病んでうつ病を経験しました。
そこから生と死をテーマにした作品が多く書かれたのです。
そのあたりのことはエッセイの中にも記されています。
少しだけ読んでみましょう。
————————
芥川賞受賞の翌年、三十七歳でパニック症を発病し、やがてうつ病の泥沼にはまり、臨床の現場はもちろん、作家の表舞台からも降りざるをえない事態に陥った。
末期がん患者さんの診療をおこないつつ文芸誌に小説を発表し続ける行為は、いまふり返れば、おのれの技術、体力の限界を無視して北アルプスの険悪な岩稜地帯に足を踏み入れ、根拠なき楽観にそそのかされて歩いていただけであり、滑落事故はあらかじめ予想されていた喜劇でしかなかったのだとわかる。

病院の健康診断部門にまわしてもらい、なんとか生きのびた。
山を歩いたり、プールで泳いだり、それまでまったく無視してきたからだの手入れを始めてようやく元気になった。
年間13000人以上の受診者を受け入れる人間ドック科責任者の立場で、40年勤続の定年退職を迎えられたのはまさに奇跡であった。
自裁の手段を考えない日はないほどに追いつめられ、周囲から、あいつはもうだめだ、とみなされることでかろうじて生きのびられた皮肉な存在である「わたし」を常に忘れない。
————————–
一文が長く重いです。
今風のライトノベルとは全く違うということもよくわかるはずです。
小屋を燃す
近年の作品には『小屋を燃す』があります。
書かなければ自死してしまう可能性があった若い日を潜り抜け、今は静かな環境にいるようです。
非常勤で仕事をしているのがごく自然なのでしょう。
私小説の短編連作です。
定年退職をした医師のその後の様子を描いています。
「畔を歩く」「小屋を造る」「四股を踏む」「小屋を燃やす」の4篇がそれです。
年齢を重ねたことで現在と過去との時間が、次第に重層的に描かれていきます。
医者はつねに死者と隣り合わせです。
何人の患者を看取ったことか。
末期のがん患者もたくさん見てきました。
自分自身が鬱病になり、苦しんだのです。
退職後の様子も描かれています。

釣りをしたり、山に登ったり。
小さな小屋を造り、そこで酒を酌み交わす日々が至福の時間でした。
仲間が次第に減っていきます。
生きることも死ぬことも全ては繋がっているという実感が作品の底を流れています。
どこまでが現実で、どこからが幻想なのか。
それさえも見極められなくなるのです。
もしよかったら、手にとってみてください。
けっして明るい小説ではありません。
しかしここに人の命の真実があるような気がしてならないのです。
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。