漢字とひらがな
みなさん、こんにちは。
元都立高校国語科教師、すい喬です。
今回はひらがなと漢字の使い分けについて考えてみましょう。
近年は文章を書く機会が非常に増えています。
さまざまなレポートや報告文だけでなく、日常的にものを書く風景がよく見られます。
パソコンやスマホの普及も一役買っているに違いありません。
そのときに一番悩むのは、この問題です。
漢字とひらがなのどちらを書けばいいのか。
自分ではきちんとやっているつもりなのに、どことなく落ち着かない。
文章が全体に黒っぽくみえる。
どうしても漢字が多い文章になってしまう。
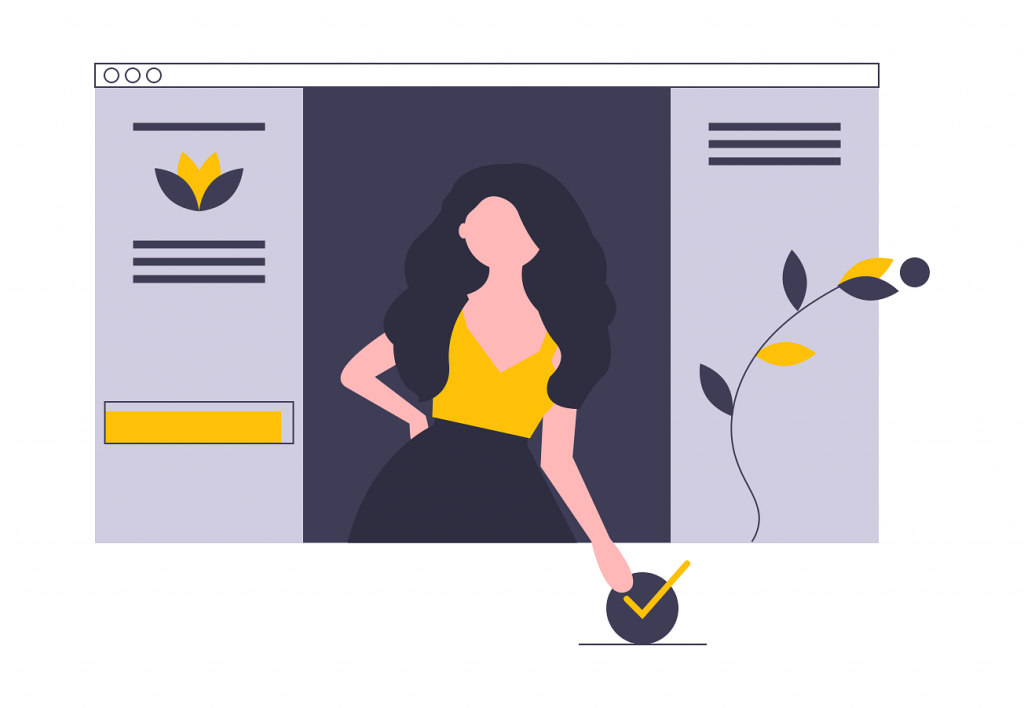
癖がなかなかなおらない。
使い分けの原則はどうなっているのか。
ぜひ知りたいところですね。
この際、きちんと覚えたいと考えている人は多いはずです。
漢字とひらがなの使い方については、完全にこれが間違いだということはないです。
それだけにかえって厄介で困ります。
つまり、どう書いても読めてしまう。
しかしなんとなく今の時代の文章の書き方とは違うような気がする。
多くの人がこの問題に直面しています。
ぼくは今までに記事を1500本以上書いてきました。
その間も随分と悩みました。
今回はそのための基本的な方法を解説したいと思います。
基本テクニック
ポイントは次の7つにまとめられます。
これだけ理解できれば、もう完璧です。
しかし文法用語を理解するのは大変ですね。
1.常用外漢字はひらがなに
2.形式名詞はひらがなに
3.接続詞はひらがなに
4.補助動詞はひらがなに
5.一部の動詞はひらがなに
6.副助詞はひらがなに
7.副詞はひらがなに
これだけです。
この内容をもう少しわかりやすくお知らせしましょう。
最近の傾向は漢字よりもひらがなをうまく使うという流れが主流です。
以前ならば漢字で書いた言葉も今はひらがながメインなのです。
その代表が3番にある接続詞の扱いでしょうか。
接続詞は文と文をつなげる役割を果たします。
とても大切なだけに、頻繁に登場してきます。
少し高齢の方が書いた文章を、読みにくいと感じることはありませんか。
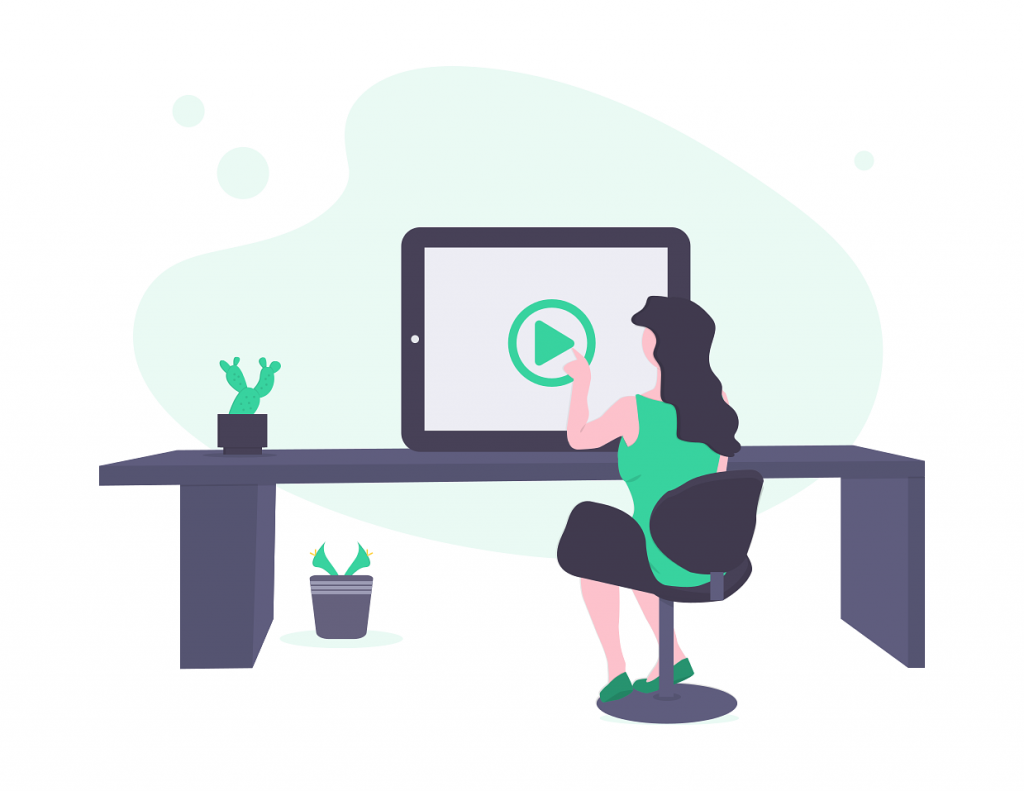
その理由の大半はこの接続詞にあります。
これからは基本的にひらがなで表記するようにしましょう。
接続詞を漢字で書くと、どうしても読みにくくなります。
ここにあげたサンプルを参考にしてください。
意識して書き直せば、それだけで十分に読みやすい文章になります。
あるいは 或いは
かつ 且つ
さらに 更に
しかし 然し
したがって 従って
ただし 但し
ついては 就いては
なお 尚
また 又
ゆえに 故に
よって 因って
どうでしょうか。
今まで、当たり前のように漢字で書いていたということはありませんか。
本当にこれだけでも読んだ時の印象がずいぶん違います。
表記ゆれを避ける
表記ゆれとは同じ意味を持つ言葉について、表記が混在している状態を指します。
例えば「引っ越し」「引越し」「引越」など。
これを避けるためにいい方法があります。
それは自分のスタイルを早くつくりあげてしまうことです。
よく使う語句については、自分なりのルールを決めてください。
使い分けについては、これが誤りという厳格なものはありません。
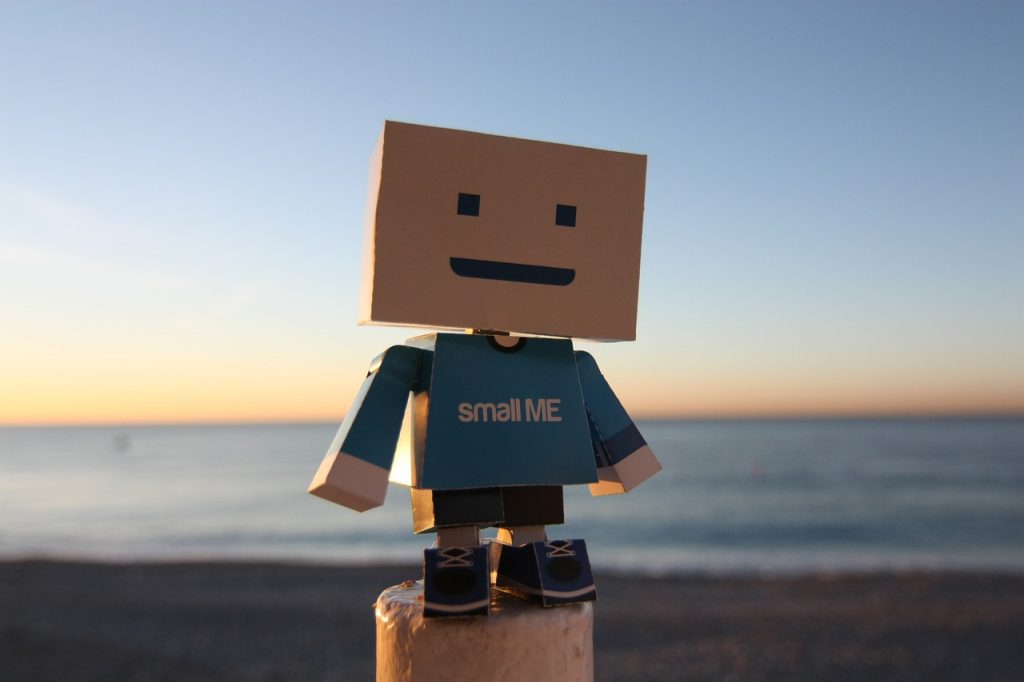
それだけに自分のルールをキープすることが大切なのです。
文章内の漢字とひらがなの割合は「漢字30%、ひらがな70%」が読みやすいと言われています。
最近は特にPCで文章を入力するケースが多いです。
機械は確かに便利です。
どのような言葉も漢字にしてくれますからね。
ところがそこに問題があるのです。
漢字変換が多くなりすぎるという弊害があります。
必然的に文章が硬くなってしまうのです。
バランスが命だと認識しておいてください。
常用外の漢字はひらがなに
接続詞はひらがなを覚えたら、次は常用外の漢字をひらがなで書くことを意識してください。
常用漢字という言葉をご存知ですね。
常用漢字とは法令や公用文書、新聞、雑誌、放送など、一般の社会生活で現代の国語を書き表す際に使用される漢字の目安です。
内閣告示の「常用漢字表」に掲載されています
迷ったら文化庁のWebサイトで確認するのも1つの方法です。
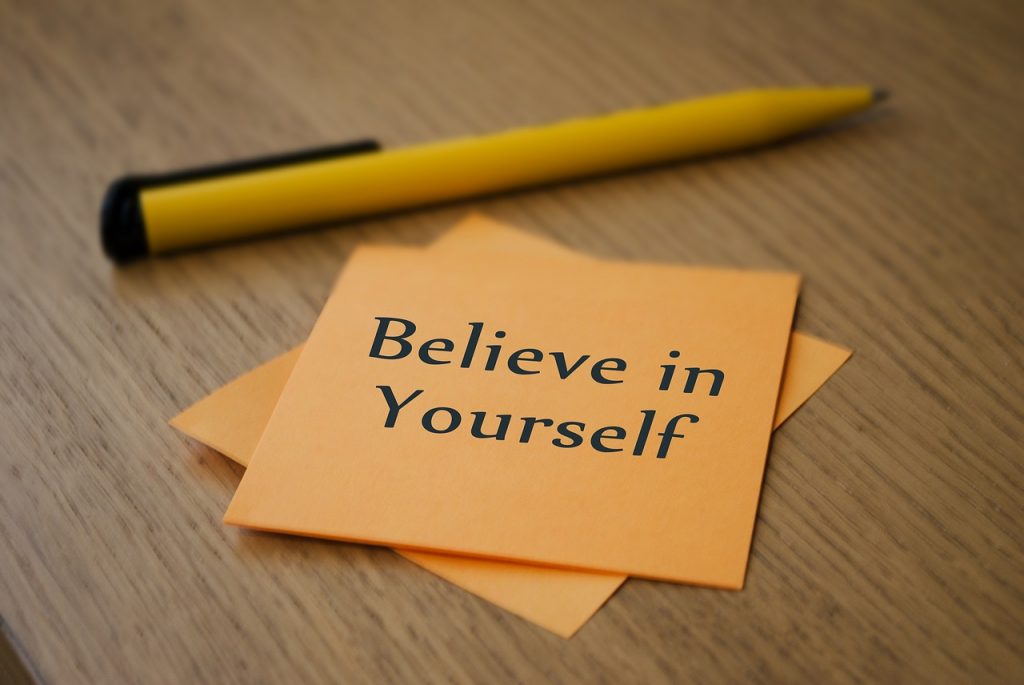
ちょっと難しいなと感じたら、常用漢字でないケースがほとんどです。
しかしこの言葉はどうしても漢字で書きたいというこだわりも当然あるでしょう。
その時こそ、自分ルールが必要なのです。
作家の文章などを読んでいると、女性の方がひらがなを使っているケースが多いように感じます。
柔らかな印象を持たせたいと考えているからでしょうか。
どうしてもこれは漢字で書くと決めたら、そのルールを続けてください。
形式名詞はひらがなに
形式名詞とは、「こと」「もの」「とき」など、実質的な意味を持たない名詞のことです。
この言葉の表記については、個人でかなりの差があります。
しかし高齢の方の文章によくみられる硬さはここからくることも多いです。
ぜひ、ひらがなにすることの意味を把握してください。
「楽しい時」と書いても「楽しいとき」と書いても同じだと感じる人もいるでしょう。

しかし現代の流れは確実に「楽しいとき」に軍配があがります。
以下、ひらがなで書く形式名詞の一例です。
もの 物
こと 事
とき 時
ため 為
ところ 所
うち 内
わけ 訳
はず 筈
ほう 方
とおり 通り
うえ 上
たび 度
よう 様
この表現を漢字からひらがなにするだけで、ガラリと文章の印象がかわります。
試しに文章を打って、ブリントアウトしてみてください。
ひらがなのもつ柔らかさが実感できます。
補助動詞と副詞はひらがなに
「買ってくる」という言葉の「くる」には意味がありません。
これを補助動詞と言います。
補助動詞は使用頻度が高いのです。
漢字で全て書こうとすると漢字の割合が急に増えてしまいます。
それを避けるために、基本的にひらがなで表記するのが望ましいのです。
いく 行く
くる 来る
みる 見る
いたします 致します
いただく 頂く
ください 下さい
さらに副詞は、名詞以外の語句をより詳しく説明する役割を持ちます。
「既に」「全く」「次第に」など、漢字で書かれることもありますが、一般的にはひらがなで表記することが多いです。
あまりに 余りに
いたって 至って
いったん 一旦
いまだに 未だに
おそらく 恐らく
しだいに 次第に
しばらく 暫く
ずいぶん 随分
すでに 既に
ともに 共に
ほとんど 殆ど
まったく 全く
もっとも 最も
わずか 僅か
細かな点を追いかけていくと、様々なケースのあることがよくわかります。
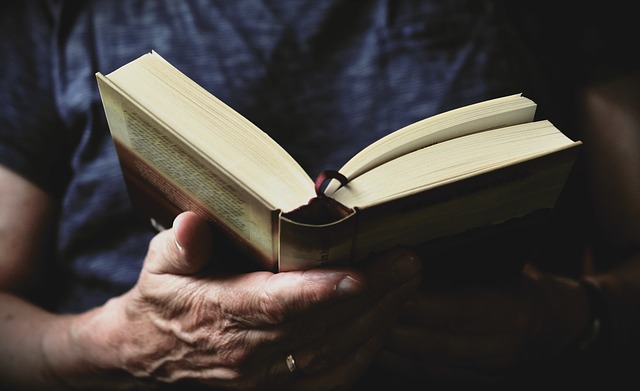
ポイントは自分ルールの確認です。
それも勝手に決めてしまうのではなく、ある意味、美意識との葛藤で決定することをお勧めします。
そんなに大袈裟なものではないという人もいるかもしれません。
しかしこれはそう単純な話ではないのです。
言葉というのは、その人の世界観そのものだといってもいいのです。
作家の中にもいまだに旧かなで文章を書いている人もいます。
表現の美しさや形に特有な力があると考えるのが普通です。
今回も最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。


