模倣となぞり
みなさん、こんにちは。
元都立高校国語科教師、すい喬です。
今回は伝統芸能の奥に秘められた継承の秘密に迫ります。
新学習指導要領にのっとった「論理国語」の教科書には、様々な文章が所収されています。
時には今まで考えたこともない、ユニークなエッセイも載っているのです。
今回の文章は尼ケ崎彬氏のものです。
日本の伝統芸能についての批評文を、たくさん著している美学者の1人です。
何気なく読んでいるうちに、ついひきこまれてしまいました。
特に伝統的な芸術や芸能がどのように引き継がれてきたのか、という内容は面白かったです。
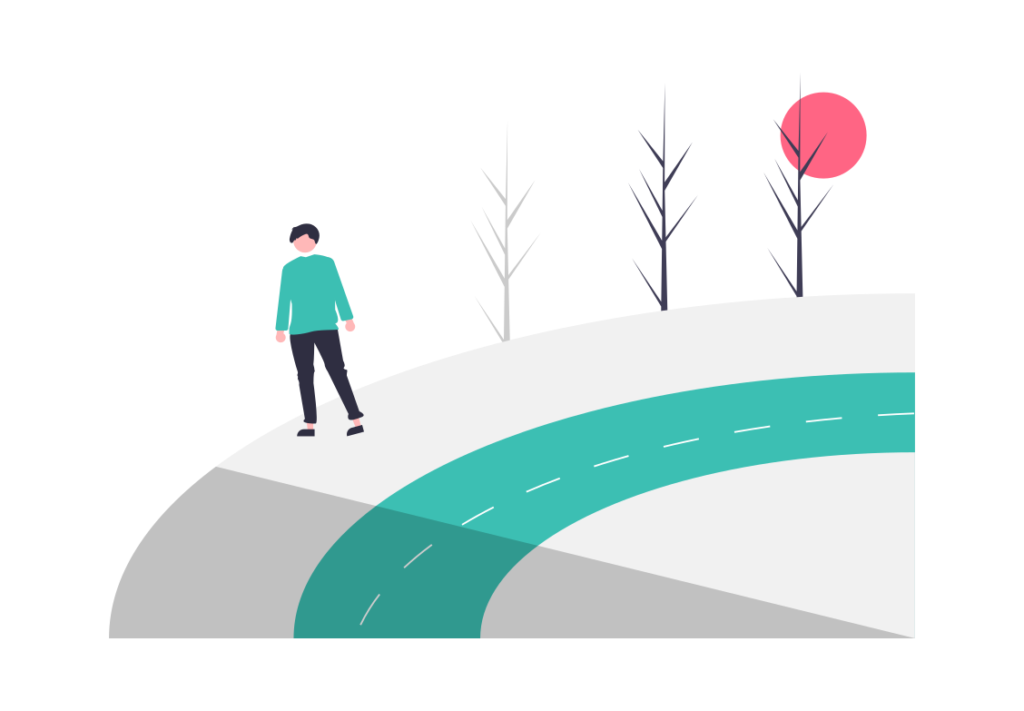
一例として、書道を習う場合を取り上げた文が印象的でした。
書道の稽古は「臨書」から始まります。
先人の書いた文字をひたすら真似していくのです。
十分に熟達したら、臨書から離れるのかといえば、そうではありません。
常に基礎基本である臨書に戻ります。
ひたすら目で手本の形を模倣していくのです。
自分の手が自然にその場所に移動するようになっても、多くの書家は臨書をやめることをしません。
模倣を繰りかえしているうちに、身体が自然に動くようになっていく瞬間があるのだといいます。
そこまでいくと、模倣とは言わなくなります。
筆者の言葉でいえば、それが「なぞり」なのです。
自発的に身体がそこにあらわれるとでもいったらいいのでしょうか。
理屈を重ねてまねをしているうちは、1つの型を追いかけている段階に過ぎません。
しかしそれが次第に何も考えなくても、できるようになっていくのです。
伝統芸能の継承
日本の伝統芸能には、似たような要素が強いです。
能や歌舞伎などの仕舞や舞踊は体系的に覚えて真似をしている段階では、身体になじんだとはいいません。
いわゆる腹に入った時にはじめて、自然な動きになるのです。
師匠の動作を意味もわからずにまねしているうちに、やがて自分の動きが、以前から決まっていたかのような自然なものになっていくのです。
もちろん、ここまで到達するには途方もなく長い時間が必要です。
能の稽古などをみていると、一挙手一投足まで先人の動きと同じになるまで続けます。
個人の考え方をそこに投入することは許されません。
足の運び方にいたるまで、少しも変えてはいけないそうです。
そこまでいかなければ、真の芸にはならないというのです。
理屈はありません。
そうしてきたから、同じようにするのだと言います。
有名な能「道成寺」の中に「乱拍子」と呼ばれる舞があります。
単純な動作の連続ですが、小鼓に合わせて、姿勢を乱さずに静止しながら下半身だけで演じる舞です。

小鼓の呼吸を計りながら、足を動かします。
道成寺の石段を蛇のように這い上がる気持ちが、足拍子として表現されていると言われています。
特殊な足遣いで舞う舞がどれほど難しいものか。
実際に見ると、その動きにどれほど神経がはりつめているのかが、よくわかります。
ただ「模倣」をしただけでは、動きが自分のものになるとは、どうしても思えません。
ある瞬間に何かを超えた時、はじめて自分の舞になっていくのではないでしょうか。
習うものと教えるものの真剣勝負は、怖いくらいです。
彼のエッセイを読んでみましょう。
本文
西欧型のレッスンは習得対象の要素分解と各要素の体系的積み上げという
「科学的」方法論に依拠しているのに対し、日本型の稽古はとにかく及ぶかぎり全体的にまねてみるという、しごく曖昧なものである。
方法論などなきに等しいように見える。
習得すべき要素が難易別に整理されているわけではないから、学習の「段階」というものがない。
したがって各段階ごとの「目標」というものもない。
ということは、学習者にとって、自分が今何を獲得すべきなのかがよく見えないということである。
師匠の指導は(とくにプロを育てる場合)「ダメだ」「そうじゃない」といった
叱責を受ける形で得られるのみで、どこがどういう理由でダメなのか教えられることは稀である。
またよい時にも「そうだ、それでいいのだ」と言われるのみで、学習者本人はなぜよいと言われたのかもわからないことが往々にしてある」。
これら日本型稽古の特徴を「模倣」「非段階性」「非透明な評価」という言葉でまとめていうことが多い。
しかしこのつかみどころのないやり方で結構芸の伝承がうまくいってきたのも事実である。(中略)
稽古の目的は、外形の模倣から入って型の「なぞり」、つまり模範例の心身態勢の再現を通じて、模範者の「身になる」ことである。
人の身になることによって、そこに具現されている身体の型がわかる。
しかし芸道の修行においては、理解するだけでは不十分である。
「なるほど、これか」と身体で理解した心身態勢をさらに繰り返し再現して、「身につく」までに至らなければならない。

これに成功して初めて、弟子は師匠と同じ境位に達し、芸の継承に成功したと言えるのである。
芸道における継承とは(実は仏道なども含めて「道」一般において)、
同じ知識や技術を「持つ」というより、同じ心身に「成る」という、いわばクローン人間の製造を目標としているのである。
(中略)
しかし興味深いことに、伝統芸能ではさらに一歩を進めることを求める。
自ら身につけた「型」を破れというのである。
既存の「型」踏み越えて自在に動きながら、しかもそれが無秩序ではなく、一つの意味を産み出す。
といって、それは新しい「型」として固定するわけではない。
むしろそのつど観客は、新たな「型」がたえまなく生成しかかっては突き崩されるという遊びの現場に立ち会うのである。
序破急
伝統芸能の深さはまさに「序破急」の中にあるとよく言われます。
型から入って、型を出ろというのです。
師匠の型をまず学ぶというのが第一歩だとするなら、次はそれを破ることです。
そして最後に自分のあらたな型を作り上げる。

本当に実力があれば、型などはいらないのです。
自然に舞い、語る姿の中に、その人の真髄が現れます。
エッセイの中にもあるように、なにがよくてどこが悪いということを先人は言いません。
ただ「ダメだ」「そうじゃない」と呟くだけなのです。
どこをなおせぱ、よくなるのかというような些末なことではなく、当事者の心性を体現できない限りは、結局まねごとに過ぎません。
落語家の名人と呼ばれる人たちはよく「登場人物の了見」になれと言いました。
その人間になりきり、そこにいる落語家の存在は離れていくのです。
目の前で噺をする落語家は、ある意味抜け殻と同じなのかもしれません。
狸の噺をする時は、自分が狸になるのです。
そこに小賢しい自分がいれば、それは観客に見抜かれるというワケです。
うまくやる必要はない。
自然にその了見になれば、芸は完成するのだとよく名人たちは言いました。
おそらく古典芸能に携わる人々にとって、ここに書かれたことは、ごく当たり前のことなのでしょう。
それだけに遥かな道のりだけが、目の前に茫漠として見えるのです。
今回も最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。

