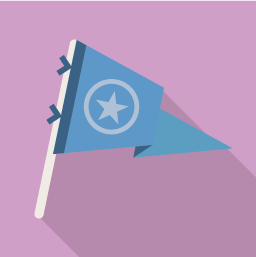仮名は女文字
みなさん、こんにちは。
元都立高校国語科教師、すい喬です。
今回は『土佐日記』をとりあげましょう。
古今和歌集の編纂者、紀貫之が国司(現地長官)の任務を終え、土佐から京都の家に到着するまでの日記です。
今ならば高知県と京都の間はごく近いですね。

新幹線を岡山で降り特急に乗り換えると、3時間50分で着きます。
昔はどうしたのでしょう。
木造の簡素な船に乗って旅をしたのです。
海上の治安は必ずしもよくありません。
海賊に財産や命を狙われることもありました。
それだけになるべく岸辺に近いところを漕いで進みました。
瀬戸内海の海は穏やかです。
しかし風の強い室戸岬では10日近くも足止めされてしまいました。
土佐守の任が終わり、任地を出たのが934年12月21日。
京都に戻ったのが2月16日です。
なんと55日間の海路の旅でした。
想像がつきますか。
現代ならばその日のうちに家に帰れます。
しかしこの時代は2か月近くの大旅行でした。
転覆せずに海上を渡れただけでもありがたいことなのです。
貫之は京都で生まれた女の子を土佐で亡くしています。
本当なら子供を連れて帰るはずでした。
その悲しみの癒えない様子が切々と綴られています。
和歌に託して子を思う気持ちをあらわすためにも仮名の文字が必要だったのでしょう。
やさしさの中に柔らかな感情の襞が描写できると考えたに違いありません。
門出の部分を取り上げます。
本文
それの年の十二月の廿日あまり一日の日の戌の刻に門出す。
そのよし、いささかにものに書きつく。
ある人、県の四年五年はてて、例のことどもみなしをへて、解由などとりて、住む館よりいでて、船に乗るべきところへわたる。
かれこれ、知る知らぬ、送りす。
年ごろよくくらべつる人々なむ、別れ難く思ひて、日しきりに、とかくしつつののしるうちに、夜更けぬ。
廿二日に、和泉の国までと、たひらかに願立つ。
藤原のときざね、船路なれど、馬のはなむけす。
上中下、酔ひ飽きて、いとあやしく、潮海のほとりにて、あざれあへり。
廿三日。八木のやすのりといふ人あり。
この人、国にかならずしも言ひ使ふものにもあらざなり。
これぞ、たたはしきやうにて、馬のはなむけしたる。
守がらにやあらむ、

国人の心のつねとして、「今は」とて見へざなるを、心あるものは、恥ぢずになむ来ける。
これは、ものによりてほむるにしもあらず。
廿四日。講師、馬のはなむけしに出でませり。
ありとある上下、童まで酔ひしれて、一文字をだに知らぬもの、しが足は十文字にふみてぞ遊ぶ。
現代語訳
男も書くという日記というものを、女も書いてみようと思って書きます。
ある年の十二月二十一日の午後八時頃に、出発しました。
その様子を、少しばかり紙に書きつけることにします。
ある人(貫之自身)が、国司としての任期の四、五年が終わって、通例の事務を全て終わらせて、解由状などを受け取り、住んでいた国司の官舎から出て、船に乗るはずの所へ移りました。
あの人この人、知っている人知らない人、見送りをしてくれました。
この数年来親しく交際していた人たちは、別れがたく思って、一日中、あれやこれやとしながら、大騒ぎするうちに、夜が更けてしまったのです。
二十二日に、和泉の国まで、無事であるようにと神仏に祈願しました。
藤原のときざねが、船旅であるのに、馬のはなむけ(送別の宴)をしてくれました。
身分の高い者も中、下の者もすっかり酔っ払って、たいそう不思議なことに、潮海のそばで、ふざけ合っています。
二十三日。

八木のやすのりという人がいます。
この人は、国司の役所で必ずしも仕事などを言いつけて使う者でもないような人です。
堂々として立派な様子で、餞別を贈ってくれました。
国司の人柄なのでしょうか。
人情の常として見送りに来ない人もいますが、真心のある人は、送別してくれるものなのです。
よい贈り物をもらったからといって褒めているわけでもありません。
二十四日。
国分寺の僧が、送別の宴をしにおいでになりました。
そこにいあわせた人々は身分の上下を問わず、子どもまでが正体なく酔っ払って、一の文字さえ知らない者が、その足は十の文字を踏んで遊んでいました。
意味がわかりますか。
あちこちにちょっとした洒落が入っています。
船の旅なのに馬のはなむけをしたとか。
十の文字を踏むとは酔って千鳥足になっている風景を面白く描写したものです。
一の文字を知らない人も十の文字を書いたというのです。
それくらいに酔っ払ったということなのでしょう。
最古の和文日記
土佐日記は紀貫之による現存最古の和文日記で、承平五年(935年)頃に書かれました。
全文がひらがなで書かれているというのが大きな特徴です。
当時は紀貫之のような男性がひらがなで日記を書くということは許されませんでした。
ひらがなは女性の文字だったのです。
漢字は真名(まな)と呼ばれ、正式な文字でした。
それに対して、ひらがなはあくまでも仮名(仮の文字)です。
ひらがなの持つやさしさ、柔らかさを知っていた貫之は、古今集を編纂する時にも前文を漢字と仮名で書きました。
一般に真名序、仮名序と呼ばれています。
学校では仮名序をよく勉強します。
少しだけ、ご紹介しましょう。
—————————–
やまと歌は、人の心を種として、よろづの言の葉とぞなれりける。
世の中にある人、ことわざ繁きものなれば、心に思ふことを、見るもの聞くものにつけて、言ひ出せるなり。

花に鳴く鶯、水にすむ蛙の声を聞けば、生きとし生けるもの、いづれか歌を詠まざりける。
力をも入れずして天地を動かし、目に見えぬ鬼神をもあはれと思はせ、男女の仲をも和らげ、猛き武士の心をも慰むるは、歌なり。
——————————–
どうでしょうか。
歌というものの持つ本質を実にみごとに解説していますね。
鬼や神の心までを動かすものが歌だと言っているのです。
この後、授業では貫之が長い間空き家にしていた京都の家に戻るシーンを学びます。
この章が実にしみじみとしていて、彼の心の中にできた空洞を感じさせます。
近いうちにご紹介しましょう。
あわせて読んでいただければ幸いです。
今回も最後までお読みくださり、ありがとうございました。