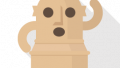読書の楽しみ
みなさん、こんにちは。
元都立高校国語科教師、ブロガーのすい喬です。
今日は読書の話をします。
みなさんには本に夢中になりすぎて、つい降りるはずの駅を乗り過ごしてしまったという経験はありませんか。
気がついた時にはすでにドアが閉まった後というパターンです。
ぼくにも何度かあります。
やれやれと思いながら、それでも読書に熱中するあまり降車駅までわからなくなるというのは、幸せなことだなと感じます。
今でも忘れられないのは、はるか以前、作家の有吉佐和子さんが中国へ行った時のルポを読んでいた時のことです。
このときは3つほど駅を乗り過ごしてしまいました。
それくらい新鮮で面白いルポだったのです。
あの頃、ぼくにとって中国はまだ遠い国でした。

それから後に自分がその国を訪れ、実験中学(日本の高校)で実際に授業までさせてもらえるとは思ってもみませんでした。
あれから何度、読書に夢中のあまり駅を通過したことでしょうか。
しまったと思いながら、しかし失敗したとか損をしたという感情が全くありませんでした。
むしろ微笑ましく感じたのはなぜでしょう。
自分自身に対する愛おしささえ覚えました。
それだけ熱中できる本を持てたということがなにより嬉しかったのです。
自分に興味のないものであれば、まさか駅を乗り越してしまうようなことはないでしょう。
興味や関心は人間を別の広い場所へ誘う水先案内人のようなものです。
どんなに他人が面白いから読んでみろと勧めてくれても、やはり興味のないものには全く手がでません。
そうした意味からいえば、いつも降りる駅を忘れてしまうくらい熱中できたというのはすばらしいことだと言えるのかもしれないのです。
小林秀雄
評論家の小林秀雄は常に3冊の本を携帯していたといいます。
スキマ時間に読む本はこれ、午前中に読む本はこれといった具合です。
もちろんその中には電車の中で読む本も入っていたのです。
彼はよく読書とは、著者に会いにいくことだと語っていました。
本を読みながら、作者の息遣いが聞こえなければ嘘だ言っていたとか。
彼らに直接会いにいくという境地になれれば、それこそが本に親しむ喜びなのかもしれません。
考えてみれば、本を読むことで何千年前の人にだって会えるのです。
実際人にあって教えを請うためには、大変な道のりが必要です。
それをわずかな時間で可能にしてしまう。
読書は時空を超えるマジックだと言えるかもしれません。
ぼくが最初に本当に本を読んだなと実感したのは中学3年生の時でした。
何気なく学校の図書館で手にとった吉川英治の『新書太閤記』がそれです。
今でもその時の本の装丁を覚えています。

何冊あったのでしょうか。
10冊以上はあったような記憶があります。
とにかく大長編でした。
それを一夏かけて読んだのです。
本を読んでいる時は自分がまさにその時代の同じ空間にいました。
あの楽しい経験がなければ、それ以降の読書量にはならなかっただろうと思われます。
読書をすれば得をするとか、勉強になるからなどという姑息なことを考える必要はありません。
ただ楽しければいいのです。
そのためにはよく言われる「積ん読」(つんどく)が1番効果的でしょうね。
読みたいと思う本を買うにしろ、借りるにしろ、とにかく積んでおくのです。
そうすれば、背表紙が囁きます。
はやく読んでくれとね。
世界が日々新しい
本を読めと言われて読むというのはあまりいい方法ではありません。
かつてよく新築の家の居間に本棚を買ったから、そこに入るだけの百科事典と世界名作全集を集めたなどという話を聞いたことがあります。
最悪なパターンですね。
本は必要な時には必ず向こうからやってくるものです。
どんなに他人が勧めてくれても、興味のない本には手が伸びません。
それでいいのです。
しかしひとたび関心がそちらへ向くと、本の方から勝手にやってきます。
これが1番の不思議です。
新聞にしても興味がない記事には全く目がいきませんね。

しかし気になり始めると、その記事だけが突然大きく見えるのです。
読書も全く同じです。
大学へ入ってからは、空気を吸うのと同じように本を読んでいった記憶があります。
すぐに役に立つというようなことはありません。
必ず1度深く沈殿します。
発酵するには時間がかかるのです。
その後本当に自分の身になって浮き上がってきます。
それまで待つのです。
読書は待つ行為に支えられています。
不意にある時、天啓のようにやってくるのです。
木々は光を浴びて
昨年、叔母が亡くなってからすでに6年がたち、盆の墓参りに行ってきました。
叔父の家を訪ね、その後墓参をしたのです。
あじさいで有名な寺です。
庭は、もうすっかり枯れた花で、茶褐色に変容していました。
あれほど見事に咲き誇っていた花々も、時期が過ぎれば嘘のように枯れていきます。
人生と同じなのかもしれません。
しかし新しい芽は確実に、また次の生命を宿しています。
さてその後、近くの懐石料理屋で、実にゆったりとした時間を過ごしました。
その庭の緑が美しく、ぼくはしばしの間みとれてしまいました。
しかし正確にいえば、美しいのは緑だけではなく、そこに降る光でした。
直射日光が容赦なく葉にあたります。
風が吹くと、ときおり枝が揺れ、そこに影が生まれます。
美しいといえば実にありきたりな表現ですが、それ以上にいい形容が思いつきません。
光が緑の葉に降りそそぐのを見ながら、遅い昼食をとりました
いい時間でした。
その時、突然、かつて読んだ森有正のエッセイ『木々は光を浴びて』のタイトルが何度も頭の中をよぎりました。
パリと東京の違いはありますが、木々の緑と光のコントラストほど美しいものはありません。

ぼくはその風景にしばらく酔ったような気分になりました。
少しもアルコールを飲まずに、人は酔いしれることができるものなのです。
その感覚は森有正がぼくに残してくれたものです。
彼の『遥かなノートルダム』『バビロンの流れのほとりにて』もいいですね。
辻邦生の小説『背教者ユリアヌス』や長大な留学記、饗庭孝雄の評論などもその頃あわせて読んでいました。
読書をしている時の気分が、さっとその瞬間舞い降りてきたのです。
この感覚は本を読んだ人にだけもたらされる共通のものだと思います。
まさにデジャビュとでもいえるものかもしれません。
プルーストというフランスの作家が追い求めた回想の記憶のような感覚です。
柔らかな秋の澄んだ陽がまさにその瞬間にふさわしかったです。
ぼくはその日、ずっと幸せでした。
本を書くのは想像以上に大変な作業です。
だからこそ、彼らに会いに行かなくてはなりません。
じっとあなたを待っていてくれるはずです。
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。