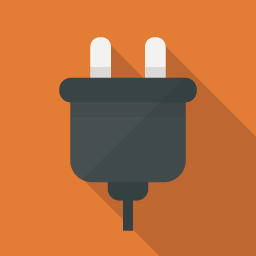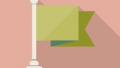立川談志という噺家
噺家立川談志が亡くなって10年の歳月がたちました。
はやいものです。
覚えていますか。
若い人の中には知らない人もいるでしょうね。
それくらい時の移るのは早いのです。
「笑点」という彼のつくった人気番組だけが残りました。
1966年5月に開始された日テレの看板番組です。
最初の頃はこれほど視聴率がとれるなどとは予想もしなかったことと思います。
創立メンバーはみな亡くなってしまいました。
落語協会から独立して立川流を起ち上げたのは1983年のこと。
確かに1つの時代を築き上げたことだけは間違いありません。
たくさん在籍していた弟子たちも今ではそれぞれが別の道を辿っています。
この落語家集団の人たちは本を書くのが大変好きなようですね。
次々と師匠に関する本や落語本などを今も刊行し続けています。
それだけのネタをつねに家元談志が提供してくれたということなのでしょう。
彼はそれまでおおまかな経験年数で二つ目、真打にしていた落語界の慣例を廃止しました。

条件をきちんとつけたのです。
二つ目昇進は、落語50席と都々逸・長唄・かっぽれなどの歌舞音曲ができること。
真打昇進は、落語100席と歌舞音曲などのマスターが必須でした。
さらに毎月の上納金もとったのです。
それまでの落語界では行われていなかったことをあえて断行したのです。
その反響は予想以上のものでした。
弟子は必死
弟子は本当に苦しんだと思います。
その中で成長していったともいえるのです。
権太楼師なども談志に入門したいと思ってはみたものの、すぐに喧嘩になって破門されるだろうと予想してやめたと述懐しています。
弟子たちの修行時代の話はたくさん本になっています。
なかでも立川談春の『赤めだか』はよく売れました。
ドラマにもなったくらいです。
立川キウイの『万年前座、僕と師匠・談志の16年』などは実に傑作です。
他にも、志らく、談慶、談四楼、談春、吉笑などと数え上げたら書き手にはキリがありません。
よくも悪くも立川談志という噺家がいて成り立った独立派です。
カリスマ亡き後の党派は独自の方向を探る以外に手はありません。

彼らはテレビの司会をやったり、本を書いたりしてはいます。
しかし1番好きなのはやはり落語なのでしょう。
寄席に出られないというハンディを乗り越えて自立していかなければならないのはつらいことに違いありません。
立川談幸などはどうしても寄席に出たいということから、落語芸術協会へ入りました。
立川流では彼の弟子だけが、現在寄席に出演しています。
師匠がなくなって10年の間に一門にも隋分と変化がありました。
それまで顧問として相談に乗っていた作家、吉川潮もその職責を退いたのです。
あれだけ談志を慕っていた彼も今では遠くから見守るという立場に位置をかえたワケです。
現代落語論
この本は今でもぼくの本棚の隅にちょこんと置いてあります。
三一書房のごくありふれた新書版です。
最初は知人に借りた記憶があります。
おそらく落語家が書いた本としては、かなり初期のものだったのではないでしょうか。
談志が20代後半に出した本です。
彼はその頃から一家言を持った落語家として知られていました。
別の言葉でいえば、かなり生意気な若造だったとも言えます。
この本は1度絶版になり、あまりにリクエストが多いので、再び世に出ることになりました。
大変に珍しいパターンです。
絶版になってからしばらくの間、噺家仲間や、好事家の間ではバイブル扱いされていました。
初版は1965年です。
どれほど古いかよくわかるでしょう。

どうしても読みたい時はどうしたのか。
あちこちの古本屋を探すしか手がありませんでした。
かなりの高額で取引されていたようです。
しかしその後、2002年に講談社から出た『立川談志遺言大全集』の中に全て所収されることになりました。
あの時は嬉しかったですね。
さっそく再読したというワケです。
実はこの本を上梓後、1985年に彼は第2部も書いてます。
それもあわせて大全集に載っていたのです。
じっくり読んでいくと、談志に対するイメージはかなり変わります。
巷間、言われている彼の風貌とはまた違う、照れ屋でいたずら坊主な少年の横顔がそこに見て取れるのです。
読んでいて1番強く感じるのは、松岡(彼の本名)青年にとって、落語は世界そのものだったということです。
落語こそが命
談志はこの世に住む人間の業を表現するに足る芸術は落語だけだと信じていました。
これほどに落語を愛していた噺家というのはそれほどいないのではないでしょうか。
半ば意地になっても1人で本当の噺家になりたいと願い続けてきたのではないかと思います。
名人と呼ばれた人々の風貌を語るときの彼は、本当にうれしそうです。
志ん生や文楽と同じ楽屋で同じ時間を過ごしたということが、何よりの勲章です。
粋な名人の芸をわかってくれる人が減ったということを嘆いています。
師匠である五代目柳家小さんに対する信頼も厚いものがあります。
師匠はどんな時でも自分をわかってくれるはずだという絶大な信仰に近いものを持っていました。
後に袂をわかち、師匠の元から離れることになります。
しかしそれでも自分は小さんの弟子だという自負が弱まることはありませんでした。
いつでも師匠は自分を許してくれる。
肉親に対するのと同じような感覚でいたようです。
落語というのは赤の他人に、自分の持つ全ての芸を無料で教えるという不思議な芸能の産物です。

それだけに憧れて入門する師匠の存在は絶対なのです。
反抗することは許されません。
三遊亭圓生が引き起こした落語協会の内紛以降、寄席の地図も大きくかわりました。
談志はいつも現代に通じる落語とは何かということを考え、むしろ焦っていたのでしょう。
この芸を愛するが故に、どうしたら本物がうまく次の時代に引き継がれていくのかということを考え続けたのがよくわかります。
悩みは深かったことでしょう。
あらゆる生活様式が変わってしまった現代。
どの噺が残るのか。
どれはもう消えていくのか。
浪曲、講談のように衰退していく芸でしかないのではないか。
彼は煩悶し続けます。
その悩みを素直に書き込んだのが、この本なのです。
かつて紀伊国屋寄席で聞いた談志の「鼠穴」が今でも耳の底に残っています。
やはりうまかったとしか言えません。
しかし今の彼を聞こうとは思いませんね。
志ん朝に真打ち昇進で抜かれた時の悔しさを語る時の談志が好きです。
とにかく面白い本です。
好きな人にはたまらないでしょう。
立川流の弟子たちが書いた落語論と比べてみるのもいいかもしれません。
吉笑『現在落語論』、志らく『落語進化論』は明らかに談志のこの本を意識して書いています。
それぞれご一読を勧めます。
最後までお読みいただきありがとうございました。