 本
本 「源氏物語・心づくしの秋風・須磨」新たな出逢いの予感と海辺の寂しい日々
源氏の須磨がえりという有名な言葉があります。桐壺から読み始めた人も、須磨の段あたりまでくると、くたびれてしまうのです。実はこのあたりからが本当に面白くなるんですけどね。ぜひ、この本を覗いてみてください。
 本
本  本
本  本
本  本
本  本
本  本
本  本
本  本
本  本
本  本
本 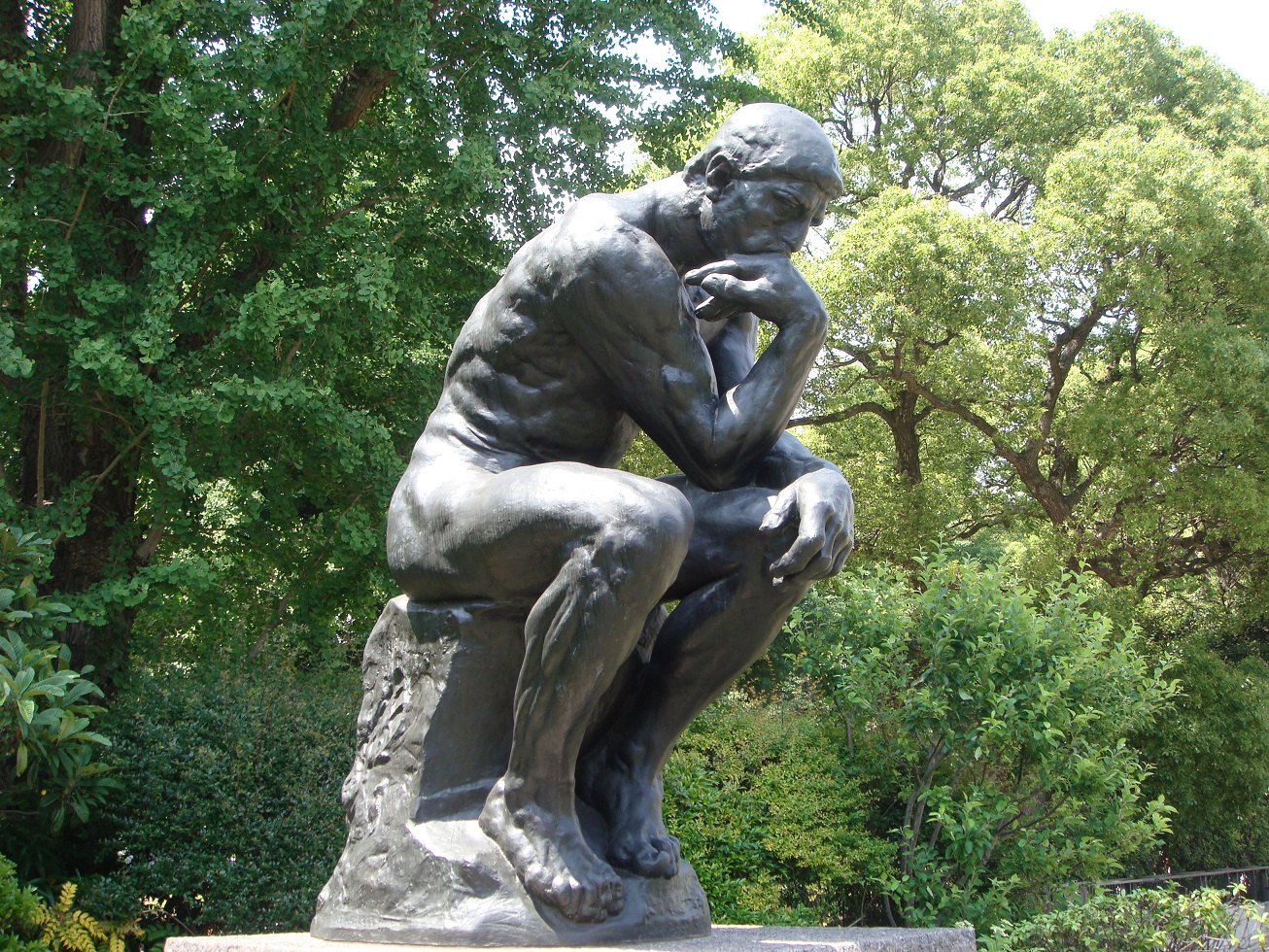 本
本  本
本  本
本  本
本  本
本  本
本