偶然の出会い
みなさん、こんにちは。
元都立高校国語科教師、すい喬です。
今回は聞いたことのある表現の1つをとりあげます。
最近よく耳にする言葉に「セレンディピティ」(Serendipity)というのがありますね。
ご存知でしょうか
元々あった単語ではありません。
イギリスの政治家、小説家であるホレス・ウォルポールが1754年に生み出した造語なのです。
彼が子供のときに読んだ『セレンディップの3人の王子』という童話にちなんだものとされています。
セレンディップとは昔のセイロン、今のスリランカのことです。
つまり「スリランカの3人の王子」という意味です。
彼がこの言葉を初めて使ったのは、友人に宛てた手紙の中だと言われています。

簡単にいえば、セレンディピティとは意図せずに新しい発見や出会いが生まれる現象をさします。
日本人に最もなじみやすい言葉に置き換えれば、「出会い」と「縁」でしょうか。
「縁は異なもの」とよく言いますね。
どこでどのような出会いが待っているか。
実はだれにもわからないのです。
人やものに偶然、出会い、新しいチャンスがそこから生まれるのです。
私たちの生活の中で、こうした偶然の積み重ねがどれほど大切であるかは誰でもが感じているのではないでしょうか。
結婚などもまさにこの出会いと縁そのものかもしれません。
あるいは仕事や会社を選ぶことも、かなり偶然の出会いに左右されることが多いです。
ぼく自身、自分の人生を考えた時、本当にさまざまな瞬間が重なったとしか思えないことがいくつもあります。
だからかもしれませんが、今も縁は大切にしています。
一期一会という言葉を日本人は好みますね。
本当に一生で一度の出会いが、その後の人生を左右することは、よくあるのです。
包容力
セレンディピティを十分に享受するためには、なんといっても人間的な包容力が必要です。
せっかく目の前にあるチャンスを逃してしまっては、なんにもなりません。
その時は、自分にとってどのような出会いなのかはよくわからないものです。
それだけに大きく手を広げて待てるだけの心のゆとりも必要です。
そのためにはどうすればいいのか。
これは簡単ではありません。
よく人が近くに寄ってくる人になれといいます。
まさに人柄と縁はリンクしているのに違いがないのです。
誰もが口にすることは、やはり笑顔が大切ということでしょうね。
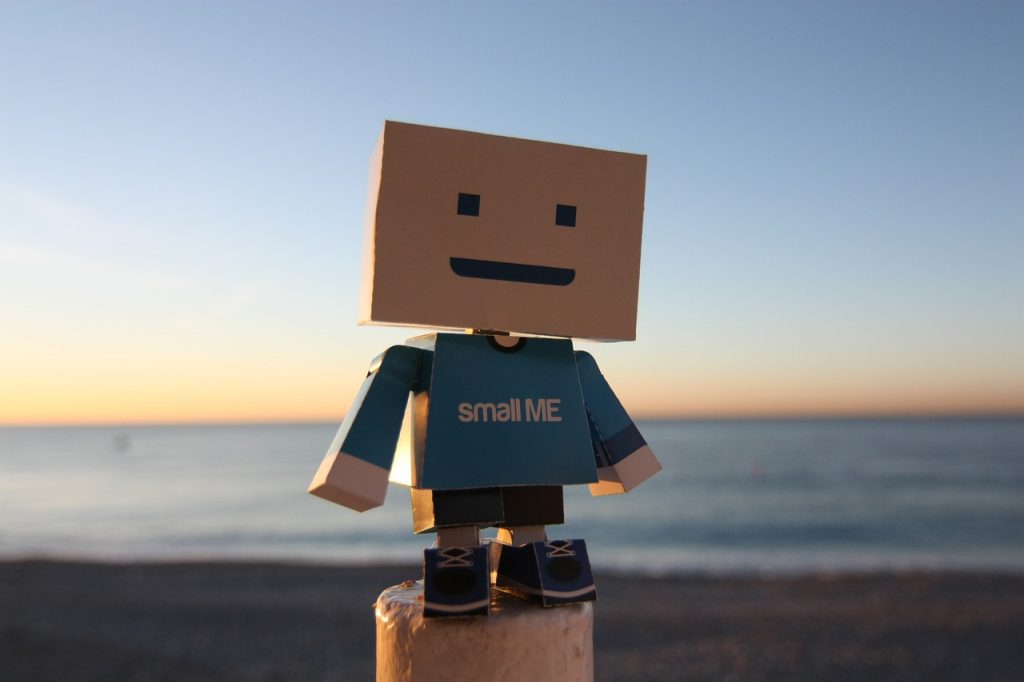
感謝の気持ちを忘れずに、他人の悪口を言わないことに尽きます。
謙虚でいれば、だれも不愉快ではありません。
一言でいえば、「上機嫌」の状態をキープするということでしょうか。
やはり機嫌のいい人は気持ちがいいですね。
感情がつねに安定しているのです。
傍にいても不愉快になることは決してありません。
具体例
セレンディピティの話をする時によくでてくる具体的な例として次のようなものがあります。
トップはなんといってもペニシリンの発見でしょうか。
アレクサンダー・フレミングは、実験室での不注意からカビが生えたシャーレを発見しました。
この青カビが実は細菌を殺していたのです。
そこから、抗生物質が発見されました。
今日では皮膚感染症、咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、肺炎、膀胱炎などに使われています。
劇的な効果をもたらしたのです。
他にも偶然の出来事が医療に革命を起こしたケースはいくつもあります。
X線の発見もその1つです。
ウィルヘルム・レントゲンは、1895年に放射線を使った実験中、偶然にX線を発見しました。

この発見は医療画像診断の基礎となり、病気の診断方法に革命をもたらしたのです。
レントゲンを使わない診療など、全く考えられません。
この他にインシュリンの発見や麻酔薬の1つ、笑気ガス(亜酸化窒素)の例などもあります。
笑気ガスは以前はパーティーでの娯楽用に使用されていました。
しかし医療用麻酔としての効果が発見され、手術の際の患者の苦痛を大幅に軽減したのです。
偶然から生まれたものにしては、あまりにも大きな影響を与えましたね。
他にはDNAの構造を解明したワトソンとクリックの研究も有名です。
彼らは、X線結晶構造解析をしていた時、偶然DNAの二重螺旋構造を発見しました。
この発見は、今日の遺伝学やバイオテクノロジーの発展に大きくつながりました。
ビジネスの場合
医療用に比べて事務用品のケースはどうでしょうか。
ポストイットの開発はご存知ですか。
ポストイットとは、裏面の一部に粘着剤が塗られていて、簡単に貼って剥がせるメモ用紙のことです。
必要なことをメモして目につくところに貼り付けられるポストイットは、いまや職場や家庭など私たちの日常生活で切っても切り離せない存在です。

開発は本当に偶然から起こりました。
3Mの科学者が接着剤の研究をしている時の話です。
研究の過程で、奇妙なものを発見しました。
表面に軽くくっつくものの、しっかりとは接着しない接着剤の存在です。
これはマイクロスフィアと呼ばれる接着剤で、粘性は保持するものの、「はがすことが可能な性質」も持ち合わせていたのです。
こんなものが役にたつはずはないと捨ててしまえば、それまでのことでした。
そのために貼り付けられた表面から簡単にはがすことができました。
しかし、そこからポストイットが生まれたのです。
事務机に必ず入っている必需品ですね。
失敗を恐れない
こうした例をみていると、どれも偶然の賜物と呼べるものばかりです。
しかしそこに至る過程は、長い道のりただったのです。
ポイントは失敗を恐れないということでしょうか。
チャレンジし続けることの大切さをしみじみと感じます。
やはりリスクをとらなければ、成功はおぼつかないということのようです。
思いがけない発見というのは、学際的なアプローチから出てくるケースが多いような気がします。
最近の学問はAIを多用します。
しかしそれだけはやはり限度があります。
飛躍的な想像力が必要なのです。
結局、最後はそこに可能性が宿っているということなのでしょう。

自由な発想が生み出されるためには、そのための環境も必要です。
他の分野とのコラボもあった方が、裾野が広がります。
過去の歴史に学びながら、少しでも先へ進もうとするタフな精神力も大きな原動力になります。
セレンディピティは偶然だけではありません。
そこには必ず必然性があるのです。
今回も最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。


