銀の匙
みなさん、こんにちは。
元都立高校国語科教師、すい喬です。
今回は中勘助の書いた『銀の匙』読みます。
あなたはこの本を御存知ですか。
タイトルくらいは聞いたことがあるという人がいるかもしれません。
手にとって読んだことがあるでしょうか。
前編が1910年に執筆され、後編が1913年に発表されました。
師であった夏目漱石に送ったところ、絶賛され、その勧めで全文が東京朝日新聞に連載されたのです。
1935年には岩波文庫版が発行されました。
和辻哲郎が解説を寄せています。
この本が話題になったのは灘中の国語科教師、橋本武氏が1冊を3年間かけて教材にしたという伝説的な話が、多くの人に知られるようになったからです。
もちろん、それ以前も名作と呼ばれていたものの、それほど多くの読者を得ていたワケではありません。
橋本氏は戦後、教科書を使わず授業をしたことで知られています。
この作品を授業に用い、1冊を3年間かけて読み込む授業を行ったのです。
当時、灘中は誰にも知られていない、私立の学校でした。
幸い、文部省の指導要領に従う必要もなかったことから、このユニークな授業をする判断をしたそうです。

その様子は岩波ジュニア新書『〈銀の匙〉の国語授業』という本に掲載されています。
全ての教材を当時のガリ版印刷で配ったという伝説の授業です。
かれの信念はこの言葉の中にあらわれています。
「すぐ役に立つことは、すぐに役立たなくなる」
学ぶ力の背骨を鍛えるという教育信念に基づく授業でした。
今から10年ほど前に出版された本です。
読んでいると、若き日の橋本氏の熱い日々が目にみえるようです。
このガリ版で刷られたブリントは、今も当時の生徒が大切にしているのだとか。
それもあって90歳を過ぎた橋本氏は2度にわたり、土曜講座という特別授業の枠で、現役の灘中学生に向けて『銀の匙』の授業を行いました。
作品の冒頭を少し読んでみましょう。
この小説を読むと、誰もが懐かしさにひたれるのではないでしょうか。
1つの時代の横顔がそこに浮かんできます。
冒頭部分
私の書斎のいろいろながらくた物などいれた本箱の抽匣に昔からひとつの小箱がしまつてある。
それはコルク質の木で、板の合せめごとに牡丹の花の模様のついた絵紙をはつてあるが、もとは舶来の粉煙草でもはひつてたものらしい。
なにもとりたてて美しいのではないけれど、木の色合がくすんで手触りの柔いこと、蓋をするとき、ぱんとふつくらした音のすることなどのために今でもお気にいりの物のひとつになつてゐる。
なかには子安貝や、椿の実や、小さいときの玩びであつたこまこました物がいつぱいつめてあるが、そのうちにひとつ珍しい形の銀の小匙のあることをかつて忘れたことはない。
それはさしわたし五分ぐらゐの皿形の頭にわづかにそりをうつた短い柄がついてるので、分あつにできてるために柄の端を指でもつてみるとちよいと重いといふ感じがする。
私はをりをり小箱のなかからそれをとりだし丁寧に曇りを拭つてあかず眺めてることがある。
私がふとこの小さな匙をみつけたのは今からみればよほど旧い日のことであつた。
家にもとからひとつの茶箪笥がある。
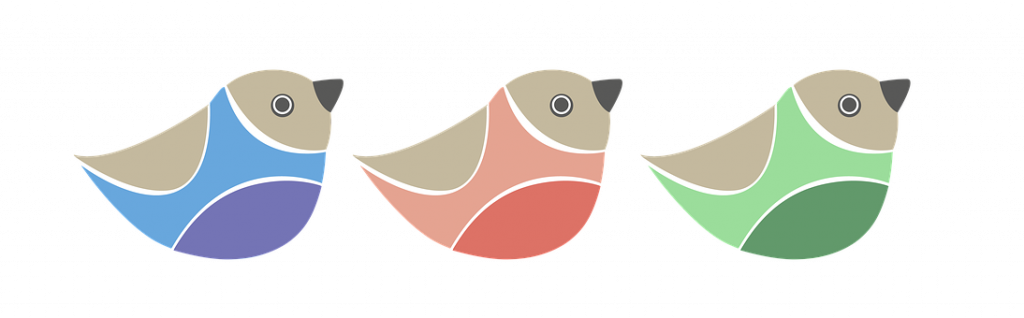
私は爪立つてやつと手のとどくじぶんからその戸棚をあけたり、抽匣をぬきだしたりして、それぞれの手ごたへや軋る音のちがふのを面白がつてゐた。
そこに鼈甲の引手のついた小抽匣がふたつ並んでるうち、かたつぽは具合が悪くて子供の力ではなかなかあけられなかつたが、それがますます好奇心をうごかして、ある日のことさんざ骨を折つてたうとう無理やりにひきだしてしまつた。
そこで胸を躍らせながら畳のうへへぶちまけてみたら風鎮だの印籠の根付だのといつしよにその銀の匙をみつけたので、訳もなくほしくなりすぐさま母のところへ持つていつて
「これをください」といつた。
眼鏡をかけて茶の間に仕事をしてた母はちよいと思ひがけない様子をしたが
「大事にとつておおきなさい」
といつになくぢきに許しがでたので、嬉しくもあり、いささか張合ぬけのきみでもあつた。
その抽匣は家が神田からこの山の手へ越してくるときに壊れてあかなくなつたままになり、由緒のある銀の匙もいつか母にさへ忘れられてたのである。
母は針をはこびながらその由来を語つてくれた。
ノスタルジア
大正時代のはじめに書かれたものです。
中勘助の幼い頃の思い出が実にていねいに書かれています。
誰にでもある子供時代の懐旧譚といってもいいでしょう。
しかしただ懐かしいだけではありません。
そこには作者の細やかな目配りがされています。
1つの時代を生きた子供が、どのように成長していったのかを、くっきりと浮かび上がらせてくれます。
今とは明らかに風俗も違います。
しかし底流に流れている民族の血のようなものの熱さが、確実に伝わってくるのです。
記憶力がいいというだけではありません。
その時の自分の立ち位置が明確なのです。
年老いた伯母や、母親などとの関係に対する表現も鮮やかです。
どういう境遇にいた人間なのかということもよくわかります。
中勘助は明治18年、東京神田に生まれました。

一高をへて東京帝国大学英文科入学、その後、国文科へ転じたのです。
その縁で漱石に教えを受けたことが、彼にとっては幸運でした。
信州の野尻湖畔で1人だけの生活を送っていた期間が長かったのです。
しかし父親の死と兄の重病という家族の危機に瀕し、一時、東京に戻ります。
『銀の匙』は彼の処女作です。
細やかな観察力が、この作品の価値を高めています。
全編の中で幼い頃に伯母の話を聞かされた時の心の柔らかさを感じさせる部分を少しだけ抜き書きします。
伯母の話
なかでもあはれなのは賽の河原に石をつむ子供の話と千本桜の初音の鼓の話であつた。
伯母さんは悲しげな調子であの巡礼唄をひとくさりうたつては説明をくはへてゆく。
その充分なことわけはのみこめないのだが、胎内で母親に苦労をかけながら恩を報いずに死んだため塔をたてて罪の償ひをしようと淋しい賽の河原にとぼとぼと石を積んでるのを鬼がきては鉄棒かなぼうでつきこはしてひどいめにあはせる。
それをやさしい地蔵様がかばつて法衣の袖のしたにかくしてくださるといふのをきくたんびに、私は息のとまりさうな陰鬱な気におしつけられ、また可哀さうな子供の身のうへがしみじみと思ひやられてしやくりあげしやくりあげ泣くのを、伯母さんは背中をなでて「ええは、ええは、お地蔵様がおいであそばすで」といふ。
地蔵様といへば路ばたに錫杖をついてたつてるあの石仏のとほりの仏様だと思つてゐた。
仏性の伯母さんの手ひとつに育てられて獣と人間とのあひだになんの差別もつけなかつた私は親の生皮を剥がれたふびんな子狐の話を身につまされてきいた。
親の白狐は皮を剥がれながら、わが子かはいや、わが子かはいやといつて鳴いたといふ。
これは私の知つてる鼓についての三つの話のうちの最もあはれな話である。

それは神秘の雲につつまれて天から降つた鼓でもなく、つれない人が綾で張つたといふ音なしの鼓でもなく、大和の国の野原にすむ狐の皮で張つたただの鼓が恩愛の情にひかれてわが子を思ふ声をだしたといふのである。
私は今でもこの話を思ひだせば昔ながらの感情の湧きおこるのをおぼえる。
この部分を読んでいると、柔らかな感性に裏打ちされた小説家の魂がそこにあるのを強く感じます。
日本人の中に流れ続けている血と呼べるものなのではないでしょうか。
この作品は岩波文庫に入っています。
今では青空文庫でも読むことができます。
懐かしい日本の風景に戻りたい時、ちょっと読み返してみてはどうでしょうか。
今回も最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。


