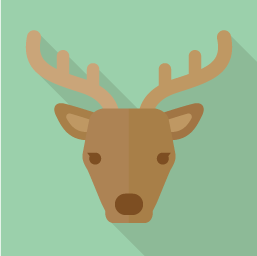文学の未来
みなさん、こんにちは。
元都立高校国語科教師、すい喬です。
今回は「文学の未来」と題された比較文学者、小野正嗣氏の文章を読みます。
高校3年向けの現代文の教科書に所収されたものです。
内容はそれほどに難しくはありません。
誰もが必ず何度かは直面する問題を指摘しています。
それは文学作品を読むたびに、印象が変わるのはなぜかという問いなのです。
別の表現で言えば、どうして「私」はあの小説ではなくて、この小説が傑作だと感じるのかという疑問です。
友人に勧められて読んではみたものの、それほど強い印象を持たずに終わってしまったという経験は誰にもあります。

その反対に、自分がすばらしいと思っても、他人にはそれほどアピールしないということもあります。
若い時に読んでとても感動した記憶があるのに、年齢を重ねてから読むと、意外なくらいにつまらなかったという経験もあるでしょう。
なぜそんなことがおこるのか。
不思議で仕方がありませんね。
読書というのは、どこまでいっても能動的な行為です。
自分が読まなければ、筆者の書こうとした意味や現実を受け入れることはできません。
しかし自分の許容量を超えた内容ならば、その真実は外に溢れ出てしまうだけのことです。
十分に把握しきれないまま、作品はそこで閉じられてしまいます。
本当にすぐれた作品は多くの人を活性化させる力を持っているに違いありません。
しかしその内容がどれほどすぐれていても、読者との関係で十分に発揮できるのかどうか。
これも大きな問題です。
ぼく自身の経験からいっても、全く同じことがいえます。
特に古典と呼ばれている作品の奥深さには、その度に驚かされてしまいます。
ここで教科書に載せられている文章の一部を読んでみましょう。
本文
どうしてもある本は面白いと思うのに、別の本には関心が持てないのか。
どうして「私」はあの小説ではなくて、この小説が傑作だと感じるのか。
どうしてあの詩ではなくて、この詩に涙が溢れてくるのか。
どうしてあの言葉ではなくて、この言葉が頭から離れないのか。
あるテクストをこんな風に読んでしまう「私」とは一体何者なのか。
我々のそれぞれがこの世界において自分自身の問いを抱えて生きている。
一人一人が世界に対して、他者に対して、そして自分に対して持っている問いに関わる何かが、いま目にしている文章の中に確かにあると感じられるとき、我々はその本に強く引きつけられる。
その何かがもしかしたら、自分の心について離れない問いに対する答えなのかもしれない。
その何かのおかげで、それまで自分でも意識していなかった問いの存在に気づくことがあるのかもしれない。
そのとき、自分自身について少しだけ理解が深まる。
あるいは、逆に自分という人間がより分からなくなったりする。

作品を読むことで、自分と自分を取り巻く世界に対する意識ががらりと変化させられることがあるからだ。
では、それまでまるっきり違う考え方を持っていた自分とは、いったい何だったのか。
あるいは、昔は読んでひどく感動した作品が今読むとちっとも心に響かない。
とても同じ本を読んでいるとは思えない。
作品が変わったのか、そうではなくて、作品と自分との関係が、自分自身が変化したのだ。
読むことはしたがって、自分のなかにある他者を絶えず発見することにつながる。
自分との対話
作品を読むということの意味をじっくりと論じた文章ですね。
1番気になるのは、読むことは自分のなかにある他者を絶えず発見することにつながるというところです。
読むことによって、どのように自分の中にある他者を発見するのでしょうか。
筆者はどんな風に考えているのか、とても気になります。
答えはいくつも考えられます。
簡単にまとめてみましょう。
ポイントは読むことによって、自分の抱えている問いの答えや無意識の問いの存在に気づくことがあるという点です。
つまり読むことは発見なのです。
自分がきちんと認識していなかった領域に踏み出すことを意味します。
それまで当たり前のような感じていたことを、すぐれた作品は本当にそれでいいのか、それが正しいのかと問いかけてきます。
1年生の最初に習う、芥川龍之介の『羅生門』などはまさにそのいい例ですね。
自分が生きていくためには何をしてもいいと下人は考えています。
目の前にいる老婆は死人の髪の毛を抜いてかつらにして売ろうとしているのです。
しかし毛を抜かれているこの死人も、生きている頃は蛇を魚だといって売っていました。
だれもが生きるためには罪を犯していたのです。

だから自分がこの死者の髪の毛を抜いたからといって悪いこととは思わないという結論に至ります。
そうしなければ死んでしまうからです。
この老婆の話を聞いて、その老婆の着物を引き剥がし、夜の闇の中へ消えてしまうのです。
下人は今まで実際に悪事をはたらくのを躊躇っていました。
それにも関わらず、ついに実行してしまいました。
単純に他人のものを盗んではいけないという正義感だけで、この小説を読み切ることはできません。
同時に『藪の中』などを読むと、事実と真実の差を垣間見ることができます。
人は自分の立場をどこにおくかによって、事実さえも違って見えるのです。
長く生きていくと、そういう経験をすることも多々あるでしょう。
多くの裁判例がそれを示しています。
このような犯罪者にも弁解の余地があるということに、驚くことすらあります。
世界に対する認識
すぐれた作品を読むことによって世界に対する認識は変化します。
深く読むことによって作品と自分の関係の変化を意識し、自分の変化に気づくのです。
そのための作品が教科書には多く所収されています。
夏目漱石の『こころ』などもその1つでしょうね。
友情を信じている人にとって、エゴイズムの極致を示した先生の行為は許されないものです。
しかしその先生も罪の意識によって、やがて自死に至ります。
恋は盲目だといいます。
人間は罪悪だという考え方もあります。
自分と世界がどのような関係であるのかということを考えるうえで、いい作品を多く読むことの意味は大きいでしょうね。
読書とは究極のところ、自分との対話なのです。
そのためには限りない想像力が必要です。

自分の周囲にあるたくさんの事実を見ながら、それぞれの関係を探っていく作業です。
うまくいくかどうか。
それは誰にもわかりません。
筆者も最後のところで言っています。
言葉によって、「いま、ここ」にはいない他者とつながることもできます。
もちろん、読むだけではありません。
書くことで、その地平に達することもできるのです。
文学とは何なのでしょうか。
やはり言葉の力でしょうね。
それに尽きると思います。
その広がりと可能性を信じ続けるということに尽きるのではないでしょうか。
今回も最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。