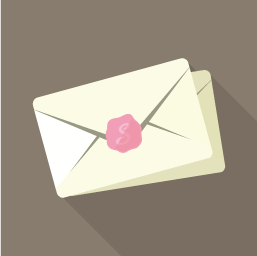私が棄てた女
みなさん、こんにちは。
元都立高校国語科教師、すい喬です。
今回は遠藤周作の小説を取り上げます。
もう亡くなって随分、年月が過ぎました。
1996年です。
もう30年近くが経つんですね。
歳月は人を待ちません。
遠藤周作といえば、誰もが『沈黙』をあげるでしょう。
それくらい重い作品です。
ぼくの友人は高校時代、この小説を読んでしばらく食事が喉を通らなかったと言っていました。
後に篠田正浩監督が映画化もしました。
『沈黙』は江戸時代、キリシタン弾圧の中、ポルトガル人の司祭の目から見た神の問題を正面からとりあげた作品です。
信仰の問題を取り上げた文学作品としては稀有なものです。
戦後の日本文学を代表する作品でしょう。
あまりにも内容が重いので、読むのがつらかったのを覚えています。
ポルトガルの司祭は牢獄に入れられた後、神が本当にいるのなら、なぜ私に救いを授けてくれないのかと呟きます。

それでも神は沈黙したままでした。
宗教にとって救済は永遠のテーマでもあります。
信仰することと、救われるという究極のせめぎあいを歴史の現実の中に見出そうとした作品だけに、多くの人に衝撃を与えたのです。
1度はぜひ手に取ってほしい本です。
学校では全く扱いません。
ここにある考え方は日本人の持つ浄土観に近いという批評家もいます。
ある女性像
『沈黙』よりも以前に書かれた作品が『私の棄てた女』です。
小説は風俗を表現した部分から腐るとよく言われます。
実際、ぼくたちの生活を取り巻く環境は、想像以上のはやさで日々変化しています。
ものの値段や、着るもの、食べもの、乗り物などどれ1つをとってみても以前とは大きく違います。
その点、時代小説の方が書き手にとってかえって楽なのかも知れません。
『私が棄てた女』を再読しました。
この作品は若い頃、映画でも見た記憶があります。
実に暗い作品だというのがその時の印象です。
しかし今回ページをめくりながら、内容以前に、描かれている社会風俗そのものの変化を強く実感として感じました。
ストーリーは大学生の遊び相手にされた女工、森田ミツをめぐる話です。
女工という表現にはそれだけでもう時代を感じてしまいますね。
中学を卒業してすぐに小さな町工場に就職したミツは、大学生吉岡努に声をかけられたということだけで、もう有頂天です。
漢字をいくつも間違えた手紙を彼に送ります。
結果は最初から明らかでした。
彼女は結局吉岡に捨てられてしまいます。

ショックから会社を辞め、職を転々としたミツはやがて水商売に入ります。
しかしすさんだ生活の中でも、男のことが忘れられません。
一方、吉岡は同じ職場の女性で、この会社のオーナー社長の姪との結婚話を進めます。
結婚相手は上流階級の環境で育ったものの、心の底でそれに違和感を持っています。
なぜなら彼女の家の経済は、伯父からの借金に支えられていたからです。
彼女は吉岡と一緒になります。
しかし結婚後も、吉岡の中にある冷たいものを漠然と感じていました。
疎外感を感じる原因が彼女にはわかりませんでした。
この女性の存在が、次第に森田ミツのおかれた立場を強くあぶりだす役割を果たすのです。
聖性への契機
ミツはある日、腕に奇妙な斑点ができたりすることから医者の診断を仰ぐと、ハンセン病と診断されます。
彼女は1度御殿場の病院に隔離されるものの、誤診であったことが判明し、再び自由を得ます。
しかしミツは自分からその病院に戻り院内の手伝いをするようになりました。
献身的な修道女達の姿を自分の目で見たことと、同じ病棟にいた仲間達への憐憫の情が断ち切れなかったからです。
本当はほかにも理由がありました。
修道女たちにとっても彼女の決心は奇特なものにうつりました。
ところがミツはある日、園内でとれた卵を配達している途中、車に轢かれて亡くなってしまうのです。
卵を大切に思う一心の事故でした。
当時、卵は大変貴重な食材だったのです。
少しでもひろわなければと慌てたのでしょう。
誠にあっけない死でした。
その彼女が最後まで口にしていたのが、最初から遊ぶつもりでつきあった大学生吉岡努への真摯な愛情でした。
そのことをミツの知り合いを通じて偶然耳にした吉岡は、完膚なきまでに打ちのめされるという話です。
この小説にはデートの場所として下北沢が登場します。

しかし現在の様子からは想像もできないうらぶれた街の様子が描かれているだけです。
まさに世の中の変化を感じる瞬間です。
駅前の様子など、現在の賑わいからは想像もできない記述が続きます。
この小説の真骨頂はどこにあるのでしょうか。
それはまさに森田ミツという存在そのものの中にあります。
すなわち彼女が持っていた「聖性」にあるのです。
遊ぶために女の心を弄んだ男は、それ故に人間としての存在を否定されます。
それは彼女があまりにも無垢で純真だったからです。
どんな仕事に身を染めた後でも、彼女の心は澄んで清らかでした。
そのことが男の心の汚れを逆に鋭く炙り出していきます。
ここには遠藤周作が他の作品でも追求した宗教的愛とは何かという問題が色濃く反映しています。
ぼくには森田ミツの造形が聖母マリアの影を限りなく反映しているものに思われてなりません。
今もこのような女性が存在するのかと問われれば、形は違うにせよ、いると思います。
『沈黙』への道のり
ミツの心の様子が全編を通じてみごとに描かれています。
ハンセン病と診断され、最初は療養所に強い抵抗を抱いていたミツの様子が細かく描かれます。
やがてその環境にも次第に溶け込んでいった頃、誤診が判明しました。
東京に戻れると思うと、嬉しくて仕方がありません。
御殿場駅で汽車を待っていると、偶然にも昔の女工仲間と再会します。
近々結婚すると幸せそうに話す友人を見て、ミツは孤独感に苛まれるのです。
自分とはあまりにも境遇が違ってしまった友人の姿がそこにはありました。
この瞬間に彼女の何かで何かがかわりました。
奉仕の日々を送る修道女たちを手伝うために自ら療養所へと戻ったのです。
吉岡は一方的に棄ててしまったミツのことが気になっています。

しばらくぶりに療養所宛に年賀状を送りました。
1人の修道女から長い文面の返事が届きます。
年末にミツが交通事故で亡くなったことを知らされるのです。
その手紙にはミツが死ぬ間際に遺したという「さいなら、吉岡さん」という言葉が記されていました。
吉岡はその瞬間、自分がしてしまったことの罪深さを知ります。
あんなに純粋な1人の女性の心を踏みにじったことへの反省でした。
しかしもう全てが遅かったのです。
正確にいえば、罪の感情というより寂しさであったのかもしれません。
人としてしてはならないことを犯したのです。
主人公ミツはどこまでも純粋に人を愛し続けられる女性です。
そこに遠藤周作はイエスやマリア像に結びつく祈りの姿を見て取ったにちがいありません。
この主題はのちに『沈黙』として次の作品につながりました。
映画化にあたって、浦山桐郎が監督をしました。
主演は河原崎長一郎、ミツを演じのは小林トシ江です。
けっして古びた作品ではありません。
人間が持つ最後の聖性を描き切った名作です。
今回も最後までお読みくださり、ありがとうございました。