英米人のことば
みなさん、こんにちは。
元都立高校国語科教師、すい喬です。
今回は英語の変化について考えてみます。
言葉というものはつねに動いています。
文化や時代とともに、やわらかな流動性がなくては生き残れません。
可塑性の少ない硬質な言語は、ラテン語やギリシャ語のように学術以外の場では、次第に衰えていく運命にあるのでしょう。
今日、世界を席巻している生きたことばは、いうまでもなく英語です。
国連の公用語はいくつかありますが、多くの人は英語を使って、コミュニケーションをとっています。
しかし英米人の所有物であったこの言語体系は、日々大きく変化しています。
ことばの裏にある文化をひきずりながら、使われているのです。
私たちはそれぞれの価値観や宗教観などとあわせて、ことばを操っています。
言葉が内側から変容していくのは、ごくあたりまえのことと考えていいでしょう。

だからこそ、英語は生きた言語としての役割を今日背負っているのだといえます。
たまたま言語の本質について考えていた時、次のような文章にめぐりあいました。
この文章は、これまでの英語学習が英米人の発想で話すことを前提としてきたことに対し、根本的な疑問を投げかけています。
筆者は、自身の思考を放棄して英語を学ぶ姿勢は本末転倒であると主張しています。
英語を柔らかな「国際言語としての語学」として捉えるべきだと論じているのです。
使用者の文化に合わせて変容するのが、本来のことばの役割だという立場です。
母語でない人々の思考様式も取り込んで表現可能にすること。
そうでなければ、意味がないと述べています。
具体例としていくつかのケースが取り上げられているので、内容をチェックしてみましょう。
一緒に考察してみてください。
課題文
私が以前あるラジオ英語番組の講師をつとめたとき、母語話者だけでなくさまざまな国からのゲストを招いたことがありました。
そのとき、私が出演交渉をした際のバングラデシュ人留学生の承諾の返事が、まさに世界的な言語としての英語そのものだったのです。
私は、“Could you come to the studio next Wednesday?”(来週の水曜日にスタジオに来ていただけますか)とたずねました。
普通、母語話者をモデルとする英会話ならば承諾の返事は“Sure.” や“Certainly.” などとなるところですね。
ところが、このとき、彼はまず“Maybe.”と答え、さらに“Idon’t know, but I will try.”(わかりませんが、努力します)と付け加えたのです。
この人は日本のラジオ番組に出演することに関してあまり気乗りがしなかったのでしょうか。
実はこれが承諾の意思表示だったのです。
この若者は、ほかのバングラデシュの人びとの多くと同じく、イスラム教徒でした。
そして、イスラム教の信仰では、未来は人間の力が及ぶ領域ではなく神であるアラーの掌中にあると考えられています。
「自分はぜひラジオに出演して母国の話を日本の皆さんに聞いていただきたいと思います。
しかし、それが実現するかどうかはアラーの御心のままです。
自分としてはいま、ここで確約をすることはできないのです」と彼は説明してくれました。
敬虔なイスラム教徒のこの学生としては精一杯の表現だったわけです。
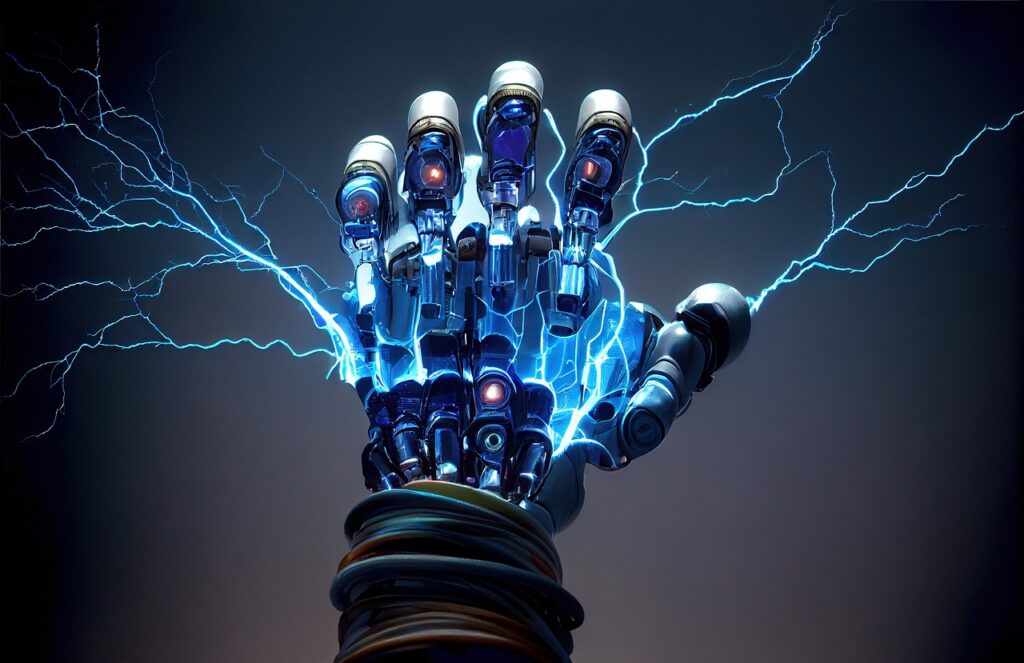
逆にいえば、これが実質的には快諾の返事であったといえます。
文化人類学者のマーガレット・ミードがかつて論じたことがあります。
清教徒の流れをくむキリスト教文化の根付く米国には次のような考え方があります。
未来は、神の助力を得ながらも人間の努力によって決まるという価値観がそれです。
しかしこのバングラデシュ人は、米国文化に基づくアメリカ英語の表現で妥協することなく、非英米的な英語でみごとに自らの世界観を表現したわけです。
英米の枠を越えた世界的言語は、このように使用者の文化に合わせて変容していきます。
それによって、非母語話者の思考を表現する手段として機能しているのです。
本名信行『多文化共生社会をめざして』
文化と言語
日本人は通常、YesNoをはっきりとは言いません。
曖昧な表現でぼかしてしまうのが普通ですね。
しかし英語で話すときは、はっきりと諾否を伝え、その理由まで述べるケースが多いです。
以前勤めていた学校には、たくさんの外国人がいました。
それと同時に外国から戻って来た英語の得意な日本人の生徒も多くいたのです。
彼らは、ふだん日本語で話していました。
しかし、時に英語を使う授業の時などはその態度が微妙に変化するのを感じたものです。
一言でいえば、いつもより強く見えたのです。
その事実に驚いた記憶があります。
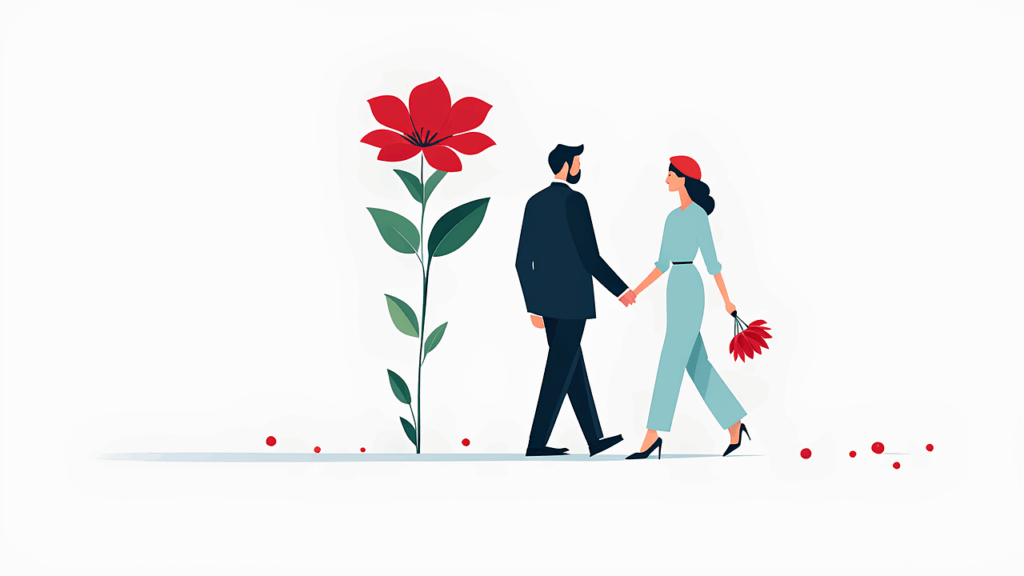
これは話者の性格が変化したというより、言語の構造がそのかたちを望んでいたといった方がいいのではないでしょうか。
英語の構造として、当初から肯定と否定を明確に示します。
そして次にその理由を述べるのです。
この話し方を次々と繰り返していくうちに、自分の思考体系を相手に示し、理解を促すのが普通になります。
文法的にも、かなり早い段階で、YesかNoがはっきりと相手に伝わります。
ところが日本語では、最後まで聞かないと、「です」なのか「ではありません」なのかが明らかになりません。
曖昧にぼかしてしまうことも可能なのです。
ましてや、いちいちその理由を説明するという習慣もないのです。
「なぜなら」という表現を使って説明を繰り返すと、こなれない日本語になります。
堅苦しい、理屈っぽい印象を相手に与えるのです。
しかし英語を使っていると、それが無意識のうちにできます。
傍らで会話の様子をみている人にとって、性格まで変わって見えるという理由はここにあります。
まさに言語の持っている構造といってもいいのではないでしょうか。
国際語としての英語
今日、英語は国際語としての地位を確立しています。
それだけにいろいろな性格の英語があっていいはずです。
むしろ、そうでなければ、生き残れない立場に置かれていると考えるのが自然なのかもしれません。
自分の考えを表現するために英語を学んでいるにもかかわらず、自身の思考を放棄してしまっては、伝えるべきものがなくなってしまうからです。
私たちが今日、習得しようとしているのは、英国や米国の言語としての英語ではありません。
「国際言語としての英語」と呼べる形式のものです。
その使用者の文化に合わせて変容するのはあたりまえのことです。
この変容を通じて、母語でない話し手の思考様式を表現する手段として機能するのです。
ある意味で、非英米文化圏に住む人々が、米国の文化に妥協することなく、自らの世界観を英語で見事に表現できるのはすばらしいことです。
これは日本人にとっても大切な視点ですね。

以前は英語学習の前提として、英語を話す際には「日本的な発想を捨てて英米人のような発想で話す」ことが求められてきました。
極端な場合、ジェスチャーまでそれらしく振る舞うことさえありました。
大切なのは、私たちが自己を表現するために英語を学んでいるという厳然たる事実です。
もし自身の文化的背景に根ざした考え方を放棄してしまったら、相手に伝えようとするもの自体がなくなってしまう可能性すらあります。
イスラム人ならば、彼らの文化を背負った形での英語があってもおかしくはありません。
異文化の価値観や信仰が英語でのコミュニケーションに大きな影響を与えるのは当然のことです。
清教徒由来のキリスト教文化が背景にあるアメリカ人にとって、未来は努力の結晶でした。
しかしイスラム教の人にとって未来は全て、神アラーの掌中にあるのです。
人間の力が及ばないことはだれもが知っている真理なのです。
このように、異文化の価値観や信仰を光源にして、ものを見る時、自身のアイデンティティや思考を放棄することなく、国際語としての英語を通じて独自の視点を伝えることを可能にしなければなりません。
そのことをどのように自分の体験の中でまとめきるのか。
それがここでの大きなテーマになりますね。
ことばという文化の根底にある1つのファクターから、さまざまな文章を書いてみてください。
今回も最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。


