紫式部日記
みなさん、こんにちは。
元都立高校国語科教師、すい喬です。
今回は日記を取り上げましょう。
『紫式部日記』は2巻からなる日本を代表する日記です。
成立は平安時代中期、1010年頃と言われています。
一条天皇の中宮彰子に仕えていた1008年7月頃から約1年半の生活を記録しています。
同時代の女房たちの批評や自分の人生についての思いが、素直にまとめられています。
その中でも、紫式部の学識の深さを知るにはこの段を読むのが一番でしょうね。
漢学の知識を他人にみせないようにしていたことがよくわかります。
深読みをすると、そこに彼女の学問に対する自負が垣間見えます。
清少納言は自分の学才をこれでもかと他人に見せびらかそうとしましたが、紫式部は内にこもります。

自分の才能を外に表そうとする態度は、彼女にとって最も恥ずべきことだったのでしょう。
だからこそ、「一」という文字でさえ、読めないふりをしていたのに、周囲の人はそんなことを気にしないのです。
これはある意味、清少納言へのあてつけもあるのかもしれません。
紫式部は「真名書き散らし」ていると、清少納言が言いふらしていることが心の底にはあったものと思われます。
真名というのは漢字のことです。
当時、漢字は男性が仕事に使う正式な文字でした。
それを女だてらに使いこなす紫式部の存在がめざわりだったのでしょう。
とはいえ、紫式部自身、中宮彰子に向かって『白氏文集」の講義をしていると自慢気に書いてもいるのです。
本来ならば帝に認められるような漢学の知識も、宮中では嫉妬の対象になります。
女房同士の複雑な人間関係が彼女の心理状態に影をおとしているのがよくわかります。
中宮彰子にいたっては『白氏文集」を講義してほしいという望みまで明らかにします。
だれもいない時にこっそりとしている講義でも、宮中のことはいつか誰かの目に触れてしまうものです。
そのことを怖れている紫式部の内面が実にみごとに描かれていますね。
また悪口を言われると思っただけで、彼女は暗い気分になったに違いありません。
本文
左衛門の内侍といふ人侍り。
あやしうすずろによからず思ひけるも、え知り侍らぬ心憂きしりうごとの、多う聞こえ侍りし。
内裏の上の、源氏の物語、人に読ませ給ひつつ聞こしめしけるに、
「この人は、日本紀をこそ読みたるべけれ。まことに才ざえあるべし。」とのたまはせけるを、
ふと推しはかりに、「いみじうなむ才がる。」と、殿上人などに言ひ散らして、
日本紀の御局とぞつけたりける、いとをかしくぞ侍る
このふるさとの女の前にてだにつつみ侍るものを、さる所にて、才さかし出で侍らむよ。
この式部丞といふ人の、童にて書読み侍りし時、聞き習ひつつ、かの人は遅う読み取り、忘るるところをも、あやしきまでぞさとく侍りしかば、
書に心入れたる親は、「口惜しう。男子にて持たらぬこそ幸ひなかりけれ。」とぞ、常に嘆かれ侍りし。
それを、「男だに、才がりぬる人はいかにぞや。はなやかならずのみ侍るめるよ。」と、やうやう人の言ふも聞きとめて後、
一といふ文字をだに書きわたし侍らず、いと手づつにあさましく侍り。
読みし書などいひけむもの、目にもとどめずなりて侍りしに、いよいよかかること聞き侍りしかば、
いかに人も伝へ聞きて憎むらむと、恥づかしさに、
御屏風の上に書きたることをだに読まぬ顔をし侍りしを、宮の、御前にて、文集のところどころ読ませ給ひなどして、
さるさまのこと知ろしめさまほしげにおぼいたりしかば、

いと忍びて、人の候はぬもののひまひまに、一昨年の夏ごろより、楽府といふ書二巻をぞ、しどけなながら教へたて聞こえさせて侍る。
隠し侍り、宮も忍びさせ給ひしかど、殿も主上も気色を知らせ給ひて、御書どもをめでたう書かせ給ひてぞ、殿は奉らせ給ふ。
まことにかう読ませ給ひなどすること、はた、かのものいひの内侍は、え聞かざるべし。
知りたらば、いかにそしり侍らむものと、すべて世の中ことわざしげく、憂きものに侍りけり。
現代語訳
左衛門の内侍という方がいます。
その人が私のことを快からず思っていたようなのです。
理解できないような不愉快な陰口が、たくさん耳に入ってきました。
一条天皇が、源氏の物語を、人に読ませなさってはお聞きになっていた時に、
「この物語を書いた人は、『日本書紀』のような歴史書を読んだにちがいない。
本当に学識があるのだろう。」とおっしゃったのです。
それをこの内侍が聞いてすぐ当て推量に、「式部はたいそう学識をひけらかす。」と、殿上人などに言いふらしました。
私に日本紀の御局というあだ名を付けたりしたのは、本当に滑稽でございました。
私は実家の侍女の前でさえ漢籍を読むことをはばかっておりましたのに、ましてや宮中のような所で、学識をひけらかしたりすることがあるでしょうか。
式部丞という人が、まだ子どもの頃、漢籍などを読んでいたことがありました。
私はそれをそばでいつも聞き習っていたのです。
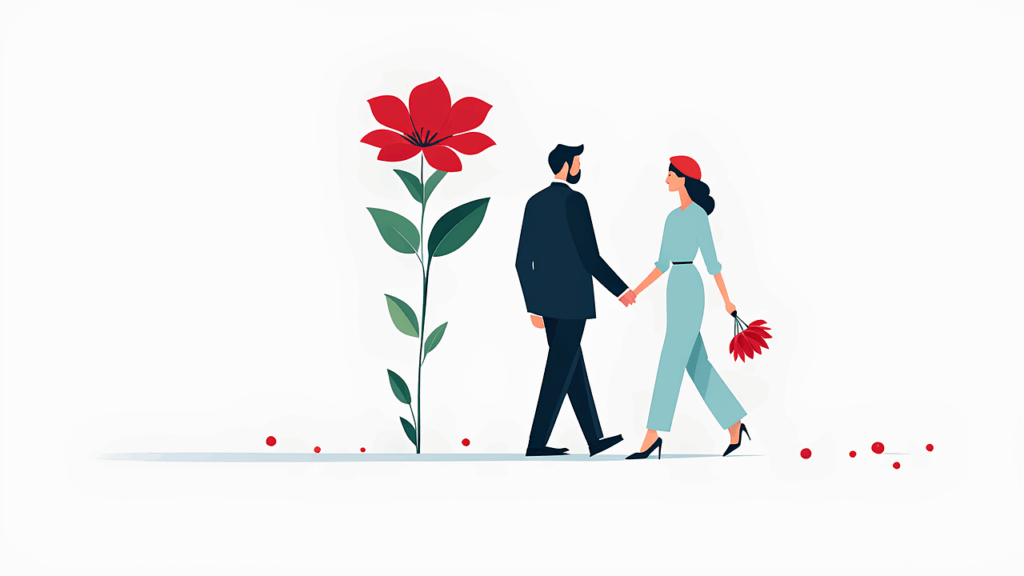
式部丞がなかなか読み取れず、忘れてしまうところも、なぜか私は不思議なくらい理解が早かったので、
漢籍に熱心だった親は、「本当に残念なことだ。この娘を男の子として持っていないことこそ不運なことだな。」と、いつも嘆いていらっしゃったのです。
それなのに、「男でさえ、学識をひけらかすなどいうのは感心したことではないのに。」と、人の言うのを聞きとどめた後は、
「一」というもっとも簡単な文字さえ書きませんでしたし、とても漢字など読み書きもできず驚きあきれるほどにしていました。
以前読んだ漢籍などといったようなものに、目をとめることもなくなっていたのに、ますますこのようなことを耳にするにつけ、
こんなうわさ話を伝え聞いて、他の女房方はさぞ私を憎んでいるだろうと思いました。
恥ずかしさのために、屏風の絵の上に書き添えられている漢詩文さえ読まないふりをしておりましたところ、中宮様が御前で、『白氏文集』のところどころを私に読ませたりなさるのです。
漢詩文のことをもっとお知りになりたそうに思っていらっしゃったので、
ほかの人がお仕えしていない合い間合い間に、一昨年の夏頃から、『白氏文集』の中の「新楽府」という書物二巻を、おおざっぱにですがお教え申し上げておりました。
私もそのことをずっと隠しておりますし、中宮様も人目につかないようになさっていらっしゃったのです。
しかしなぜか、殿も一条天皇もその様子をお知りになって、殿が書家に漢籍などをすばらしくお書かせになって、それを中宮様に差し上げなさいます。
本当にこのように中宮様が私に漢籍を読ませたりしたら、きっと、あの口さがない内侍が、聞きつけるにきまっています。
もし知ったならば、どんなにか陰口を言うことでしょうと考えただけで、何事につけて世の中にはさまざまなことがあり、煩わしくて仕方がありません。
複雑な人間模様
藤原道長が自分の娘彰子に家庭教師役の女房、紫式部を召したのは大きな成果でした。
彼はどうしても権力が欲しかったのです。
そのためには一条天皇との間に男子が必要でした。
その子が帝になれば、道長は外戚になれます。
紫式部の持つ学識がどうしても必要だったのでしょう。
特に物語を作り出す彼女の才能は、定子に向かっていた天皇の関心を彰子に向けるきっかけとなりました。

当時、高価だった紙をふんだんに与え、時間との戦いのようにして、『源氏物語』を自分の戦利品にしていきます。
その結果、天皇が彰子のところを訪れる機会が増えました。
やがて彰子に男の子が生まれたのです。
紫式部はその役目を果たし、やがて疲れ果ててしまいます。
しかし日記に描かれた時期は、ある意味、最も精神的に高揚していた時に違いありません。
彼女の人となりを知るには、やはりこの日記と『源氏物語』を読むのが、一番手っ取り早いのではないでしょうか。
複雑な精神構造をもった知的な女性であることがよくわかります。
その周囲にいた人びとたちとの関係を丹念に追いかけていけば、さらに多くのことがわかると思います。
ぜひ、多くの機会に触れてください。
今回も最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。


