価値観の転換
みなさん、こんにちは。
元都立高校国語科教師、すい喬です。
今回はよりAIのもたらした変化について、より本質的な問題を考えてみます。
AIの進歩があまりにもはやく、人間はかなり追い詰められつつあります。
自動運転やロボットの制御などは、AIによってかなり正確に判断されるようになりました。
かつて人工知能がやり遂げた領域をはるかに超えつつあるのです。
このまま進んでいくと、どこまでいくのかまったく予測がつきません。
日進月歩という言葉がもっともふさわしいでしょう。
しかしだからといって、人間はAIに全ての判断を委ねるというレベルまでは達していません。
裁判における法律の判断や、政治的に最善の決定をAIに任せるという話はまだないです。
そこまで話が進めば、次は国家間の懸案にまで踏み込んでいくに違いありませんね。

複雑な世界の政治状況を判断し、自国にとっての有利な政策とは何かということが、大きなテーマになるはずです。
では現状はどうなのか。
ここではある大学の入試に出題された文章をヒントに考えてみます。
このテーマは昨年、小論文の課題として提示されました。
AI時代において人間に期待される望ましい価値とは何かということです。
もっとわかりやすくいえば、人間にしかできない究極の要素とは何か。
それを考えてみようという本質をついた鋭い問いです。
このような問題が入試にでるようになったということが、時代の変化そのものなのかもしれません。
問いは2つありますが、難しいのは以下の内容です。
AIが飛躍的に進化する時代を迎え、どのような能力が高く評価されるようになるのか。
あなたが考えることを600~800字以内で述べなさいというものです。
課題文は長いので、ここでは一部だけ取り上げます。
課題文
AIは「普通の人」や「普通のエリート」に求められるようなことは、ほぼ全てできます。
個性のない仕事は全てAIがやるようになっていくでしょう。
あとは法的な整理がどこまで追いついてくるか。たとえば人間以外の人が弁護士になれるのか、会社の代表になれるのか。
そういったことが整理されるまで、人間は一種の人身御供として、AIの後見人として必要とされるはずです。
しかし、それもそんなに長い間は続かないし、そうしたときに人間の価値は相対的に下がっていくように見えるかもしれません。
このような時代に価値を持つ能力とは、これまでどちらかというと無価値と思われていた2つの能力でしょう。

一つは、「人のやらないことをやる」ということ。
誰かの真似をするだけで飽き足らず、自分なりの工夫をしようとする能力です。
クリエイティビティと呼んでもいいでしょう。
特に日本の教育現場では、このクリエイティビティを伸ばす教育が全くケアされていません。
それどころか、クリエイティブなことをしようとする児童や生徒をスポイルしようとすることが多い。
しかしこれからの時代は、クリエイティブであることが何よりも重要になります。
今後、最も価値が高い労働は表現労働であり、これまでのような定型処理を没個性的にこなすという仕事は、どんどん価値が下がっていくでしょう。
もう一つの能力は、繰り返しになりますが、こちらもこれまで教育現場で価値を認められなかった能力です。
それは他人を思いやる力。
いわば「ホスピタリティ」とでも呼ぶべき能力です。
「思いやりのある子です」は褒め言葉ですが、「思いやりがある」という理由で上位の学校に行けることはあり得ません。
反対に、「思いやりのない子」でもテストの成績が高いという理由で上位の学校に行くことはごく当たり前にあります。
ところが、テストの成績が高いという能力は、AIの持つ本質的な能力に勝てません。
むしろAIが苦手とする、「人のやらないことをやる」「他人の気持ちを思いやる」ことを大切にすることが、これからの時代の人々に求められる能力であると言えるでしょう。
(「教養としての生成AI」清水亮著 幻冬舎新書 2023年)
クリエイティビティとホスピタリティ
筆者のポイントを整理します。
それはAI時代において価値を持つとされる2つの能力についてです。
すなわち「人とは違うことをする能力(創造性)」と「他人を思いやる能力(ホスピタリティ)」です。
このキーワードをきちんとおさえておかないと、この問題では全く評価されません。
受験者は、AIの出現による変化と、今後の時代に求められる能力について、それぞれ指定された文字数で説明を求められるのです。
今までは「真面目であれ」「平凡であれ」、あるいは「テストにパスしてエリートになれ」といった価値観が先行していました。
あるいは今もそうした考えにとらわれている人は多くいます。
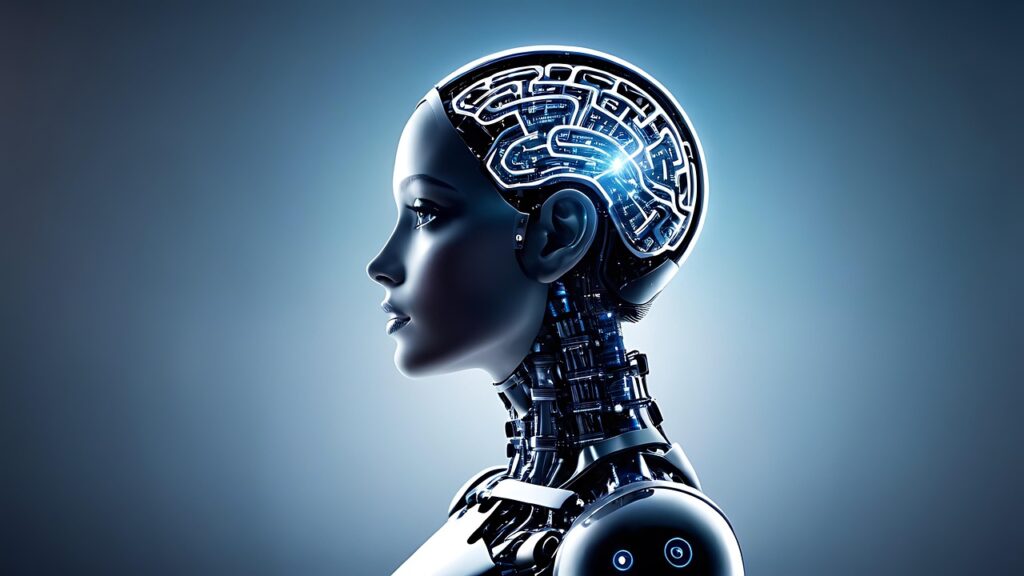
しかしそれはAI時代に通用しないというのが、筆者の論点です。
テストのための勉強に高い価値があった時代が終わりを告げようとしているのです。
なぜでしょうか。
この分野ではAIの方がずっと優秀だからです。
AIは一度記憶したことを忘れません。
新しい思考がインプットされると、以前の情報は消されて上書きされるのです。
AIは「普通の人間」や「普通のエリート」に求められていたほぼ全てのことを実行できます。
結局、個性のない仕事はAIが担うようになり、結果として人間の価値が相対的に低下する可能性があるのです。
消えていく職業の一覧を見た人は理解できますね。
単純作業をはじめとして、繰り返しに頼るタイプの仕事は急速にAIにとってかわられつつあります。
これからの価値観
教育の世界は過去を踏襲するのが得意です。
人間はそれほど急速に変化できませんのでね。
そこで偏差値が跋扈するような不自然な学校教育がいつまでも蔓延するのです。
筆者はそれを否定しています。
一つは、「人のやらないことをやる」という能力、すなわちクリエイティビティです。
誰かの真似をするのではなく、自分なりの工夫を凝らす力を指し、これからの時代において最も価値が高い労働は表現を主体とする労働になると筆者は指摘しています。
日本人にはこのクリエイティビティという観念が薄弱なのかもしれません。
人間独自の創造性や表現力こそが、これからの価値です。
逆にいえば、創れない人間は早期に退場せざるを得ないということなのです。
もう一つは、他人を思いやる力です。
「ホスピタリティ」と呼ぶべき能力です。
「思いやりがある」ということをたかく評価したとしましょう。
しかしそれが理由で高偏差値の学校に進学できるとは限りません。
テストの点数と「思いやり」はむしろ反比例してきたような気さえします。
成績もひとつの能力には違いありません。
しかしそれはAIにとってかわられやすいものの代表なのではないでしょうか。

やがてシンギュラリティと呼ばれるAIが人間を追い越す日が来るのは近いと思われます。
その一方で、AIが苦手とするものの代表が「他人の気持ちを思いやる」ことです。
この筆者の考え方に反対するのは困難な気がします。
AI時代において、人間は従来の競争から脱却する道を考えなくてはなりません。
競争からの脱け出るための道筋はどこにあるのでしょうか。
「真面目」「平凡」「優秀なテストの成績」を頭から否定するつもりはありません。
しかし着実にAIに駆逐されつつある従来の価値観が、今呻吟しつつあるようにも見えます。
自分なりの工夫を凝らす能力をどうしたら育めるのか。
教育現場の意識改革も必要でしょう。
共感が生まれる土壌を育てることも大切です。
多様な表現活動を評価する環境も不可欠です。
問題はまさに山積しています。
どこから切り開いていけばいいのか。
それをあなたの言葉で書き込んでみてください。
今回も最後までお付き合いくださり、ありがとうございました。


