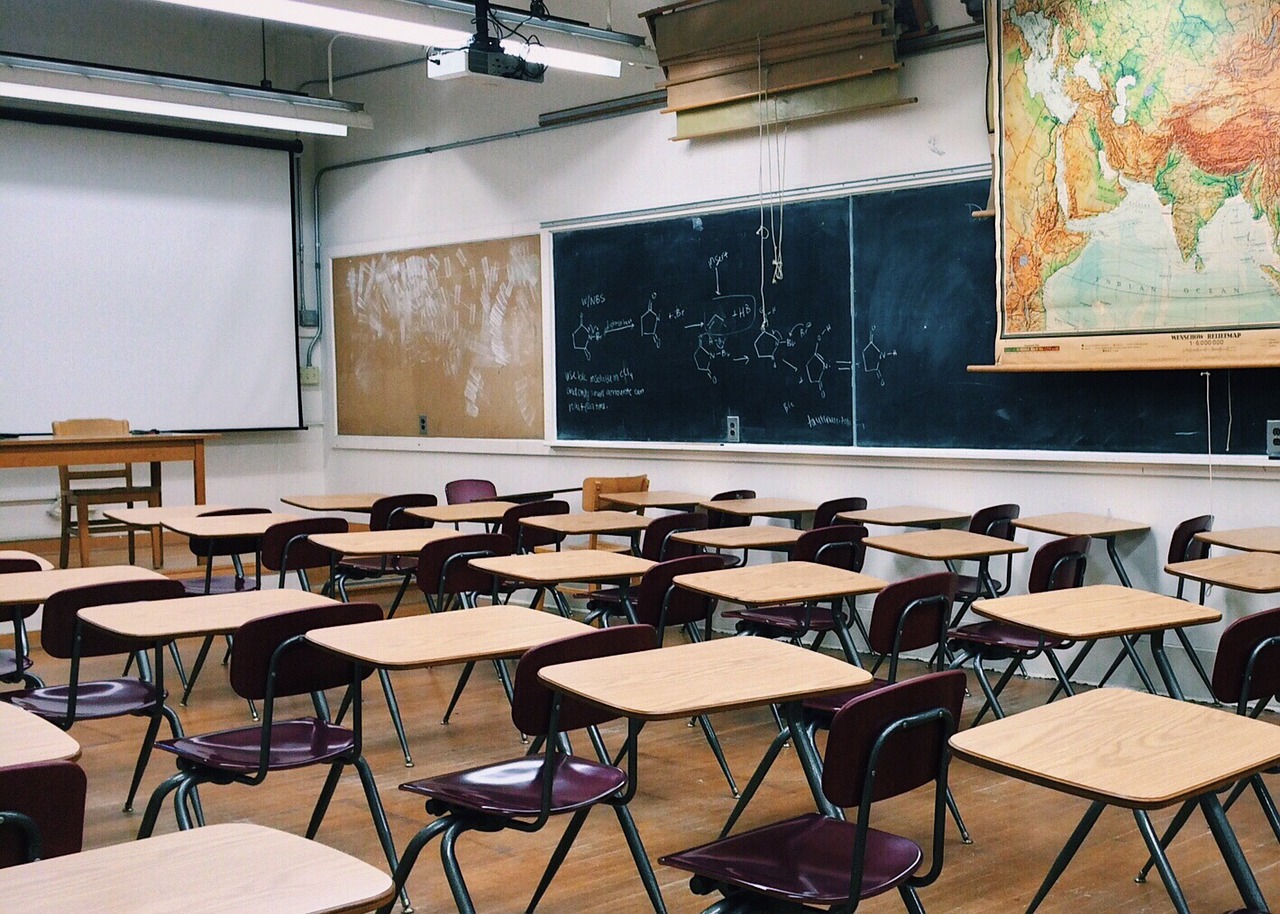調査の結果
みなさん、こんにちは。
元都立高校国語科教師、すい喬です。
今回は2024年度「経年変化分析調査」の結果を考えてみたいと思います。
この調査は、小学6年(約3万人)と中学3年(約7万人)を抽出して3年ごとに同じ問いで変化を分析するものです。
教科は小6が国語と算数、中3は国語と数学と英語です。
あわせて、保護者にも質問調査があります。
いずれも内容は明らかにされていません。
同じ問題を非公表で3年ごとに繰り返すという点がユニークですね。
それだけに学力の変化もよく見えます。
今回のトピックスは2021年度に行われた前回の時より、全教科で成績が下がったことです。
これには関係者のショックが大きかったと報道されました。
今回の結果は以下の通りです。

500を基準とするスコア表示で、平均スコアが小6、国語489.9(前回比15.9ポイント減)、算数486.3(同20.9ポイント減)。
中3、国語499.0(同12.7ポイント減)、数学503.0(同8.0ポイント減)、英語478.2(同22.9ポイント減)でした。
全ての科目において、平均が下がるというのは、やはり何かの原因がそこにあると考えられます。
最もイメージしやすいのはやはりコロナ禍の影響で、コミュニケーション重視の指導が不十分であった可能性もあります。
声に出して互いに伝達しあうというタイプの授業が、きちんとできなかった弊害があると考えられるからです。
しかしそれにしても全科目で数値が低いということの背景には、もっと別の理由があるのかもしれません。
保護者への質問
保護者への質問調査も気になりますね。
ここからは明らかにスマホやゲームに依存して生活をしている子供たちの姿が、浮き彫りになってきました。
デジタル機器の使用に時間を費やす子供が、明らかに増えています。
先日もその結果、視力が低下しているという記事がありました。
当然、学校外の勉強時間も減っています。
しかしポイントはそれだけではありません。
子どもが良い成績をとることにこだわらない保護者も、増えているという事実なのです。
そんなばかな話があるだろうかと思う人も多いのではないでしょうか。
平日に子どもと学校の勉強の話を「いつもしている」「よくしている」と答えた保護者は小6が40.0%、中3が35.1%でした。
前回の調査より、2.1~3.3ポイント低くなっています。
また子どもについて保護者に次のような質問もしました。
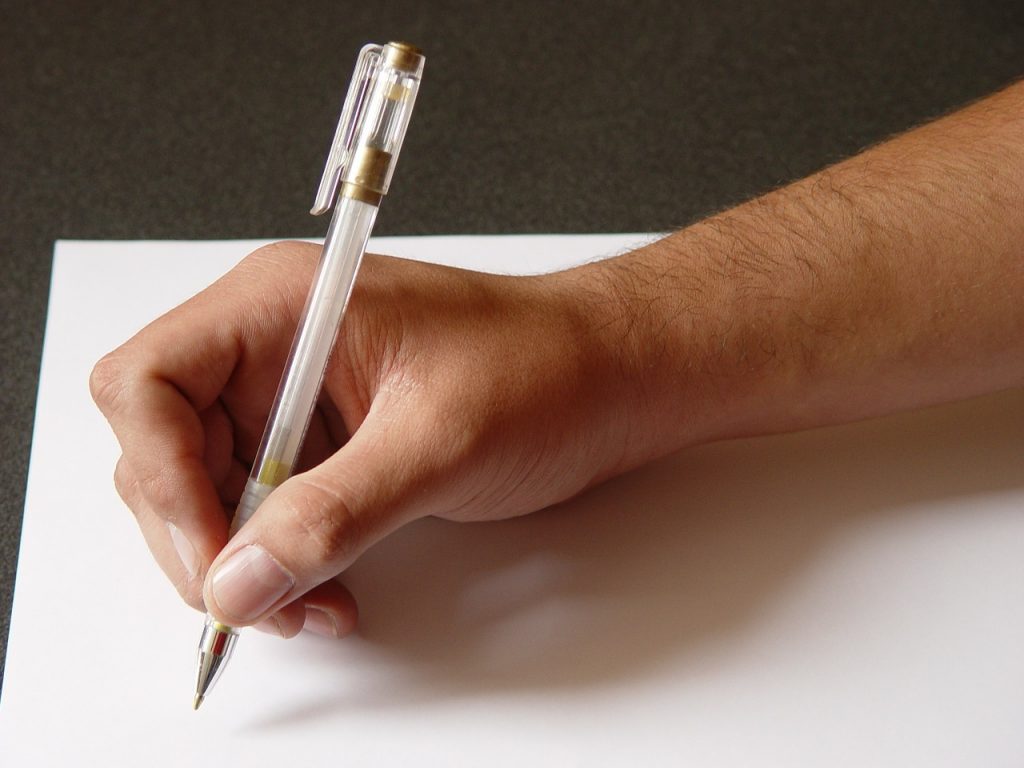
「学校生活が楽しければ、良い成績をとることにはこだわらないと考えている」かどうかということです。
「当てはまる」「どちらかといえば、当てはまる」は、小6が59.7%、中3が52.4%。
2013年度の調査より、小6は4.8ポイント、中3は6.0ポイント高いのです。
どういう理由からでしょうか。
ここに最近の学校が抱えている重大な問題があると思われます。
その最大の要因は「不登校」です。
かつて不登校児はクラスの4%と言われていました。
しかし中学校段階になると、10%を超える学校も多くなっているのです。
そのために不登校児だけを比較的自由なカリキュラムの中で扱う、特別クラスも増えています。
親の希望としては学力が高いことを気にする以前に、とにかく「楽しく登校してくれればいい」という最低限の望みがそこにあるのです。
経済的な環境
子ども食堂のことはよくマスコミにも取り上げられますね。
経済的に苦しくて、満足に食事も与えられないという話はよく聞きます。
そのために特別な食堂を運営しているNPO法人などがたくさんあります。
最も厄介なのは夏休みのような長期的な休業の時です。
普段は給食により、ある程度の栄養が取れていても、長い休みに入ると、それも不可能になります。
休み明けに痩せてしまった児童の様子がマスコミでよく報じられます。
物価高で経済的に苦しい世帯では、満足に食事がとれない家庭も多いのです。
逆にいえば、子どもの成績など気にしていられないというのが、親の本音でしょう。
また昨今では入試の形態も大きく変化しています。
特に少子化が顕著になるにつれ、閉校になる学校も増えてきました。
無理に背伸びをしなければ、大学に入学することも可能です。
大学側も入試の形をさまざまに工夫し、なるべく早い時期に定員を確保したいという本音が見えます。

「総合型選抜」と呼ばれるかつてのAO入試は、学校の成績だけでははかれない要素を多く加味します。
特に「探求」と呼ばれる生徒個人の特性にあわせた研究の内容は、学校の成績とは違うレベルの話になります。
しかし「良い成績にこだわらない」とした保護者の子の方が、学校外の勉強時間が短い傾向は確実にあります。
一方では「不登校」の問題におびえている親もいます。
さらに「経済的に苦しい」家庭では、子どもの学力以前に生きていくというレベルが最も大切な目標になりつつあるのです。
その一方で、定員を充足したい大学は、年内入試に舵をきったところもあります。
文科省も2科目で、年内に行う推薦入試さえ認めることになりました。
問題の背景は輻輳化しています。
スマホとゲーム
勉強時間が少ないことの原因は以前はテレビでした。
しかし今は圧倒的にスマートフォンです。
平日の使用平均時間は、小6、ゲーム1時間43分(前回比18分増)。
スマホ1時間5分(同22分増)。
中3、ゲーム1時間48分(前回比22分増)、スマホ1時間56分(同20分増)。
ゲームの時間が長い子どもほど、調査のスコアは低い傾向でした。
またスマホも一定の時間を超えると、スコアは下がりました。
それだけ時間を費やすことで、学習に対するエネルギーが低くなっていったことは容易に推測されます。
勉強時間もそれぞれ前回よりも当然減っています。
保護者はこの数値とどう向き合えばいいのでしょうか。
やはり「ルール」を親子で作り上げる以外にはないでしょうね。
親子のコミュニケーションももちろん大切です。
デジタルだけが全てではないことを知らせる必要も親にはあります。

メディアとの接触だけでは、経験値が不足します。
それを補うのがスポーツであり、芸術などの活動であることは明らかです。
しかし経済的な資力がなければ、それもかなわないのが現実なのです。
格差社会のなかで、そのあたりのバランスをどう探っていくのか。
学校の教科目から抜け出た「探求」の意味なども、親子で語り合えれば、それも新しい学力観の中に組み込めると思います。
親の役割がますます複雑になっていることは明らかです。
スマホ、ゲーム、勉強時間の組み合わせについて、ゆっくりと家族で検証していく必要があります。
今回も最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。