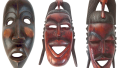マークスの山
みなさん、こんにちは。
元都立高校国語科教師、すい喬です。
今回は作家・高村薫が朝日新聞へ寄稿した文章をもとに、少しだけ考えたことをまとめます。
ぼくは彼女の作品を数冊しか読んでいません。
あまりいい読者ではないのです。
最初に手にとったのは『マークスの山』でした。
生徒を引き連れて夏の合宿へ行った時の記憶と重なっています。
1986年、三原山の噴火の衝撃がやっと癒えた頃だったのです。
この作品が発表されたのは1993年3月。
分厚い本でした。
それをもって大島のセミナーハウスへ向かったのです。
合宿でどんなことをしたのかは、ほとんど覚えていません。
しかしこの小説の重苦しさだけは忘れられないのです。
登場人物たちの行動がそれぞれの日常性の中に埋没しています。
特に奇妙なこともありません。
しかしそれが複雑にからんでいくと、殺人事件になってしまうのです。
警察内部の複雑な人間関係には、嫌気がさしました。
北岳の山中で、心中によって両親を失った少年・水沢は山で救助されます。
マークスという名の青年が誕生したのです。
ここからドラマが始まります。
彼は盗みに入った家で偶然遺書を手に入れました。
癌を患って苦しんだ男のものでした。
そこにはかつて北岳で起こった犯罪行為のことが告白されていたのです。

遺書に登場する人物たちをゆすることを考えたマークス。
水沢の網に捉えられた男たちは、一様に抵抗します。
そこから次の殺人事件が起こっていくのです。
今までにこれほど重い気分を引きずった小説はないですね。
合宿中に読み切れず、家に戻って読了しました。
気分は暗かったです。
救いはどこにもない。
ここまで人間の気分を暗鬱にする小説は珍しいのではないかと感じました。
この後、続けて読んだのは『照柿』です。
どちらの作品も大変重苦しく、心象風景はどんよりと霞んでいました。
彼女の冷静な視野には、羨望さえ感じます。
朝日新聞への寄稿
2025/7/3の朝刊に載った高村薫の文章は、この作家の冷静な目を感じさせるに十分なものでした。
それは日本がどこへ向かっていくのかを予見させるものです。
世界がこれだけ傍若無人になっていく中で、日本はどんどん委縮し、その力を失いつつあります。

かつての威信はどこへ消えたのか。
今は極東の島国として、アメリカの傘の中に入り、台湾包囲網の最前線に立たされているというのが現実です。
本文
年初めの1月28日朝、埼玉県八潮市の県道交差点で道路が突然陥没し、たまたま通りかかったトラック一台が転落、地中に呑み込まれた。
そのため、事故直後に生存が確認されていた運転手の救出は予想外に難航し、大量の土砂と下水に埋まったトラックと運転手が引き揚げられたのは、事故発生からほぼ3カ月経った5月のことだった。
近年の私たちはいつの間にか生活道路の陥没やひび割れに慣れ、ああまたかと思いながら漫然とやり過ごしているに過ぎない。
そしてくだんの陥没事故を目の当たりにしたとき、私は一抹の寂しさとともに突如、これこそ自分が生きている社会の掛け値なしの実相というものだと腑に落ちていたのだ。
この感じは近年、社会の至るところで目にするものである。
たとえば、明確なテーマを欠いたままめぼしいコンテンツを寄せ集めただけの大阪・関西万博がある。
1970年の万博と比べれば個々の展示にかける意気込みも創意工夫も費用も大きく見劣りがし、よく言えばSDGs、悪く言えば安普請のやっつけ仕事は目を覆うばかりである。
もともとテーマの設定にも無理があったところへ、無理に税金をつぎ込んで強行してみたものの、いまや国力の衰退までは覆い隠せなかったと言うべきか。
マイナ保険証は使い勝手が悪すぎて普及せず、医療機関のオンライン資格認証も現場ではトラブルが絶えない。
根底にあるのは 抽象的な規格を立てることはできてもそれを具体化して推進するための計画と管理運用のためのシステム設計ができない日本人全般の残念な資質である。
思えば94年前、私たち日本人はこうして満州事変に突き進んだのだろう。
そこから日中戦争を経て 太平洋戦争に至るまで、世界恐慌下の国際情勢を正確に読み取り、自国の国力や 戦力を慎重に測りにかけ、出口戦略を含めた周到な見通しを立てていたなら、元より侵略戦争などできるはずがなかった。
2025年の夏、21世紀初頭まであった国際秩序はもうない。
今や自国第一主義を掲げて専横を極めるアメリカと他国への武力侵攻を狙う覇権国家の中国とロシアが、世界をそれぞれの勢力圏に分割する勢いである。
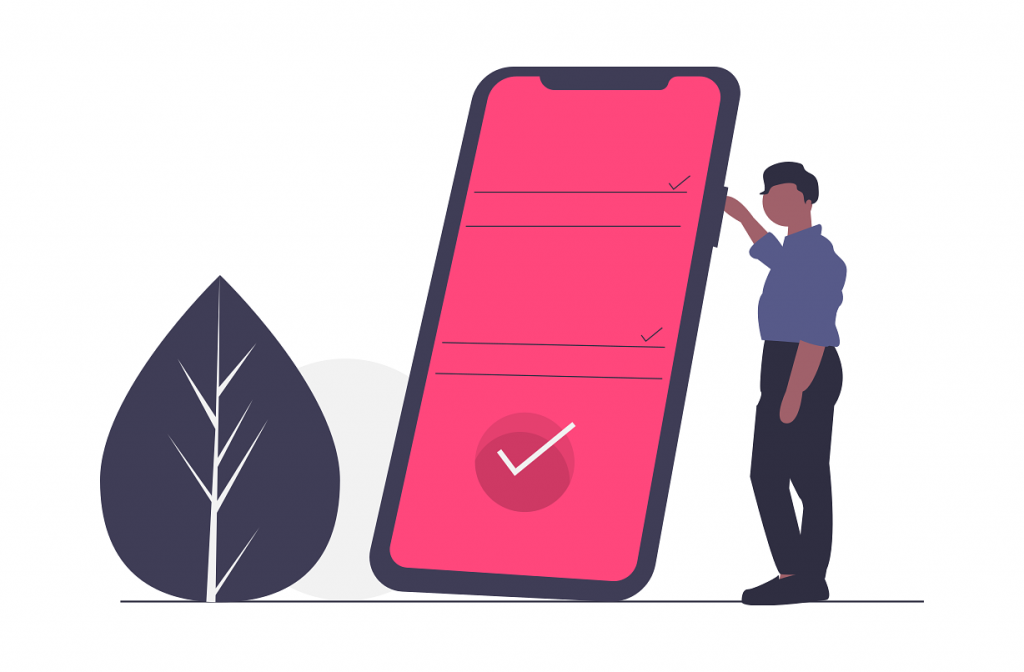
最新の日本の相対的貧困率はアメリカや韓国にも抜かれて15.4%であり、先進国で最も貧しい。
それでも群を抜いて国内の治安はよく、私たちは生活不安を抱えながらもグルメだの、「推し」だのと、それなりに生活を楽しみ、町ゆく人々の表情も明るい。
しかしそれもそのはず、私たちはそうして今だけを見、見たくないものは見ない。
老若男女は日々の刺激を求めてWebに集まり、それが時に一過性の潮流を作ったりもする。
政府の債務残高が1323兆円を超え、国家の信用が揺らぎつつある日本に戦争する金はない。
しかしながら雨が降ろうが槍が降ろうが、この現実をだけは変わらないことは肝に銘じておけば今しか見ない私たちでも、多分何とかなる。
慣れの怖さ
かつて評論家・加藤周一は『夕陽妄語』にこう書きました。
「人は歴史に学ばない」
この言葉は彼の諦めそのものだったのでしょうか。
次々と戦争が引き起こされ、たくさんの人が死んでいきます。
多くの難民がガザのような狭い地域に閉じ込められ、そこをめがけて爆撃が続いているのです。
核の脅威は衰えるどころか、日々増殖しています。
昨今はSNSをめぐる、さまざまな事件も起こっています。
特にスマホが普及してから、盗撮や誹謗中傷などが頻発しました。
匿名の犯罪が増えているのです。
スマホを使って短期の闇バイトに応募することも容易です。
それが犯罪につながるケースも大変多いです。
電話やメールを使った振り込め詐欺もあとを絶ちません。
それでも、日本はまだいい方だと言われると、どこに臨界点を置けばいいのかわからなくなります。
慣れは恐ろしいです。
かつては小さなコミュニティの中で完結していた人々の暮らしが、際限なく広がりを持ち始めました。
それが全て匿名を可能としているのです。

最近では高度に匿名性をもった通信アプリも利用されています。
これでも日本はまだ無事なのでしょうか。
確かに人々の生命の安全が守られるのなら、少々生産性が低くなり、貧しくなったとしても私たちは我慢をしていくべきなのかもしれません。
問題はそのレベルです。
どこまでGNPが落ちていっても、現在の不思議なくらい平安な日常を守り続けることができるのか。
むしろその方がずっと心配になります。
身体が動くかぎり働いて生きていくことだという彼女の結論には、もちろん賛成ではあります。
しかし問題は引き続き、山積していると言わずにはいられません。
今回も最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。