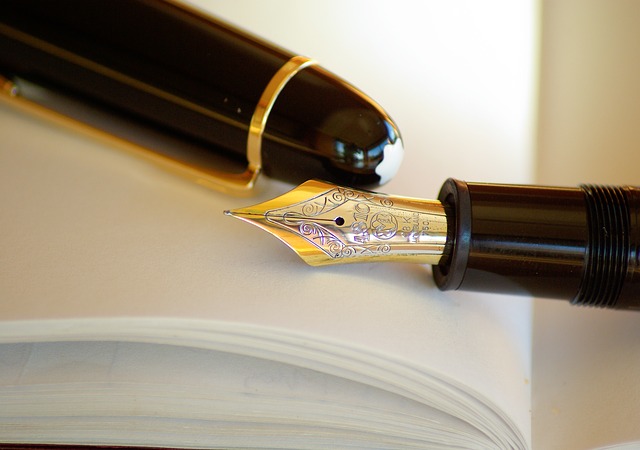個人的な体験
これは1960年代の話です。
ノーベル賞作家、大江健三郎にとって長男の誕生は大きな試練の道への一歩でした。
生まれた時から子供の頭蓋骨には異常がありました。
そのことが結果的に作家としての想像力を飛躍的に増大させたのです。
『個人的な体験』に綴られた内容を読んでいくと、その意味がよくわかります。
障害児に対する社会の認知が今ほどは進んではいませんでした。
以前は発達障害などという言葉さえなかったのです。
それが彼を取り巻く状況に大きな影響を与えたことは、彼の小説を読めばよくわかります。
「特殊教育」から「特別支援教育」への流れは現在も続いています。

近年は、身体障害、知的障害だけでなく、学習障害(LD)、注意欠陥多動性障害(ADHD)などに細分化され、より細かな指導がなされているのです。
保護者の心理的な抵抗感が少なくなり、社会全体で広く受け入れていくという土壌ができつつあります。
財政的支援も以前とは比べものになりません。
しかし現在の状況が十分であるとはまだまだいえないのも事実です。
近年ではさらに不登校児童の増加という現象もみられ、学校を取り巻く事情は、以前とは大きく変化しています。
あまりにも教員の仕事が過重になり、志望者が急減するという考えられなかった現象も起こっているのです。
ここに取り上げられた文章は、大江健三郎のエッセイ『「自分の木」の下で』という2001年に発表されたものの一部です。
内容は非常にわかりやすく、誰でもすぐに読めます。
しかしそこに書かれた内容は、大変に複雑で根源的です。
かつていくつかの大学の入試に出題されました。
教育の本質についてたくさんの疑問符を投げかけていると言っていいのはないでしょうか。
自分の木の下で
私の家庭の最初の子供は、光という男の子ですが、生まれて来るとき、頭部に異常がありました。
頭が大小、ふたつあるように見えるほどの、大きいコブが後頭部についていました。
それ切り取って、できるだけ脳の本体に影響がないように、お医者さんが傷口をふさいでくださったのです。
光はすくすく育ちましたが、4、5歳になっても言葉を話すことはできませんでした。
音の高さや、その音色にとても敏感で、まず人間の言葉より野鳥の歌を沢山おぼえたのです。
そして、ある鳥の歌を聞くと、LPで知った鳥の名をいうことができるようにもなりました。
それが、光の言葉のはじまりでした。
光が7歳になった時、健常な子供より1年遅れて「特殊学級」に入ることになりました。
そこには、それぞれに障害を持った子供たちが集まっています。
いつも大きい声で叫んでいる子供がいます。
じっとしていることができず、動きまわって、机にぶつかったり、椅子をたおしてしまったりする子もいます。
窓から覗いてみると、光はいつも耳を両手でふさいで、身体を固くしているのでした。
そして私は、もう大人になっていながら、子供だった時と同じ問いかけを、自分にすることになったのです。

光はどうして学校に行かなければならないのだろう。
野鳥の歌だけはよくわかって、その鳥の名を両親に教えるのが好きなのだから、3人で村に帰って、森のなかの高いところの草原に建てた家で暮らすことにしてはどうだろうか。
私は植物図鑑で樹木の名前と性質を確かめ、光は鳥の歌を聞いては、その名をいう。
家内はそのふたりをスケッチしたり、料理を作ったりしている。
それでどうしていけないのだろう。
しかし大人の私には難しいその問題を解いたのは、光自身だったのです。
光は「特殊学級」に入ってしばらくたつと、自分と同じように、大きい音、騒音がきらいな友達を見つけました。
そしてふたりは、いつも教室の隅で手を握り合って、じっと耐えているということになりました。
(中略)
いま、光にとって、音楽が、自分の心のなかにある深く豊かなものを確かめ、他の人につたえ、そして自分が社会につながってゆくための、いちばん役にたつ言葉です。
それは家庭の生活で芽生えものでしたが、学校に行って確実なものとなりました。
国語だけじゃなく、理科も算数も、体操も音楽も、自分をしっかり理解し、他の人たちとつながってゆくための言葉です。
外国語も同じです。
そのことを習うために、いつの世の中でも、子供は学校へ行くのだ、と私は思います。
設問
長い引用になってしまいました。
途中、少しだけ省略してあります。
課題文の後にある設問は次の通りです。
あなたならこの設問を読み、どのように文章をまとめますか。
一緒に考えてみてください。
問いはごくオーソドックスなものです。
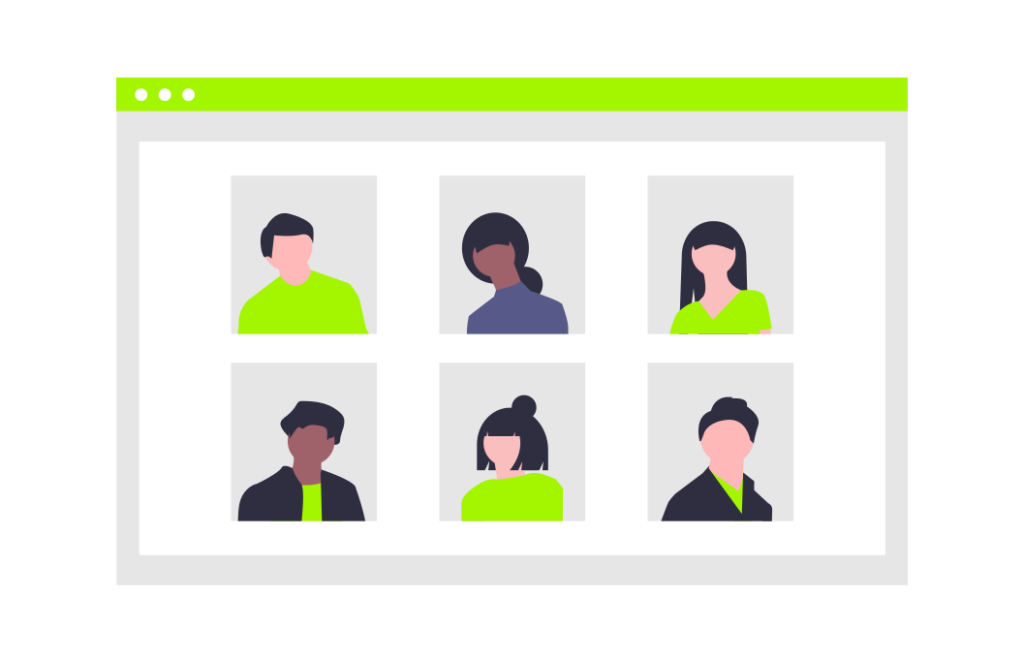
子どもの成長や発達にとって、家庭教育と学校教育はそれぞれどのような役割を果たしていますか。
また両者はどのように関連していますか。
800字以内で書きなさい、というものです。
この問いに先立って、光くんの在籍する学級で、教師はどのような役割を果たしたと思うかという小問もあります。
最初に考えなくてはならないことは、どこまでの範囲で文章を書けばいいのかということです。
キーワードを正確に
800字の小論文というのはそれほど長いものではありません。
主題をいくつも書いてしまうと、それだけで終わってしまいます。
大切なのはキーワードです。
ポイントは「家庭教育」「学校教育」の役割は何か。
その関連性をどう考えればいいのかということです。
全ての子どもに対する教育という視点で書き込まないと、偏狭なものになってしまう怖れがあります。
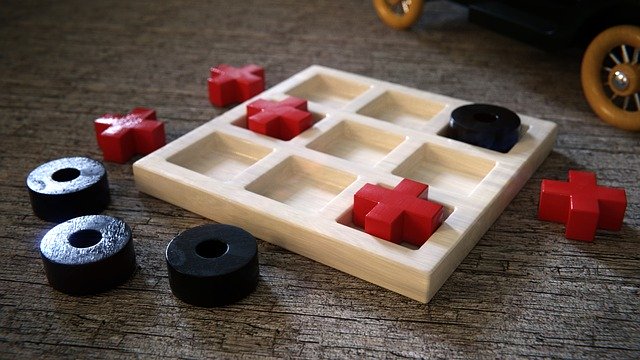
ただし課題文を読んでから書くことを忘れないでください。
内容を全く無視して自分勝手な文章を書いては意味がありません。
そこが一番のポイントでしょうか。
あなたならどこから書きますか。
家庭や学校はどういう態度で子どもに向き合えばいいのか。
非常に多岐にわたって書き込める内容ですね。
しかし課題文がある限り、絶対に無視してはなりません。
勝手に書けばいいというものではないのです。
ここが小論文の難しさです。
いつも冷静に課題文の中にある評価ポイントを意識し続けるのです。
ここでは障害児の子供が通っていた学校の先生の態度はどのようであったのか。
どこにそのすぐれた特徴がみられるか。
そこを忘れずに書き込むことです。
解答は広い視野でまとめなければなりません。
それが難しさに繋がります。
知育偏重の意味
意識しなくてはいけないポイントは、近年の学校が知育に偏りすぎているところです。
情報化社会の中を生き抜くために、AIを中心とした知育と外国語習得だけを中心にしたのでは、明らかに弱い文になってしまいます。
大江健三郎が最後に書いた「自分をしっかり理解し、他の人たちとつながってゆくための言葉」を獲得するための場所として、学校が存在するのだという論点を有効に使ってはどうでしょうか。
子どもの人格や能力は全て違います。
家庭でも学校でも、その違いに着目し、なにがもっともその子供にとってふさわしいのか。
安全で安心できる環境の中で、夢や目標を持つことができるのか。
わかりやすくいえば、個性を見極めることが全てなのです。
もちろん、教える側に人間をみつめる目と経験がなければできません。
しかしそれ以上に人間として謙虚であることが最も大切なのです。
その両輪を機能させながら、他の人とつながっていくための方法を共に探るということになるのでしょう。

1つのテーマに過度に集中しすぎると疲れてしまいます。
その兼ね合いこそが、最も難しいのかもしれません。
自ら考える力を育て、それを社会の中へ生かしていく。
与えるべき知識と技術の量も当然、個人によって異なります。
自然や社会に対する興味や関心をどう広げていくのか。
書くべきことはいくらでもあります。
健常者も障害者も同じ空間で成長していくために、何が必要なのか。
そのための方法論を確立することに、エネルギーを傾けて書いてほしいのです。
材料が多いため、その取捨選択に悩むに違いありません。
しかしそこにこそ、あなたの力量を示すための可能性があるのです。
長くなりました。
今回も最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。