学問をする意味
みなさん、こんにちは。
元都立高校国語科教師、すい喬です。
今回は日本を代表する国学者、本居宣長(もとおりのりなが)の文章を扱います。
ここに取り上げる『玉勝間』(全15巻)は学問的な要素の濃い随筆です。
1795年ごろに成立しました。
内容は学問論、歌論、文学論や折々の随想など、幅広い話題から成り立っています。
彼は伊勢の国、松坂(現在の三重県)に生まれました。
初め、医学を志しましたが、やがて国学に転じ、賀茂真淵に入門して古典を研究し、国学を大成したのです。
代表的な作品は30余年を費やした『古事記伝』です。
その他に「もののあはれ」の文学論を展開した『源氏物語玉の小櫛』や随筆『うひやまぶみ』などがあります。
宣長は日本の精神や文化を探求し、国学を一つの独立した学問分野として確立しました。
特にすぐれているのは古典の再解釈です。
『古事記』や『源氏物語」が持つ日本人特有の感性を探りました。

「もののあはれ」という概念は、日本人の持つ感覚を象徴するものとして評価され、国学の根幹の一つとなったのです。
『古事記伝』は日本最古の歴史書である『古事記』を詳細に解釈、注釈したものです。
神話や日本独自の宗教観、価値観を研究し、新しい認識として捉えなおしました。
宣長は「日本らしさ」の内側に視線を向け続けたのです。
従来の儒学や仏教思想とは異なる見地から、国学の理念を受け継ぎました。
彼はこの文章に先立って、古代研究の学問の方法において、師の説の誤りを正すのに決して遠慮をしてはならないと述べています。
当時、心の中では思っていても、これだけズバリと発言するのには勇気が必要だったでしょう。
学問の進歩を願う、潔さを読み取らなくてはなりません。
宣長は年を経て学問が次第に進歩すれば、学説は必ず変わるものであると主張したのです
したがって、1人の学者の一生の間にも、初めの学説と後の学説とが違ってくることはよくあることだと論じています。
ここでは学問、学説に対する基本的な考え方を読んでみましょう。
本文
同じ人の説(ときごと)の、こことかしことゆきちがひて、ひとしからざるは、いづれによ
るべきぞと、まどはしくて、おほかたその人の説、すべてうきたる心地のせらるる。
そはひとわたりはさることなれども、なほさしもあらず。

初めより終はりまで、説の変はれることなきは、なかなかにをかしからぬ方もあるぞかし。
初めに定めおきつることの、ほど経て後に、また異なるよき考への出で来るは、つねにあ
ることなれば、初めと変はれることあるこそよけれ、年を経て学問すすみゆけば、説は必
ず変はらでかなはず、またおのが初めの誤リを、後に知りながら、つつみ隠さで、きよく
改めたるも、いとよきことなり。
ことにわが古学の道は、近きほどより開けそめつることなれば、すみやかにことごとくは考へ尽くすべきにあらず。
人を経、年を経てこそ、次々に明らかにはなリゆくべきわざなれば、一人の説の中にも、
前なると後なると異なることは、もとよりあらではえあらぬわざなり。
そは、一人の生の限りのほどにも、次々に明らかになりゆくなり。
されば、その前のと後のとの中には、後の方をぞ、その人の定まれる説とはすべかりける。
ただしまた、みづからこそ、初めのをばわろしと思ひて改めつれ、またのちに人の見るに
は、なほ初めの方よろしくて、後のはなかなかにわろきもなきにあらざれば、とにかくに選びは、見ん人の心になん。
現代語訳
同じ人の学説が、あちらこちらに食い違いがあって考えが等しくないのは、どちらに従っ
たらよいのかと、判断がつきかねることがよくあるものです。
確かに主張の内容が根拠のないことに思えてしまうこともあります。
一応はもっともではあるけれども、それでも、そうとも言い切れないところがあるからです。
初めから終わりまで、その人の学説が変わらないというのは、かえって賛成する気になれ
ないという見方もあるくらいなのです。
初めに、断定しておいたことなのに、年月を経てみると、また別のよい考えが出て来るこ
とは、つねにあることです。
初めと変わることがあってあたりまえなのです。
年を経て学問が進んでいけば、学説はどうしても変化しない訳にはいられません。
また自分の最初の誤りを、後になって知りながら包み隠さずに、潔く改めるということも、理にかなったことです。
特に私が研究している国学の道は、まだ始まったばかりです。
それだけに早いうちから、すべてのことを極め尽くすことはできません。
人の力を経て、年月を経ていくうちに、次々と明らかになっていく学びなのです。
したがって一人の主張する考えの中にも、前の学説と後の学説で異なることは、もとよりあって当然のことなのです。
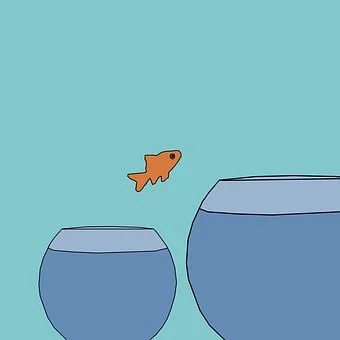
一人の学者の人生に限ってみただけでも、次々と明らかになっていくものです。
そうなると、前の学説と後の学説との間では、後の方をその人の定まった説ととらえることができます。
ただし本人としては、最初の学説の方を不都合だと思って改めたわけですが、第三者から
見ると、かえって初めの学説の方が良くて、後の方がむしろ悪いということも十分あり得ます。
とにもかくにも、どちらが良いかを選ぶのは、見る人の考えによるのだと言えるでしょう。
話の展開を読み取る
学問において、先入観で良否を判断することはできないと本居宣長は言っています。
この文章は前後で2つの段落に分かれています。
前段では、同じ人の学説でも初めと後とで変わることがあると強調しているのです。
しかし時間がたつと別の考えがでてくるということがあります。
それを否定してはいけないというのが基本的なスタンスです。
後段では年を経て学問が進歩すると、学説は変わるものだと主張しています。
特に国学は新しい学問なので、1人の学説の中でも変わるのは当然の現象とみるべきだというのです。
前後の学説の選択も見る人によるということだと意見です。
ここでは学問の進歩とは何かという基本的な、考え方が示されています。
1人の研究者の学説が変わらないことがいいのかどうかというのが、ポイントです。
個人の学説も後に訂正されることがあるのは、少しもおかしなことではないと、宣長は主張しているのです。
真剣に学問に取り組めば、学説の変化がありうる。
この考えの基本には師であった賀茂真淵の思想があると考えた方がいいでしょう。
馬淵は常に次のような考えを持っていました。

「あとで良い考えが浮かんできたときには、先生の説と違うからと言って必ずしも遠慮してはならない。」というのです。
宣長自身、「この論点はとても立派で優れています。文字通り私の先生がとても優れていらっ
しゃることの一つなのです。」と『玉勝間』の中に書き込んでいます。
学問をするということの本質的な問題を正面から取り上げたという意味で、この章段の持つ意味は大きなものがあります。
自分に正直に研究を続け、信念を曲げなかったという意味で大きな功績を残したと言えましょう。
学問というのはとかく狭い領域に多くの研究者が集まってしまうものです。
それだけに先人の学説を否定するのはなかなかに難しい側面があります。
近代に入って、象牙の塔などと呼ばれる大学の研究者たちのなかには、まさにここに示されたような動きすることがかなりありました。
宣長はそうした矛盾までを、江戸時代に予見していたのではないかと思われます。
彼の鋭い先見性には、驚かされますね。
今回も最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。


