 ノート
ノート 「小国寡民・老荘」便利な道具や技術を避け質素な暮らしを望む人生のあり方
d
 ノート
ノート  本
本 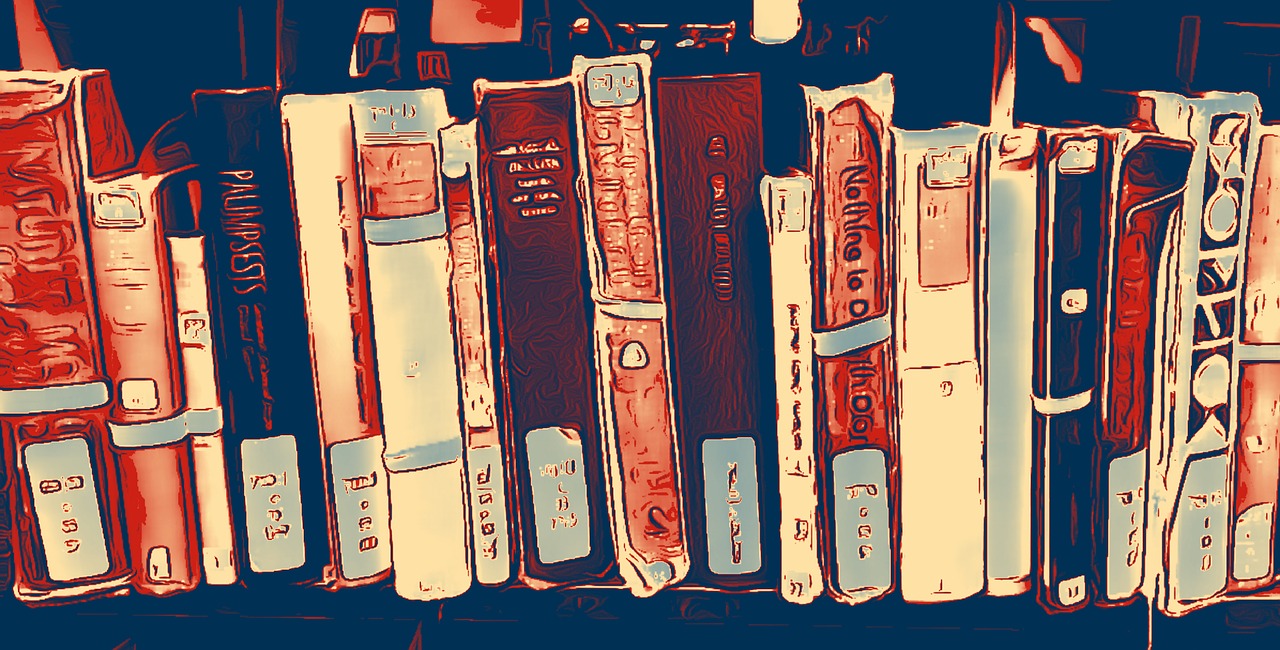 ノート
ノート  ノート
ノート  小論文
小論文  本
本  ノート
ノート  本
本  小論文
小論文  学び
学び  本
本  ノート
ノート 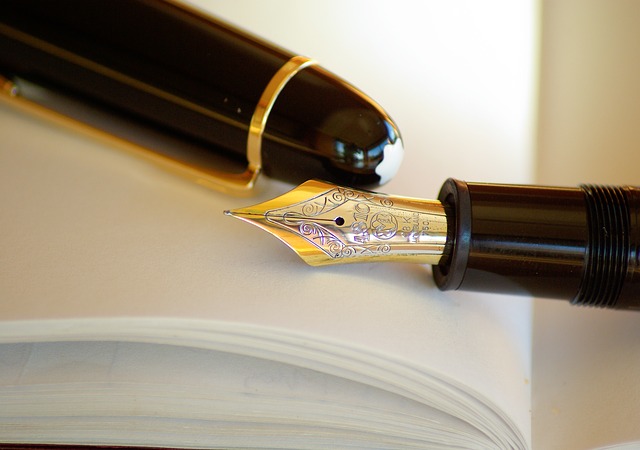 小論文
小論文  ノート
ノート  ノート
ノート  ノート
ノート