 本
本 「讃岐典侍日記」亡き堀河天皇と幼帝鳥羽天皇とに対する作者の心情は
讃岐典侍の日記です。堀河天皇のことを思い出しながら、つい涙をこぼしてしまったところを幼帝に見られます。父親のことをそれぞれに思い出しながら、まとめた日記に愛情が仄見えます。
 本
本 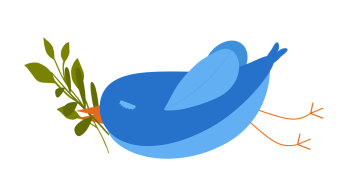 本
本  本
本  本
本  本
本  本
本 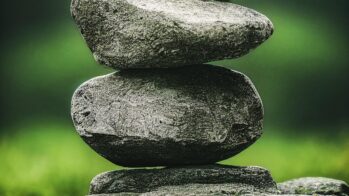 本
本  本
本  本
本  本
本  本
本  本
本  本
本  本
本  本
本  本
本