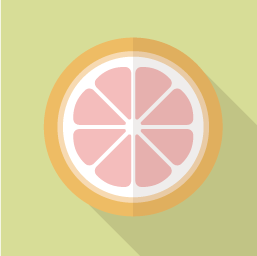文学離れ
みなさん、こんにちは。
元都立高校国語科教師のブロガー、すい喬です。
今までにいろいろな小説をご紹介してきました。
授業で取り扱ったのもあれば、そうでないのもありました。
特に反道徳的な三島由紀夫とか、谷崎潤一郎などという作家のものは、あまり読んだことがないようですね。
そういう時代になったのでしょうか。
なにより表現が難しいですからね。
これからますます文学離れが進む予感がします。
以前書きましたが、高校の新しい指導要領になれば、国語は論理性の強い評論がメインになっていくものと思われます。
いわゆる「論理国語」という科目です。
「文学国語」という科目も設置されますが、4単位ということを考えると、先生方は躊躇してしまうでしょう。
それでなくても入学試験は論理優先の評論が多く出題されますから仕方がありません。
時代はまさにAI全盛。
論理性を重視した小論文重視という姿勢も、その先端にあるのかもしれません。
とにかく記述式の時代です。
国語だけじゃありません。
数学も記述式を重視しているのです。
今回はそういう流れの中で、あえて梶井基次郎の『檸檬』を紹介します。

高校時代に習いましたか。
必ずやるという単元ではありません。
しかし今でも多くの教科書に所収されています。
ごく短いものです。
数時間でやれるので、教師の側からいうと、大変にありがたいです。
しかしわかりやすいのかと訊かれると、とんでもありません。
大変に複雑な神経のありようがこれでもかと描かれています。
その横顔
この作家についてよく知っているという人はそれほど多くないと思います。
彼の他の作品を読んだという人も少ないはずです。
梶井基次郎という作家は、まさに短編『檸檬』一作だけで、人々に記憶されているのです。
今から15年ほど前、日本橋の丸善という書店が移転しました。
その時に、お客が書棚のあちこちに檸檬を置いていったというエピソードが話題になったことがあります。
いくつもの檸檬が、ひっそりと本の上に置かれたのです。

なぜそんなことをしたのか。
不思議ですよね。
その理由はまさにこの小説にあるのです。
少しだけ、この作家の横顔をご紹介しましょう。
作家、梶井基次郎は1901年に生まれ、1932年に亡くなりました。
31年の短い生涯です。
感覚的というのか、詩的な文体の小品を残しました。
死因は肺結核です。
ほとんどの作品は死後、人々に読まれるようになりました。
その生活はデカダンスと呼ぶにふさわしいものだったといわれています。
頽廃と訳されますが、ただだらしのない生活を送ったというわけではありません。

三高から東大英文学科に入学します。
三高は現在の京都大学の教養部にあたります。
京都での暮らしが彼の神経のあちこちに様々な想念を描き出したのでしょう。
夏目漱石と谷崎潤一郎を最も好んだといわれています。
肋膜にかかって休学をしたり、転地をしたこともありました。
キリスト教的社会主義や他力仏教の洗礼もうけました。
文学の道に進む意志はかたいものの、精神は頽廃したままです。
その頃の行状にはとんでもないことがたくさんありました。
泥酔の後、甘栗屋の鍋に牛肉を投げ込んだり、ラーメン屋の屋台をひっくり返したり、借金の重なった下宿から逃亡したり、自殺未遂をしたり…。
あまりにも鋭敏すぎる感性に、現実が追いつかなかったのかもしれません。
結局5年間の三高生活でした。
『檸檬」はその時代の彼の心象風景を描いたものです。
檸檬の主題
この小説は現在、青空文庫で読むことができます。
ご存知ですね。
有志の方々が、著作権の切れた作品をネットにアップしてくれているのです。
本当に頭が下がります。
なかなか読むことのできない作品がたくさんあり、近年ますます充実してきました。
ちょっと覗いてみてください。
「檸檬、青空文庫」とグーグルでひけば、すぐに読めます。
専用のリーダーなどもありますので、いろいろと試行錯誤をする価値があると思います。
最初の段落の文章にこの作品の全てが色濃くにじみ出ています。
冒頭の一節です。
えたいの知れない不吉な塊が私の心を始終壓へつけてゐた。
焦燥と云はうか、嫌惡と云はうか――酒を飮んだあとに宿醉があるやうに、酒を毎日飮んでゐると宿醉に相當した時期がやつて來る。
それが來たのだ。
これはちよつといけなかつた。
結果した肺尖カタルや神經衰弱がいけないのではない。
また脊を燒くやうな借金などがいけないのではない。
いけないのはその不吉な塊だ。
以前私を喜ばせたどんな美しい音樂も、どんな美しい詩の一節も辛抱がならなくなつた。
蓄音器を聽かせて貰ひにわざわざ出かけて行つても、最初の二三小節で不意に立ち上つてしまひたくなる。
何かが私を居堪らずさせるのだ。
それで始終私は街から街を浮浪し續けてゐた。
何故だか其頃私は見すぼらしくて美しいものに強くひきつけられたのを覺えてゐる。
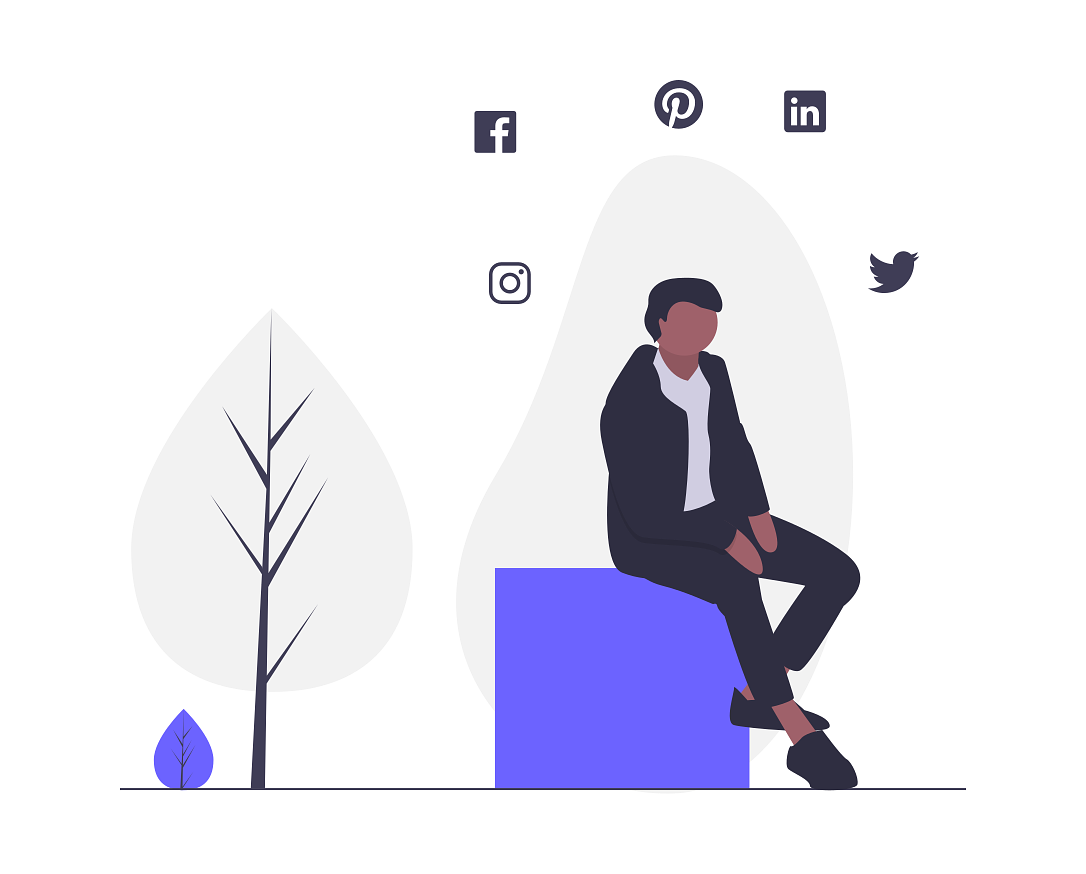
見すぼらしくて美しいものとはなにか。
授業で随分と生徒に問いかけました。
通常ならば、見すぼらしいものは、美しくありません。
しかし作家の目には見すぼらしいのに美しく映る。
その一点から、既に彼は病んでいたのかもしれません。
あるいはつねに不安が心の中に渦巻いて、自分という存在をかき立てる。
いたたまれない感情だと何度も告白しています。
焦燥でもあり嫌悪でもあり、二日酔いに似た何かです。
雑貨屋でみかけるものに目がいきます。
オードコロン、オードキニン、切子細工、香水瓶、煙管、小刀、石鹸、煙草。
そうした彷徨の果てに辿り着いたのが、夜の中に煌々と白色の灯りをつけた果物屋でした。

その様子を直接見るのではなく、近所にある店の二階のガラス窓をすかして眺めるのです。
その店先に置いてあったのが檸檬でした。
冷たさの感覚
その檸檬を1つ買い求め、つまりはこの重さなんだと1人で呟きます。
幸せな感情に満たされるのです。
何がこの重さなのか。
これも随分と生徒に訊ねました。
最後に丸善に入ると、それまでの幸福な感情が消えていくのを感じます。
画集をひっぱり出して積み重ね、その上に檸檬を置いたらどうなるのか。
その想念が蘇ってきた時、たった1つ本の上に乗せた檸檬の周囲が緊張します。
丸善の棚へ黄金色に輝く爆弾しかけてきたような想像が、作家を愉快にさせるのです。
気詰まりな丸善を粉葉みじんにしてしまう。
そう思うことで、自分自身が孕んでいる現実から逃避してしまうことができると信じたのでしょう。
彼はこの小説でいったい何を言いたかったのか。
その問いだけがいつも残る授業でした。
答えはないと思います。
胸苦しさの残る最終局面には、さまざまな思いが宿ったことでしょう。
夕方から微熱が続く結核の症状。
それと戦いながら、死を他の人より身近に感じたことは間違いありません。
彼の短編『冬の蠅』などを読むと、死の感覚がどれほど近くにあったのかということがよくわかります。
学校でしか習わず、読むこともない作家の作品です。
こうした複雑な感情をもった人間の生き様を知るということが、ますます必要な時代になっている気がしてなりません。
最後までおつきあいいただき、ありがとうございました。