日本文化との違い
みなさん、こんにちは。
元都立高校国語科教師、すい喬です。
今回は国際的な環境で活躍している人に共通している特性について考えます。
集団の中で目立つことを避けようとする日本人の傾向については、よく指摘されますね。
「出る杭は打たれる」ということわざもあるくらいです。
日本人はYesNoをはっきり言わず、なんとなく曖昧な表情で微笑んでいるという不思議な民族なのかもしれません。
なぜ必要以上に協調性を優先しようとするのか。
積極的に自分の意見を述べようとしない傾向も強いです。
単一民族と島国の属性が、長い年月をかけて物言わぬ日本人をつくりあげてきたのかもしれません。
しかし時代はグローバル化へ舵を切っています。
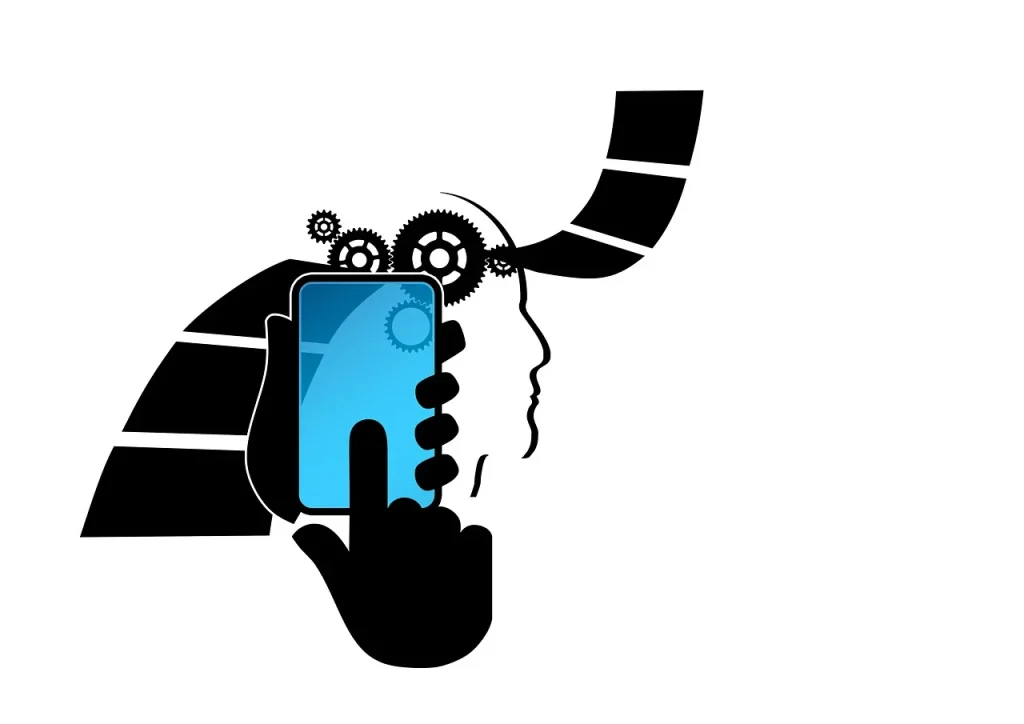
世界で活躍する日本人が、同じであるとはとても思えません。
彼らは実際どのように、自分をアピールしているのか。
興味深い文章を見つけました。
国連職員としてイタリアで勤務した経験を持つ、田島麻衣子氏のエッセイがそれです。
国際的な環境で活躍する人々が共通して持つ特性とは何かというテーマを論じているものです。
海外の文化と比較し、自身の意見を建設的に述べるために必要なことは何か。
彼女は他者の評価よりも、クライアントや上司の意向を重視することが大切だと論じています。
さらに協調性と個性の両立が十分にできないと、世界で働くのは難しいと断じているのです。
本文
日本の有名コンサルティング会社で長く働く北欧出身の知人に、こんな話を聞いたことがあります。
「クライアント先で会う日本人は、会議であまり発言せず、常に会議室の後方に固まって座っていて、消極的に見える」。
確かに、日本人は集団の中で個として目立つことを避ける傾向にあります。
それぞれ思うところはあっても、発言することで、下手に「出る杭」になることを、意図的に避けようとします。
日本社会には、他人と同じでなければならないという無言の圧力が、確かにあるように感じます。
この傾向は、日本を外から眺めてみると、さらに目立ちます。
みんな同じ型のランドセルを背負って通った小学校時代から始まり、みんなと「違う」人間がいじめの標的になった中学・高校時代。
そして、同じリクルートスーツに身を包み、懸命に就職活動している私たちの思考に、このことは少なからず影響を及ぼしていると思います。
ある商品が爆発的に流行する現象も、裏を返せば、「周りと同じでありたい欲求」の表れでしょう。
イタリアも、日本と同じように地域社会の連帯力が強いですが、集団で同じような行動を取るといった、無言の圧力による縛りはありません。
世界に視点を移してみれば、自分と同じ要素を他人の中に見つけることのほうが、むしろ困難になります。
異なる目の色、異なる肌の色といった身体的な違いから始まり、倫理的な価値観や宗教観など、基本とする考え方、信条さえも異なってきます。
このような環境においては、自分が他人と違うことは、至って自然なことだと考えられます。

逆に、人と違うことが、その人の個性として周りから認められる要素になります。
例えば、「こんなユニークなアイディアを思い付いた」、あるいは、「特別な人的ネットワークを持っている」など、人と違うことを積極的に表現することで、自分の存在を周りにアピールすることができます。
ただし、人と違うことがいいと言っても、独りよがりの主張は疎まれるので要注意です。
建設的な意見を述べる人、共通のゴールを見つけるために意見を出す人こそが、周囲に尊重されます。
グローバルな仕事環境においては、会議中、一度も有用な発言ができない人は、残念ながら周りから認めてもらえません。
当然、集団で会議室の後方に固まって座るなど、あり得ない話です。
グローバルな場で活躍している人であれば、一般的には、司会役の視線を受け止めやすい場所など、自分が有利に発言できそうな席を選んで座ります。
冒頭のコンサルティング会社勤務の知人が、日本人を見て不思議がるのも無理のない話です。
国境を越えて活躍する人々は、「人と同じでなければならない」と考えない代わりに、実は死ぬほど気にしていることがあります。
それは、「自分のクライアントと自分の上司が考えていること」です。
それ以外のこと、例えば、「周りに自分がどう思われているのだろう」、あるいは、「周りに合わせなければならないのではないか」については気にしていません。
むしろ人と違うほうが、自分を有効にアピールできると踏んでいるようです。
なお、自分らしさを大切にし、人と違う意見を持つことは、日本人の強みの一つである「協調性」を失うことではありません。
(田島麻衣子『世界で働く人になる!』)
ネット社会と多様性
日本人の同調圧力は、他国とは比較になりませんね。
「周りと同じでなければならない」という社会の無言の圧力はあらゆるシーンに登場します。
その反対側にあるのがグローバルな仕事環境でしょう。
異なる身体的特徴や倫理的価値観、宗教観など、人々はあまりにも多様です。
自分が他人と違うことは至って自然なことなのです。
しかしそれがなかなか日本人には受け入れられません。
海外旅行をして日本に戻ってくると、不思議なくらい同じ顔つきをした人が歩いている風景に違和感を感じたりしたことはありませんか。
それくらい、日本という国は同じ民族で溢れかえっているのです。
ここで考えなくてはいけないのが、ネットワークの普及です。
世界は新しい技術の登場で劇的に変化しました。
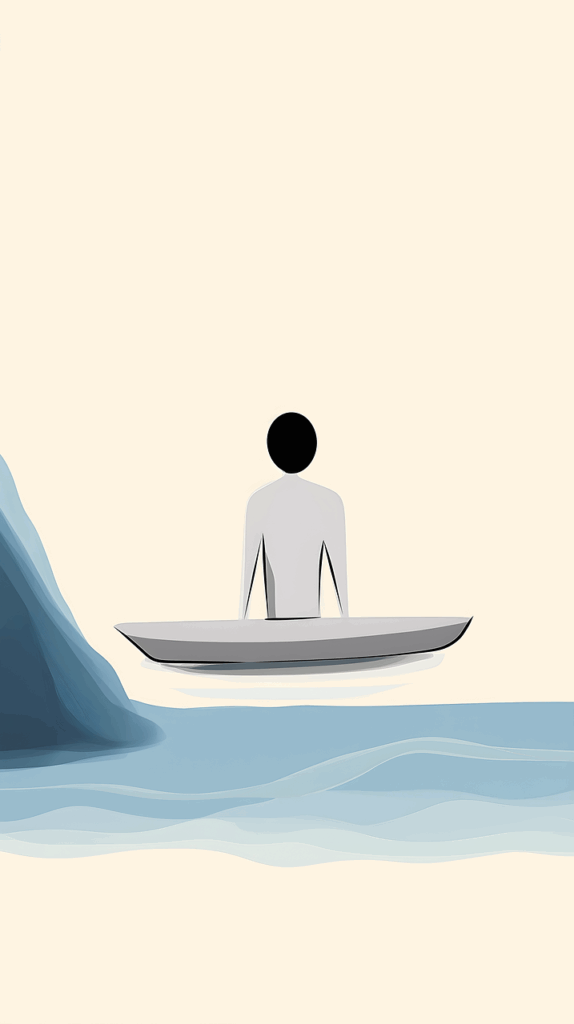
あっという間に世界中の人々がダイレクトにつながる環境が生まれたのです。
同時に今まで誰も想像しなかった新しい価値観、文化も醸成されたのです。
さまざまなバックグランドをもった人間が、日々新奇なアイデアを持ち寄り、意見を闘わせ、ビジネスをしています。
この変化乗り切るために必要な考え方とは何か。
国境を越えて活躍する
おそらく多様性を受けれ入れることに尽きますね。
それを尊重する組織こそが最も強いのです。
しかし、日本の社会はもともと多様性とは遠い位置にあります。
その証拠に新しい商品がなかなか生まれません。
型破りを認めようとしない社会なのです。
いくら挑戦をしようとしても、失敗に終わったら即「恥」として非難されることになるからです。
これからの企業は、世界標準を強く意識しなければなりません。
人種、国籍、性、年齢を問わないことです。
これが日本の企業にとって最も欠けていると考えていいのではないでしょうか。
よく言われる5つの場面展開は次の通りです。
①抵抗(違いの拒否)、②同化(多数派への同質化)、③尊重(違いの尊重)
④分離(局所的な成果)⑤統合(新しい価値創造)
グローバルな場では、会議中の発言は必須です。
そのためには語学力も重要でしょう。
「周りに自分がどう思われているのだろう」ということを気にしてばかりいたのでは、何も生み出せません。
人間は多様であるという一点を信じ切ることです。
人と違うことがその人の個性として認められる要素となるのです。

最初は苦しいかもしれません。
個として目立つことになりますからね。
全否定される不安を感じないといえば、嘘になるでしょう。
しかしそこからが始まりです。
「気心のしれた人」になってはいけないのです。
我慢することを美徳としていては、生き残れないでしょう。
自分が攻める人間なのか、守りが得意なのかという人間性に負うところもあるでしょう。
リーダーの顔色だけを見ているようでは、組織が先に進むことはないはずです。
このテーマをもう少し掘り下げてみてください。
今回も最後までお付き合いくださり、ありがとうございました。


