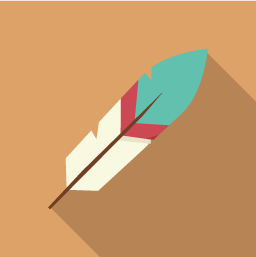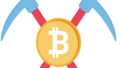再婚話
みなさん、こんにちは。
元都立高校国語科教師、すい喬です。
今日はちょっと昔のお話をさせてください。
つばめの出てくる説話です。
元になる話は『今昔物語』にあります。
ここには1115年頃に成立したといわれる源俊頼の歌論書『俊頼髄脳』から文章を載せました。
俊頼は白河院の院宣により、5番目の勅撰和歌集『金葉和歌集』を編纂した歌人です。

この話には最初に和歌が示されています。
「かぞいろはあはれと見らむつばくらめふたりは人に契らぬものを」がそれです。
「かぞいろ」などという言葉はもう完全に死語になってしまいました。
聞いたことがありますか。
かぞいろというのは父母のことです。
父母は夫に死別した私をかわいそうだと思っているだろう。
しかしつばめでさえも2人の夫とは結婚をしないというのに…。
これが直訳です。
なぜこのような歌があるのか。
その理由を原文にあたってみます。
原文
昔、男ありけり。
娘に男あはせたりけるが、失せにければ、またこと人に婿取らむとしけるを、娘聞きて、母に言ひけるやう、「男に具してあるべき末をあらましかば、ありつる男ぞあらましか。
さる宿世のなければこそ死ぬらめ。
たとひしたりとも、身のくせならば、またもこそ死ぬれ。

さることおぼし、かく」など言ひければ、母聞きて、大きに驚きて父に語りければ、父これを聞きて、「我死なむこと近きにあり。さらむのちには、いかにして世にあらむ。」と
て「さることは思ひ寄るぞ。」と言ひて、なほあはせむとしければ、娘の、親に申しけるは、「さらば、この家に巣くひて、子生みたるつばくらめの、男つばくらめを取りて殺して、つばくらめにしるしをして放ち給へ。さらむに、またの年、男つばくらめ具して来た
らむ折に、それを見ておぼし立つべきぞ。」と言ひければ、げにもと思ひて、家に子生みたるつばくらめを取りて、男つばくらめをば殺して、女つばくらめには、首に赤き糸をつけて放ち、つばくらめ帰りて、またの年の春、男も具せで、ひとり、首の糸ばかりつきてまうで来たれば、それを見てなむ、親ども、また男あはせむの心もなくてやみにけり。
昔の女の心は、今様の女の心には、似ざりけるにや。
つばくらめ男ふたりせずといふこと、文集の文なりとぞ。
現代語訳
今は昔、男がおりました。
その男が娘をある男と結婚させました。
ところが婿が死んでしまったので、親はまた娘に別の男をあてがおうとしたのです。
娘はこれを聞いて母親に次のように話しました。
「夫に一生連れ添う運命にあったならば、前の夫が亡くなるようなことにはならず、添いとげることができたはずです。
しかしそのような運命が私になかったから夫は先に死んだのです。
たとえ私が再婚したとしても、それが私の運命であるならその方とも死に別れることになるに違いありません。
そういう訳ですから、このお話しはなかったことにしてください。」
母親はこれを聞いてたいそう驚いて、父親に伝えたところ、父はこれを聞いて「わしはもう年老いている。間もなく死ぬことにもなろう。そのとき娘はどのようにして生きていこうとするのだ。おまえのいうことはわからない訳ではないけれど」と、強引に再婚話を進めようとしたのです。
そこで娘は父母に次のように話しました。

この家には巣を作って子供を産んでいる燕のつがいがいます。
その雄の燕を殺して、雌の燕に目印をつけて放してみてください。
来年にその雌が他の雄を連れてくるようなら、私に夫を世話してください。
これを聞いて両親は納得し、その家に巣を作って子供を産んだ燕を捕らえて、雄を殺し、雌には赤い糸を首につけて放しました。
翌年の春、燕がやってくるのを待っていると、首に赤い糸をつけた例の雌燕は雄を連れずに帰って来たのです。
両親は、娘に再び男と結婚させようという気持ちがなくなりました。
昔の女の人の心はこれくらい貞節なものだったのです。
当世の女の人の心ばえとはこんなにも違うものなのでしょうか。
雌燕が雄燕を2度持たないことは白氏文集の中に載っているということです。
つばくらめという言葉の響きがきれいですね。
娘の決心の堅さには驚かされます。
家に巣をつくっているつばめのつがいの雄を殺してしまうというのも衝撃的です。
さらに雌の首に赤い糸を結んで放し、翌年別の雄つばめと共に還って来るなら再婚しましょうという進言もものすごいです。
赤い糸というところになんとなく男女の縁を感じますね。

雄つばめを殺してまでも試してみるというのは現代の感覚ではちょっと考えられません。
しかしそれがギリギリの決心だったのでしょう。
古いことわざに「貞女は二夫に見えず」(ていじょはじふにまみえず)というのがあります。
貞操堅固な女は、夫を持ったら、離別・死別しても別の夫を持つことはしないという意味です。
このことわざはいつ頃まで通用していたものなのか。
現代ではちょっと考えられませんけど。
女の心ばえ
この話を読んでいて気になる箇所が2つあります。
その1つが「男に具してあるべき末をあらましかば、ありつる男ぞあらましか」というところです。
これは古文の文法を勉強した人は覚えていると思います。
反実仮想というのです。
簡単にいえば仮定法です。
直訳すると「男に一生連れ添って生きるはずの運命が私にあるのなら、前の夫は生きていたであろうに」となります。
つまり持って生まれた定めということです。
これを昔は宿縁といいました。
今でもあの人には結婚運がないとかいう言い方をしますね。
それともう1つ。
最後のところに出てくる表現です。
「昔の女の心は今様の女の心には似ざりけるにや」です。

直訳すると、「昔の貞節な女の心というものは当世の女の心とこんなにも異なったのであろうか」です。
昔のと言われても、この話は今から千年も前の話です。
それになのに、その頃の女性はもうこういう気分を持っていなかったということなのでしょうか。
平安、鎌倉時代でもこの考えがなくなっていたとしたら、ここに出てくる昔というのはいつの話なのか。
近頃の子供はどうだとか、近頃の女性はどうだなどという言い方をよくします。
それと全く同じ文脈が飛び出てくることに、ちょっと驚かされます。
もうこの時代には「貞女は二夫に見えず」などという思想は消えていたんでしょうか。
なんとも不思議でなりません。
時代はどんどん変わります。
この女性だけが特別な性格だったのか。
それとも憧れが先行した話なのか。
「近頃の若い者は」というフレーズはいつの時代にも通用します。
永遠に使えそうですね。
今回も最後までお付き合いいただきありがとうございました。