総人口予想
みなさん、こんにちは。
元都立高校国語科教師、すい喬です。
今回は人口問題について考えます。
この課題文は、昨年ある大学の推薦入試に出題された問題です。
800字程度であなたの考えをまとめなさいとあります。
テーマは日本の急速な人口減少とそれに伴う社会への深刻な影響についてです。
日本経済新聞の社説から引用したものです。

文章によれば、2070年には総人口が8700万人になるという将来推計人口が示されています。
外国人の人口が大幅に増加することと、平均寿命の延伸が人口減少のペースを緩やかにする要因であると説明されています。
しかし、楽観的な予測を安易にしてもいいものなのかどうか。
生産年齢人口の減少への対応や、外国人受け入れに関する議論の必要性があるのは言うでもありません。
問いはいくつかあります。
その1つは海外の人材獲得競争における日本の課題と対策です。
さらに人手不足を克服するための具体的なテクノロジーの開発はどうあるべきかということです。
どちらも考えをまとめるのは非常に難しく、しかもテーマは喫緊のものです。
自分の考えを示せといわれても、それほど容易にはまとめきれないと考えられます。
問題の核心はどこにあるのか。
それを少しずつ、解きほぐしながら文章をつくりあげていきましょう。
課題文
次の文章を読み、以下の問いに答えなさい。
日本の人口減少は着実に進み、社会のあちこちに深刻な影響を与える。
労働力が急速に減る中で社会機能をどう維持し、増え続ける高齢者を支えていくのか。
厳しい未来図を直視して社会全体の変革を急がなければならない。
国立社会保障・人口問題研究所が26日公表した将来推計人口によると、外国人を含む日本の総人口は2070 年に8700万人になる。
2020年の1億2615万人から50年間で約3割減ることになる。
それでも総人口が1億人を割り込む時期は、前回の予想である2053年から2056年に3年遅くなったのである。
これは出生率が上がるためではない。
大きな要因は日本で暮らす外国人の人口を大きく見積もったからだ。
前回調査では外国人の入国超過数を年6.9万人とみていたが、今回は年16.4万人と2倍以上になった。
この結果、70年時点の外国人数は939万人と20年時点の3.4倍に増え、総人口の1割を超える推計になっている。
もう一つの要因は平均寿命が延びることだ。
20年時点の平均寿命は男性81.58歳、女性87.72歳だったが、70年には男性85.89歳、女性91.94歳になる。
さらに日本人の出国超過がわずかに減少したという要因も加わり、将来の推計人口が上振れした。
しかし今回の推計をもって人口減少のトレンドが改善したと受け止めるのは楽観的すぎるだろう。
確かに在留外国人数は2022年6月時点で296万人と、2015年末時点の223万人から約3割も増えたが、この流れが中長期的に続く保証はまったくないからだ。
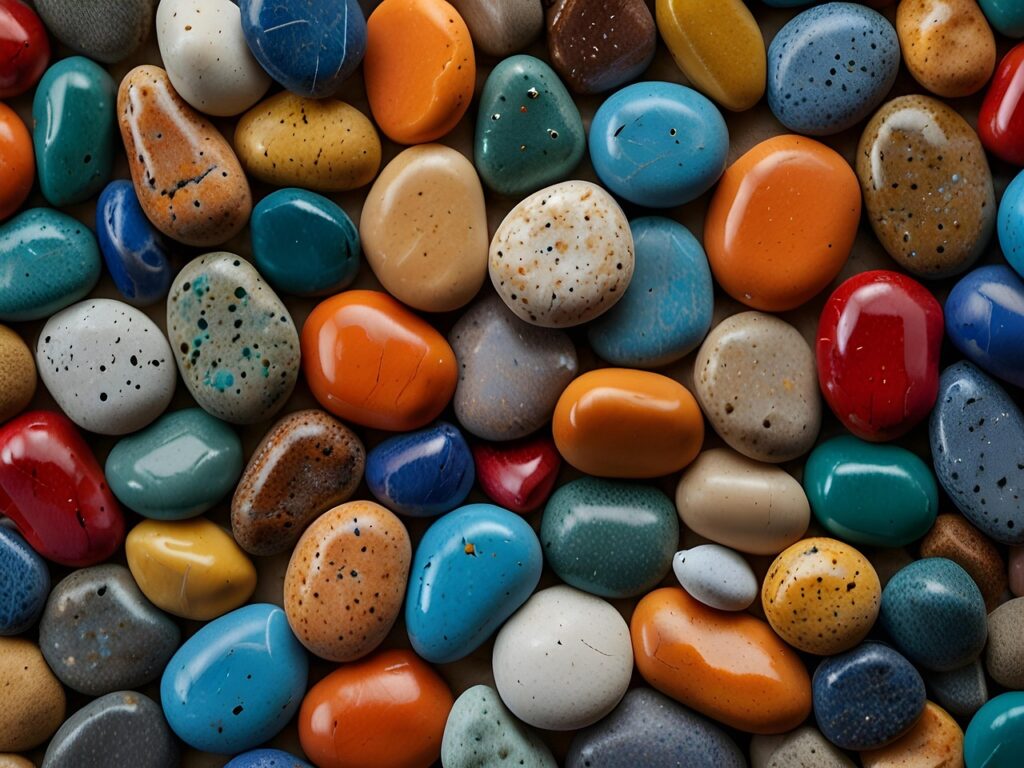
①中国や韓国など人口減や少子化に直面する国が増え、今後は人材獲得競争が一段と激しくなる。
日本人と同等に処遇して海外に見劣りしない水準に賃金を引き上げないと日本は選ばれなくなる。
足元で必要なのは人口への楽観を排し、急激に進む人手不足への対応に全力を注ぐことだろう。
15〜64歳の生産年齢人口は2020年に7509万人だったが、2045年には2割減の5832万人になる。
外国人数が横ばいなら減少率は3割に近づく。
②テクノロジーで省人化を徹底するなど知恵を結集し、社会の機能を維持できる方策を見いださなければならない。
日本はさまざまな場面で決断を迫られる大きな変革期にある。
外国人を今後どのくらい受け入れるのか、日本社会のなかでどう位置づけるのか。
もっと正面から議論しなければならないであろう。
(日本経済新聞電子版 2023年4月26日)
問題
内容は以下の通りです。
問1 ➀の文章にある海外から優秀な人材を獲得するため、競争を有利に展開する上で日本が直面する課題は何だと考えますか。
問2 ②の文章で社会機能を維持するため、今後どのような技術の開発を優先的に推進すべきであると思いますか、その理由とともに書きなさい。
問1と問2の解答をそれぞれ800字以内で答えなさい。
それぞれの解答を短時間でまとめるのは大変に難しいです。
あなたがこのような問題に関心を持っているかどうかで、半分は内容が決まってしまいます。
あらゆるテーマに対して、全方位で興味や関心を抱くことが大切です。
過去問を10年間ぐらいチェックして、自分の受ける学部の頻出テーマについては、確実にチェックしておく必要がありますね。
一般的には内容が人文系、社会系に分かれると考えていいでしょう。
人文系ではコラム記事や家庭欄などを中心に、社会系では政治経済記事などに注意深く目を配ってください。
新聞を家庭でとっていない場合は新聞社系のネット記事を丹念に読むことです。
ファクトチェックをしていない記事を誤って信じてはいけません。
そこだけが注意点といえます。
➀では海外から優秀な人材が集まるとしていますが、この傾向が中長期的に続く保証はありません。
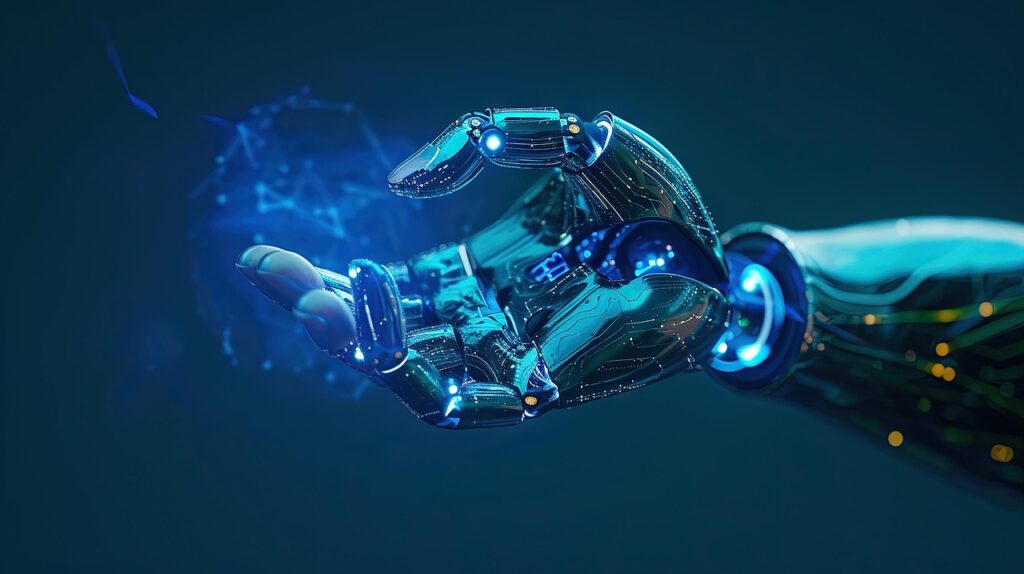
最大の課題は、国際的な人材獲得競争の激化です。
周辺には中国や韓国など、日本と同様に人口減少や少子化に直面する国が増えています。
当然、世界中で人材の奪い合いとなることが予想されます。
その際、日本の弱点は何か。
安全な環境など、治安面がいいとしても、他国と比べて見劣りするのが賃金の水準や処遇です。
「日本人と同等な処遇」の場合、明らかに海外に比べ、賃金は見劣りします。
さらに非経済的な面でも課題を克服する必要があります。
例えば、言語の壁、日本特有の硬直化した雇用慣行、社会における外国人に対する地位の不確実性などが挙げられます。
これらの課題に対して、何をどのようにしたらいいのか。
取るべき方策とは何か。
それを自身の経験や見聞などとかからめて論じる必要があります。
第1にあげるべきなのは、国際競争力に匹敵する賃金水準を実施すべきだということです。
特に専門性の高い人材や若手研究者に対しては、日本人以上の処遇をしなければ来てくれないものと思われます。
それに加えて、昇進の機会、教育訓練へのアクセス、福利厚生などが充実していないと、極東の国をめざして人材が集まるとは思えません。
第2は外国人の地位に対する保証要件です。
長期的に安定した生活ができるよう、永住権や市民権取得の要件を整備しなくてはなりません。
1番の不安は家族の日常生活です。
日本人が外国で定住する場合の教育や医療をイメージすればよくわかります。
最も不安なのは医療や教育体制です。
言葉が十分にわからない段階で、身体の具合が悪くなった時、どうすればいいのか。
現地校とインター校との違いなど、広報活動をして、安心な環境を確保しなければなりません。
さらに特定分野における起業家活動や研究者に対する優遇措置を設けなければ、優秀な人材は去ってしまいます。
ハード、ソフトからの両面からの支援が必要でしょう。
テクノロジーの問題
技術の問題はますますAIの活用に集中するでしょう。
とくに介護、医療、物流などにおけるエッセンシャルワークの省人化が喫緊のテーマです。
高性能な汎用ロボットの開発が大切だと思われます。
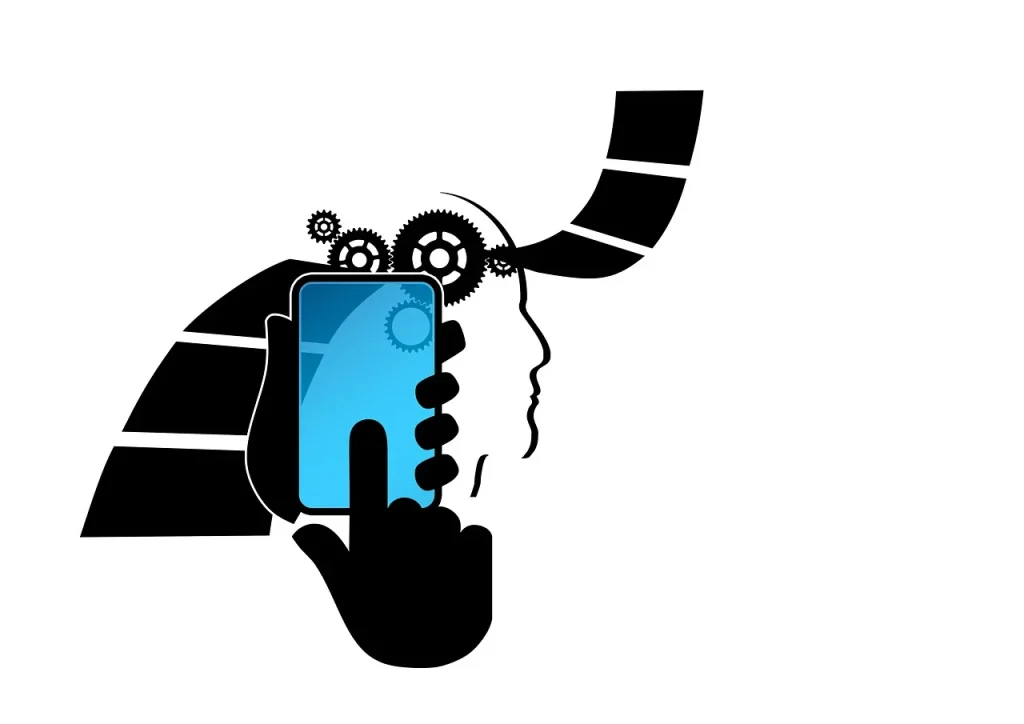
さらにエネルギー、食料生産における完全自動化システムも必要でしょう。
これらの技術開発を優先的に推進することで、日本は人口減少を前提とした新しい社会構造を築き、深刻化する人手不足の問題を克服しつつ、社会の機能を維持・向上させることができると考えます。
今回も最後までおつきあいいただき、ありがとうございました。


