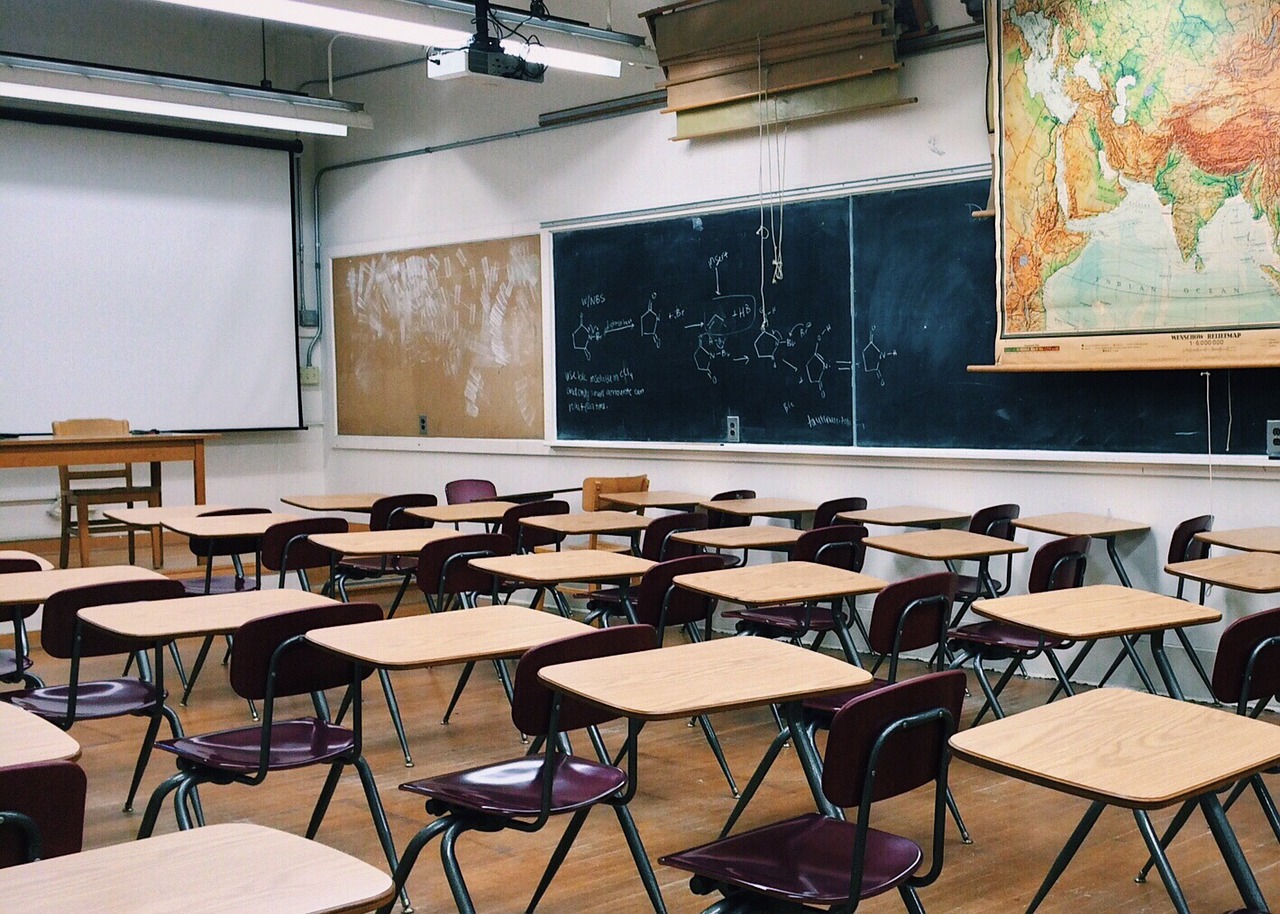実売数激減
みなさん、こんにちは。
元都立高校国語科教師、すい喬です。
毎年、新聞社から公称発行部数が報告されます。
その数字を見ていると怖いです。
元々、雑誌なども含めて公称と実売部数の間にはかなりの差があることは、誰でもよく知っています。
媒体は広告量で稼いでいますのでね。
なるべく派手な数字を強く押し出したいのです。

しかしあまりに過剰になりすぎたため、実売部数をきちんとカウントする必要が生まれました。
日本ABC協会という組織の発足がそれです。
新聞、雑誌、フリーペーパー等の発行社からの部数報告を公査し、その結果を公表する活動を行う会員制の業界団体です。
1958年、通産省によって正式に認可されました。
新聞の場合、1~6月、7~12月の年2回、販売部数、都道府県部数、発行延ページなどについて、新聞別、地域別に分析して発表しています。
記載している部数は、新聞社がそれぞれの販売経路を通じて販売した販売部数で発行部数ではありません。
新聞の場合、販売部数と発行部数との間には大きな乖離があるのです。
業界ではごく当たり前のこととして知られています。
慣例ともいえるものです。
各紙の公称発行部数には「押し紙」(売れ残り含む)の存在があるのです。
耳にしたことがありますか。
もちろん、実際に印刷した新聞が全て売れるワケではありません。
そのため、読者の手元に届いている数は確実に少ないのです。
「押し紙」とは
「押し紙」とは新聞本社から各販売店に「押し」つける形で売る新聞のことです。
新聞社側は新聞のほとんどを販売店経由で売っています。
毎日、新聞を届けてくれる販売店のことです。
そこに売った部数がほぼそのまま「販売部数」になるのです。
しかし新聞社はとにかく発行部数を多くしたいのが本音です。
その分、媒体の訴求効果が強くなります。
当然、広告料金もたくさん稼げるのです。
しかし販売店としては配る世帯をはるかに超えた量を買いとっても売れ残りがでるだけです。
なるべく配達の実数と同じにしたいでしょう。
ところがこの取引では新聞本社の方が立場が圧倒的に上です。
これだけ引き取ってくれないと、今後、新聞は卸さないという強い態度を取ります。
そこでしぶしぶ販売店側も余分に引き受けざるを得ないのです。
もちろんこれは公にはできません。
犯罪行為に近いからです。

独禁法などにも抵触する可能性があります。
よく抱き合わせ販売などという言葉を、いろいろな場面で聞くことがありますね。
どうしてもある商品を売りたいと販売店が言う場合、同じメーカーが別の売れない商品を無理に卸すという方法です。
新聞社側もはっきりとはいいません。
お願いする形にはしているのです。
そのかわり、バックマージンの形で一定数を引き受けてくれたら「販売奨励金」を提供する場合などもあります。
販売店側にしてみたら、新聞の実売数が多ければ多いほど、自分達が直接収入を得られる「チラシ代(地元の商店街などから依頼される、新聞の折り込みチラシの料金)」も多くなります。
だから新聞購読者数を増やしておこうということになるのです。
お互いに持ちつ持たれつの関係があります。
これが「押し紙」の実態です。
SDGs
ところが昨今、コンプライアンス重視の風潮が強まっています。
資源を極力使わないように暮らしていくという「もったいない」の思想もあります。
発行部数を誇るためだけに、無駄な紙を大量に使い、インクをそれに刷り込むことの意味が問われるようになりました。

さらに新聞の需要減退は目を覆うばかりです。
新聞社側の「売りたい」部数と販売店側が「売れる見込みのある」部数との間にはかなりの隔たりが生まれています。
販売店はどこもそれほどの規模ではありません。
ここへきて、もう以前のように押し紙を受け入れる余裕がなくなってきたというのが実態に近いのです。
購読者激減
新聞の購読者が減っていることは誰もが知っています。
今や、高齢者だけが新聞を読んでいるというのが、実情です。
都会のマンションの場合、勝手に配達人が住居区域には入れません。
入り口の郵便受けに投げ込むのが普通です。
朝、起きていちいちエントランス近くまで行かないと、新聞が手に入らないのです。
それでなくても今はネットの時代です。
ほとんどのニュースはネットで瞬時に読めます。
物価高の昨今、毎月5千円近くも払って新聞を読むメリットはかなり少なくなっていると考えても不思議ではありません。
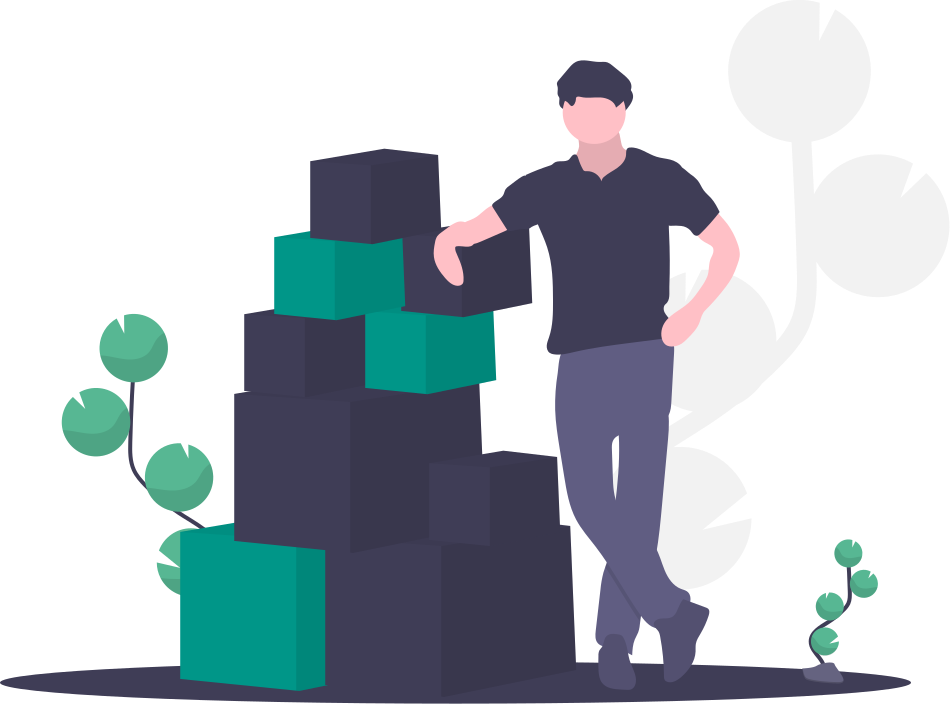
夕刊に至っては、採算がとれないという理由で、かなりの新聞社がとりやめつつあります。
日本特有の各戸配布という現在の方法もやがて、消えてしまうかもしれません。
もちろん、新聞社側の苦しい台所もあります。
リストラをして、人員をカットしつつ、校閲などはきちんと続けなくてはなりません。
赤字体質から抜けられなくなりつつあるのです。
印刷機械のメンテナンスや製造を取りやめる会社さえ、出てきているのが実情です。
新聞をネット化できれば、紙代も印刷費も、販売店への押し紙もいらないのです。
流れは今や、大きく変化しつつあるのが、よく理解できるはずです。
実態はどうなのか
数字をみてみましょう。
かつて購読者数1000万部と言われた読売新聞も600万を切りました。
毎年、数字が下がっていく様子がわかります。
新聞社 2023年12月 2024年6月 減少部数 減少率
読売新聞 6,270,000部 5,856,320部 -413,680部 約6.60%
朝日新聞 3,680,000部 3,391,003部 -288,997部 約7.85%
毎日新聞 1,610,000部 1,499,571部 -110,429部 約6.86%
日経新聞(朝刊)1,409,147部 1,375,414部 -33,733部 約2.39%
日経新聞(電子)902,222部 971,538部 +69,316部 約7.68%
産経新聞 1,160,000部 849,791部 -310,209部 約26.74%
この数字に押し紙率をかけると、次のようになります。
新聞社 押し紙率 実売部数(推定)
読売新聞 30% 約4,099,424部
朝日新聞 30% 約2,373,702部
毎日新聞 50% 約749,785部
日経新聞(朝刊)30% 約962,789部
日経新聞(電子)0% 971,538部
産経新聞 30% 約594,854部
1番、力を蓄えているのが日経電子版です。

今や、毎日新聞より上位にいます。
ネットにニュースを流さず、独自のルートで読者数を増やしています。
最後に全国紙の他に地方紙のことも考えておかなくてはなりません。
地方紙は単に“地元の話題が多い”ということではなく、読者の生活リズムに深く入り込んだ存在です。
その中心的な記事は次の通りです。
地元高校、大学の部活動、大会情報
市町村レベルの議会、求人、イベント情報
冠婚葬祭、訃報欄、農業情報
地域で暮らす人にとって実用的かつ必要な情報を集約している点で、地方紙の価値は維持されています。
ぼくの見聞では特に冠婚葬祭や、俗におくやみ欄と呼ばれる訃報記事などは確実に読者を捉えていますね。
新聞はネット時代の中で、かつてとは全く違う横顔を見せています。
学校で、新聞を使う授業などをしていた時代が夢のようです。
今回も最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。