源氏物語の続編
紫式部が書いた『源氏物語』は本当に長い小説です。
これを原文で読める人は、古文をよほど勉強した人に限られます。
現実的には不可能に近いですね。
なぜでしょうか。
敬語を理解するのが大変に難しいのです。
古文の勉強で最も厄介なのは敬語だとよく言われます。
昔の文章にははっきりとした主語や目的語が出てこないことが多いのです。
それを補うのが敬語です。
誰が話しているのかを知るためのカギが敬語なのです。
ひとつひとつ関係を読み解きながら、先へ進んでいきます。
尊敬と謙譲に丁寧が入り混じった文を読むのは容易なことではありません。
『源氏物語』には実に複雑な敬語がたくさん登場します。
最も込み入っているのが二方向以上に対する敬語です。
尊敬と謙譲が折り重なっているため、読者は誰の発言なのかを判断していく以外、手がありません。
そこで最初は現代語訳したものから入っていくのがベストです。
特に敬語を詳しく翻訳したものでない作家のものの方が、読みやすいようです。
最近では小説家、角田光代さんのがよく読まれています。
それ以前のでは林望、瀬戸内寂聴、円地文子の手になる翻訳本をお勧めします。
与謝野晶子のを読みたければ、無料の青空文庫で読めます。
谷崎潤一郎のは現在、同文庫で入力作業が着々と進められているようです。
もうしばらく待つしかありませんね。
いずれにしてもどれかを手にとってみてはどうでしょうか。
あなたにあった文体のものを探してみてください。
まず読み始めること。

途中で疲れたら、そこで休むことです。
無理に全部読破しようなどと、気負い込むとかえって疲れてしまいます。
光源氏の一生は、女性との出会いに満ちています。
しかしその全てがうまくいったというワケではありません。
実に細かな人間関係が、周到に張り巡らされた伏線の上を流れていきます。
そのいくつかを辿るだけでも、読書の楽しみが増すはずです。
宇治十帖
全部で54帖もあるので、どこから手をつけたらいいのか悩んでしまいますね。
「源氏の須磨帰り」という言葉を聞いたことがありますか。
最初の「桐壺」の段から読んでいるうちに「須磨」あたりまでくると、くたびれてしまうことをいいます。
それだけに最後の「宇治十帖」までたどり着いたとしたら、あなたはすごいです。
光源氏が亡くなった後の話は、2人の主人公、薫と匂宮にうつります。
ここからの章にも、何人かの女性があらわれるのです。
その中で、愛情に翻弄される人の代表が浮舟でしょう。
彼女の母は「中将の君」といい、正妻をなくしたばかりの八の宮に仕える女房でした。
やがて女児が誕生します。
浮舟ですね。

ところが八の宮は自分の屋敷にこの親子を留めてはおきませんでした。
中将の君は娘の浮舟を連れて常陸介の後妻となったのです。
全ては生きていくためでした。
多くの兄弟姉妹の中、一人だけ父親の違う浮舟は、常陸介から疎まれて成長するのです。
母は娘にいい縁を得たいといつも願ってはいたものの、なかなかうまくはいきませんでした。
浮舟は源氏物語に登場する女性の中で、最も生まれが賤しい部類に入ります。
当時は実家の地位が全てでした。
もちろん、彼女には特筆するようなものは何もありません。
ところが数奇な運命をたどることになるのです。
たまたまあずけられた二条院で、帝の子、匂宮に言い寄られたりする事件もありました。
その後、宇治へ薫に連れられて行くといく羽目になります。
薫は源氏の子という形になっていますが、実際は柏木と源氏の正妻、女三宮との密通の時にできた子供です。
浮舟は2人の男性にさんざん翻弄され、最後は川に身を投げます。
危うく一命をとりとめ、高徳の僧の加護を得て出家します。
その後、薫は亡くなってしまったと思い、傷心の日々を過ごすことになるのです。
ここで宇治十帖最後の章「夢浮橋」が終わります。
浮舟と薫の再会
多くの読者は、突然話が閉じられてしまったことで、その後の2人がどうなるのかを知りたかったものと思われます。
浮舟と薫の再会を願ったのです。
しかし紫式部はここで全てを終わらせました。
ところが後の世の人が、どうしても浮舟と薫の行く末を見届けたいと念じました。
夏目漱石の『明暗』の続きを、作家の水村美苗が『続明暗』として書いたようなものです。
鎌倉初期の擬古物語『山路の露』がそれにあたります。
この作品は宇治十帖の主人公である薫の後日談で、『源氏物語』の最終巻である「夢浮橋」巻の続編に位置づけられます。

作者は『源氏釈』の著者として知られる世尊寺伊行(せそんじこれゆき)とも、その娘の建礼門院右京大夫(けんれいもんいんうきょうのだいぶ)ともいわれています。
はっきりしたことはわかっていません。
現在まとまって残っている『源氏物語』の補作の中では最も古いものです。
紫式部が書いたものでないことは明らかです。
実際のところ、成立時期や作者もはっきりとはわかっていません。
1271年(文永8年)以後~応永以前の間に成立したとの説があります。
本文
小柴といふもの、はかなくしなしたるも、同じことなれど、いとなつかしく、よしあるさまなり。
妻戸も開きて、「いまだ人の起きたるにや」と見ゆれば、茂りたる前栽のもとより伝い寄りて、軒近き常盤木のところせく広ごりたる下に立ち隠れて見給へば、こなたは仏の御前なるべし、
名香の香りいとしみ深く薫り出でて、ただこの端つ方に行ふ人あるにや、経の巻き返さるる音も、忍びやかになつかしく聞こえて、しめじめと、もののあはれなるに、
何となくやがて御涙すすむ心地して、つくづくと見居給へるに、とばかりありて、行ひ果てぬるにや「いみじの月の光や」と、ひとりごちて、簾のつま、少し上げつつ。
月の顔をつくづくとながめたるかたはら目、昔ながらの面影ふと思し出でられて、いみじうあはれなるに、見給へば、月は残りなくさし入りたるに鈍色・香染などにや、
袖口なつかしう見えて、額髪のゆらゆらと削ぎかけられたる、目見のわたり、いみじうなまめかしう、をかしげにて、かかるしもこそ、らうたげさまさりて、
忍びがたうまもり居給へるに、なほ、とばかりながめ入りて、
里分かぬ雲居の月の影のみや見し世の秋に変はらざるらん
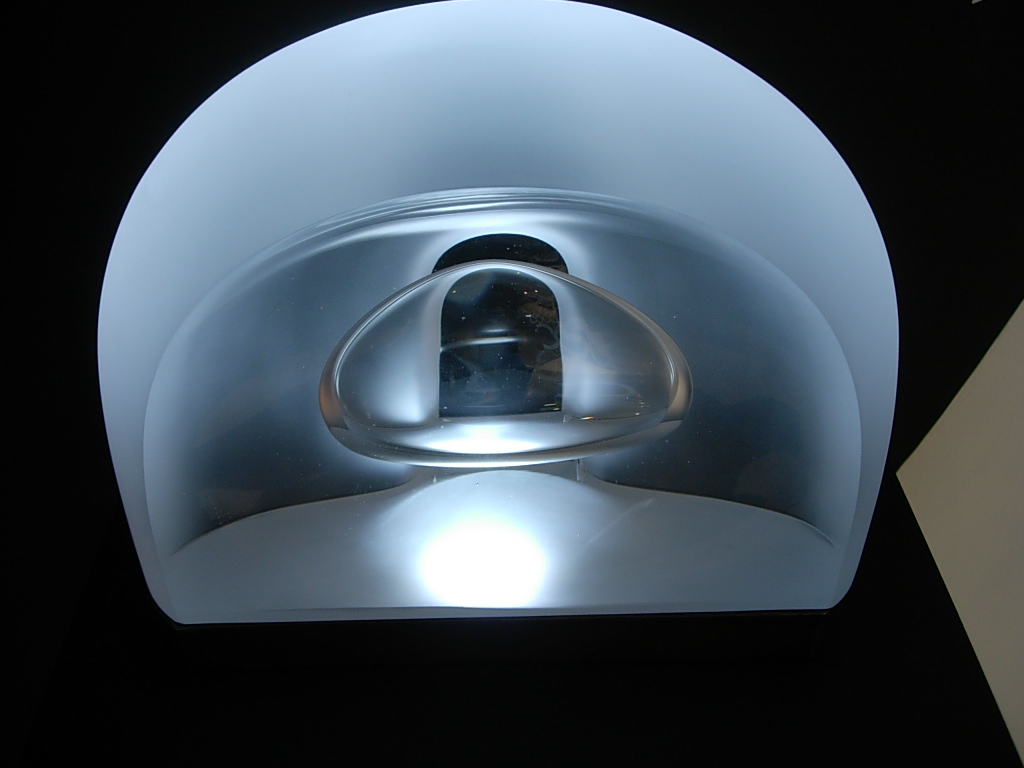
と、忍びやかにひとりごちて、涙ぐみたるさま、いみじうあはれなるに、まめ人も、さのみはえしづめ給はずやありけん。
古里の月は涙にかきくれてその世ながらの影は見ざりき
とて、ふと寄り給へるに、いとおぼえなく、「化けものなどいふらんものにこそ」と、むくつけくて、奥ざまに引き入り給ふままに、せき止めがたき御気色を、
「さすが、それ」と見知られ給ふは、いと恥づかしう口惜しくえぼえつつ、
「ひたすらむくつけきものならば、いかがはせん、世にあるものとも聞かれ奉らん」
ととざまかうざまに、あらまされつるを、「のがれたく見あらはされ奉りぬる」
とせんかたなくて、涙のみ流れ出でつつ、我にもあらぬさま、いとあはれなり。
現代語訳
小柴というものを形だけととのえてあるのも、このような山奥の小さな庵ではいずれも同じことだが、ここはとても親しみ深く、風情ある様子である。
妻戸も開いており、「まだ人が起きているのだろうか」と見受けられるので、茂っている前栽のもとから伝い寄って、軒に近い常盤木の枝が一面に茂りわたっている下に立ち隠れてご覧になると、
手前は仏が安置してあるらしく、香がとても深く香ってきて、ちょうどこの端の方で仏道修行をする人がいるようである。
経典を巻き返す音も、ささやかに親しみ深く聞こえて、しんみりと心にしみてきて、なんとなく、そのまま涙があふれる思いがして、しみじみとご覧になっていると、しばらくして、おつとめも終わったのだろうか。
女君がとても美しい月の光だこととつぶやいて、簾のはしを少し巻き上げ、月をじっと眺めている横顔は、昔のままの面影がふと思い出されてくる。
この上なく趣深く、ご覧になると、月の光が一面に差し込んでいるところに、鈍色、香染などであろうか、袖口が親しみ深く見えており、
額髪が削がれてゆらゆらと揺れている目元の様子はとても美しく趣深い。
このような尼の姿であるのがかわいらしさが増して、耐え難くみつめなさっていると、やはりもうしばらく月を眺めて、
女君『里を区別なく照らす月の光だけが以前の秋に見たのと変わっていないようだ。特に私はこのように変わってしまったのに』

とひそかに一人つぶやいて涙ぐんでいる様子はとても趣深く男君も、それほど心を静めることができなかったのであった。
男君『ふるさとの月は涙にくもってしまい、あのころのままの月は見えません。あなたがいなくなってから、私は涙にくれ、月をまともに見ることもできないのです』
と詠んでふと近寄りなさると、女君はとても思いがけないことであり、
女君は物の怪かもしれないと不気味に思って、奥のほうへ入ろうとなさるその袖を引き寄せなさるにつけてもこらえきれなかったのであろうか。
男君のご様子を見ると、女君はやはり、男君だと分かりなさり、ひどく恥ずかしく、口惜しくも思われる。
女君はただただ不気味な物の怪であった、どうしようと不安になる。
物の怪ならしょうがないと諦めることもできたのに。自分がこの世に生きていると男君に知られてしまった。
女君は、男君の前から姿を消し、もう死んだものと思われたいと考えていたのだ。
しかし、男君に自分の生存が知られてしまい、童を通じて連絡が来ていたのが辛いことだと思い自分はもうこの世にいないと聞き直していただきたいことだと思う。
女君は既に死んでいた、と男君に改めて伝えてほしいとあれこれ願っていたのにもう逃れがたく見つけられてしまったと、どうしようもなく、涙ばかりが流れ出て取り乱した様は、ひどく痛々しいものだった。
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
『源氏物語』では書かれなかった2人の再会は夜の場面です。
出家した浮舟が住んだのは小野の里という比叡山の麓の山里で、月明かりだけの静かな世界です。
忍んで庵室に近づく薫の嗅覚がとらえた名香のかおりや、聴覚のとらえた経典を巻き返す音など、研ぎ澄まされた五感の様子にも注目をしてみてください。
今回も最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。


