をかしげなる猫
みなさん、こんにちは。
元都立高校国語科教師、すい喬です。
今回は『更級日記』を読みます。
作者は菅原孝標女(たかすえのむすめ)です。
母の異母姉は『蜻蛉日記』の作者、藤原道綱母です。
作者が13歳の1020年から、52歳頃1059年までの約40年間が随想として綴られています。
平安女流日記文学の代表作といえるでしょうね。
ようやく『源氏物語』を手に入れた作者は、物語を読みふけって日々を送り、新しい年を迎えました
姉の夢の前と後では、作者の猫に対する見方が大きく変化しています。
どのように変わったのかを読み取ってみると、この段の深みが増しますね。
猫は奈良時代、中国からやってきたと伝えられています。
もっぱらネズミの退治に使われたようです。
しかしその後、次第にペット化していったようです。
古典文学の中にもいろいろと登場しています。
『枕草子』などでは「上にさぶらふ御猫は」の段が一番有名です。
五位の位を持ち、名前までつけてもらいます。

「命婦のおとど」がそれです。
しかしなんといっても存在感を持っているのは『源氏物語』に出てくる猫ではないでしょうか。
『若菜上』の巻では恋の物語が語られる際、その大きなきっかけとなる垣間見の機会を作るのが唐猫でした。
柏木が源氏の正妻、女三宮をつい見かけてしまうのです。
光源氏と女三の宮が暮らす邸宅で、女三の宮の飼っていた猫が追いかけあいを始め、
つないでいた紐が絡まって、外と室内を隔てていた御簾(みす)が引き上げられてしまいます。
蹴鞠をしていた柏木は女三の宮を何気なく、見染めてしまうのです。
そこから柏木の苦しい恋が始まりました。
紆余曲折を経て、女三の宮は柏木の子を出産するまでにいたるのです。
光源氏は、柏木の子を自らの子として抱くことになります。
まさに光源氏が藤壺との間に起こした事件と同じ、苦い経験を繰り返すことになったのです。
因果応報といえば、それまでですが、猫が果たした役割がいかに大きなものか、わかってもらえたでしょうか。
ほんのわずかの手違いから、過ちの恋が始まるのです。
猫がいなかったら、このシーンの構成はかなり違ったものになったものと思われます。
本文
花の咲き散る折ごとに、乳母(めのと)亡くなりしをりぞかし、とのみあはれなるに、
同じ折亡くなりたまひし侍従の大納言の御むすめの手を見つつ、すずろにあはれなるに、
五月ばかり、夜ふくるまで物語をよみて起きゐたれば、来つらむ方も見えぬに、
猫のいとなごう鳴いたるを、おどろきて見れば、いみじうをかしげなる猫あり。
いづくより来つる猫ぞと見るに、姉なる人、「あなかま、人に聞かすな。
いとをかしげなる猫なり。飼はむ」とあるに、いみじう人なれつつ、かたはらにうち臥したり。
尋ぬる人やあると、これを隠して飼ふに、すべて下衆のあたりにも寄らず、
つと前にのみありて、物もきたなげなるは、ほかざまに顔をむけて食はず。
姉おととの中につとまとはれて、をかしがりらうたがるほどに、
姉のなやむことあるに、もの騒がしくて、この猫を北面にのみあらせて呼ばねば、
かしがましく鳴きののしれども、なほさるにてこそはと思ひてあるに、
わづらふ姉おどろきて「いづら、猫は。こち率(い)て来(こ)」とあるを、
「など」と問へば、「夢にこの猫のかたはらに来て、『おのれは侍従の大納言の御むすめの、かくなりたるなり。
さるべき縁のいささかありて、この中の君のすずろにあはれと思ひ出でたまへば、
ただしばしここにあるを、このごろ下衆の中にありて、いみじうわびしきこと』
といひて、いみじう泣くさまは、あてにをかしげなる人と見えて、

うちおどろきたれば、この猫の声にてありつるが、いみじくあはれなるなり」
と語りたまふを聞くに、いみじくあはれなり。
その後はこの猫を北面にも出ださず思ひかしづく。
ただ一人ゐたる所に、この猫がむかひゐたれば、かいなでつつ、
「侍従の大納言の姫君のおはするな。大納言殿に知らせたてまつらばや」
といひかくれば、顔をうちまもりつつなごう鳴くも、心のなし、目のうちつけに、例の猫にはあらず、聞き知り顔にあはれなり。
現代語訳
花の咲き散る時節ごとに、乳母が亡くなった時期だと心がふさぐことであったのに、
同じ時期に亡くなられた侍従の大納言の姫君の手習いの跡を見ながら、なんとなく心が沈んでいた五月ごろのことでした。
夜ふけまで物語を読んで起きていたところ、
どこから来たかもわからないのに、猫がたいそうのんびりと鳴いたのを、はっと気づいて見れば、たいそうかわいらしい猫がそこにいたのです。
どこから来た猫なのだろうと見ていると、姉が、
「静かに。人に言ってはだめよ。たいそうかわいらしい猫だこと。飼いましょうよ」と言
うので、かたわらに寝かせました。
きっと訊ねてくる人があるだろうと、ひそかに飼っていると、
召使などのところには立ち寄らないで、私たち姉妹の前にばかり座っていて、
食べ物もおいくないのは顔をそむけて食べようとしません。
私たちの間にぴったりまとわりつくので、可愛がっていました。
そのうちに、姉が病気にかかったことがあって、家の中が看病でなんとなくざわついていました。
この猫を北面に追いやっていると、うるさく鳴きさわぐのです。
猫にもなにか事情があるのだろうと思っていたところ、病気の姉が起きだして、
「どこにいるの猫は。こっちに連れてきて」というのです。
「なぜ」と訊ねると、「夢にこの猫が私のそばに来てね」。
「私は侍従の大納言の姫君の生まれ変わりのなのです」。

「前世からの縁があって、あなたの妹がしきりに私のことを
あわれに思い出してくださるので、ほんのしばらくここに住んでいたの」
「それを、このごろは召使部屋に追いやられて、たいそう侘しくて」といいます。
ひどく泣く様子は、高貴に美しい人と見えて、はっと目をさましたところ、この 猫の声であったのです」。
「それが、たいそうあはれなことでね」とおっしゃるのを聞いた時には、たいそうしみじみとしました。
その後はこの猫を北面にも出さず、大切にお世話したのです。
私がただ一人いる所にこの猫が向かい合っていると、かきなでながら、
「侍従の大納言の姫君でおはしますね。大納言殿にお知らせしないといけませんね」
と言葉をかけると、私の顔をじっと見つめながら、なごやかに鳴くのも、
気のせいか、ちょっと見たところ、並大抵の猫ではない感じがします。
私の話を聞き知っているような顔に見えて、しみじみ愛しいと感じるのです。
猫のしぐさ
この段を読んでいると不思議な感覚にとらわれますね。
姉の台詞が実に不思議な猫との縁を象徴しているようにみえます。
全部夢の中の風景なのです。
「私は侍従の大納言の姫君の生まれ変わりのなのです」という言葉が強いインパクトを感じさせます。
「前世からの縁があって、あなたの妹がしきりに私のことを
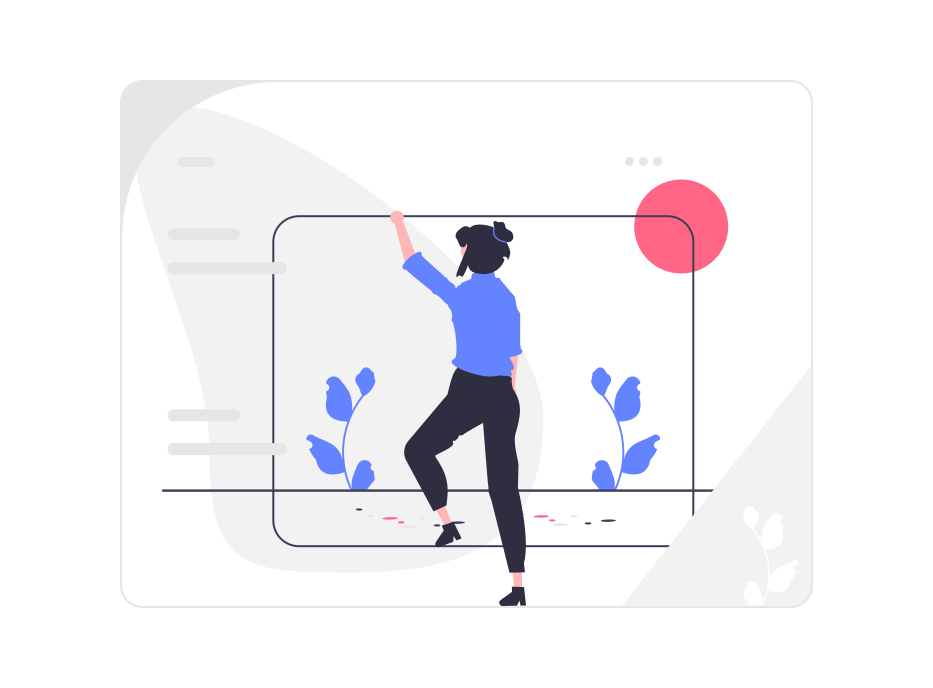
あわれに思い出してくださるので、ほんのしばらくここに住んでいたの」
「それを、このごろは召使部屋に追いやられて、たいそう侘しくて」というのです。
猫が本当にそんなことをいったかどうかではなく、可愛がっていた気持ちが、
どこかで生まれ変わりとしての存在をつくりあげたのでしょう。
ペットというものの持っている不思議な力を感じさせます。
今回も最後までお付き合いくださり、ありがとうございました。


