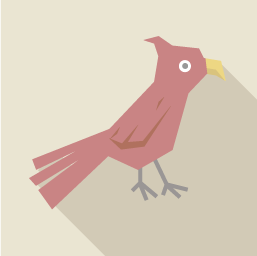翻訳の創造性
みなさん、こんにちは。
元都立高校国語科教師、すい喬です。
今回は文学の翻訳という作業について考えます。
今はいい時代です。
多くの国の文学作品を日本語で読めます。
その反対に日本で出版された小説なども、主要な外国語に翻訳されています。
感覚の鋭い、語学力のある人々のおかげだと言っていいでしょう。
外国の文学を翻訳して読むことの意味はどこにあるのでしょうか。
その反対に日本語で書かれた文学を外国語にすることの意味は何か。
このテーマは実に深い内容を伴っています。
1つだけ例をあげてみましょう。
川端康成の小説『雪国』の冒頭をあなたは御存知ですね。
大変に有名です。
思い出してみてください。

「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。夜の底が白くなった。」
多くの人が知っている冒頭の表現がこれです。
この小説を英語に翻訳したのは、アメリカ人で日本文学に詳しいサイデンステッカー氏でした。
1957年に翻訳がなされ、出版されたのです。
彼の翻訳がなければ、川端康成が1968年にノーベル文学賞を受賞することはなかったに違いありません。
実に感覚的な表現ですね。
日本語の作品が海外に多く翻訳されることのきっかけにもなった小説です。
しかしよく考えてみてください。
この表現を英語に訳すことは、それほど簡単なことではありません。
特に「夜の底が白くなった」という曖昧な表現をどのように翻訳すればいいのでしょうか。
新訳の存在
おそらく多くの日本人にとってなじみがあるのは、翻訳文学だと思われます。
大正期にはロシア文学、昭和の初期にはフランス文学などが、ものすごい勢いで流入してきました。
それらを多くの翻訳者たちが、日本語にしてくれたのです。
今でも名訳とよばれる作品は、この時代になされたものが多いですね。
あるいは新訳とよばれるものも、近年たくさん出版されています。
ドストエフスキー作『カラマゾフの兄弟』などは亀山郁夫氏によって2006年に発表され、累計120万部も売れました。

その他、シェイクスピア全集などもかつて小田島雄志氏によって全巻翻訳され、多くの舞台で使われました。
その後は英文学者、松岡和子氏の翻訳が相次いで出版され、今も上演されているのです。
文学を翻訳して読むことに、どのような意味があるのでしょうか。
文化や風俗の違いは当然あります。
それなのに、わざわざ違う国の作品を自国語にしてまで読もうとする熱意は、どこから生まれるのでしょうか。
実際に翻訳をしていく上での苦労とは何か。
そのための参考テキストとして、教科書に次のような文章が載っていました。
これをそのまま小論文の問題にすることも十分に可能だと思われます。
設問を次のようにすればいいでしょう。
次の文章を参考にして、外国文学を翻訳で読むこと、日本文学が外国語に翻訳されて読まれることの意味について、あなたの経験をふまえ、800字以内で論じなさい。
本文
実際に文学作品を翻訳する上ではどのような問題が起こってくるのか。
たとえば語順の問題がある。
それぞれの言語の間では文法や文の構造が同じとは限らないから、主語、述語、目的語、補語といった文の要素の配列は異なってくる場合がある。
あるいは語彙の体系の差異もある。
そこで、しばしば翻訳者が翻訳元の文章の意味を全体として理解した上で、語順の変更や語句の省略や付加などを行いながら、目標言語の文章として読みやすくなるように工夫を行う。
特に文学作品の翻訳の場合、翻訳者の積極的な関与によって元の文章の持つ核のようなものを移し替え、翻訳された文章が一つの自立した文学作品として鑑賞に堪えるものになるべきといった議論がなされる。
身近な問題に目を向けてみよう。
先ほど触れた人称代名詞の問題である。
現代の日本語では「彼/彼女」という三人称代名詞が多く用いられている。
だが話し手と聞き手以外の第三者を「彼/彼女」という語で指示することが普通になってきたのは、明治時代以後の比較的最近のことである。
それも、そのような用法には翻訳が関わっていると考えられる。
翻訳論・比較文化論を専門とする柳父章(やなぶあきら)は、日本語の人称代名詞「彼/彼女」が、明治期の文学の近代化の中で翻訳文の影響を受けて用いられるようになってきたと指摘する。
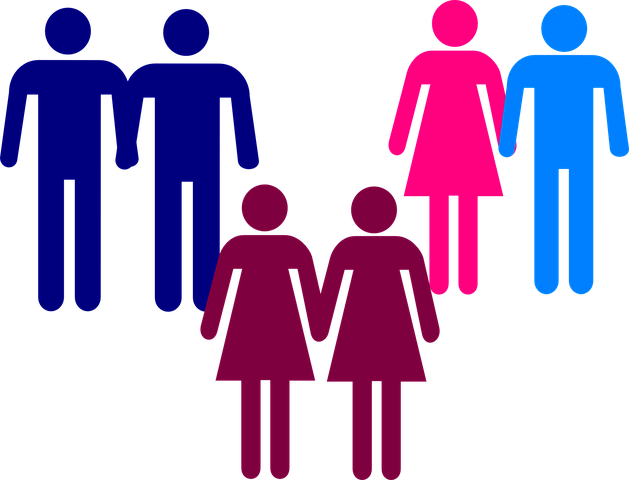
ここから言えるのは、翻訳は元の文章に対して二義的なものを生み出す行為ではなく、時に創造性を発揮するものだということである。
目標言語の体系における言葉の用いられ方に揺さぶりをかけ、新鮮な言葉の使い方を生み出していく。
文学者に自ら翻訳を行う者もあるのは、翻訳行為がその人の言語使用を相対化させ、新たな魅力ある文学言語を生み出す糧となる場合があるからだと言えるだろう。
もっと言えば、翻訳行為そのものが1つの創造行為である。
翻訳された文章には、翻訳者がこしらえた様々な工夫や、翻訳者の個性が表れている。
翻訳された文学を読むとは、二重の創造性を感受できるという意味で、2度おいしい読書行為だといえるかもしれない。
価値の泉
ここには実に興味ある指摘がありますね。
その1つが第三人称の呼び方です。
これはぼく自身の経験です。
中学に入って驚いたことは、彼と彼女という呼び方そのものでした。
英語の授業の中ではじめて知ったのです。
それまでは多分、「あの人」などと口にしていたに違いありません。
ところが英語の文章には当たり前のように、彼と彼女が跋扈していました。
文章を日本語訳する時にも、当たり前のように、彼と彼女を使ったのです。
それだけで世界が大きく広がりました。
日常の会話の中にも当然、応用されるようになったのです。
翻訳は新鮮な体験を次々ともたらしてくれました。
確かに文法は違います。
語順も同じではありません。
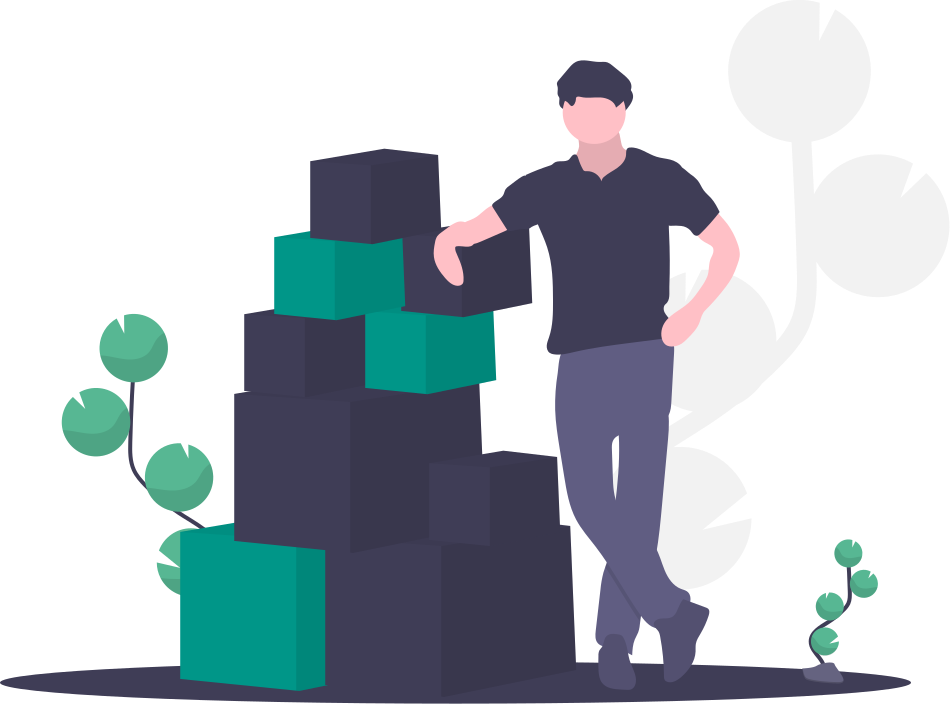
さらにいえば、接続詞の使い方も同じではないのです。
肯定と否定がはっきりと区分けされ、日本語に多い曖昧な表現はあまり見受けられませんでした。
つまり新しい土台がそこには用意されていたことになります。
翻訳はそれを使って、全く別の価値観を自分の近くに引き寄せることも可能なのです。
わかりやすくいえば、西洋的な一神教の神を想像することもできます。
アニミズムの世界に生きていた『万葉集』の言葉を英語に翻訳しようとすれば、必ず呻吟せざるを得ません。
川端康成の新感覚的な表現をどう英語にするのか。
これも新しい試みです。
つまり創造そのものだといっていいでしょう。
翻訳は元の文章に対して二義的なものを生み出す行為ではないのです。
新しい地平を切り拓く試みととらえることができるのではないでしょうか。
小論文のテーマとしてあえて書くとすれば、そこに不可能の芽はあるのかを考えてみるのも有効です。
何が翻訳できないのかもあわせて論じてみたいところです。
筆者にべったりでは、高評価を得ることはできません。
メリットとデメリットを冷静に見て取ることが大切です。
じっくりと考え、論文を組み立ててみてください。
今回も最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。