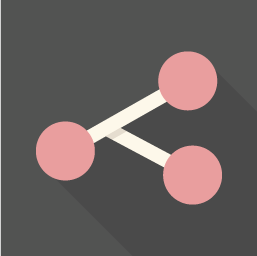沈黙する花
みなさん、こんにちは。
元都立高校国語科教師、すい喬です。
今回は映画の中に登場する花について考えます。
たまたま、教科書で映画監督、西川美和氏のエッセイを読みました。
その瞬間、評論家、小林秀雄の有名な警句を思い出したのです。
御存知でしょうか。
「美しい花がある。花の美しさというものはない」というものです。
小林秀雄は美を追求し続けた人です。
ひときわ、そのもの自身が持っている本質を見ようとしたのです。
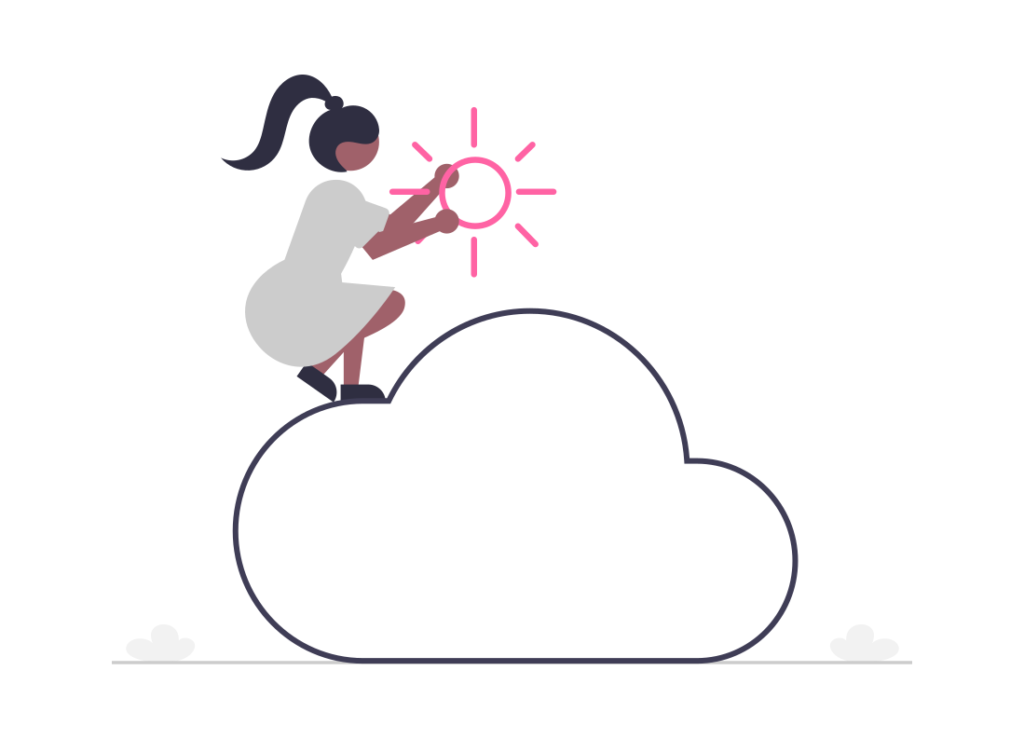
しかしその時、「花の美」という想念が頭をよぎりました。
ものの美は観念ではなく、自分の肉体そのもので受け止めるものであることを感じたのです。
美しいと感じた瞬間に、花と美は一体化していたのです。
「美」だけがそこに単体で屹立するなどいうことはありえないということです。
人間は観念的な生き物ですからね。
心を虚しくして実在や自然を受け入れるべきだとする、小林の魂の叫びといえるかもしれません。
その言葉を思い出しながら、西川氏の文章を読みました。
彼女は映画の中に出てくる花の印象を語っています。
『ひまわり』と『それから』です。
どちらもぼくには懐かしい映画です。
特にロシアのウクライナ侵攻が始まって以来、『ひまわり』は日本中で鑑賞会が開かれていると聞きました。
ヨーロッパの各地にひまわり畑はあります。
広大な花の咲く平原を歩く女の姿は、人間の愚かさをそのものを示す象徴かもしれません。
ここにエッセイの一部分を載せます。
映画の中の花
花の美しさを映画で捉えることは、きわめて難しいと私は思う。
言わずもがなのその美しさが、落とし穴である。
目で見て美しく感じるものを、撮ればそのまま物語になるかというと、実はそうではない。
映画は時間を縦軸にして、物事の「運動」を捉えて物事を語る。
「好きだ」という概念一つとっても、ただ思い巡らせるのではなく、声にして発語するとか、目くばせするとか赤面するとかという何らかの運動を伴わなければ、観客にその「好きだ」は伝わらない。
どんなに奥深いテーマをだろうと、主人公に机の上で腕組みして沈思黙考されていたのでは、いつまでたっても映画にはならないのである。
運動は「動き」と「音」とで表現されるが、花にはその「動き」と「音」がない。
美しさが、あまりにも静的なのだ。
演じ手の中にも「花」に似た人がいる。
容姿端麗で肉眼や写真で見ればまばゆいばかりなのに、映像で捉えてみると、どこか血の通わない無生物のような映り方をする。
きれいな映像は撮れても、「映画」が生まれるとは限らない。
しかしそれでも映画を撮る者たちは花に引きつけられ、風を待ち、花びらを散らし、カメラを動かし、懸命に花に運動をもたらそうとする。
黒澤明も小川におびただしい数の椿の花を流して、『椿三十郎』の演出をした。
私にとって映画の中にある花は、死の匂いを放つものの印象が強い。
野に咲く花で思い出すヴットリオ・デシーカ監督の『ひまわり』は第二次世界大戦末期に極寒のソ連戦線で行き倒れた兵士たちの死肉の上に広がった見渡す限りのひまわり畑が、底抜けに明るい陽の光を受けている。

元来大輪のひまわりさながらのタフな美貌のソフィア・ローレンが、消えた夫を求めて色あせた亡霊のようにその大地を歩く。(中略)
切り花で思い出すのは漱石の『それから』(森田芳光監督)の中の真っ白い百合の花、確か一つの濡れ場も出てこない映画だったが、暗い雨の夕方、三千代が持ってきた百合の花に、一つ傘の下で代助がそっと鼻先を近づけるシーンには、許されない男女の死出の道行きのような重苦しさに、むせ返るほどの欲動が充満している。
想像力たくましき中学生だった私は、百合の花弁をそっと握る松田優作の大きな手を見ながら「うむむ」と興奮したものだった。
花は美しさだけではなくて、いやおうもない生命の巡りを予感させる怖さをも秘めてもいる。
可憐に咲いたかと思えば、ものも言わず散り、くたくたに醜く枯れて腐臭を漂わせることも恐れない。
役者としては静的すぎるのかもしれないが、一方で全ての物や人間が絶えず動き回る活劇の中において、 その静謐さがときに時間を止め、生命の危うさや時の移ろいをフィルムに焼き付けている気もする。
何もせず、何一つ余計なことを言わないで「ただそこにいる」ことが、実は俳優にとって最も難しい演技であり、最も座をさらう術であるとも聞く。
花たちを中身空っぽのお人形として撮るも、無為のままに森羅万象を語らせるも、とどのつまり演出家の腕次第ということなのか。
死の匂いを放つもの
ヴットリオ・デシーカ監督の『ひまわり』を見たのは、はるか以前のことです。
50年前の映画と聞いて、月日の過ぎるはやさを感じます。
第二次世界大戦下のイタリアが舞台です。
結婚して幸せな日々を送っていた男が招集され、当時のソ連に送られます。
妻は戦争が終わっても帰らない夫を探しに現地へ赴きます。
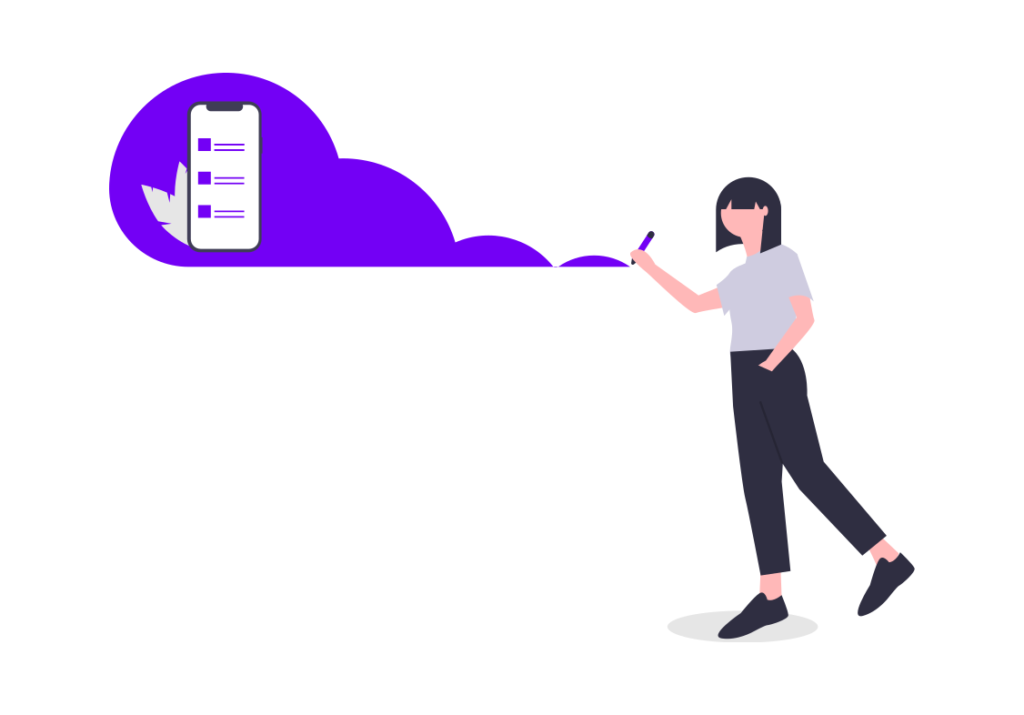
かつての夫は戦場で倒れ、命を救ってくれた地元の女との間に家庭を築いていたのです。
圧巻はソフィア・ローレンが演じる女が、広大なひまわり畑をさまようシーンです。
この映画の主役はひまわりそのものです。
他にはありません。
半ば狂ったように夫の無事を信じて、彷徨うのです。
観客の目には、風に揺らぐひまわりの花が、死んでいった兵士の姿に見えたかもしれません。
圧倒的に死の匂いのする映画です。
花のさだめ
花というのは不思議な生命体です。
エッセイにもある通り、可憐に咲いたかと思えば、ものも言わず散り、くたくたに醜く枯れて腐臭を漂わせることも恐れないのです。
ある意味、人の一生と重なりませんか。
人間も生まれてしばらくの間は、人々に愛されあたたかく育まれていきます。
やがて花の時代が去る頃には、散り果て、さらに腐っていくのです。
その姿の変容ぶりは、みごとというしかありません。
花は自らが腐っていくことも黙って受容するのです。
やがて捨て去られ、地に戻ります。
そこから新しい芽がでることもあるのでしょう。
輪廻転生することも考えられます。
花は何も言わずに、ただそこにいるだけです。

それ以上、何もしません。
だからこそ、貴いのかもしれません。
悲しいにつけ、嬉しいにつけ、人は花を飾ります。
それが自然だからです。
腐らない花は花ではないと言えます。
造花の中には、確かに本物かと見間違えるほどの出来栄えのものもあります。
しかしそれはやはり違うのです。
枯れて腐らないから、便利だといえば確かにそう言えます。
能楽者、世阿弥の説く「まことの花」になるには、枯れて腐る可能性があるぎりぎりとところで踏みとどまる人間の叫びが聞こえていなければなりません。
今回は西川美和氏のエッセイを読み、自分なりに考えたことをまとめてみました。
最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。