明石の君の不安
みなさん、こんにちは。
元都立高校国語科教師、すい喬です。
今回は『源氏物語』を読みます。
昔から「源氏の須磨がえり」という言葉があります。
聞いたことがありますか。
12巻目「須磨」、13巻目「明石」です。
このあたりまでくると、疲れてきます。
複雑な話の展開を頭に入れながら、読み続けるのに挫折してしまうのです。
それがちょうど「須磨」あたりなんですね。
ところがここからまた話が面白くなっていきます。
源氏が須磨に流された経緯を御存知ですか。
なぜ彼がそういう運命になったのかという説明を、簡単にしておきます。
宮中の桜見の宴の後で、源氏が関係を持った姫君が、朧月夜でした。
光源氏は彼女の素性を全く知らなかったのです。
父の桐壺帝は亡くなり、右大臣派と左大臣派で政争が繰り広げられていました。
光源氏の正妻、葵上は、左大臣の姫君です。
そこで右大臣の側は、源氏が朱雀帝の女御として入内を予定していた朧月夜と関係を持ったことを利用して、左大臣の源氏を陥れようと画策しました。

つまり帝に対する不敬をしたという理由です。
源氏はその策略を知り、罰せられる前に須磨へ隠遁したのです。
自ら無位無官となりました。
そこで知り合った明石の君との間にできた娘が明石の姫君です。
彼女はその後、帝の后になるべき、数奇な運命を背負っていました。
しかし地方豪族の娘、明石の君が産んだ子供では、家柄がよくありません。
当時は女性の生まれた家の家格が、大きな意味をもっていたのです。
そこで源氏の妻である紫の上の養女にするという方法をとろうということになりました。
母、明石の君は自分の娘が継子扱いされるのが不安で仕方がないのです。
それでも涙をのんで、子供の将来のため、光源氏にその運命を預けることにしました。
なぜか、源氏の妻、紫の上には子供が生まれません。
この微妙な人間関係も『源氏物語』を複雑なものにしています。
本文
冬になりゆくままに、川づらの住まひいと心細さまさりて、上の空なる心地のみしつつ明かし暮らすを、
君も、「なほかくてはえ過ぐさじ。かの近き所に思ひ立ちね」とすすめたまへど、「つらきところ多く試みはてむも残りなき心地すべきを、いかに言ひてか」などいふやうに思ひ乱れたり。
「さらばこの若君を。かくてのみは便なきことなり。思ふ心あればかたじけなし。
対に聞きおきて常にゆかしがるを、しばし見ならはさせて、袴着の事なども、人知れぬさまならずしなさんとなむ思ふ」と、まめやかに語らひたまふ。
さ思すらん、と思ひわたることなれば、いとど胸つぶれぬ。
「あらためてやんごとなき方にもてなされたまふとも、人の漏り聞かんことは、なかなかにやつくろひがたく思されん」とて、放ちがたく思ひたる、ことわりにはあれど、
「うしろやすからぬ方にやなどはな疑ひたまひそ。かしこには年経ぬれどかかる人もなきが、さうざうしくおぼゆるままに、前斎宮の大人びものしたまふをだにこそ、
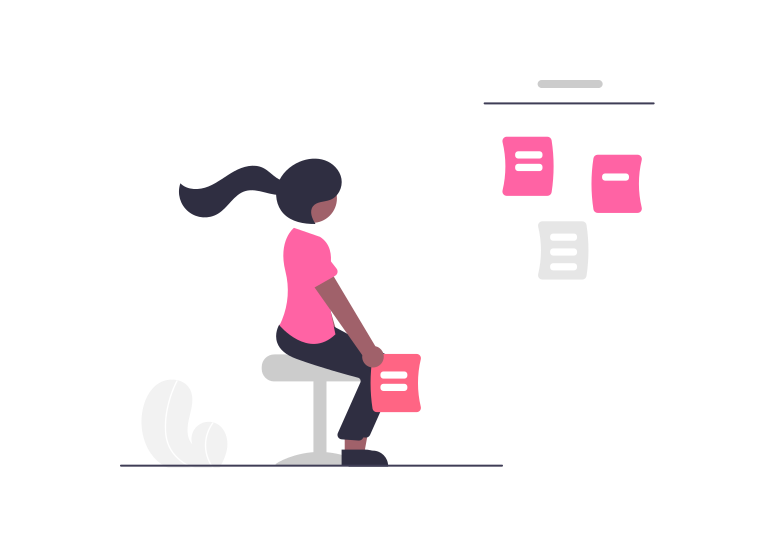
あながちに扱ひきこゆめれば、まして、かく憎みがたげなめるほどを、をろかには見放つまじき心ばへに」など、女君の御ありさまの思ふやうなることも語りたまふ。
「げにいにしへは、いかばかりのことに定まりたまふべきにかと、伝にもほの聞こえし御心のなごりなく静まりたまへるは、おぼろけの御|宿世にもあらず、
人の御ありさまも、ここらの御中にすぐれたまへるにこそは」と思ひやられて、「数ならぬ人の並びきこゆべきおぼえにもあらぬを、さすがに、立ち出でて、
人もめざましと思す事やあらむ。わが身はとてもかくても同じこと、生ひ先遠き人の御|上《うへ》もつひにはかの御心にかかるべきにこそあめれ。さりとならば、げにかう何心なきほどにや譲りきこえまし」と思ふ。
また、「手を放ちてうしろめたからむこと。つれづれも慰む方なくては、いかが明かし暮らすべからむ。何につけてかたまさかの御立寄りもあらむ」など、さまざまに思ひ乱るるに、身のうきこと限りなし。
現代語訳
冬になってゆくにつれて、大堰川に面した住まいはいよいよ心細さがまさって、ただ上の空といった気持ちで、日々明かし暮らしているのを、
源氏の君も、「やはりこんなふうに過ごしてはいられないでしょう。あの近い所に移るよう決めておしまいなさい」とおすすめになりますが、
明石の君は「冷淡なお気持ちをことごとく見届けたなら、もうお終いという気持ちになるに決まっているのだから、その時何を言って嘆いてよいのか」などと、そんなふうに思い悩んでおりました。
源氏の君は「ならばこの姫君を、こうしてばかりいるのは不都合なことです。私に考えがあるのだから、このままでは勿体ない。西の対の女君(紫の上)も話は聞いていて、いつも姫君に会いたがっていますから、
しばらく女君に姫君の世話をさせて、袴着の事なども、人知れずという形ではなくちゃんと行おうと思うのです」と、真剣にご相談を持ちかけなさいます。
明石の君は、源氏の君がそうお思いになっているだろうとずっと思っていたことなので、ひどく胸がつぶれる思いでありました。

明石の君は「今さら身分高い方のように姫君をお取り扱いになったとしても、世間の人が漏れ聞くように母親である自分の身分が低いことは、かえって姫君には取り繕いがたいことにお思いになるのではないでしょうか」といって、
姫君を手放し難く思っているのは当然の道理ではありますが、源氏は「不本意な扱いを受けるのではないか、などとお疑いになってはいけません。紫の上には年月が経ってもこういう可愛い子も生まれないので、
物足りなく思っているのにまかせて、前斎宮のもうすっかり大人になっていらっしゃるのをさえ、強いてお世話申し上げているような次第なのです。
ましてこんな、憎むに憎めない幼い人を、無下に見捨てることなどできぬあの方のご気性ですから」などと紫の上の御人柄の申し分のないこともお話になります。
「なるほど以前は、どんな人のもとに落ち着かれるのだろうかと人伝えにわずかに聞いていた源氏の君の浮気心が、跡形もなくお静まりになっていらっしゃるのは、前世からのご因縁が並々ならぬものであられたのだろうし、
またそのお方の御人柄も、そこらの人では及ばないほど優れていらしたからだろう」と想像され、
「私のような人数にも入らない者がそのお方と並び申し上げるような信望もないのに、出ていったら、その御方も、いかによい御人柄とはいっても私のことを目障りだとお思いになることがあるでしょう。
わが身はどうなっても同じことだが、将来が長いこの子の御身の上も、結局はそのお方の御心にかかってくるようだ。それならば、本当にこうして姫君がまだ物心つかないうちにお譲り申し上げようかしら」などと思い悩むのです。
また一方では、「姫君を手放してしまえば気がかりなことになることでしょう。所在ない時も慰めようがないので、どうやって日々を明かし暮らしていけばよいものか。
また源氏の君は何かにつけて時たまの御立ち寄りもしてくださるだろう」など、さまざまに思い乱れるにつけ、わが身のつたなさがどこまでも情けなく思われるのでした。
紫の上
源氏は前の章で紫の上に明石の姫君の袴着のことを相談しています。
その内容は正式な住まい、二条院で盛大に行いたいというのです。
3歳くらいで行う儀式です。
明石の君に向かって、あなたが二条院に移らないならこの可愛い娘を二条院に移しなさいと何度も説得しました。
将来、必ず天皇の后にするという強い意志を示したワケです。
そのため姫君を紫の上の養女にしようというのです。

しかし母親である明石の君は、結局粗略に扱われ、かわいそうなことになるのではないかと心配でなりません。
作者、紫式部が周到なのは、この上もなく気品に満ちて、すばらしい女性である紫の上に子供がうまれないという造形をしていることです。
母親である桐壺の更衣によく似た継母、藤壺に対する愛情から数奇な物語が始まっているのが、『源氏物語』です。
子供だった紫の上を自分好みに育てたのも、光源氏です。
しかし彼女に子供はうまれませんでした
作者は別の女性の産んだ子をひきとって養女にするという、紫の上の気持ちを容赦な描いています。
自分の乳房を子にくわえさせる場面などを読んでいると、紫式部のある意味冷徹な側面も垣間見えてきます。
「源氏の須磨返り」は実はここからだという暗示でもあるのです。
ものすごくスケールの大きな創作であることが、よくわかると思います。
今回も最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。


