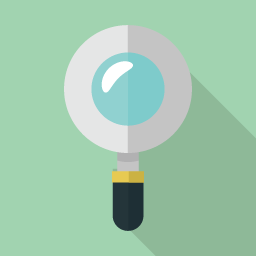平安時代の恋愛観
みなさん、こんにちは。
元都立高校国語科教師、すい喬です。
今回は平安時代の結婚観や、男女の恋愛観について考えてみます。
といっても特別な話ではありません。
いつの時代も男女の中は厄介なものです。
互いの心の状態を理解するということが、本当に難しいのです。
男女関係のトリセツの本は枚挙にいとまがありませんね。
つまり永遠のテーマだと言えます。
平安時代に書かれた『枕草子』の内容が、令和の今になっても十分に通用するのだから不思議です。
ここでは中世において、女性を評価する指標がどのようなものだったのかについて考えてみましょう。

『源氏物語』にも「雨夜の品さだめ」という有名な章があります。
紫式部の人間観が実によく表現されている部分です。
では『枕草子』はどうでしょうか。
清少納言と紫式部との違いについて考えてみるのも興味深いですね。
この時代は、家柄や教養を重視する傾向が大変高かったのです。
高貴な女性になればなるほど、女性は他人に顔を見せることがほとんどありませんでした。
一日中、御簾の奥深くにいて、廊下を歩いたりすることもなかったのです。
端近(はしぢか)という言葉をご存知ですか。
「そこは端近だから」という言い方をします。
外から誰かに覗かれるので、縁側の方へ行ってはダメですよというワケです。
随分と息苦しい暮らしぶりですね。
出会いのキッカケ
男性はどのようにして、女性の存在を知ったのでしょうか。
基本的には噂です。
どこそこの屋敷に誰の令嬢で、大変な美人が住んでいるらしいという風の便りが飛び込んできます。
そこで女房などを通して女性に手紙を送るのです。
基本的に自作の和歌を必ず添えます。
紙の質にも気を使わなければいけません。
どのような墨で書くのかも大切なポイントです。
書の腕前が教養を示すのです。
女性から返事があれば、男性が女性の部屋に赴くことになります。
それにも女房の采配が必要です。
男性の教養はなんといっても歌と書で計られます。
言葉の使い方をみれば、その人のレベルがわかるワケです。。
和歌には全てが表現されます。
季節感やウィット、さらには過去の歌に対する知識など、あらゆる要素が必要になるのです。

現在と違って、写真もメールも何もありません。
夜、忍んでいくのが普通なので、信じられないことに姉のところへいく予定が妹に会ってしまったりなどということすらありました。
『源氏物語』などにそのような場面が出てきます。
男性が女房に導かれてこっそり入ってきたら、女性は逃げることもできません。
一夫多妻制です。
拒否する術がなかったのです。
ほとんどのケースは、夫が妻の家に行く通い婚でした。
基本的に女性はずっと実家で暮らします。
結婚に伴う諸費用は、すべて女性の実家で面倒を見るのです。
それだけに女性の実家が権力者であればあるほど、後見人が確実だということになりました。
また女性からの離婚の申し入れはできませんでした。
男性が通ってこなくなれば、結婚生活は自然消滅したのです。
清少納言の結婚生活
現在の常識から考えれば、随分ひどい話です。
『伊勢物語』などにも、夫が遠い土地へ仕事に出かけ、なかなか帰ってこないという話があります。
そこへ新しい男性がやってきて、仕方なく一緒になるなどというケースもあったのです。
清少納言の結婚生活については、いろいろな説明がなされています。
彼女は、歌人・清原元輔が59歳の時の子供です。
きっと可愛がられて育ったのでしょう。
漢学の教養なども父親から学びました。
彼女は、16歳の頃に橘則光と結婚します。
翌年、男の子を出産していますが、やがて離婚しました。
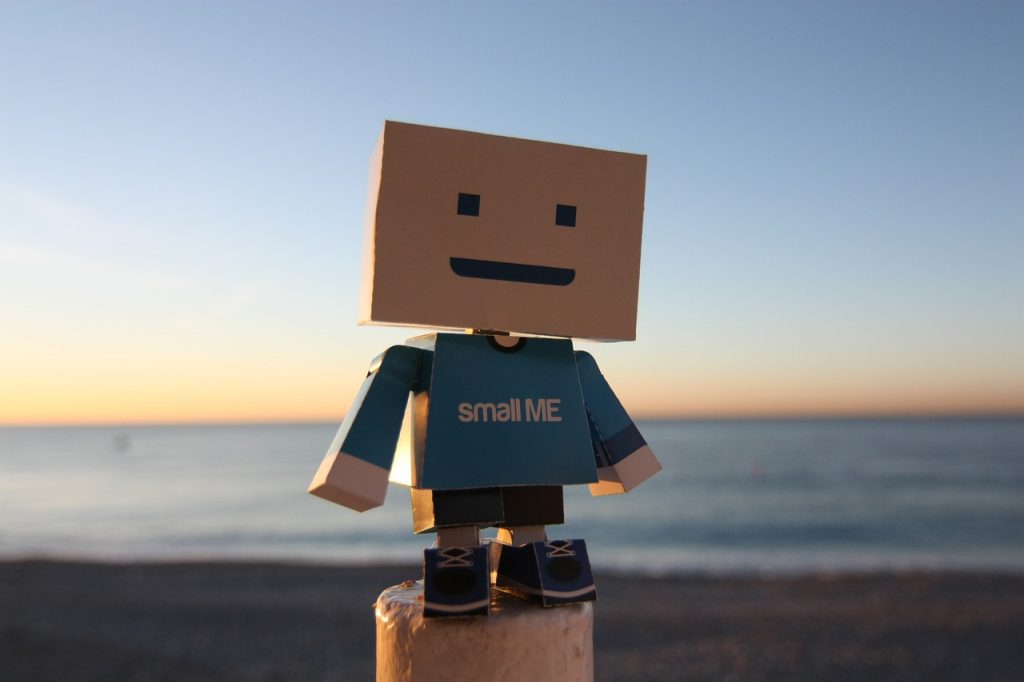
清少納言はその後、父娘ほども年齢の違う藤原棟世と再婚します。
そこに飛び込んできた話が、一条天皇の中宮、定子の女房として出仕しないかというものでした。
28歳前後であった清少納言は、結婚生活では満たされない感情を持っていたに違いありません。
もっと知的で華麗な宮中での生活を、自分の目で見るチャンスでした。
そこでの見聞が『枕草子』に結晶したというワケなのです。
ここでは「男こそ、なほいとありがたく」の章段を読みましょう。
彼女の男性観が色濃く反映されたユニークなところです。
本文
男こそ、なほいとありがたくあやしき心地したるものはあれ。
いと清げなる人を捨てて、憎げなる人を持たるもあやしかし。
公所に入り立ちする男、家の子などは、あるが中に、よからむをこそは、選りて思ひたまはめ。
およぶまじからむきはをだに、めでたしと思はむを、死ぬばかりも思ひかかれかし。

人のむすめ、まだ見ぬ人などをも、よしと聞くをこそは、いかでとも思ふなれ。
かつ女の目にもわろしと思ふを思ふは、いかなることにかあらむ。
かたちいとよく、心もをかしき人の、手もよう書き、歌もあはれによみて、恨みおこせなどするを、返りごとはさかしらにうちするものから、寄りつかず、らうたげにうち嘆きてゐたるを、見捨てて行きなどするは、あさましう、公腹立ちて、見証の心地も心憂く見ゆべけれど、身の上にては、つゆ心苦しさを思ひ知らぬよ。
現代語訳
男というものは、何とも類のないほど奇妙な心を持っているものです。
たいそう美しい女を捨てて、醜い女を妻としているのも誠におかしなことです。
朝廷に出入りする男性やその一族などは、数多くある女性の中からとくに美しい人を選んで愛しなさったらいいのに。
相手が自分には及びもつかない高貴な身分の女性であっても、すばらしいと思うのなら命がけで恋愛するのがいいのです。
どこかのお嬢様とか、まだ見たこともない未婚の女性などでも、美しいと聞けば、どうにかしてわがものにしたいと思うものでしょう。
それなのに、同性の私の目から見てもよくないと思うような女性を愛するのは、どういうわけなのか、まったく理由がわかりません。
顔かたちがとてもよく、気立てもよい女性で、字もきれいに書き、歌も趣豊かに詠める人がいます。

その女性が手紙などで恨み言を言ってきても、男性はその返事はうまくあしらったりできるものです。
それなのに、女性のところへは寄りつきもせず、いじらしく嘆いていても、見捨てて他の女性のところに行ったりするのは、あまりのひどさにあきれてしまいます。
本当に人ごとながら腹が立ち、傍目にもわびしく見えるのに、男性の側は自分自身のふるまいについて、少しも相手の人のつらさなど意識していないのです。
これはどうしたことなのでしょうか。
女性の地位
清少納言がどのような女性を高く評価していたのかみてみましょう。
➀顔かたちがとてもよい。
②気立てがよい。
③字もきれいに書ける。
④歌も趣豊かに詠める。
この4つの点を挙げています。
平安時代の女性たちは、親の決めた男性と結婚し、その人の出世によって我が身の社会的地位も上がり、経済的にも恵まれ、幸福に暮らすというのが理想でした。
恋愛結婚という感覚はおそらく一般的ではなかったのです。
女性は自分勝手な恋愛や結婚後の浮気もしません。
ところが夫の女性関係には目をつぶらなければいけません。
右大将道綱の母として有名な『蜻蛉日記』の筆者などは、夫の女性通いに苦しみ続けました。
清少納言はどのような立ち位置にいたのでしょうか。
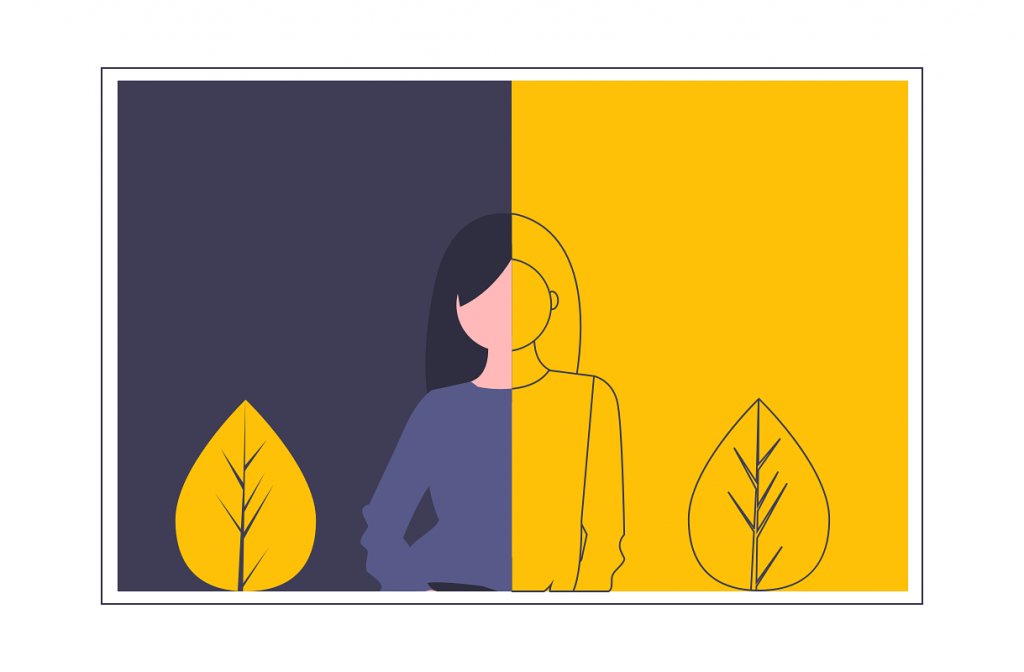
彼女は我慢をするのが嫌だったに違いありません。
男性の価値観にNoが言える強い女性の部類でした、
今ならばジェンダーフリーを当然のように主張したでしょうね。
なぜ彼女がそうなれたのか。
広い世の中を見たからです。
宮仕えをしたことで、世界が一気に広がりました。
はじめて宮仕えに出た時の緊張感が次第にほどけて、自由に宮中を観察できるようになりました。
狭い世間から自由な空間に移動したことが、彼女の天性の批評眼を育てたのです。
そのことが『枕草子』という中世に比類のないエッセイを生み出した原動力です。
彼女はそこであまりにも多くのことを目の当たりにしてしまいました。
没落していく一族の様子もその1つです。
定子の父道隆が亡くなり、その後定子の兄・伊周が左遷されます。
道隆の死により定子の立場がにわかに不安定なものとなっていくのも、新しい権力者、道長の姿もすべて目に焼き付けました。
それが人の世のすべてだったのです。
今回も最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。