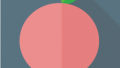古典論
みなさん、こんにちは。
元都立高校国語科教師すい喬です。
今回は古典の成り立ちについて少しお話をします。
皆さんは『ガリバー旅行記』をご存知ですか。
アイルランドの作家ジョナサン・スウィフトにより、仮名で執筆された小説です。
主人公はわずか身長6インチ(15.2センチメートル)の小柄な人々に取り巻かれます。
リリパット国とブレフスキュ国でのガリヴァーの冒険話が面白いんですね。
しかしこれは当初、イギリスとイギリス社会に対する批判を行うための風刺作品でした。
彼は当時のイギリスの対アイルランド経済政策に不満を持っていたのです。
イギリスにばかり富が偏っていました。
アイルランドは極度の貧困にあえいでいたのです。
リリパット国は18世紀のイギリス、ブレフスキュ国はフランスをイメージしています。
この本は現在世界の子供にたくさん読まれています。

しかしもともとは児童文学などではなくて政治風刺小説だったのです。
18世紀のイギリス政治は腐敗していました
それを作者のスウィフトは架空の国の遠い話として書きました。
ところが人々はこの話を現実のこととして読んだのです。
やがて時代が19世紀になると、全ての政治的要素が飛んでしまいました。
発表した当時ならば登場人物が誰のことか皆分かりました。
しばらくすると風刺としての命がなくなったのです。
今でもそうですね。
ちょっと前のことになるともうすぐに忘れてしまう。
特に政治の世界はそうです。
時代がかわれば
時代が変わって社会が変われば意味はどんどん変化していきます。
歴史の中に飲み込まれてしまうのです。
作品の命が消えてなくなるのは想像以上に早いものです。

『ガリバー旅行記』も文学作品であることをやめてしまいました。
それでは何になったのか。
架空の童話になったのです。
巨人と小人のお話です。
子供達はとても喜びました。
今でも『ガリバー旅行記』というと子供向けの童話ですねと誰もがいいます。
驚いたことにガリバーは日本にも来ているんですよね。
知っていましたか。
今ではこれが痛烈な社会風刺の作品だなんて誰も思いません。
つまり作品は作者の手を離れると全く違うものに生まれ変わってしまうのです。
では誰がそれを決めるのか。
まさに読者なのです。
筆者の外山滋比古はそのことをあらためて強調しています。
読者が新しい作品を生み出すと言ってもいいのかもしれません。
ガリバーの話というのは主人公の巨人が小さな国を次々と巡るという物語です。
それだけに子どもにとっては夢があってすごく楽しいのです。
なんとなく読んでいてもワクワクしますよね。
アリスの不思議の国の冒険
一方、ルイス・キャロルが書いた作品に『アリスの不思議の国の冒険』というのがあります。
これも夢のある作品ですね。
最初は童話のつもりで書かれたといわれています。
ところが、いつのまにか童話のイメージから離れてひとつの文学作品になってしまいました。
幻想的な世界をそのまま提供するレベルの高い文学になったというワケです。
まさか作者のルイス・キャロルはそんなものになるとは夢にも思わなかったでしょう。
しかし現実はまさにこの通りです。
誰がそれを文学作品にしたのかといえば、それは読者なのです。
だから読者は強いのです。
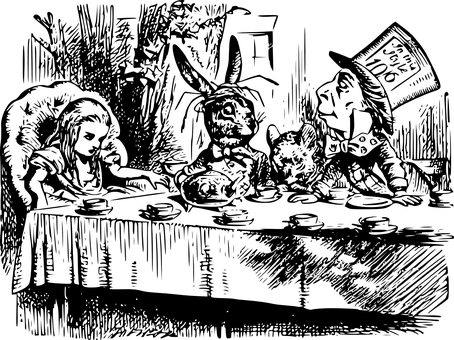
どんな作品でもそれが書かれたときとは全く違うものに変わってしまうことがあります。
作者が予想もしなかった性格に変質していくのです。
作品は作り手の元を離れて独り歩きを始めます。
生き延びる契機を得ようとしているのかもしれません。
そう考えると、無名性ということにも通じますね。
誰の作品であってもいい。
自らの価値だけが生き残るのです。
ここに芸術の不思議があります。
吾輩は猫である
有名な夏目漱石の小説に『吾輩は猫である』という小説がありますね。
どういう話かご存知の方もいるでしょう。
名前のない猫が主人公です。
自分のことを吾輩と言いながら苦沙弥先生の家に住み着きます。
高等遊民と呼ぱれた美学者の迷亭、理学者の水島寒月、詩人の東風などが、そこに集まるのです。
もともとどうしてこんなものを書こうとしたのか。
有名な高浜虚子という俳人が作っていた「ホトトギス」という本に載せたものです。
漱石はこの頃大変に苦しんでいました。

ロンドンからの留学を終えて帰ってきてから、東京帝国大学で講師をします。
文部省の命令は英文学を学んで来いというものでした。
その間に彼はロンドンのアパートで毎日、本を読み続けました。
夏目は狂ったと言われるほどのノイローゼ状態になって帰ってきたのです。
結局日本人である彼は、どうやったら西洋の哲学や文学や歴史を学べるのかに悩み続けました。
結局それがなかなかできないということがわかったのです。
1904年には日露戦争が始まります。
日本中が沸き立ちました。
苦しみ
本当に苦しくて何もする気が起きなかった漱石に、何か書いてみてはどうかと勧めたのが高浜虚子だったのです。
ふと猫の気分で書いてみたらどうかと考えたのでしょう。
漱石は自分の見てきたもの感じたことを猫の視点に置き換えて書きました。
結局この猫は最後どうなったかご存知ですか。
名前なんかつけてもらえないまま宴会の後の飲み残しのビールを飲み、酔っ払って水瓶に落ちて死んでしまうのです。
面白いといえば面白いですけど、まさに彼の苦しみがそのまま描かれた作品だと言えるかもしれません。
しかしこれが大変なユーモア作品として読まれ、今でも多くの人にそのタイトルだけはよく知られています。
読んだことのある人はどれぐらいいるのでしょうか。
それほど多くないはずです。
中に出てくる人物も寺田寅彦や小宮豊隆などたくさんの弟子たちがいます。

しかしそれを皆分かって読んでる人はほとんどいません。
当時の人たちはそこに漱石山房と言われている、彼の弟子たちの名前と登場人物のイメージはきっちりと重ねていたワケですね。
あの人はこんなことをしているんだ。
漱石のところへ来てこんな馬鹿なことをやっているんだ。
それがまた非常に楽しかったのです。
まさに『ガリバー旅行記』と同じことが漱石の作品の中でも見られるのです。
誰がユーモア小説にしたのか。
それはわかりません。
最初は本当に短い落語の枕のようなものを書くつもりだったのでしょう。
資産家の金田鼻子という妙な女性との結婚話が次々と沸き起こる中で、作品が膨らんでいったのが本当のところだと思います。
月日が作品の真価を変化させます。
実に不思議な力学が働くものです。
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。