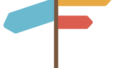不思議な小説
みなさん、こんにちは。
元都立高校国語科教師、すい喬です。
今回は夏目漱石の小説について書かせてください。
漱石と言えば最初に思い浮かぶのが『坊ちゃん』でしょうか。
『吾輩は猫である』『こころ』などもよく知られています。
しかしその他の作品となると、急に声が小さくなってしまいます。
今やこの作家の名前は森鴎外と並んで完全に古典のカテゴリーに分類されるようになりました。
時代はどんどん進んでいますからね。
もう漱石を読むという人も少なくなりつつあります。
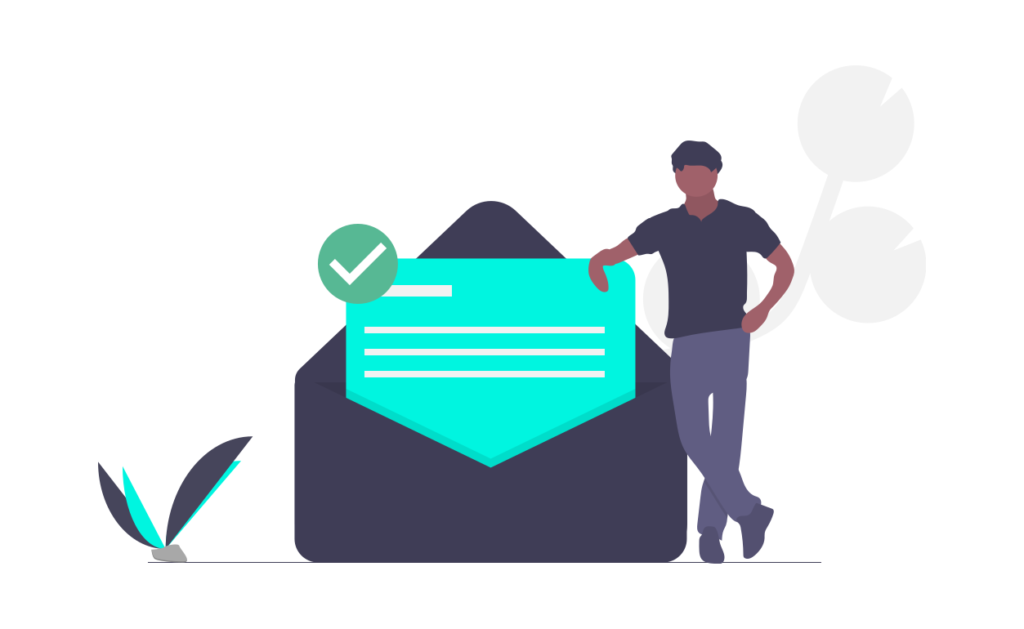
しかし漱石の小説というのは、時々無性に読みたくなるんです。
すごく不思議です。
なぜなんでしょう。
心がとても静かになります。
つい先日も『門』を読みました。
ご存知ですか。
『三四郎』『それから』『門』は3部作と呼ばれています。
登場人物も設定も違いますが、内容が続編のような形になっているのです。
1番若い時が『三四郎』、その次が『それから』の代助、最後が『門』の宗助です。
全く違う登場人物でありながら、次第に年をとり、考え方も変化していきます。
その後を追っていくだけでも味わい深い小説になっています。
ぼくにとって、漱石はリトマス試験紙ですね。
自分が酸性に傾いているのかアルカリ性に寄っているのかを計る装置のような気がします。
この作品を読むことで、軌道が自然に修正されるのです。
門
『門』は何度読んでも趣き深い作品です。
ストーリーが特にあるという訳ではありません。
ある下級官吏の日常が淡々と描いてあるだけです。
『それから』は主人公代助が他人の妻となった女性を取り戻そうとして、往来へ飛び出していくところで終わりました。
しかし『門』はその後に続く作品とはいえ、もっと日常を色濃く反映しています。
宗助と妻のお米は諦念に満ちた暮らしをしています。
大学時代の親友と暮らしていた彼女を奪って遁走し、暮らし始めたものの、子供を流産し、今ではすっかり静かな生活の中にひたりきっています。

しかし弟の小六が書生として世話になることになった坂井という大家のところに偶然、お米の前夫がやってくるという話が届きます。
それを聞いたことで、宗助の神経症がさらに強くなっていくのです。
頭の疲れを少しでも和らげるべく、鎌倉への参禅を試みるというのが、この作品の概略です。
漱石の作品には三角関係がよく登場します。
『こころ』などはその代表的なものでしょう。
人は己に正直に生きていこうとすればするほど、難しい場面に遭遇するものかもしれません。
他者の存在が、自分のこころを照射するという側面をもっているのです。
愛憎が世界を照らすとも言えます。
かつて大学で学んだ自分が、このようにひっそりと市井の中に暮らしているということを主人公は、強く自覚しています。
しかしそのことを大声で話すこともありません。
ところが彼の知的レベルを自然にあぶり出してしまうのが、崖上に住む大家の坂井です。
社交的な坂井は、宗助の中にある鬱屈したものを時にとらえながら、しかしそれを殊更表面に取り出そうとはしません。
やがて大学時代に今の妻、お米を奪った友人との出会いまでセットされそうになり、慌てふためくというあたりも見事に構成されています。
どうしてもそこまでいかなくてはならないように、小説はじりじりとすすんでいきます。
偶然が偶然を呼ぶのです。
その意味で崖上に住む大家の坂井という人の存在が大きいのです。
一方には崖下の借家に住む宗助の借家があります。
この対比も心の内面を象徴しているのでしょう。
円覚寺参禅
この小説のクライマックスは禅寺でのシーンです。
これには多分に漱石自身の経験が色濃く反映しているものと思われます。
彼は友人のすすめでかつて鎌倉の円覚寺へ坐禅を組みに行きました。
今でいう神経衰弱の強度な兆候があったのです。

帰源院という塔頭で坐禅を組み、円覚寺の隠寮で宗演老師と会います。
この時に老師が出した問答はその後、ずっと漱石の頭に残ったようです。
釈宗演老師は漱石に、父母未生以前の本来の面目は何かを見つけよという公案を出しました。
公案とは問答のことです。
質問ですね。
この言葉の意味がわかりますか。
父母の生まれない前のあなた自身を見つけてこいというものです。
まさに禅問答そのものです。
帰源院へ帰った漱石は坐禅を組んで7日くらい経ってから、再び老師に会い、考えを伝えました。
老師は側にそばにあった鈴を振り、「そのようなことは少し大学を出て勉強をすればいえる、もう少し本当のところを見つけていらっしゃい」と軽くいなされてしまいました。
小説『門』には次のような書かれています。
僧侶に言われた言葉が宗助の胸にささるのです。
「法華の凝り固まりが夢中に太鼓を叩くようにやって御覧なさい。頭のてっぺんから足の爪先までがことごとく公案で充実したとき、俄然として新天地が現前するのでございます」
「道は近きにあります。つい鼻の先にあるのですけれども、どうしても気がつきません」
宗助はこの言葉を聞いて悲しくなります。
確かに自分は神経衰弱気味ではあるものの、そこまで盲目的に考えられるような人間ではない。
自分には門を入る資格がなく、門外に佇んで門を仰ぐに過ぎなかったと漱石はその時のことを書いています。
まさに『門』という小説のテーマそのものです。
主人公の宗助と漱石が重なってみえます。
この参禅のシーンは後半のハイライトそのものですね。
この心象風景を描くために彼は『門』を書いたのだと思います。

最後、家に戻った宗助に向かって、春になった喜びを告げるお米が登場します。
その彼女に「うん、しかし又じき冬になるよ」と呟く宗助に救いはありません。
人生にこれといった勝者もなく、また敗者もない。
ただ日常が永遠に続くという漱石のテーゼがここに示されているのです。
不思議なほどに静かで寂しい小説です。
ここに彼の最も素直な側面がよく出ているといってもいいでしょう。
『坊ちゃん』の漱石からは想像もできないような別の人間がそこにはいます。
硝子戸の中
漱石には短編もたくさんあります。
その中でもぼくが好きなのは『硝子戸の中』と『文鳥』です。
なんということもない日常が表現されています。
ああ、漱石という人はこういう風に生活していたんだなということが、とてもよくわかります。
『道草』にも出てくるような話もありますが、大概は他愛もないエッセイの積み重ねです。
読んでいて一番に感じるのは、この作品が全編を通じて末期の眼に彩られているということです。
多くの登場人物の死がここにはごく自然に描写されています。
『文鳥』では飼っていた鳥の死が語られます。

あんな元気な人が自分より先に死ぬはずがないのに、どうして自分はこうやって病気をしながら生きているんだろうといった表現が、あちこちに散りばめられています。
なんということなしに入った床屋の主人が、共通の知り合いを持っていて、そこから話が懐古談に発展します。
かつての寄席や妓楼がごくさりげなく登場します。
あるいは勝手に送りつけてきた色紙に賛を書けと要求する人物や、自分の身の上話を小説にしてくれないかと懇願して帰る女性の話など、大変面白い内容のものもあります。
しかし読んでいて感じるのは、漱石という人が複雑な内面の人だったという印象でしょうか。
妻の夏目鏡子さんが書いた『漱石の思い出』にもかなり気むずかしい夫の一面が描かれています。
つまらない短編を読むのなら、漱石の方がずっと味わい深いです。
末期の眼がこれほど奥まで染み通っているとは、今回読み返してみるまで気がつきませんでした。
是非、ご一読をお勧めします。
最後までお読みいただきありがとうございました。