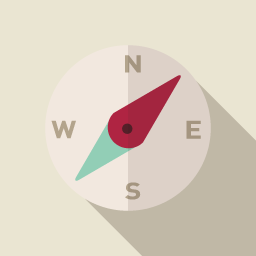内田百閒大好き
みなさん、こんにちは。
元都立高校国語科教師、ブロガーのすい喬です。
今日は大好きな本のお話。
なんとなく嬉しくなります。
みなさんにご紹介できると思うだけで、いい気分になるんです。
作家、川上弘美さんのことはご存知ですか。
なんとなくふわふわとした空気感が好きという人も多いですね。
幻想的な世界と日々の暮らしが渾然一体となった描写は、いわばお家芸のようなもの。
彼女が大好きだという内田百閒(うちだひゃっけん)の影響をとても強く受けています。
知ってますか、内田百閒って。
彼の代表的な小説はなんといっても『阿房列車』です。
でも個人的には『ノラや』が一番好き。

lavnatalia / Pixabay
いなくなった猫のノラを探し続けていい年をした男がさまよう話です。
ノラちゃん、なんで出てきてくれないのと叫びたくなるくらい、ノラのことで頭がいっぱいになります。
そういう世界を書かせたら、第一人者ですね。
あの文豪夏目漱石に通じる高踏派作家です。
わかりますか。
へんな単語ばかりでごめんなさい。
つまり簡単にいえば、世の中のことなんて、どうでもいいという趣味人のことです。
存在そのものが誠にうらやましいな。
考えてみればブロガーも似たようなもんですかね。
暢気にキーボードに向かい、パチパチとやってるんですからね。
まあ、そんなことはいいや。
とにかくその内田百閒さんの影響をもろに受けてます。
受賞歴
1999年『神様』第9回紫式部文学賞、第9回Bunkamuraドゥマゴ文学賞。
2000年『溺レる』で第11回伊藤整文学賞、第39回女流文学賞受賞。
2001年『センセイの鞄』第37回谷崎潤一郎賞受賞
2015年「水声」第66回読売文学賞受賞
2016年『大きな鳥にさらわれないよう』第44回泉鏡花文学賞受賞。
この受賞歴を見ただけでもただものではないということがよくわかると思います。
ぼくは『蛇を踏む』と『センセイの鞄』を読みました。
どちらも実に淡々とした内容で、何か事件が起こるというワケじゃありません。
『センセイの鞄』は中年女性と初老の男性とのなんともいえない恋愛を描いた小説です。
ドラマチックな展開なんてありません。
かつての高校の先生とツキコさんとのたわいない日常が飲み屋さんのカウンターを通して、これという山場もなくずっと展開していきます。
あえていえば、そこに高校時代の同級生が入り、2人の関係が不安定になるところでしょうか。

Capri23auto / Pixabay
それでは普通の恋愛話とどこが違うのか。
この物語には「死」というものがたえず付きまとっています。
40歳と80歳の人間にも、やはりまた春は来る。
しかしそれはいつ消えてしまうかもしれないはかないものです。
結局一緒に暮らしてはみたものの、高齢のセンセイが先に亡くなってしまいます。
しかしその描写も淡々としています。
人間というものはそれほど特別なものではなく、ごくありふれた生き物に過ぎないということをこれでもかというくらい、美しくさりげない日本語で描写しています。
食事の風景も執拗に繰り返されます。
人間は結局食べて寝るというだけの存在なのかもしれません。
この小説の気分に一番近いのが、実は彼女のデビュー作『神様』なのです。
教科書ではじめて読む
1994年、短編集『神様』で彼女はパスカル短篇文学新人賞を受賞しました。
これが作家になるきっかけでした。
パソコン通信で応募選考を行う文学賞だったと聞くだけで、隔世の感がありますね。
審査員だった筒井康隆と井上ひさしが絶賛しました。
子供がテーブルのそばに寄ってきてどうしようもない中、2時間ほどで書いたのです。
最初の短編「神様」でした。
書けるかなと思って書き出したら、次々と言葉があふれ出てきて止まらなかったそうです。
これは川上弘美ファンにとって、今や大切な伝説になっています。
まさか連載なんてと思っていたら、「マリ・クレール」がシリーズ化してくれたとか。
全体は9つの短編でできています。
ぼくがこの作品に触れたのは10年前くらいのこと。
どうして知ったのかといえば、教科書に載っていたからです。
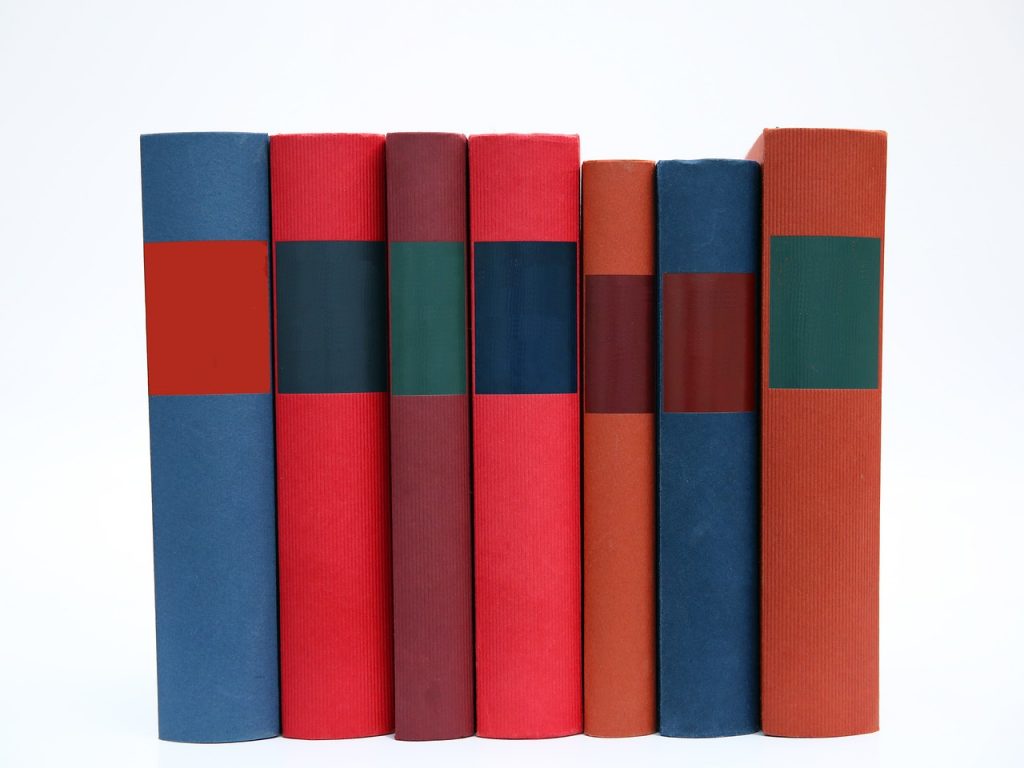
Hermann / Pixabay
それまでに読んでいたのは、先ほどあげた2冊だけです。
だいたい「神様」なんて随分ばかにしたタイトルじゃありませんか。
最近の高校では長い小説の間に、こうした短編を挟む傾向があります。
あまり長いと授業で取り扱えないということなんでしょうか。
とにかく使えるかどうか考えながら読みました。
大切なのは、生徒が食いついてくるか。
後で試験が作りやすいかということです。
読んでみて驚きました。
熊が人間と散歩にでかける話なんです。
あまりにも唐突でした。
書き出しはこうです。
川原に行くのである。
だいたい「である」を小説の文末にもってくるのは難しいのです。
文体が硬くなりがちです。
しかしそんな危惧はムダでした。
むしろいい味わいを出しています。
律儀な熊は雄の成熟した熊で、3つ隣の305号室に最近引っ越してきたばかり。
近頃の引っ越しには珍しく、引っ越し蕎麦を同じ階の住人に配ります。
なぜそんなことをしたのか。
くまだからというのが答えです。
つまりいろいろとまわりに対する配慮が必要だというワケです。
このくまが実にかわいい。
川原までアスファルトの道をてくてく歩いていると「もしあなたが暑いのなら、国道に出てレストハウスにでも寄りますか」と気を遣ってくれます。
また道であった子供が「お父さん、くまだよ」と叫ぶと「小さい人は邪気がないですなあ」などと呟く。
ところが突然くまは水の中にじゃぶじゃぶと入り、魚を掴みあげます。

cuncon / Pixabay
「さしあげましょう、今日の記念に」というわけで、小さなナイフとまな板を器用に使い、魚を開いて粗塩をかけます。
何から何まで行き届いたくまなのです。
ちょっとお昼寝の後、帰りに「抱擁を交わしていただけますか」と305号室の部屋の前で言います。
わたしはもちろん承知します。
「今日は本当に楽しい1日でした。熊の神様のお恵みがあなたの上にも降り注ぎますように」といって部屋に戻ります。
悪くない1日だったという文章で、この作品は終わるのです。
どうでしょうか。
童話テイストですが、明らかに童話じゃない。
それぞれの短編には熊、梨喰い虫、叔父の幽霊、河童、魔法のランプ中の霊、人魚などが次々と登場します。
しかし不思議なことに人間との境目はありません。
それぞれが人間の言葉を話す。
意思疎通ができるのです。
「河童玉」の中にでてくる河童の悩みも面白いです。
アラジンの魔法のランプから顔を出す回文のような名前のコスミスミコ。
「星の光は昔の光」では父親が浮気をしている家庭の男の子が大人の世界を覗きみたという設定になっています。
「離さない」は捕まえた人魚の話です。
実はこれも教科書に載っているのだとか。
ぼくが使ったものにはなぜかありませんでした。
この人魚も不思議な味わいを持っています。
さらに最後の「草上の昼食」では再びくまと散歩をします。
読んでいると不思議な透明感に満たされ、癒やされるのを感じます。
神様2011
実は「神様」には後日談があります。
というのもこのタイトルを見ておわかりの通り、川上弘美は福島の原発事故の後、「神様」を一部手直しし、「神様2011」を発表しました。
この2つの作品だけを収録した本も出版されています。
どこが違うのか。
以前勤めていた学校の図書館にあり、詳しく調べたことがあります。
ほとんど変わっていません。
ただところどころに付け足した記述があります。
例えば、外出時にふたりは防護服を着て出かけます。
川原までの道が元水田になっています。
別れ際にはガイガーカウンターで体表の放射線量を測定したりもします。
ただし終わり方は前の作品とおんなじ。
悪くない1日だったという記述があります。

cherylholt / Pixabay
この小説をそのまま教科書に載せた会社もあったそうです。
随分とつまらない作品になってしまったなというのが率直な感想です。
彼女のことです。
わざとそう書いたのでしょう。
それが何を意味するのか考えて欲しかったに違いありません。
長くなりました。
ここいらでそろそろ終わります。
彼女のデビュー作の味わいはやはり、原発事故以前のくまさんの散歩でなくちゃいけませんね。
どうぞ一度は手にとって読んでみてください。
夢の話ですかと言われれば、そうともいえます。
フロイトの深層心理と関係がありますかと聞かれれば、そうかもしれませんと答えます。
しかし正解は多分ないのでしょう。
要はそこに寂しい人がいて、日常があるということです。
一度読んでみてください。
きっとやさしい気持ちになれますよ。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。