日本人だけなのか
みなさん、こんにちは。
元都立高校国語科教師、すい喬です。
今回は「空気を読む」という表現について考えます。
実にユニークな言い回しですね。
日本人はよく使います。
しばらく日本にいた外国人なら、何度も耳にしたことがあるはずです。
短縮語は「KY」です。
しかし旅行者には、なんのことか理解できないでしょう。
それくらい謎に満ちた表現だといえます。
日本人はどのような場合でも、周囲の様子をそれとなく観察し、その場でどのような会話やリアクションをすればいいのかを瞬時に判断します。
それができないと、生きていけないからです。

集団で集まる場合、自分がどの位置に座ればいいのかを常に気にします。
宴席においても「上座」から「下座」まで、どこに位置を占めるのかを瞬時に判断しなければなりません。
機転がきくというようなレベルではないのです。
それが生き残るための最低限の知恵といえるかもしれません。
外国にも全くそういうことがないのかといえば、そんなことはないはずです。
ただし日本ほど重点をおくケースは少ないでしょうね。
難しくいえば、「暗黙知」です。
口には出さなくても、それくらいはわかるだろうというレベルの常識です。
個人主義の発達した国ではみられない構図かもしれません。
個人主義の社会では
相手が理解できないなら、説明すればいいのです。
しかしそれを日本人はあえてしません。
手間のかかるくどい作業になってしまうからです。
相手がもし理解できない時はどうなるのでしょうか。
個人主義の社会では個性が強く求められます。
つねに自分の意見を述べなければなりません。
自分の考え方と著しく違っても、それは個人の問題になります。
相手が理解しなくても、あるいは理解できないとしても、それは空気が読めないからではありません。
個人の意見なのですから、当然尊重されるのです。
空気を読むのが必要な社会の背景には、暗黙のルールがたくさんあります。
狭い島国で国民のほとんどが同じ民族であるという要因が大きいことは、容易に想像できます。

いくつもの宗教や民族が陸続きの土地で暮らしている場合を考えてみてくだい。
いちいち相手の空気を読んで暮らしていたら、何も先に進まないという現実が実感できるはずです。
次の文章は、研究者として日本で長く生活をしているマリ共和国出身の空間人類学者、ウスビ・サコ氏のものです。
日本人の生活についてまとめたエッセイです。
「空気を読む」ということに対する彼の文章を読んで、あなたの考えをまとめてみてください。
異文化理解のための参考になると考えます。
課題文
どの地域や社会にも、共同体の構成員が共有する一定の決められたルール、慣習やしきたり、つまり「生活のコード」があります。
共同体の中で円滑に生活しようと思うならば、それらの共同体のコードを身につける必要があります。
特に、言葉を介さずに交わされる非言語的なコミュニケーションや、相手に期待する反応を求めることなどが挙げられ、これらのコードの活用こそが、いわゆる「空気を読む」ことと言われています。
コードの活用には、感覚的に「その集団の決まりごと」を読み取る努力が必要となります。
私自身も、様々な集団と接する中で、常にその集団の独特な生活習慣を理解する努力をしてきました。
私は世界中を旅し、いくつかの国や民族の言葉を話すことができますが、日本ほど生活習慣の理解に苦労した国や文化はありません。
日本の社会や文化圏の外で生まれ育った私のような人間にとって、日本の「空気を読む」ことは、非常に難しいことでした。
例えば、日本の家を訪ねるとき、家の中へ誘われる言葉として、「上がってください」と言われ、さらにドアが外側へと開きます。
これは、何か上方向に移動するのではなく、「入ってください」ということなのだと分かります。
また、京都の「町屋」のような伝統的な日本家屋に行くと、一定の土間までは靴のままで入ることができ、ある境界を超えたときに靴を脱ぐことが許されます。
このような経験は日本に来てから無数にありました。
日本の生活文化や家屋の構成がわかる人には、「上がって」と言われることや、靴を脱ぐべき境界の認識に対して違和感はないはずです。
このような経験を重ねながら日本で長く生活をしていると、「空気を読む」ことはより複雑で奥深い意味を持つことが少しずつ見えてきます。
「空気を読む」ことは言語的な体験だけではなく、日本で生活する人々の行動パターンを理解し、表現することなのです。

それゆえ、「空気を読む」ことを理解するためには、かなり高度な日本社会や文化への理解が必要になると思います。
一方で、「空気を読む」、「相手にはっきり意見を言わない」、「否定的な意思を見せない」など、日本では協調性と考えられている行動様式には、今でもときどき疑問を覚えてしまいます。
日本に住んでいる多くの外国人はこれらのコードをシェアしていないと考えられるため、多様性が重んじられるこの時代においては、同調的に他者と合わせることを強制し、同化させるのは難しいでしょう。
これからの日本社会は、多様性の中で、いかに相手の立場に立って物事を考えるか、いかにその違いを認めるのか、時には配慮することが重要になってくると思います。
(ウスビ・サコ「ニッポンの空気と空間利用」)
ホンネとタテマエ
日本人を理解する時、いちばん大切なのがこの2つの考え方ではないでしょうか。
これが瞬時に読み取れれば、観察力の鋭い人物として一目置かれますね。
まさに「空気を読む」ということの基本になる発想です。
ではどうやって判断すればいいのか。
ポイントは言葉よりもむしろ「しぐさ」にあります。
「視線」「姿勢」「動作」に着目することです。
基本は口に出す言葉ではなく、その背景に存在します。
非言語情報が真実を多く語っているのです。
日本人は言葉に重きを置かない民族なのでしょうか。

そうだとすると、あまりにも悲しい気がします。
一種の「腹芸」と呼ばれるものに重きをおく傾向は他の民族より強いのでしょうね。
表に出た時はすでに決定済みなことが多いのです。
「根回し」と呼ばれる外に出ない裏のコミュニケーションが大切です。
そのためには「しぐさ」に表われるサインを読み取ることで、相手のことをもっと理解しやすくなります。
ここまで非言語コミュニケーションから本音と建前を見抜く方法を考えました。
それでも空気が読めない人はどうすればいいのか。
いわゆる「KY」と呼ばれるタイプの人間です。
場の空気が読めないことは明らかにマイナスですね。
ネガティブなこととして捉えられ、人間関係において厄介な問題となります。
仲間はずれ
空気が読めないと、明らかに距離を置かれることが増えます。
子どもの場合より、大人の人間関係の方がより深刻です。
さまざまな感情をうまく包み込んで、外にあらわさない技術にたけています。
それだけに空気を読むのは難しいのです。
必要なポイントは「距離感」でしょう。
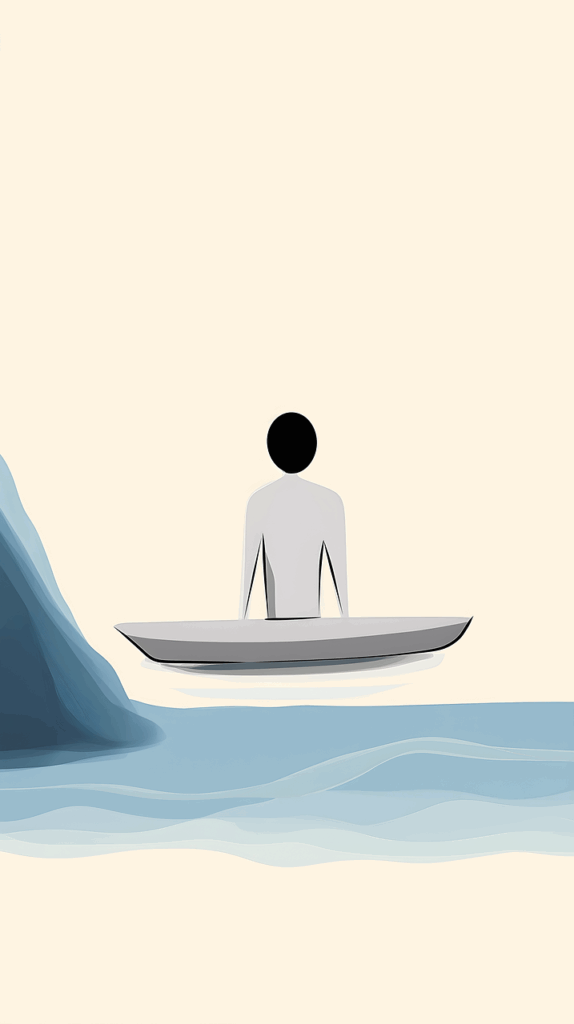
特に会話の中で沈黙と話しかけるタイミングの「間」がとても難しいです。
最も大切なのは「聞く力」でしょうね。
自分から発信することは誰にでもできます。
しかし相手が話している間、適当な相槌を打ちながら親身になって聞くという態度は、相手との関係を潤滑にする要素に満ちています。
皮膚感覚で相手との距離感をつねに測りながら、それをごく自然に態度に出す。
話を聞いてくれる人に、人は好意を抱くものです。
それだけでも十分に「空気を読む」ことにつながるのではないでしょうか。
ポイントは1つの考え方に対して自分の意志をどうあらわすか。
ここが最も難しいのです。
「空気を読む」は日本を理解するときのキーワードです。
これからも考察を続けてください。
今回も最後までお付き合いくださり、ありがとうございました。


