虚栄と愛欲
みなさん、こんにちは。
元都立高校国語科教師、すい喬です。
今回は今、話題の『源氏物語』について語ることにしましょう。
須磨の段です。
昔から源氏の「須磨帰り」と呼ぶ章段なのです。
御存知ですか。
この段あたりまでくると、『源氏物語』を読むのにくたびれてきます。
読むのを諦める人が多くなる頃なのです。
登場人物が増え、内容も複雑になります。
12巻目の「須磨」、13巻目「明石」まではなんとか頑張って読もうとします。
しかしここで挫折してしまい、放り出すのです。
そのうちにストーリー忘れてしまい、また最初からということになります。
やがて再び1巻目の「桐壺」に戻るというワケです。
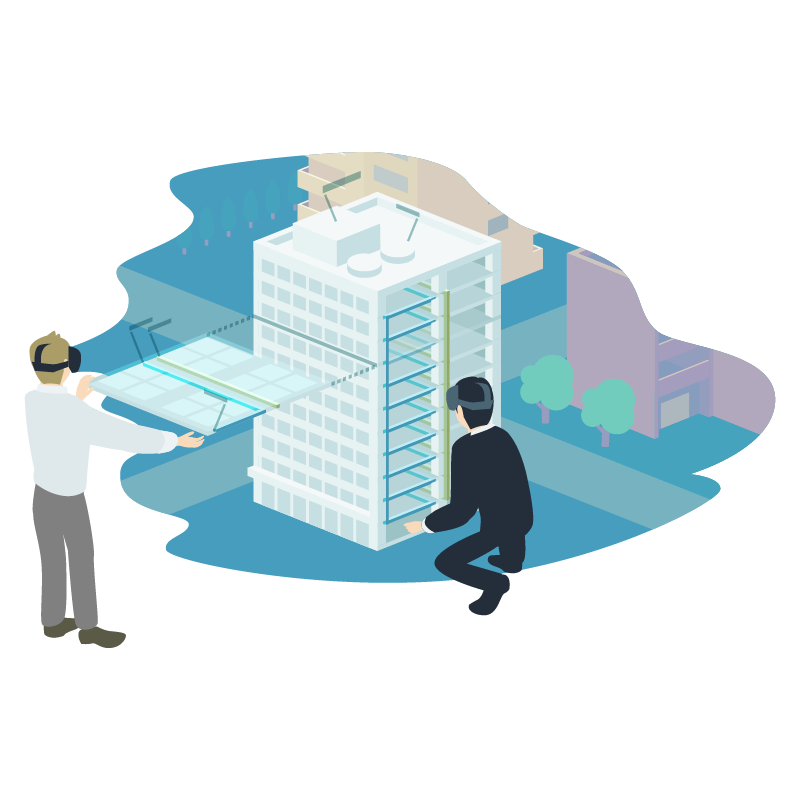
そこからついた名前が「源氏の須磨帰り」です。
ちょうど、一服するのに好都合だったのでしょう。
内容的にも、今までの華やかさから、一転して少し情景も寂しくなります。
季節も秋からのものなので、背景の色合いも落ち着いてくるのです。
それだけに、読書の疲れが滲んでくるのかもしれません。
しかしここで英気を養った源氏は、みごとに復活します。
少し大人になるといった方がいいのです。
たくましい男性に成長し、人生の難問を抱えることになります。
須磨の段を少しみていきましょう。
不思議な作品
『源氏物語』というのは本当に不思議な作品ですね。
これだけ多くの人を惹きつける理由は何なのでしょうか。
紫式部はよくこれだけ複雑な話をつくりあげたものだ、と感心してしまいます。
1人の人間の中に描きこみたかった思いとは、どのようなものであったのか。
やはり「虚栄と愛欲」なのでしょうか。
人間というものがもっているどうしようもない性質を、彼女は底まで見抜いていたのかもしれません。
そこに人間という生き物の面白みも感じたでしょう。
しかし同時に哀しみを抱いたと思われます。
千年前にこういうスケールの大きな物語を書いた女性がいるということに、あらためて驚かされますね。
次々と展開していく世界に入り込んでしまうと、目の前の現実がどこか薄く刺激のないものに思われてなりません。
今年はテレビで紫式部の生涯が描かれるということもあり、多くの人がこの作品を手にするはずです。

物語のストーリーだけでなく、彼女の持っていた資質にも注目して欲しいのです。
どのようにして独特の人間観を育てていったのか。
その芯の部分が見えないと、十分に作品世界に没入できないような気もします。
須磨の段は特に憂愁の深い、味わいのあるところです。
光源氏の父、桐壷院が亡くなったのは彼が23才の年でした。
その後、時の権威は朱雀帝の外戚である右大臣方に移ったのです。
翌年、源氏が複雑な思いを寄せた藤壺中宮は29才の若さで出家してしまいました。
前々から光源氏のことを快く思っていなかった右大臣や弘徽殿の大后は、光源氏を失脚させようと画策を始めます。
そこで光源氏は、自ら須磨に退去することを決意したのです。
春、最愛の妻紫の上を都に残して、僅かな従者を連れて旅立ちました。
光源氏26才、紫上18才、藤壺中宮31才の時のことです。
原文は大変長いので、冒頭の部分だけ掲載します。
本文
須磨には、いとど心づくしの秋風に、海は少し遠けれど、行平の中納言の、関吹き越ゆると言いけむ浦波、よるよるは、いと近くに聞こえて、またなくあはれなるものは、かかる所の秋なりけり。
御前にいと人少なにて、うち休みわたれるに、一人目を覚まして、枕をそばだてて四方の嵐を聞き給ふに、波ただここもとに立ち来る心地して、涙落つともおぼえぬに、枕浮くばかりになりにけり。
琴を少しかき鳴らし給へるが、我ながらいとすごう聞こゆれば、弾きさし給ひて、
恋ひわびて泣く音にまがふ浦波は思ふ方より風や吹くらむ
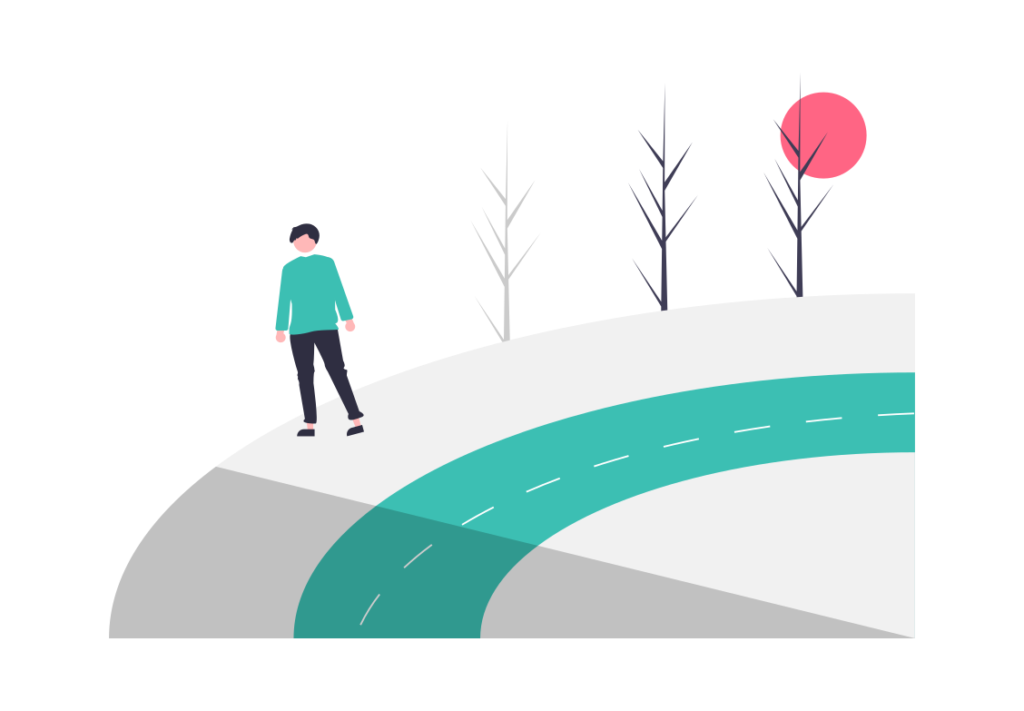
とうたひ給へるに、人々おどろきて、めでたうおぼゆるに、忍ばれで、あいなう起きゐつつ、鼻を忍びやかにかみわたす。
「げにいかに思ふらむ、わが身一つにより、親はらから、かた時たち離れがたく、ほどにつけつつ思ふらむ家を別れて、かく惑ひ合へる。」
とおぼすに、いみじくて、いとかく思ひ沈むさまを、心細しと思ふらむとおぼせば、昼は何くれとたはぶれごとうちのたまひ紛らはし、つれづれなるままに、いろいろの紙を継ぎつつ手習ひをし給ひ、
めづらしきさまなる唐の綾などにさまざまの絵どもを書きすさび給へる、屏風のおもてどもなど、いとめでたく、見どころあり。
人々の語り聞こえし海山のありさまを、はるかにおぼしやりしを、御目に近くては、げに及ばぬ磯のたたずまひ、二なく書き集め給へり。
「このころの上手にすめる千枝、常則などを召して、作り絵つかうまつらせばや。」と心もとながり合へり。
なつかしうめでたき御さまに、世のもの思ひ忘れて、近う慣れつかうまつるをうれしきことにて、四、五人ばかりぞつと候ひける。
現代語訳
須磨では、ひとしおさまざまにもの思いをさそう秋風が吹いていました。
源氏の住まいは波は少し離れていますけれども、行平の中納言が、「関吹き越えるゆる」とよんだという浦波の打ち寄せる音が、毎夜、本当にすぐ近くに聞こえて、またとなくしみじみとするのは、このような所の秋なのです。
源氏のおそばには、お仕えする人が少なくて、みな寝静まっているのに、源氏は一人目を覚まして、枕から頭を上げて四方の激しい風の音をお聞きになっていました。
すると、波がすぐ枕もとに打ち寄せてくるような心地がして、涙がこぼれるのにも気づかないうちに、枕が浮くくらいになってしまったのです。
琴を少しかき鳴らしなさいましたが、我ながらたいへんものさびしく聞こえます。
私が恋しさに堪えかねて泣く声に浦波がにているのは、私が恋しく思っている都の方から風が吹いてくるからであろうか。
と歌を詠まれると、寝ていた人々が目を覚まして、すばらしいと思うにつけ、悲しさをこらえきれず、むやみに起き出しては、鼻をそっとかんでいるのです。
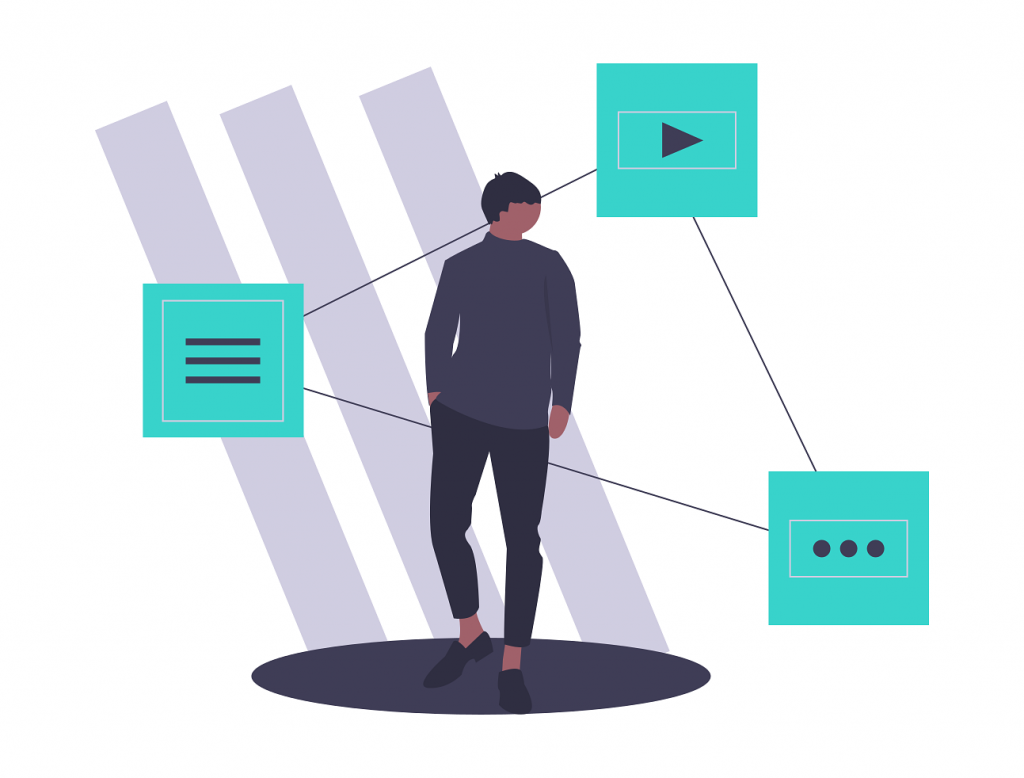
「本当に、彼らはどう思っているのだろう、私一人のために、親兄弟とも離れにくく、それぞれに境遇に応じて思っているだろう家から遠く離れて、このようにさすらってしまっているのだ。」
とお思いになると、気の毒でたまらないのです。
「このように自分が思い沈んでいる様子を見せたら、心細いと思ってしまうだろう。」
とお思いになります。
そこで昼は、あれこれと冗談をおっしゃって気を紛らわし、所在ないままに、さまざまな色の紙を継いでは歌をお書きになるのです。
珍しい様子の唐の綾織物などにはさまざまな絵などを興にまかせて描いていらっしゃいます。
屏風の表の絵などは、実にすばらしく見事なものでした。
人々がお話した海山の様子を、はるかに想像していらっしゃっていたのを、今は目の当たりに御覧になって、想像もできないほどすばらしい磯の景色を、このうえなく上手にお描き集めなさっています。
「このごろ世間で名人といっているらしい千枝、常則などを召して、墨書きの絵に彩色させ申し上げたいものだ」と歯がゆく思いあっています。
源氏のご様子に、お仕えしている人々は世の辛さも忘れて、おそば近くにいられることがうれしく、四、五人ほどがいつも近侍しているのでした。
なぜ須磨なのか
都から遠く離れた地で、光源氏はどのような思いで暮らしたのでしょうか。
紫式部はなぜ、この地を選んだのか。
不思議ですね。
源氏物語では、この地で光源氏と明石の君が結ばれます。
そして新たな命を宿すのです。
やがて源氏は都へ返り咲き、ひたすら出世街道を駆け上がっていくことになります。
この地を選んだ理由はいくつか考えられます。
須磨の地名の由来は「畿内の西の隅」という意味です。
つまり「スミ」が「スマ」になりました。
光源氏は畿内の果てまで辿り着いたというワケです。

もう1つ、この主人公のモデルの1人と言われている在原行平(業平の異母兄)が蟄居した土地が須磨だったのです。
彼は中央の要職を歴任し、最後には太宰権師にもなりました。
しかし文徳天皇の時に、関係が悪くなり、須磨に引きこもったと言われています。
これが1番西の境にまで、光源氏を配置し、そこからの復活をめざすストーリーが、生まれた背景なのです。
貴種流離という言葉がありますね。
尊い人は必ず流されて、遠い場所へ追放されるという日本人の世界観です。
その背景として、海に近い須磨の浜の波の音も、源氏の世界を作り上げるのに一役買ったのでしょう。
ぜひ、この機会に作品に触れてみてください。
描かれている世界の大きさに驚かされるはずです。
今回も最後でお付き合いいただき、ありがとうございました。


