懐疑を乗り越える
みなさん、こんにちは。
元都立高校国語科教師、すい喬です。
今回は哲学的な問いを扱います。
「懐疑」というのは非常に難しい考え方です。
どこまで徹底して追求すれば、真理につきあたるのかということだからです。
デカルトの「コギト」という言葉を聞いたことがありますか。
Cogito ergo sumです。
ラテン語です。
「コギト・エルゴ・スム」と発音します。
「我思う故に我あり」という表現の訳で、多くの人に知られている哲学の大原則です。
自分がいるのかいないのか証明する方法はよくわからないけれど、今その事実を考えている自分の存在は確かにここにあるという論理です。
そこだけを唯一の原点にして、あらゆる事象を考えていこうとする姿勢なのです。
埴谷雄高の小説などを読んでいると、ほとんどすべての内容が、このコギトに絡んでいることがよくわかります。
「自同律の不快」などという表現を知っているでしょうか。
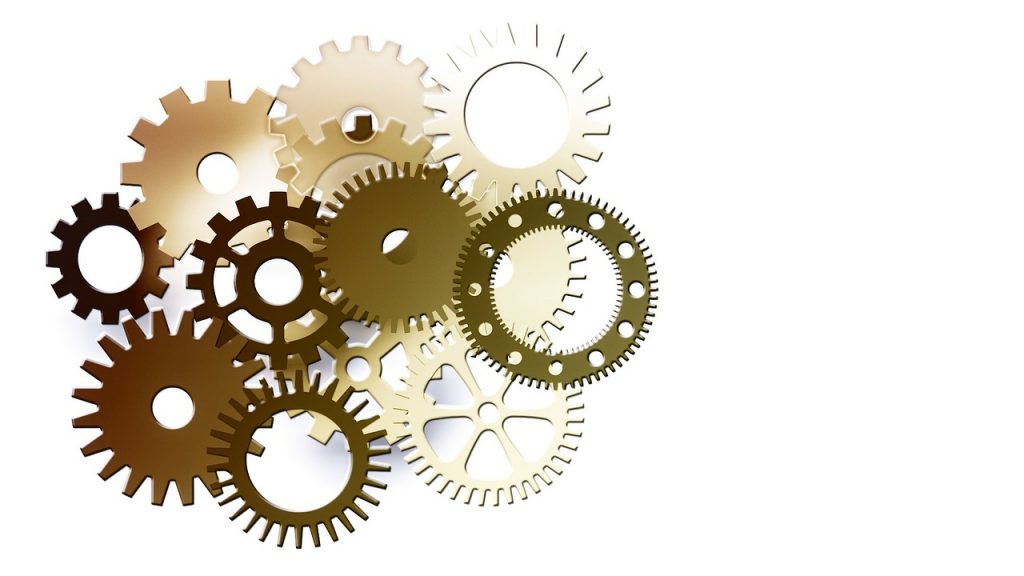
「AがAである」という事象ほど、確認の難しい作業はありません。
確かに、なんでも疑い始めてしまうと、どこが最終地点なのかわからなくなりますね。
自分に見えている風景が、他の人にも同じように見えているという「信頼」がなければ、会話などは成立しないのかもしれないのです。
しかし実際に同じ風景を絵に描いてみたら、印象が全く違っていたりすることに愕然とします。
厳密にいえば、人は同じ風景を見ているワケではないのかもしれません。
そう言い出すと、この世の中に確実なものはなにもないとも言えます。
哲学はそうした曖昧なものの輪郭を、少しでも明確にしていく作業です。
課題文は社会学者、橋爪大三郎氏の著書『「心」はあるのか』から取りました。
この文章を読んで考えたことを800字以内で書きなさいというのが、今回の設問です。
人は何を信じていけばいいのかという、ある意味で究極のテーマかもしれません。
本文
懐疑とは何か
懐疑とは、ものを疑うことである。
ものを疑うためには、これは確実だろうかと疑問文を発することができ、その疑問文の内容を理解し、今これを疑っているという意識が持続しなくてはならない。
疑問文の意味すら理解できない人には、そもそも懐疑は実行できない。
疑問文を理解しているということは、言葉のシステムを信頼しているということですね。
言葉のシステムを信頼しつつ、疑問文を発しながら、この世の全ては疑わしいなどと言うのは間違っている、と書いているんです。
とても正しい、と私は思うんですけれども、みなさんはどう思いますか。
このように考えると『哲学探究』は、確かにさまざまな懐疑によって占められ、全ての常識が覆されていくような印象を読者に与えますけれども、単なる懐疑論、相対主義の本ではない。
彼にとって何が確実なのか、何が一番本質的なのかを突きとめようして書かれた、「信頼」のための本ではないだろうか。

こうした懐疑の試練をくぐり抜けると、他の人間は存在しないかもしれないとか、自分だけが赤い色を見ているのではないかとか、そういう奇妙なことを考えてもかまわないと、自分を許せるようになってきます。
同時に、自分が自分であるなら、相手も自分を自分と思っている。
相手も自分と同じように権利をもっていると、心底から承認できるようになります。
互いを認め合うわけです。
そういうたくさんのかけがえのない「自分」がいるのが社会です。
懐疑をつきつめる
懐疑を徹底して行うとどうなるのでしょうか。
1万円札をただの紙だといってしまった途端、そこから戻ってこられなくなってしまうのです。
つまり究極の迷路の中に入り込んだ状態になるのです。
あらゆる道徳も信じられなくなり、どう行動をしても許されるのではないかという気持ちになります。
アルベール・カミュの『異邦人』などはまさにそうですね。
突然太陽がまぶしいといって、前を歩いていた男をピストルで撃ってしまいます。
通常、人間の行動には、動機と呼ばれるものがあります。
人をピストルで撃ち殺すには、強い殺意が必要なのです。
しかしそれもなく、ただ太陽がまぶしかったからという理由で、殺人を犯すことになると、日常生活は全く送れなくなります。
性格異常などというレッテルをはることで、あたりまえの人々は一安心します。
しかしだからといって、究極の問題が解決したワケではありません。
そこにはより哲学的な命題が横たわっているのです。
安部公房が好んで描いたのも、こうした世界です。
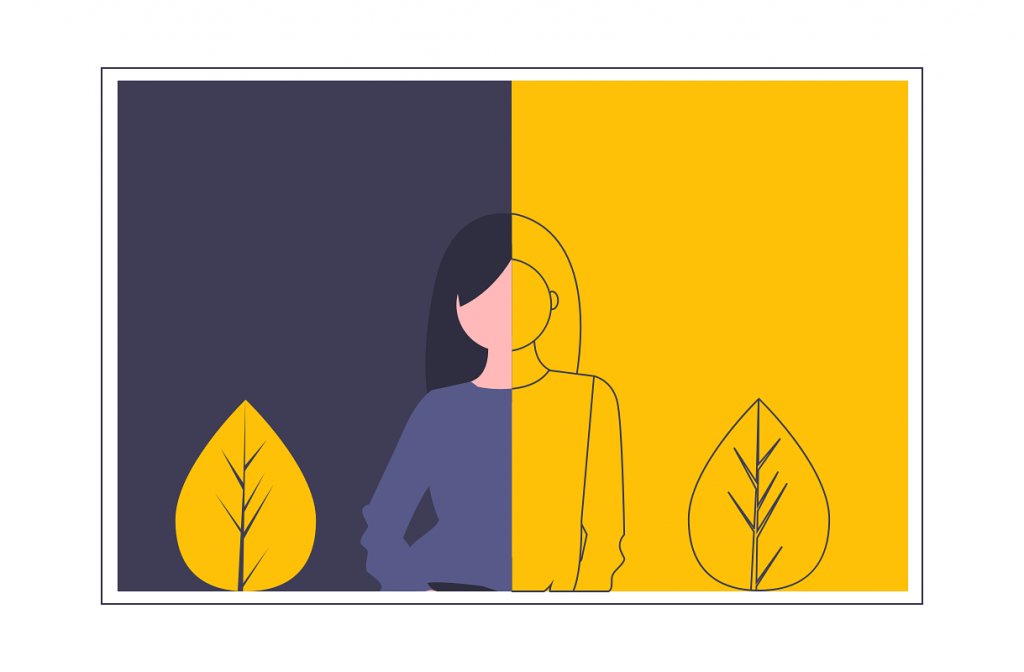
『砂の女』という作品を読めば、そのことがよくわかります。
なぜ砂丘の中に家をたて、そこで暮らしているのかも、特に明らかにはされません。
そこへ迷い込んだ男との暮らしには、人間の原型が仄見えるのです。
最初はそこから逃げようと画策した男も、やがてその日常に取り込まれていきます。
懐疑を繰り返しているうちに、それがどこか甘い日常の風景になっていくという、実に不条理な小説です。
あらゆるものは確かに懐疑の対象になりうるのです。
それをしようとする意志さえあれば。
ただし、その後にあらわれる形がどのようなものであるのかについては、誰も結論を持ちえません。
ただそこに原型として横たわっているだけです。
無数の自分
それぞれの人間が確かに自分の場所を手にしています。
それこそがかけがえのないものだと認識しているはずです。
しかし本当にそれは信頼するに足るものであるのか。
それも本当のところは、よくわからないのです。
しかしたくさんの異なった価値を持つ、たくさんの人間が存在していることは間違いがありません。
それぞれの人が、それぞれの人生を送っています。
その事実は重いものです。
だとしたら、自分はどのように他者を認識すればいいのでしょうか。
目の前にいる人間も、自分なのだという基本的なスタンスをとる以外に道はないはずです。
ますます相互の「信頼」が大切な要素になりますね。

そういう関わりの中での1つの存在として、他の人間を認め合うということ以外に、何ができるのでしょうか。
結局、自分の外にいる人間も、もう1人の「自分」でしかないのです。
その事実を厳粛に受け止める以外に、有効な方法はありません。
あなたなら、ここから結論をどこへ導きますか。
人生というゲームの中で、自分の陣地は同時に他者の陣地にもなりうるという事実を重く受け止めなければいけません。
信頼という名の「覚悟」を明確に述べることには、大きな意味があります。
それこそが取り換えの効かない、厳粛な「個性」の発現なのではないでしょうか。
確かに、この話はどこまでいっても堂々巡りの様相をもっています。
しかしその現実を受け入れない限り、「懐疑」というテーマの結論には至らないのではないかと感じます。
複雑な問題です。
しかし考えるに足るアジェンダであることは間違いありません。
今回も最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。


