他者との距離感
みなさん、こんにちは。
元都立高校国語科教師、すい喬です。
今回は他者との距離感について考えます。

あなたは「ヤマアラシのジレンマ」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。
鋭い針毛を持つヤマアラシは、互いに寄り添い合おうとすると、自分の針毛で相手を傷つけてしまうため、容易には近づけません。
親しくなりたいのになかなか近くに寄れないのです。
そこにジレンマがあります。
他者との距離感をどうとるのかというのが、ヤマアラシにとっては最大の悩みなのです。
相手に好意を持って近づくと、それがかえって相手を傷つけてしまうという逆説。
これと同じことが人間にも言えますね。
複雑な社会の中で、自分の立地点をどうみつけるのかというのが最も厄介なテーマなのです。
他者との距離感を測るのは難しいです。
今の時代、人間関係を上手に切り拓いていくことが、最も大切なことはいうまでもありません。
近年、「コミュ力」という表現をよく耳にするようになりました。
他者との間でコミュニケーションを上手にとれる人は、それだけで羨望の対象になります。
人間にとって、もっとも悩ましいのが他者との距離をどうとるのかという問題なのではないでしょうか。
他者との円滑な関係さえうまくキープできれば、学校でも職場でもトラブルなく生きていけるに違いありません。
それだけにこれは最も根本的なテーマだといえます。
たまたま、ある大学の入試小論文を読んでいたとき、ふさわしい内容のものに出会いました。
日本の茶室の佇まいについてまとめられたものがそれです。
この文章は日本の文化における人間同士の距離感が、日常生活と非日常の空間でどのように巧みに利用されてきたかを論じています。
特に、わずかな空間の中で五感を研ぎ澄ませ、非日常の安らぎを得る茶室の構造と機能に焦点を当てている点が出色です。
課題文
日本では人と人との距離による効果を、日常・非日常の空間に巧みに取り入れることで独特な文化を育んできた。
例えば小間と呼ばれる四畳半以下の茶室がそれにあたる。
中でも利休が作ったとされる京都の待庵などは、わずか二畳のとても狭い空間である。
なぜ茶室を極端に小さく作る必要があるのかと疑問に感じるが、座った際の五感の働きを加味すると小間の茶室の魅力が見えてくる。
茶室の位置、亭主と客の座る場所はあらかじめ定まっている。
相手の上半身が認識できて、顔の表情が強調されるが、密接距離のようにゆがんで見えるような圧迫はない。
床の間は視線の置きどころとなり、飾る花や書画などによっては小さな空間から大きな世界を想像することができる。
このような視覚的効果に加え、四方の壁が迫ることで遮断された空間であることを肌で感じる。
時には外から鳥の鳴き声や葉擦れの音が聞こえるかもしれない。
しかし壁の外の世界は耳や気配で感じることはできるが、目には見えない。
茶を味わいながら研ぎ澄まされた五感は体の中で一つになっていく。

茶室でのくつろぎは日常を逸脱したものであり、いわゆるリラックスとは違う。
今、この時にお互いの存在を感じ、共に生きている喜びを実感することなのだ。
たしかに茶室は清浄な環境と節度ある距離を保つという意味で、平穏な世を象徴している。
小間の茶室のにじり口と呼ばれる小さな入り口は、腰を曲げないと潜って入ることができない。
それはあえて刀を持ち込めない寸法に設計されているからで、憂世を離れ、敵味方であっても武器を捨て茶室の中では平等に茶を喫する。
香で空気を清め、新品の木地桶に入れた水を用いて茶を点てる。
平和な距離とは、些細な日常の動作や文化に育まれ人間の体や心に宿りながら、おのずと広がっていくのが理想ではないだろうか。
節度ある空間
筆者の桐谷美香さんは現代美術の世界で活躍されている造形作家です。
彼女にとって、極端に小さく作られた茶室の持つ意味はなんであったのか。
ここには日本の伝統文化に見られるような「節度ある距離」を保つことの安逸が示されています。
茶室はあまりにも狭い空間です。
その中で長時間、対座を強いられるのです。
一般的には圧倒的な息苦しさを連想してしまいがちですね。
しかし彼女はそれを否定しています。
むしろ心地良さを感じるのだと述べています。
なぜでしょうか。
亭主と客の座る場所の距離感が守られているからです。
圧迫感が全くないとはいうものの、相手の上半身が認識でき、顔の表情が強調される距離だというのです。

さらに、床の間を視線の置きどころとすると、小さな空間から大きな世界を想像することもできます。
このような環境で研ぎ澄まされた五感が、身体の中で一つになるというのです。
日常を逸脱し、互いの存在を感じ、共に生きている喜びを実感することの意味がそこにはあります。
また距離の取り方を「平等と清浄」の観点から確立することも大切だと主張しています。
茶室の躙口(にじりぐち)は、あえて刀を持ち込めない寸法に設計されており、敵味方であっても武器を捨て、茶室の中では平等に茶を喫することが大切です。
これは憂世を離れるための空間であり、清浄な環境と節度ある距離を保つことで、平穏な世を象徴しているというのが論点の中心です。
この論拠に対してあなたはどう考えますか。
彼女は「素晴らしい日本的距離感」が平和な世界の象徴であるというのです。
この文章を参考に、他者との距離の取り方をあなた自身の体験を加え、800字以内でまとめてみてください。
日本人の文化観
課題文を読んでいてユニークなのは、日常的な動作や文化を通じて平和を育むという視点です。
距離の取り方には、空間を巧みに利用し、五感の働きを加味した独特な文化を取り入れるという日本人的な感性がみられます。
わずか二畳の茶室をイメージすれば、よくわかりますね。
基本的な要素は相手に対する信頼と尊敬でしょうか。
互いの人間性を尊重する配慮も重要です。
あらかじめ身を清め、狭い空間でも互いに視線を合わせません。
それていて相手の気配を身体中に浴びるのです。
他者との距離を測り、動作一つ一つにも配慮が込められています。
このような距離感は、些細な日常の動作や文化に育まれ、人間の体や心に宿りながら、おのずと広がっていくのが理想なのではないでしょうか。
わずかな空間で感じる他者との関係を、少しづつ外に広げていけば、より多くの人とのコミュニケーションも可能になります。
視覚、聴覚を通じて研ぎ澄まされた五感は、より広い人間の関係にも敷衍できるのです。
互いの存在を感じ、共に生きている喜びを実感する瞬間だともいえます。
他者との距離を測ることは、想像以上に疲れを覚えるものです。
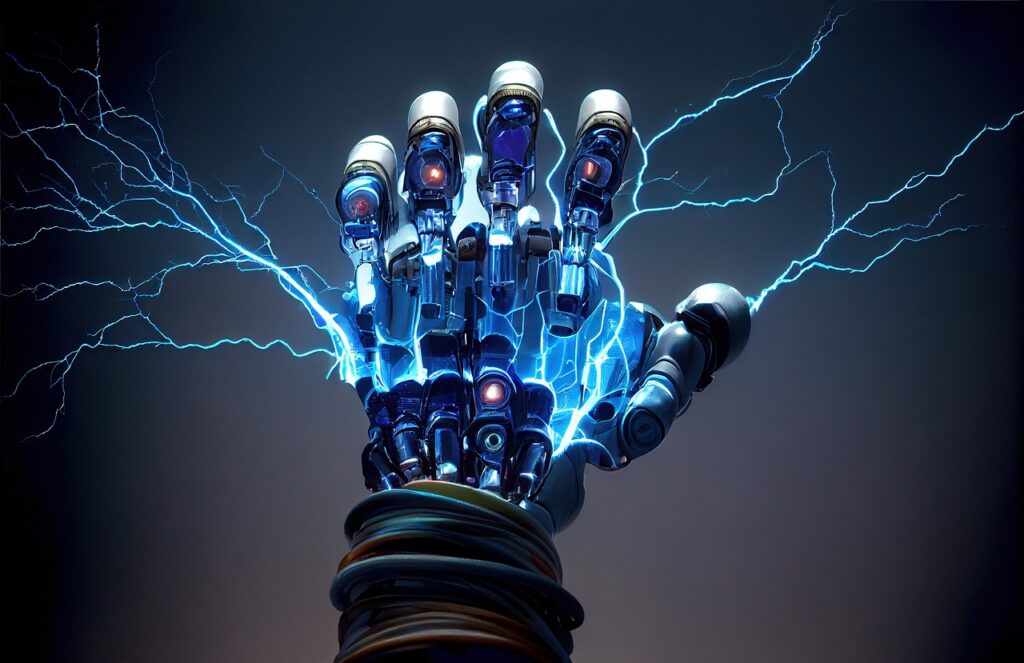
それをごく自然に実践できるようになるためには、人間としての基本的な心情を穏やかなものにする心構えが必要でしょう。
距離を意識するのではなく、自然体でふるまいながら等距離に身を処すという流れができれば、それが最もふさわしいのです。
少しこのテーマについて考えてみてください。
それを文章にしてみることをお勧めします。
今回も最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。


