背景と文脈
みなさん、こんにちは。
元都立高校国語科教師、すい喬です。
日本はハイコンテクストな国だとよく言われますね。
意味をご存知でしょうか。
コンテクスト(context)とは、背景や文脈を意味する英単語です。
背景や文脈が共有されている割合が高ければハイコンテクスト。
その反対がローコンテクストに分類されます。
どちらのレベルが高いという話ではありません。
歴史的・文化的な背景により、言葉やコミュケーションのスタイルが全く異なるのです。
日本では言葉で明確に示されていない背景や文脈から想定して、コミュニケーションをとるのが普通です。
ひとことで言えば場の空気を読む文化です。
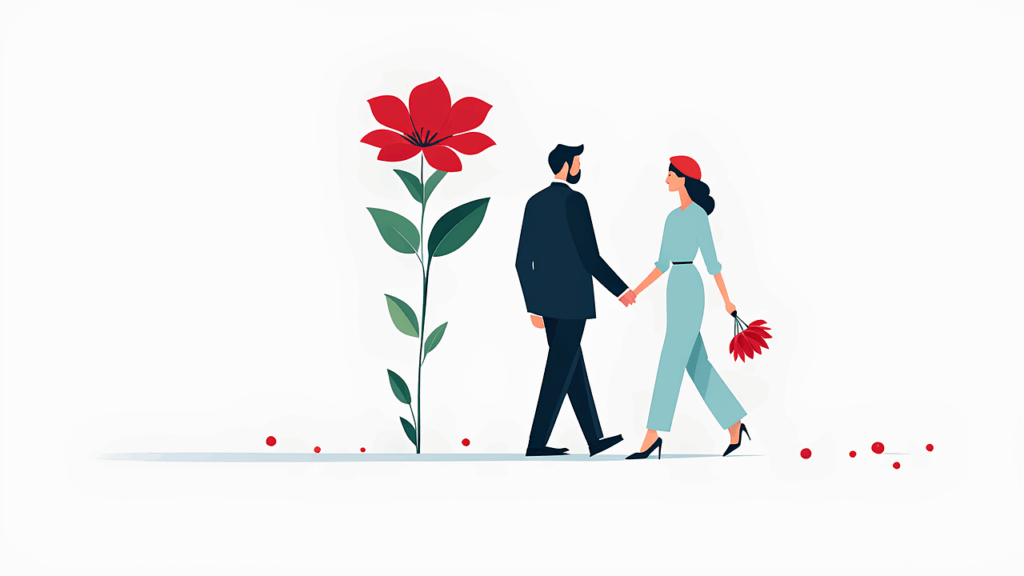
外国人が感じるハイコンテクストな日本語の難しさはよく語られますね。
空気を読む、行間を読む、忖度する、阿吽の呼吸、以心伝心などです。
日本語にはハイコンテクストを指す言葉がいくつもあります。
一方、その反対のローコンテクストとはどんなものでしょうか。
一言でいえば、背景や文脈の共有が少ない状態で言語によるコミュニケーションに重きをおく状態です。
意図することや指し示すことを明確に言葉で示すので、シンプルなスタイルとも言えます。
一般に英語圏のコミュニケーションは、言葉で明確に示すことが重視されローコンテクストであると言われています。
なぜそうなるのでしょうか。
背景としては複数の民族が集まっていることや移民が多いなど、共通するバックグラウンドが少ないことが考えられます。
このような地域では背景や文脈に依存せず、言葉を重視します。
ある意味、嫌なら断ればいいし、できないときは断ることも当然なのです。
このようにハイコンテクストとローコンテクストでは、コミュニケーションスタイルが全く異なります。
このテーマを扱った劇作家・平田オリザ氏の文章がありました。
課題文
日本語は、日本国内だけで使われ発達してきた言語です。
日本は島国ですから、国境線と言語の境界線がほぼ重なっている。
こういった国家や言語は実は珍しいのですが、日本人はそれを当たり前と考え、あまり意識していません。
それだけではなく、人口や職業の流動も少なく、限られた土地で暮らしていると、同じ生活習慣、同じ価値観を持つ共同体が生まれます。
そのなかにいる限り、言葉で多くを説明しなくても互いに理解しあえます。
言語学では、このような社会を「ハイコンテクスト」な社会といいます。
一方、ヨーロッパは異なる価値観、異なる文化的背景、異なる宗教を持つ人たちが陸続きの国で暮らしてきました。
人と出会ったときには、相手が敵か味方かわかりません。
どのような文化で育った人かもわからない。
自分が何者で、何を愛し、何を憎み、どんな能力で社会に貢献できるかを明確に相手に説明し、伝える必要がありました。
自分のことを詳細に説明しなければ、相手にわかってもらうことができません。

私は日本文化を「わかりあう文化」「察しあう文化」、ヨーロッパ文化を「説明しあう文化」とも呼んできました。
日本では、わかりあい、察しあう文化の中から素晴らしい芸術を生み出してきた。
俳句や短歌などがその顕著な例です。
世界に目を向けてみると、日本ほどの大きな国家で、ここまでハイコンテクストな社会はほとんどなく、多くの社会では相手がわかるようにていねいに言葉で説明する必要があります。
そこに良し悪しはありませんが、「日本のようなハイコンテクストな社会は少数派だ」と認識しておくことが必要です。
私が世界中の劇場からオファーをいただいてきたのは、私が世界的に見れば少数派に属するハイコンテクストな日本社会の文化を背負い、日常的に使っている日本語の特徴を活かして戯曲を書いているからです。
そして、それを相手にわかるように、相手の文脈に翻訳して説明できるからです。
決して自分の文化を卑下したり、相手の文化に合わせたりする必要はありません。
ただ、相手の文脈で説明する能力は必要だということです。
(平田オリザ「ともに生きるための演劇」による)
問題
この文章は、平田氏が日本とヨーロッパの社会や文化の違いについて述べたものです。
彼の意見を踏まえた上で、あなたがグローバル社会の中で、世界の人々とどのようにコミュニケーションをとりたいと考えるか、800字以内で述べなさい。
これは昨年、ある大学の入試に出題された問題です。
あなたならどの視点から書きますか。
日本では言葉で多くを説明しなくても相互理解が可能であり、「わかりあう文化」「察しあう文化」と表現しています。
一方、ヨーロッパは異なる価値観や文化的背景を持つ人々が共存してきたため、詳細な説明が必要な「ローコンテクスト」な社会、すなわち「説明しあう文化」であると述べています。

日本は、島国で言語と国境線がほぼ重なり、生活習慣や価値観が共有されやすい環境にあるため、言葉で多くを説明しなくても互いに理解しあえます。
反対にヨーロッパ社会は、共通の文脈が少ないため、自分が何者で、何を愛し、どんな能力で社会に貢献できるかなどを明確に相手に説明する必要があると述べています。
日本のようなハイコンテクストな社会は少数派であり、多くの社会では相手がわかるようにていねいに言葉で説明する必要があると指摘しています。
ポイント
ポイントはグローバル社会の中で世界の人々とコミュニケーションをとることの難しさを強調することです。
察しあう文化が少数派であることを認識し、説明しあう文化を積極的に取り入れることの意味を書きましょう。
具体的には、文化的な背景や価値観が異なり、共通のコンテクストがあまりない相手に対し、誤解を避けるために、自分の考えや意図を曖昧にせず、言葉で詳細に明確に伝える努力を徹底しようということです。
しかし、自分の文化を卑下したり、相手の文化に迎合したりする必要はありません。
むしろ、自分の属するハイコンテクストな日本の文化を強みとして活かしつつ、それを相手の文脈に翻訳して説明する能力を重視することです。
相手の視点や文化的背景を理解した上で、彼らが最も理解しやすい形で情報を提供すること。
その結果、相互理解を深め、建設的な関係を築いていきたいと考えることを強調するのです。
日本語はひとつの単語で複数の意味があることが特徴です。
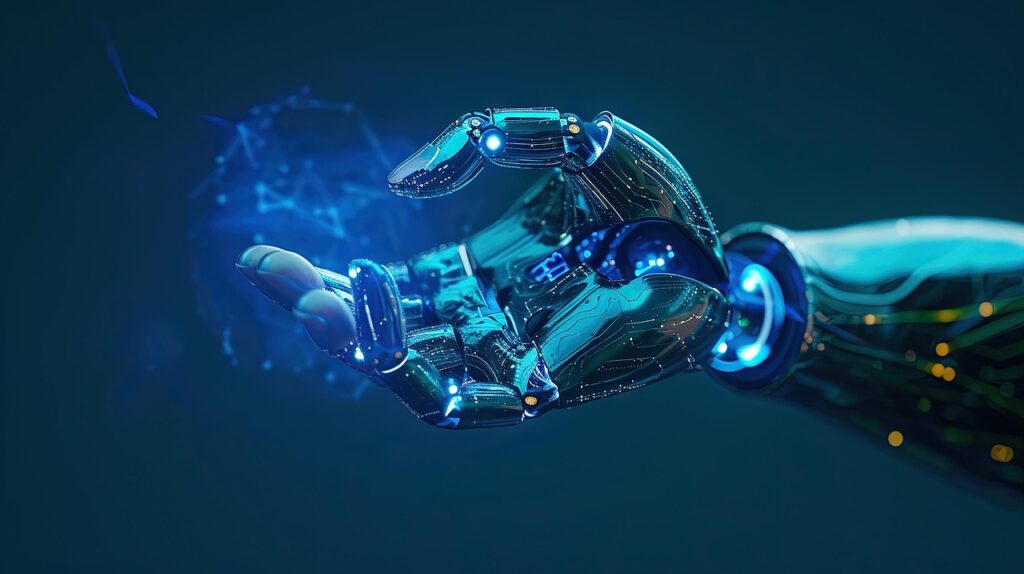
同音異義語がその代表です。
同音異義語以外にも状況によって意味が変わる言葉があります。
「だいじょうぶ」「けっこう」などという表現は諾否のいずれにも使えます。
言葉を聞いただけでは「もういらないのか」「もっと欲しいのか」がわかりません。
このニュアンスを読み取るハードルはとても高いのです。
もっと言えば、日本語の文章は主語や目的語が省略されることが多いです。
日本語には、状況によっていくつもの意味にとらえられる言葉があるのです。
「すみません」「いいです」などさまざまです。
しかしそうしたものを全て含んで、それが日本の文化だということを明確に認識することです。
グローバルな社会の中を生き抜くためには、やはりある程度はっきりとイエスかノーを言わなければならないでしょう。
しかしそれだけではとても息苦しい社会になっていきます。
言語以外のノンバーバル・コミュニケーションが必要な所以です。
他者を理解するためには、豊かな想像力も大切でしょう。
あらゆる場面で自らを鍛えていくことが重要です。
それぞれの違いを認め合いつつ、暮らしていく中で、文化の違いをきちんと切り分けていく理性が求められるのです。
今回も最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。


