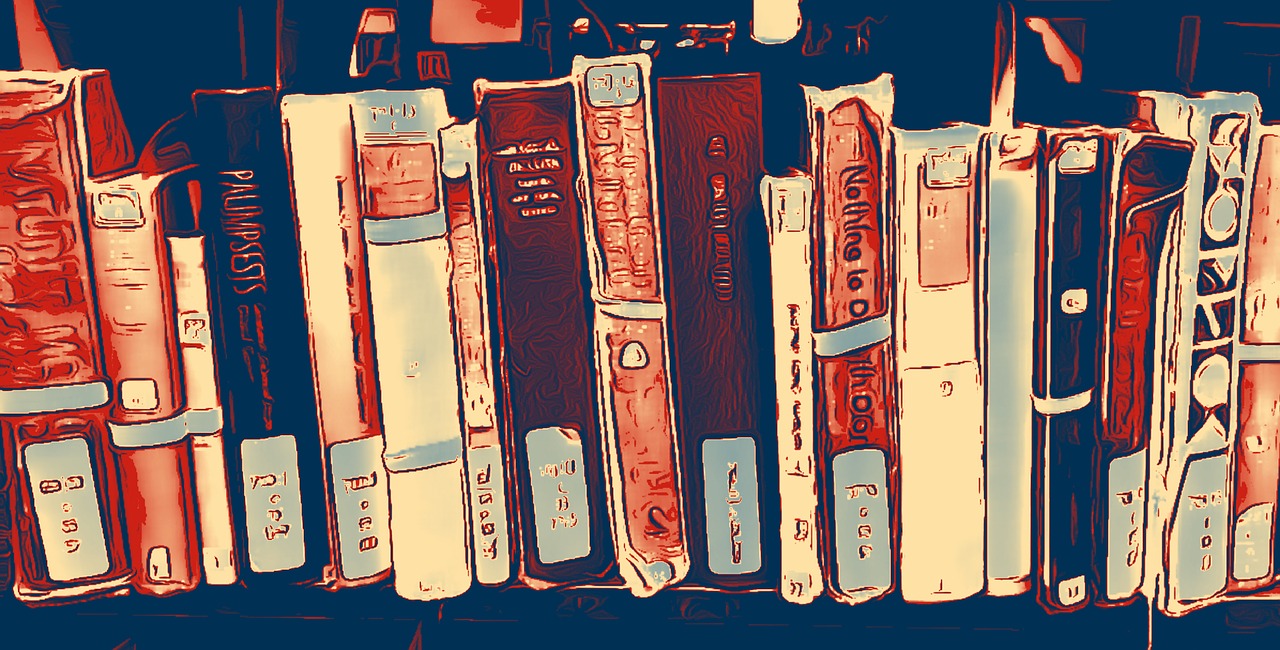働くことの意味
みなさん、こんにちは。
元都立高校国語科教師、すい喬です。
子ども時代との断絶を経験しなかった人が増えていますね。
大人と同じような価値観を、いかにも自分の考えとして述べる子どもも増えました。
学歴厨などと呼ばれる人も、その中に入るかもしれません。
親のクローンのような子どもをみていると、不気味な印象さえ覚えます。
彼らは多くの愉しみを将来の自分のために犠牲にして、勉強に励んでいるのです。
それが自発的なものであれば、まだ許せますが、そうでない場合には痛々しさを感じます。
外からの情報にただ左右されているだけです。

しかし現実には、このタイプの子どもが多く存在するのも事実です。
早くから大人化した子どもは、子ども時代との断絶を明確に意識していません。
夢や憧れを見ることもなく、現実と呼ばれる大人の価値観にからめとらたままなのです。
希望通りにうまく物事が運べばいいのでしょうが、そう簡単にものごとは進まないものです。
やがて大人になり、社会に出た時、自分がどの組織に繰り込まれていくのかという図式も明確に見えていないケースがたくさん見受けられます。
仕事に徹して修練を積むという発想や集中力にも欠けるようです。
現代の仕事はほぼ断片化されつつあります。
総合的にすべての分野に目を通すなどということは不可能です。
たとえ、経営者でも会社全体の流れが鳥瞰図的に見えているなどということはありません。
幸福はどこに
最悪の場合、仕事を通じて自分の行動を組織化することができないうえに、得られる情報からも、幸せな将来を見通すことができないということがおこりがちです。
本来なら、働くことを通じて、やりがいや生きがいを感じ、他者のために生きているという実感が幸福感を育てるものでした。
それが生きることの大前提だったのです。
しかし今はそれも難しくなっています。
チャップリンの映画「モダンタイムス」は、現代の労働がますます無名化し、意味を充足しなくなっていることを戯画化したものでした。
実際は、そこまで極端でないとしても行動が断片化していて、自分の行動を組織化することができていないのです。
そのため、幸せは現在の自分とは切り離された別な場所にあると考えがちになります。
かつて「労働の疎外」という表現がよく使われました。
結局、多くの人が現在からの連続性の中で幸せを築くというイメージをもつことができなくなっています。

その結果、人格改造セミナーなどに走る人がいても不思議はありません。
自分が得られる情報の外側に、自分を幸せにしてくれる本当の何かがあるはずだと、信じたい気持ちが起こってくるのです。
これが、多くの人たちに見られる現象のひとつです。
彼らは焦っていて、現在の自分と切り離されたどこかまったく別な場所に幸せがあると考えがちです。
子ども時代をうまく終えられなかった大人はどこへ向かうのか。
社会学者、橋爪大三郎氏の文章に『幸福のつくりかた』と評論があります。
参考に読んでみましょう。
参考文
子どもはいつまでも子どものままではいられないから、どこかで断念しても、もう自分は子どもではないと、はっきり認識しなくてはならないときがやってくる。
そのときは、奈落の底に突き落とされたような断絶を味わうけれど、でも、そのことで別の生き物に生まれ変わるんですね。
この先どうしようかと真剣に考えて、新しい幸せを目指し、新しい人生を自分の力で歩み始める。
(中略)
昔は知的労働のホワイトカラーと肉体労働のブルーカラーの二つのタイプの仕事があって、マルクスも言ったように、ブルーカラーは断片化した単純労働であり、ホワイトカラーは統合された複雑労働のはずたった。

ところが最近ではブルーカラーの仕事の大部分を機械が代行するようになり、ほとんどの仕事がホワイトカラー的な仕事になっている。
しかも統合されていたはずのホワイトカラーの仕事の断片化が進んで、知的能力に関係なく誰でもできるような仕事が多くなり、ホワイトカラーのプロレタリアが、あらゆる職場で大量にあふれることになったんです。
ホワイトカラーの職がどんどん地盤沈下を起こして、いまや彼らから仕事全体を見通す感覚は失われてしまっているのでしょう。
そうなると、仕事はやらなければならないからやっている、というだけのもので、いったい何のためにやっているのかはよくわからない。
これがいまの一般的な労働者の心の風景なのではないでしょうか。
そうすると仕事場は、できれば逃げ出したい場所でしかなくなる。
その気持ちをまぎらすために、外でいろいろなことをするけれど、次の日にはまた仕事場に舞い戻らなくてはならない。
毎日はその空しい繰り返しになっていく。
そういう人たちの特徴は、指示待ちということです。
自分の仕事を自分で組織できないから、言われるまで何もしない。
遊ぶにしても集中力がないからひとり遊びができない。
チームワークの能力もないから、集団遊びもできない。
その結果、一人でもいられず集団の遊びもできないので、大勢でなんとなく群れているという状態になるんですが、群れていても何をするわけでもない。
ただ群れていて、解散しても群れていたいものだから、お互いに連絡を取り合って、同じ群れだということを確認しあうことになる。
大人と子ども
大人と子どもの違いにはいくつかの側面があります。
主な違いは、責任感や判断力、社会的な役割の理解などです。
大人には自己管理能力や他者との関係を築く力が求められ、さまざまな選択肢から最適な行動を選ぶことが期待されています。
しかしそれがどこかでストップしてしまうケースがあります。
十分な成長を遂げていない場合です。
自分の価値観や目標を理解し、自分自身を受け入れることが重要なのはもちろんです。

しかし、それが本来の子ども自身の価値観ではなく、大人によってゆがめられている場面も多々あるのです。
誰が悪いのかを断定することはできません。
大人になる過程で自分の強みや弱み、価値観を理解し、自分自身を受け入れる能力を高める必要があります。
このプロセスをきちんと過ごさなかった場合、曖昧な人間が生まれてしまうのではないでしょうか。
通常は日常の小さなことに感謝することで、他者に対するポジティブな感情を育てることができます。
さらに信頼できる友人や家族との関係を大切にし、支え合うことが幸せにつながるのです。
自己表現を十分に楽しんだ経験が、伸びやかな成長を約束するということも当然あります。
逆にいえば、こうした体験がない場合、その人のたどる道は険しいものです。
SNS時代の幸福
今はSNS全盛の時代です。
いわゆる「映える」映像や動画がこれでもかというくらい、溢れかえっています。
大人になった彼らはリアルに充足していると思われる他者の姿をみて、当然自分と比べます。
さまざまな情報の中には、見事にこれが幸せだという図式が次々と現れます。
その時、どういう対応をするのでしょうか。
なぜ自分は彼らと違うのか。
なぜ自分は幸福になれないのか。
「映える」世界が自分の周囲にないことの意味を深く詮索することもなく、どこへいけば、それがあるのかを探したいと思う人が多いのです。
人は自分のまわりに求めるものがなければ、それをどこかへ出かけて探そうとします。
自分の内側にそれを探すために遡るという作業をするとは思えません。
どこかへいけば、それがあるとすれば、そこへ向かって進む以外に道はないのです。
しかし実際にあるのかどうか。
現実には自分の内側を深く掘っていく作業を続ける以外、なんの方法があるのか。
子ども時代をうまく過ごせなかった彼らにとって、大人になった後にそれをしろというのはかなり苦しいことなのです。

仕事で自己を成長させることができなくなった場合、多くの大人が自分の現在の延長上に夢を描けなくなっている現象は想像以上に根が深いと言わざるを得ません。
本来な自分の感情をより良く理解し、コントロールすべきです。
ストレスや困難な状況に対する対処法も知らなくてはなりません。
これらの変化は、個人の成長や社会への適応に大きく寄与します。
心理的に成熟することで、より充実した人生を送ることができるようになるはずです。
しかしそれが容易でないことは、ここに書くまでもありません。
この問題は根が深いです。
今回も最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。