詩的リズム
みなさん、こんにちは。
元都立高校国語科教師、すい喬です。
今回は詩の音律ということについて考えてみます。
中原中也の「汚れつちまつた悲しみに」をサンプルに取り上げます。
詩集『山羊の歌』に収められたこの詩は、昭和9年に発表されました。
詩の冒頭の部分を知らない人は、いないのではないでしょうか。
この詩の音の連なりについて、ある文学者がエッセイを書いています。
菅谷規矩雄(1936~1989)という詩人がその人です。
ドイツ文学研究者でもあります。
詩誌「暴走」「凶区」などにより,詩と批評を発表しました。
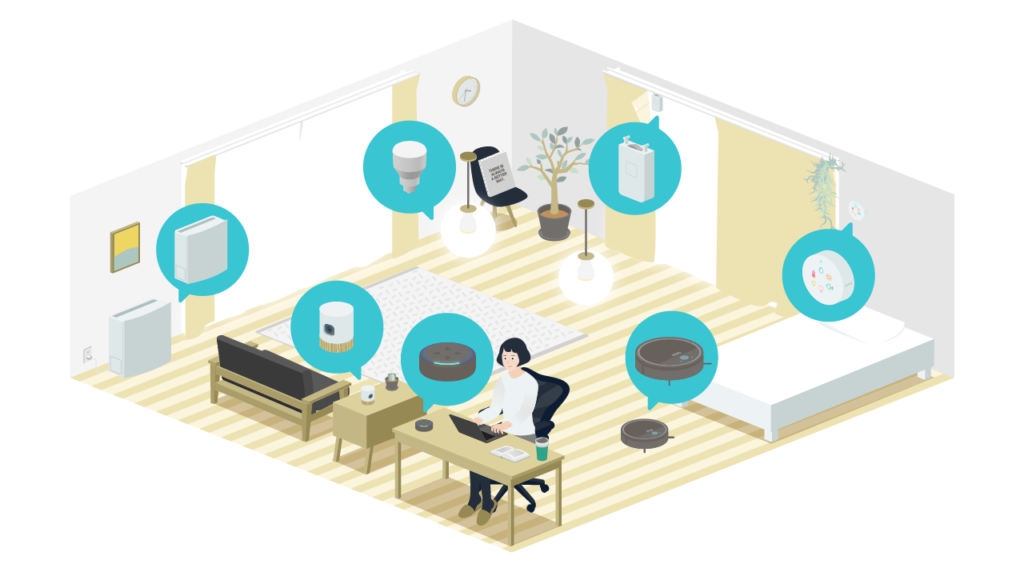
日本語におけるリズムの問題を研究テーマにした人です。
その詩人が実にユニークな文章で中原中也の詩を扱っているのです。
普通だったら、全く気にならない話です。
しかし言葉の韻律を研究していると、この問題を脇に放っておくことはできなかったのでしょう。
具体的にはどんな話なのか。
江藤淳の評論『小林秀雄』という作品についてのものです。
現代では、この2人の文学者の名前を全く聞いたことがないという人も、増えつつあるのかもしれません。
亡くなってから、かなりの年月が過ぎました。
両者とも文学の世界で功績を残した偉人です。
小林秀雄と江藤淳
小林秀雄はフランス文学を学び、江藤淳は英文学を学びました。
日本人の美に対する感覚を研ぎすます作業を続けたのが小林秀雄です。
フランス象徴詩人の研究から始まり、晩年は本居宣長の生涯を追いかけました。
一方、江藤淳は夏目漱石の研究を一生続けた研究者です。
『漱石とその時代』は新鮮な切り口に満ちていました。
彼らの著作を全く読まずに、昭和文学を語ることは不可能です。
江藤淳の著書『小林秀雄』の中に中原中也の『山羊の歌』が引用されているとあります。
その抜き書きが、オリジナルと違うことに、江藤淳は気づき指摘したのです。
なんのことか。
たった1つの促音「つ」の扱いです。
もう少し説明します。
小林と中原は友人と呼ぶ以上に深い精神的な繋がりを共有していました。
小林は評論、中原は詩の創作で、その活躍した分野は違いますが、深いところでは通奏低音をかなでていたのです。
ここへその音律に関する部分の抜き書きをしてみます。
小林秀雄は中原の詩の一節を次のように書き写していると、江藤淳が書いています。

有名な詩の一節です。
誰もが1度は聞いたことがあるはずです。
汚れちまつた悲しみに
今日も小雪がふりかかる
汚れちまつた悲しみに
今日も風さへ吹すぎる
実は中原中也の詩はこの小林が書いたものとは違います。
こちらがオリジナルです。
汚れつちまつた悲しみに
今日も小雪の降りかかる
汚れつちまつた悲しみに
今日も風さへ吹きすぎる
これを読んで何が問題なのかわかるでしょうか。
菅谷規矩雄の気づき
菅谷規矩雄は次のように書いています。
この箇所を読みかけてふと私は納得しないものを感じ、やはり同じ詩の引用されている小林秀雄の『中原中也の思い出』を当たってみずにはいられなかった。
その結果、何より私自身にいつの間にかしみこんでいた錯覚に驚いたのだった。
事柄は単純明瞭である。
言うまでもないだろうが、右の引用では「汚れつちまつた」と2つ重なる原詩の促音の初めの1つが抜け落ちている。(中略)
肝心なことは、私自身が実は、この詩の印刷された文字面の僅かな食い違いに違和を感じるほどの視覚的な印象を持ち続けていながら、他方では、何年間もリフレインを記憶の中で復唱している間に、音声的には完全に促音を1つ脱落させて覚えこんでいたのである。
————————————

この文章を読んで、筆者が言おうとして内容が理解できた人は、相当な文学好きと言わなければなりません。
ぼく自身、最初はなんの話かわかりませんでした。
しかし菅谷は詩のリズムになんとなく違和感を感じたのです。
それがどこからくるものであったのか。
彼は十何年も、中原中也の詩のリズムを少しも本当に感じとっていなかったのではないかと悔やみ、自問したとあります。(中略)
———————————-
結論から先に記す。
「汚れつちまつた悲しみに」は三拍子的である。
「汚れちまつた悲しみ」であれば四拍子的である。
差異を決定するモメントは促音である。
そこには近代詩の韻律にとって最も本質的な条件の所在が示唆されている。
詩への痛恨
もう少し菅谷規矩雄の文章を書き抜きます。
もし私たちが中原がこの詩に刻み込んだ促音へのこだわりに注意を向けるなら、ほとんど痛撃の予感に等しい波紋が拡大してゆくのを目の当たりにできるはずである。
中原中也が立ち尽くした詩の危機の実体を一言で要約するなら、それは近代七五調の局限を解体するラディカルなシンコペーションの連続という特性を帯びて現れる。
あゝ、秋が来た
胸に舞踏の終らぬうちに
もうまた秋が、おぢやつたおぢやつた
「秋の愁嘆」において中原は、あらゆる影響を突き抜けてその向こう側へ出る方法をつかみ取ったのだと思える。
ダダイズムの影響も、あるいは富永太郎の影響も、突き抜けたのである。

「もうまた秋が」の単調な二拍子は、「おぢやつたおじやつた」で不意に、ジャズのアフタービートにも比すべきリズムへと転換し跳躍する。
この瞬間が中原の全ての詩のモメントとなってゆくのだ。
根本のところ、中原中也の詩法は生涯を通じて、1つのものに還元できると思う。
七五調に乗ってあたう限り加速的に書き進むこと。
するとその加速と圧縮の局限で、何ものかが七五調の二拍子を突き崩すように噴き出すのである。
音律から抜け出す
日本人の好きな音律は昔から五音と七音です。
一般的に日本人の多くは無意識に「2音」をベースにして読もうとする傾向があります。
おそらく日本語はこの音の数から永遠に抜けられないのではないでしょうか。
それを中原中也は本能的に感じていたに違いありません。
フランス象徴詩に代表されるソネットという形式は14行で出来上がっています。
これがおそらくこの時代の詩の形式としては、一番安定感に満ちていたのでしょう。
それが日本語の場合は五音と七音なのです。

交通標語から俳句、短歌、演歌にいたるまで、耳に心地のいい表現は、みなこの韻律で出来上がっています。
詩人はその響きの心地よさを痛切に感じ取っていたに間違いありません。
日本語に対する呪縛と考えた可能性もあります。
逆にいえば、そこからどうやったら抜け出せるのかを考えたのでしょう。
それも理屈に満ちたものではダメです。
より、実感に近い身体から直接に噴き出した自然なものでなければいけません。
それを「シンコペーション」と筆者は言っています。
ご存知でしょうか。
音楽用語です。
強拍と弱拍を意図的にずらすことで、独自のリズムを作り出すことが新しい感覚を生み出すという考え方です。
ジャズのアフタービート(裏打ち)をイメージすることも可能です。
それを意識せずに詩の中で実行することが、中原中也の場合、自然にできたということでしょう。
加速と圧縮の局限で噴き出すものがなんであるのか。
それをさぐることが、詩人として自分のアイデンティティの確立に必要なことであったに違いありません。
今回も最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。


