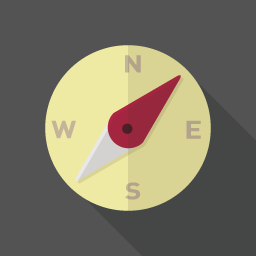腹悪しき女房
みなさん、こんにちは。
元都立高校国語科教師、すい喬です。
今回は説話集の中から解説します。
これは北条時頼の人柄を彷彿とさせる逸話です。
と同時に登場人物の男の孝行心もみごとに描かれています。
時頼は鎌倉時代中期の鎌倉幕府第5代執権として、北条氏の権力確保につとめました。
相州禅門と呼ばれていた人です。
禅門とは在家のまま仏門に入った人をさします。
話そのものは少しも難しくはありません。
誰が読んでもすぐに理解できる内容です。
怒りっぽく気性の激しい女房が、息子ともども相州禅門(北条時頼)に仕えていた時のことです。

ある時、その女房はささいなことで息子に腹を立てて殴りかかろうとし、ものにつまづいて倒れてしまったのです。
その後、どういうことになったのか。
その顛末を読んでいきましょう。
出典は『沙石集』(しゃせきしゅう)という、鎌倉時代後期の仏教説話集です。
無住道暁(号は一円)が編纂しました。
1279年に書かれ始め、その後も加筆されたと思われます。
『沙石集』という本のタイトルは「沙から金を、石から玉を引き出す」という意味を表します。
日常の出来事の中から、大切な真理を導き出そうというものです。
単なる説教集のレベルを超え、1つの文学作品となっている点が興味深いのです。
このような仏教説話集は他にもかなりありました。
代表的なのは『沙石集』の他に『日本霊異記』『今昔物語集』『発心集』などです。
関心があったら、ぜひ読んでみてください。
中世の人々が、どのような思想を持っていたのかが、実によくわかります。
原文
いよいよ腹を据ゑかねて、禅門に、子息某、わらはを打ちて侍るなりと訴へ申しければ、不思議のことなりとて、かの俗を召せとて、まことに母を打ちたるにや、母しかしか申すなりと問はる。
まことに打ちて侍ると申す。
禅門、返す返す奇怪なり、不当なりと叱りて、所領を召し、流罪に定まりにけり。
こと苦々しくなりけるうへ、腹もやうやう癒えて、あさましくおぼえければ、母、また禅門に申しけるは、
腹の立つままに、この子を、打ちたると申し上げて侍りつれども、まことにはさること候はず、おとなげなく彼を打たんとして、

倒れて侍りつるを、ねたさにこそ訴へ申し候ひつれ、
まめやかに御勘当候はんことはあさましく候ふ、許させ給へとて、けしからぬほどにまたうち泣きなど申しければ、
さらば召せとて、召して、ことの子細を尋ねられけるに、まことにはいかで打ち候ふべきと申すとき、さては、など初めよりありのままに申さざりけると、
禅門申されければ、母が打ちたりと申し候はんうへには、わが身こそいかなる咎にも沈み候はめ、
母を虚誕の者には、いかがなし候ふべきと申しければ、いみじき至孝の志深き者なりとて、大きに感じて、別の所領を添へて給ひて、ことに不便の者に思はれけり。
末代の人には、ありがたく、めづらしくこそおぼゆれ。
現代語訳
相州禅門(北条時頼)に仕えていた、怒りっぽい女が、同じく禅門に仕えていた息子を殴ろうとして、つまづいて転んでしまいました。
女はいよいよ怒りをこらえられなくて、禅門に、「息子の某が、私を殴りました」と訴え申しあげたのです。
禅門は「けしからんことだ」と思い、「その男を呼べ」とおっしゃいました。
男に向かって、「お前は本当に自分の母親を殴ったのか。
お前の母はこれこれだと言っているぞ」とお訊きになったのです。
男は「本当に殴りました」と申しあげました。
禅門は、「まったくもって とんでもないことだ、許せない」と叱り、男の所領を全て取り上げ、流罪にすることに決めました。
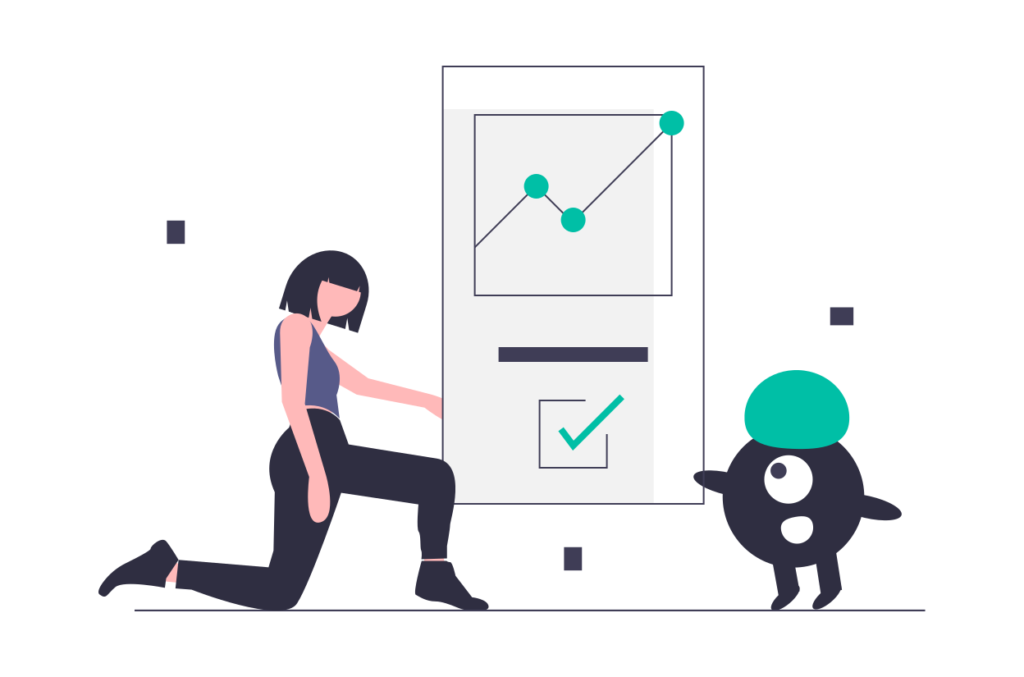
事態が想像していた以上に大きくなったうえに、怒りもやっとおさまってきた母親は、あきれたことになったと思い、再び禅門に申しあげたました。
「憤りのあまり、この子が私をなぐったと申し上げましたが、実はそんなことはございませんでした。
おとなげなく息子を殴ろうとして、転んでしまいましたのを、くやしさのために訴え申しあげたのです。
実際に息子を処罰するなどというのはあまりでございます、許してやってくださいませ」と言って、ひどく泣いて申しあげたので、
禅門は「それならその男を呼べ」と言って、詳しい様子をお尋ねになります。
男は「私がどうして母を殴ったりいたしましょう」と申すので、
「それでは、どうして最初からありのままに言わなかったのだ」と、禅門がおっしゃいました。
男は「私が殴ったと母が申しましたうえには、自分の身はどんなお咎めをこうむりましょうとも、母を嘘つきには、どうしてすることができましょうか」と言ったのです。
禅門はその返事を聞き大変に「孝行の心の深い者だ」と感じ入りました。
男に今までの所領の他に別な土地を加えてお与えになって、人品の整った人物として遇されたということです。
今のような末代の者には、珍しい、すばらしいことだと私(筆者)は思います。
母に対する息子の思い
息子のけなげな様子が実にみごとに描かれていますね。
最初に母親の申し出を聞いて、ショックを受けたことは容易に想像できます。
しかし母に反論せず、そのまま認めた息子の気持ちを考えると、少し切なくなります。
かなり気性の激しい母親のようですから、それまでにもいろいろなことがあったのでしょう。
そんなはずはないと反論すれば、それなりに自分が有利になる局面であったかもしれません。
ところがそれをせずに、全て母親の言う通りですと認めた息子の気持ちもわからないわけではありません。

仏教では5つの戒めを大切にします。
その1つに「妄語戒」があります。
ご存知ですか。
嘘をついてはならぬということです。
ここでは正直にいえば、母を貶める行為に繋がってしまいます。
背後で男を支えたのが、母への「孝行心」でした。
どちらをより大切に考えるかで、この文章の意味が大きく違ってくるでしょうね。
さらに深く考えてみると、息子は母を嘘つきにしないために、自分が犠牲になるという論理を貫いたということになります。
最後に「末代の人には、ありがたく、めずらしくこそおぼゆれ」とあります。
自分の生きた時代を末代とするのは、まさに末法思想が強く影響していると思われます。
13世紀はもう末代だったのです。
釈迦の死後2000年を経ると末法の世となります。
仏法が衰えて世の中が乱れると考えられたのです。
日本では1052年からその時代に入るとされました。
最後の1文に末代の人には、ありがたく、めづらしくこそおぼゆれ、とあります。
「ありがたし」という表現は「あることが難しい」という意味です。
現代語に翻訳すると、「めったにない」となります。
それだけ、親への孝行心を前面に出した文章の意味をあらためて考えなくてはならないほど、乱れた世の中になりつつあったということでしょうか。
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。