落語の国の精神分析
みなさん、こんにちは。
アマチュア落語家、すい喬です。
今までに落語関係の本を、随分と読んできました。
基本は演芸評論家の書いたものと、噺家本人の聞き語りが多いですね。
どちらも面白いです。
文楽、志ん朝、談志、円生、志ん生などのものはどれも、そこに噺家本人がいるような気がします。
最近の噺家も随分と本にまとめていますが、ぼくにとってはもう1つかな。
落語は口承文芸ですからね。
本来は高座にあがって噺をして、それでおしまいなのです。
それ以上のものではないと思います。
しかしいつの頃からか、データをきちんと録音したり、文章化することも可能になりました。
最近では有名な噺家の落語がそのまま、活字になっています。
文庫本の本棚を探してみてください。
小三治のは読んでいるだけで楽しいです。
まくらだけの本も出版されています。
便利なのか、不便なのか。
落語家にとって、記録に残るというのはありがたい反面、怖いことでもありますね。
円生が100席を完全にレコード化したあたりから、この流れは始まっています。
長い歳月をかけて、自分の芸を残した執念には、敬服します。
鬼気迫るものがありますね。

後に続く噺家にとっては、いわば百科事典のようなものです。
わからない箇所は、すぐにチェックできます。
しかしそこへ戻ってばかりもいられません。
落語はつねに時代との切っ先が勝負の要です。
口承芸が時代と離れたら、それでもう終わりなのです。
さて、今まで読んだ落語関係の本で最も難しかった本をご紹介しましょう。
ある精神分析学者が書いた本です。
落語の本は、普通笑って終わるものが多いのです。
もちろん、『志ん生一代』のような小説もありますけどね。
さて評論としては、これ以上、綿密に落語を分析した本はないでしょう。
いったいどんな人が書いた本なのでしょうか。
大学入試問題
東京大学2014年の入試に使われた評論がそれです。
精神分析家、藤山直樹氏の『落語の国の精神分析』です。
以前、入試問題の研究をしていた時、偶然発見しました。
試験に取り上げられる前に、確かに一度読んだ記憶がありました。
しかしその大部分を忘れていたのです。
慌てて読み直した記憶があります。
筆者は精神分析医、藤山直樹氏です。
趣味で自らも落語をやっている精神分析家です。

古典落語の登場人物を、精神分析の土俵に乗せた評論といえばいいのでしょうか。
文章も練れていて、かつ本業の精神分析の切れ味は鋭く、多才多能な人だと感心して一気に読み終えました。
談志の「らくだ」について言及した部分が多いですね。
この噺に興味のある人は、ぜひ彼の落語をきいてみてください。
ぼくもレパートリーに持っていますが、大変に難しい噺です。
もう1つは文楽の「よかちょろ」です。
これは若旦那ものですが、誰でもできるという噺ではありません。
ある意味、職人芸の要素が強い道楽噺です。
その他、「芝浜」「文七元結」「粗忽長屋」「居残り佐平冶」「明烏」「寝床」などをネタとして扱っています。
談志へのオマージュ
筆者の説によれば、落語家には職人芸を磨き上げるタイプの名人(円生、小さん、志ん生など)と、芸術を目指して苦闘するタイプの名人とがあるというのです。
そういう意味で談志は明らかに後者だと断定しています。
よほど彼の噺が好きだったのでしょう。
それがよくわかります。
あらためて、じっくりと文章を読むにつれ、事実を正確に描写するというのはこういうことなのだと実感させられる点があちこちにありました。
東大の入試問題は論文型が主流です。
字数制限もきつくなく、自分の考えを枠内に書き込むのです。
どんな問題文が出題されたのか、ここに示してみましょう。
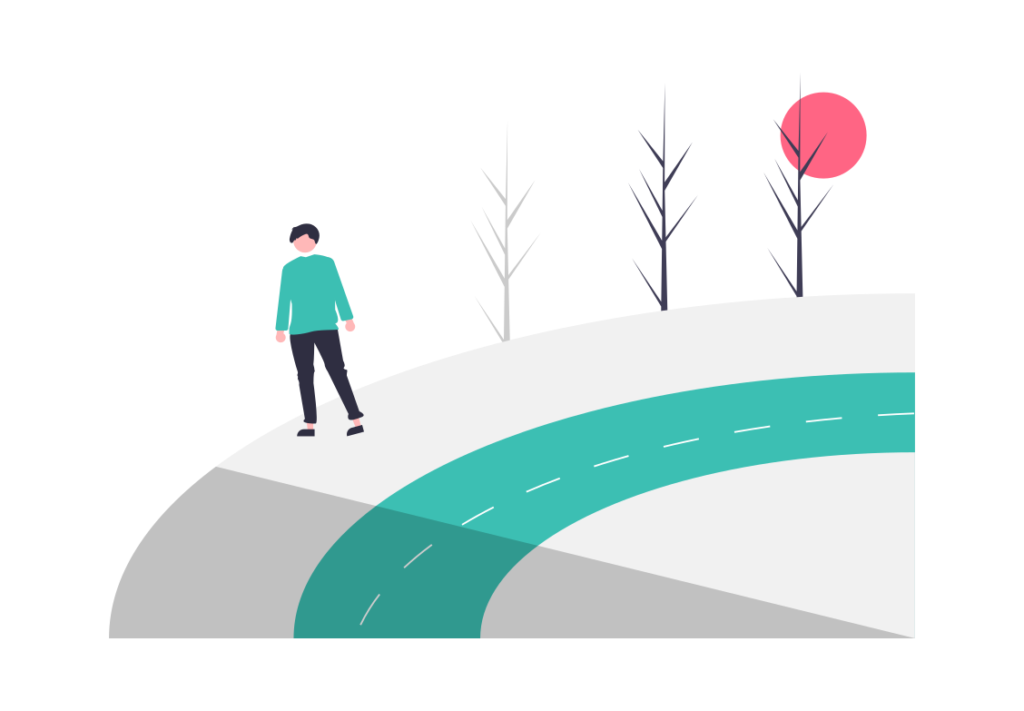
基本は、それぞれの文章をわかりやすく説明せよというものです。
少しだけ問題文を書き抜きます。
—————————–
いざ仕事をしているときの落語家と分析家の共通するものは、まず圧倒的な孤独である。
落語家は金を払って「楽しませもらおう」とわざわざやってきた客に対して、たった一人で対峙する。
多くの出演者の出る寄席の場合はまだいいが、独演会になるとそれはきわだつ。
他のパフォーミングアート、たとえば演劇であれば、うまくいかなくても、共演者や演出家や劇作家や舞台監督や装置や音響のせいにできるかもしれない。
落語家には共演者もいないし、みんな同じ古典の根多を話しているので作家のせいにもできず、演出家もいない。
すべて自分で引き受けるしかない。
しかも落語の場合、反応はほとんどその場の笑いでキャッチできる。
残酷までに結果が演者自身にはねかえってくる。
受ける落語家と受けない落語ははっきりしている。
その結果に孤独に向かい続けて、ともかくも根多を話し切るしかない。
設問
設問は以下の通りです。
傍線部分がないので難しいですが、どのようなことが問われたのかはわかります。
問1 「このこころを凍らせるような孤独」(傍線部ア)とはどういうことか、説明せよ。
問2「落語家の自己はたがいに他者性を帯びた何人もの他者たちによって占められ、分裂する」(傍線部イ)とはどういうことか、説明せよ。
問3「ひとまとまりの「私」というある種の錯覚」(傍線部ウ)とはどういうことか、説明せよ。
問4)「精神分析家の仕事も実は分裂に彩られている」(傍線部エ)とはどういうことか、説明せよ。
問5)「生きた人間としての分析家自身のあり方こそが、患者に希望を与えてもいる」(傍線部オ)とあるが、なぜそういえるのか、落語家との共通性にふれながら100字以上120字以内で説明せよ。
以上です。
——————————-
落語には何かを演じようとする自分と、見る観客を喜ばせようとする自分の分裂が存在します。
もっといえば「演じている自分」とそれを「見る自分」の分裂です。
世阿弥が「離見の見」として概念化したものと同じ種類の構造で出来上がっているのです。
演者はネタの中に出てくる人物たちにその瞬間同化します。
登場人物たちがお互いに何を語るのか知らないというのが基本の設定です。
それでいて、噺家本人はその全てを掌握していなければならないのです。
つまり観客の前で自己分裂を続ける存在こそが、噺家そのものなのかもしれません。
その他者性こそが落語の命なのでしょう。

そこに観客は不思議な味わいを感じます。
ギャグもくすぐりも生きてくる。
落語家はお客でもあり、登場人物でもあり、そして他ならぬ彼自身でもあるのです。
だからこそ苦しく難しいのに、悪魔的な魅力にひかれ、翻弄されていくのです。
実に底の深い不思議な芸能だということが言えますね。
能でいえば、シテとワキを同時に1人の人間が行うようなものです。
完全に分裂した個人とどこまで屹立し合うのか。
それが楽しみでもあるのです。
今度、落語を聞く時は、そういう視点からも鑑賞してみてください。
きっと新しい発見に出会えると思います。
今回も最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。


