前頭葉活性化
みなさん、こんにちは。
元都立高校国語科教師、すい喬です。
ここ数日、精神科医和田秀樹の本を4冊読みました。
70歳、80歳という数字の入っているベストセラーのことは御存知ですね。
『70歳が老化の分かれ道』、『80歳の壁』の2冊です。
本屋さんにいくと、平積みになってたくさんおいてあります。
出版社によれば、数字の入っている本は売りにくいとか。
それが突然の大ベストセラーです。
大化けしました。
団塊の世代がいよいよ後期高齢者になろうとしています。
読書習慣を持っている彼らが、自分のことを思って手にとったのでしょう。
そこには脳から老化が始まると書いてあります。
ジムに通って運動をする以上に、前頭葉を鍛えろとあるのです。
さらに加えて2年ほど前に書かれた本もあります。
『高齢になっても脳を健康に保つ特効薬』、『60歳から脳を鍛える健康法』です。

いずれも論点は全て脳に集中しています。
突然、感情のコントロールが効かなくなり、切れて暴走する老人の話などを聞くにつけ、他人事とは考えられなくなったに違いありません。
年齢を重ねるにつれ、誰でも脳は委縮していきます。
しかし訓練を積み、使い続けることで、委縮した部分を十分にカバーできるのです。
それ以上に和田さんは人間として人間らしく、創造的に生きることの重要性を論じています。
集中的にまとめられているのが、「前頭葉」の話題です。
人間の脳はひろげてみると、新聞紙1枚くらいだそうです。
そのうち。前頭葉が41%、側頭葉が21%、頭頂葉が21%、後頭葉が17%。
前頭葉は人間の思考や理想を、側頭葉は言語の理解や記憶と聴覚、嗅覚を、頭頂葉は計算力と図形や空間の把握、後頭葉は視聴覚情報の処理を担っています。
前頭葉がこれほど発達している動物は人間だけなのです。
まさに、脳が人間の存在をつかさどっているという言葉の所以でしょう。
反論をイメージ
和田さんの本は非常に読みやすいです。
どれもタイトルを見ると、すぐにポイントになる話題の中心に辿り着けます。
難しい単語は少しも出てきません。
今も精神科医を続ける傍ら、著述の仕事をしています。
医師としての所得よりも、著作からの印税の方が多いそうです。
わかりやすい本を書く訓練を、徹底的にしたのでしょう。
とにかく文章を書くことのメリットを声高に主張しています。
できれば反論を用意しながら、理解しやすい文章を書くことの大切さです。
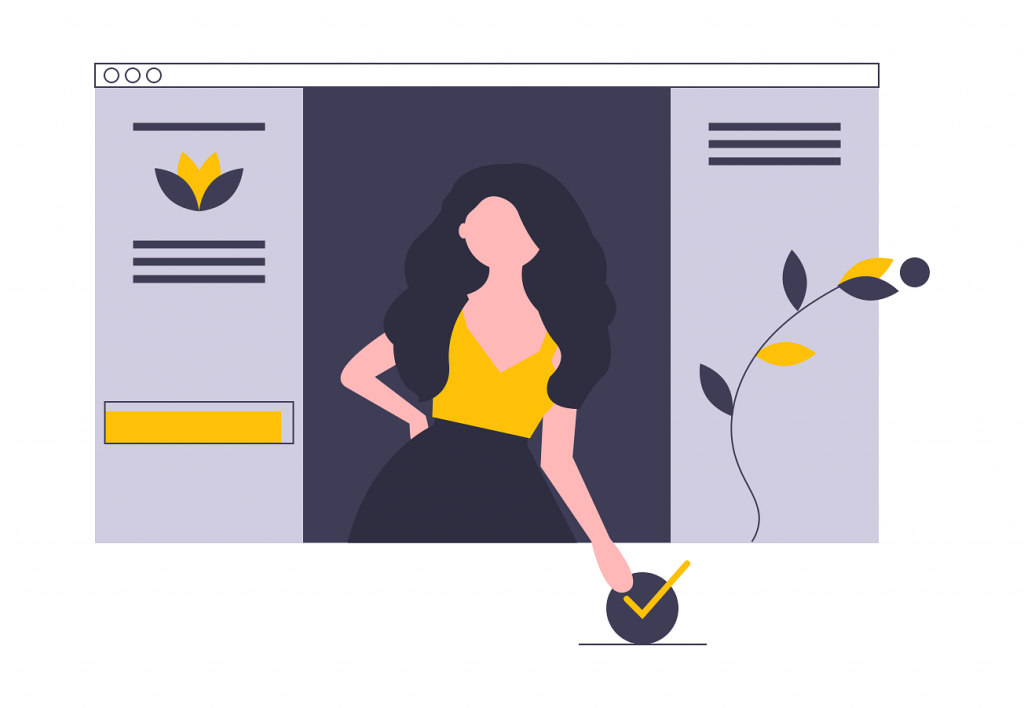
会話での発言というのは、その時だけのものになりがちです。
つい感情的になって、本来の趣旨とは違うことを口にすることもないワケではありません。
しかし文章は残ります。
後日、読み直した時、自分の論点とは違う場合は修正も可能です。
いずれにしても、静的な方式なのです。
ある意見に対して、必ず追随する必要もありません。
冷静に言葉を選んで、対応することが可能です。
その際、前頭葉がフル稼働します。
あらゆる語彙の中から、最も適した言葉を探しだし、それをアウトプットする。
当然、読者を説得できるだけの論理がそこになければなりません。
これは想像以上に脳を使う作業です。
終わったあとには、ある種のカタルシスもあります。
アウトプットの効用
ここまで読んでみて、どんな印象を持ちましたか。
まさにこれがアウトプットそのものなのです。
本を読むだけでは、完全な理解には進みません。
解釈をし、自分なりの道筋をつけながら文章を読み終わったとしましょう。
試験の場合なら、課題文を読んだ状態です。
そこから設問の指示にあわせて、文章を組み立てていきます。
どこへ進むのか。
筆者に対してYesNoのレベルで答えられるのか。
あるいはそれ以上に別の視点が必要なのか。
筆者の使っている語彙に対して、疑問を持つこともあるでしょう。
その全てがアウトプットへの道しるべになるのです。

普段考えないような反論や、意見を理解したり、考えたりすることは非常に有用なことです。
自分の認識が歪んでいないかを冷静にモニターします。
最悪の場合、それを修正する必要があるかもしれません。
その作業を続けていく中で、「メタ認知」が形成されるのです。
「メタ」とは「超えた」という意味です。
より高い次元の内容をそこに出現させ、文章を作り出します。
「多様性」という言葉を知っていただけの人は、課題文の中に出てくるその表現の本来持っている意味を再認識する必要が出てくるのです。
それが意味のあるアウトプットに繋がります。
これ以上に脳を使う瞬間はありません。
脳に楽をさせない
人間はつねに楽な行動を好みます。
同じ刺激の中にいれば、疲労は少ないのです。
それだけに、必要以上の驚きを欲しません。
その状態がしばらく続くと、もう認知の伸びがなくなってしまうのです。
これは怖いことです。
自分では新しいことをしているつもりでも、ただのルーティンワークになってしまいます。
その意味で、小論文は非常に有効な手段です。
あらゆる場面の問題をつきつけられ、それに対してアウトプットをしなくてはなりません。
基本的な書き方だと言われる方法は、2、3度試みれば未来がないことがわかります。
つまり同じ方法論で、書かれた文章にはどれにも新鮮味がないのです。
いつも半分は肯定し、半分は否定する方法。
あるいは最初から否定すると見せかけて、後で迎合していく書き方。
今までに多くのスキームが登場しました。
しかしやってみればすぐにわかります。
いい加減に考えもなしに始めると、効果的な結論にまで達することができません。

必ず論理が破綻するのです。
脳に絶対楽をさせてはいけません。
どんな時でも、最高度に思考を加えて、自分の過去の経験と照らし合わせ、アウトプットをすることです。
それが採点者のこころを揺さぶります。
論理的な文章の運び方でもそんなことがあるのかと考える人もいるでしょう。
採点していると必ずわかります。
文章が書けるようになったら、人生がかわると言います。
これは一生のスキルです。
神に出会うことができます。
脳の活性化は永遠のテーマなのです。
今回も最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。


